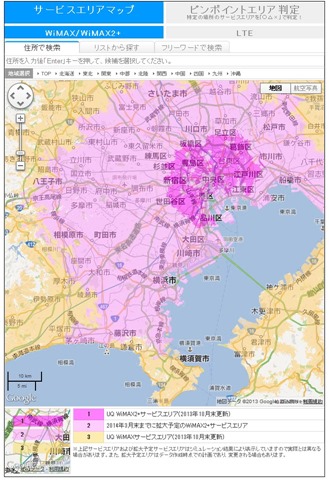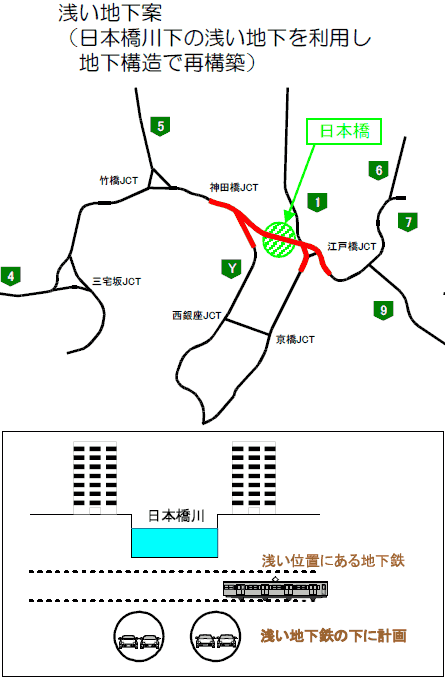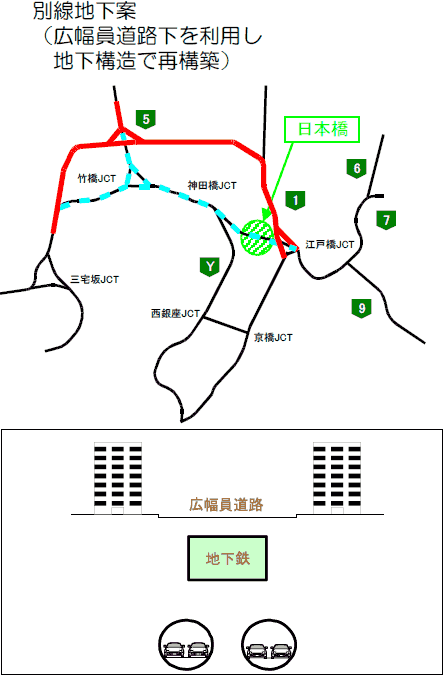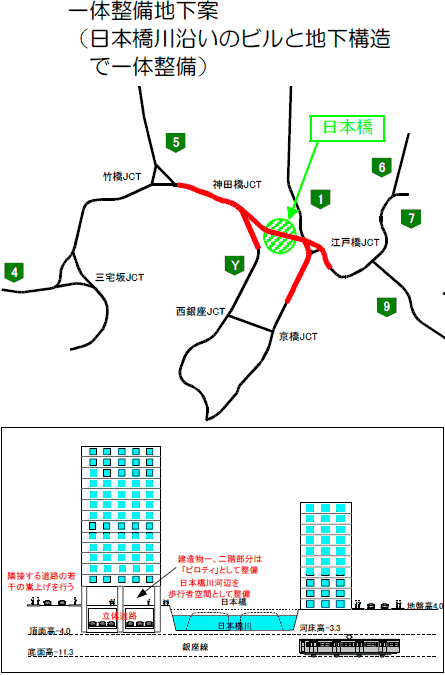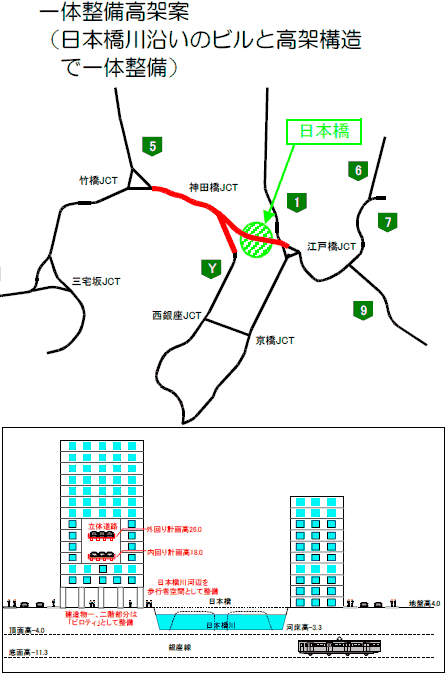Search
カテゴリー:経済
2025年6月 6日
環2平戸交差点に大型電機店開店
国道1号線と環状2号線が交差する環2平戸交差点の、第一パン工場があった場所に、ヤマダ電機の横浜本店︵Tecc LIFE SELECT 横浜本店︶が移転開店しました。
国内最大級の規模ということで、大々的に宣伝しておりましたので、開店初日は国道1号線、環状2号線とも平戸付近は大渋滞しておりました。


2階のフロアはほとんど家具インテリア、リフォーム関連となっていて、業種の枠を越えた内容になっています。 それにしても、国道1号線とはいえ、この付近は実質片側1車線︵中央車線側は東戸塚駅方面への右折レーン︶であり、環状2号線も側道なので、駐車場への出入りには相当時間がかかっている模様です。
また、大型店舗の出店により、商圏も変わりますし、交通状況も変わっていきます。
環2平戸交差点付近は、これまで以上に渋滞が予想されるため、この付近を通る場合には交通情報に充分留意しておく必要がありそうです。
それにしても、国道1号線とはいえ、この付近は実質片側1車線︵中央車線側は東戸塚駅方面への右折レーン︶であり、環状2号線も側道なので、駐車場への出入りには相当時間がかかっている模様です。
また、大型店舗の出店により、商圏も変わりますし、交通状況も変わっていきます。
環2平戸交差点付近は、これまで以上に渋滞が予想されるため、この付近を通る場合には交通情報に充分留意しておく必要がありそうです。


2階のフロアはほとんど家具インテリア、リフォーム関連となっていて、業種の枠を越えた内容になっています。
 それにしても、国道1号線とはいえ、この付近は実質片側1車線︵中央車線側は東戸塚駅方面への右折レーン︶であり、環状2号線も側道なので、駐車場への出入りには相当時間がかかっている模様です。
また、大型店舗の出店により、商圏も変わりますし、交通状況も変わっていきます。
環2平戸交差点付近は、これまで以上に渋滞が予想されるため、この付近を通る場合には交通情報に充分留意しておく必要がありそうです。
それにしても、国道1号線とはいえ、この付近は実質片側1車線︵中央車線側は東戸塚駅方面への右折レーン︶であり、環状2号線も側道なので、駐車場への出入りには相当時間がかかっている模様です。
また、大型店舗の出店により、商圏も変わりますし、交通状況も変わっていきます。
環2平戸交差点付近は、これまで以上に渋滞が予想されるため、この付近を通る場合には交通情報に充分留意しておく必要がありそうです。
2025年5月21日
上永谷周辺のスーパー勢力地図が変わるか
現在、上永谷周辺には、さまざまなスーパーマーケットがあります。
駅前にはイトーヨーカドーがあり、広い商圏を持っているのですが、ここ数年は特色あるさまざまなスーパーの進出もあり、競争による入れ替わりも激しくなっています。
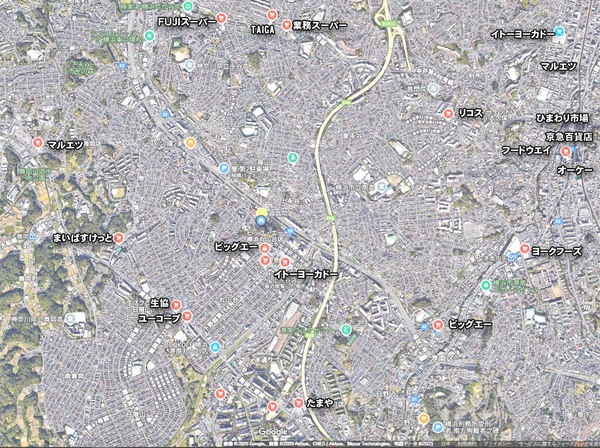
そんな中、中部地方で出店展開をしている﹁バロー﹂が関東地方1号店を永谷の地に決定したというニュースがありました。
関東進出を正式表明 バローHD、今期中にスーパー事業で 地域売上高500億円へ
バローホールディングス︵HD、本部多治見市︶は13日、2026年3月期に食品スーパーのバロー単独で関東地方へ進出することを正式に表明した。オープン時期や出店規模など詳細は明らかにしていないが、進出先は神奈川県内が有力で﹁まずは横浜︵の市内︶とか、神奈川の郊外型の物件を狙おうと思っている﹂︵バローHDの小池孝幸社長︶との考えを示した。バローグループとしての出店を加速させ、中期的に関東での売上高500億円を目指す。
(Yahoo!ニュース2025/5/14配信︶
魚介類など生鮮食品に大きな強みをもつ大型スーパーは、ヤマダ電機が移転した後に入る予定です。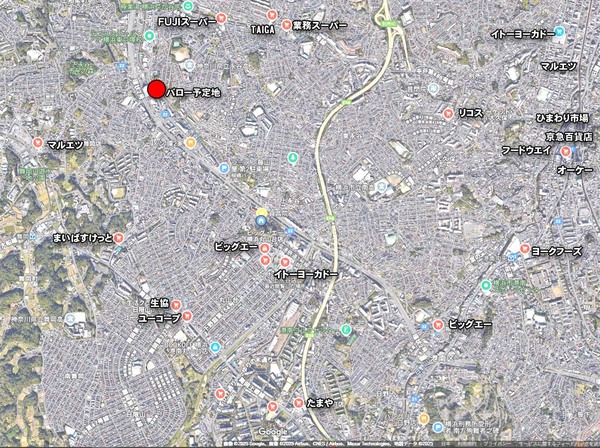 これにより、周辺のスーパーの勢力地図が大きく変わることが予測されます。
今後の推移に着目したいところです。
これにより、周辺のスーパーの勢力地図が大きく変わることが予測されます。
今後の推移に着目したいところです。
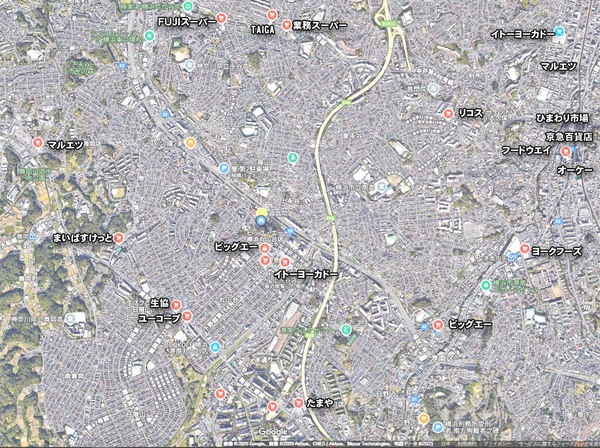
そんな中、中部地方で出店展開をしている﹁バロー﹂が関東地方1号店を永谷の地に決定したというニュースがありました。
魚介類など生鮮食品に大きな強みをもつ大型スーパーは、ヤマダ電機が移転した後に入る予定です。
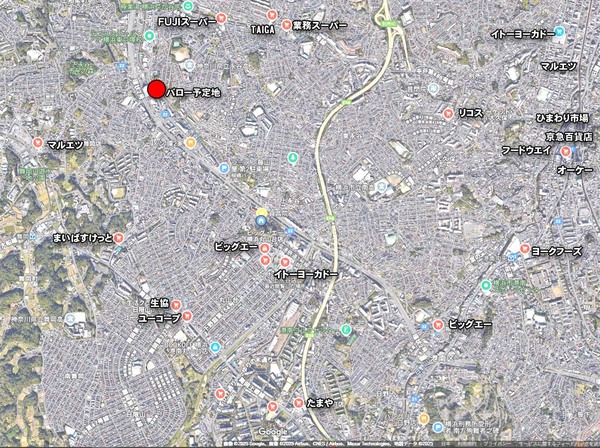 これにより、周辺のスーパーの勢力地図が大きく変わることが予測されます。
今後の推移に着目したいところです。
これにより、周辺のスーパーの勢力地図が大きく変わることが予測されます。
今後の推移に着目したいところです。
2025年2月11日
上永谷に見るファミリーマートのドミナント戦略
上永谷駅前ビルに入っていた三菱UFJ銀行上永谷支店がATMのみに縮小し移転したため、この場所にファミリーマートが1月29日に開店しました。
 ファミリーマート上永谷駅前店
ところが、この出店場所のわずか30mほど先の上永谷駅構内にはファミリーマートがすでにあります。
さらに、その先、L-ウィングの広場にもファミリーマートがあります。
ファミリーマート上永谷駅前店
ところが、この出店場所のわずか30mほど先の上永谷駅構内にはファミリーマートがすでにあります。
さらに、その先、L-ウィングの広場にもファミリーマートがあります。
 ファミリーマートはまりん上永谷駅店
ファミリーマートサンズ上永谷L-ウィング店︵上写真の中央奥︶
ということで、おおよそ100mの間にファミリーマートが3店舗集中して出店していることになります。
このエリアに他系列のコンビニエンスストアは無し。
ファミリーマートはまりん上永谷駅店
ファミリーマートサンズ上永谷L-ウィング店︵上写真の中央奥︶
ということで、おおよそ100mの間にファミリーマートが3店舗集中して出店していることになります。
このエリアに他系列のコンビニエンスストアは無し。
 もう少し範囲を広げると、
ファミリーマート上永谷駅前店
ファミリーマートはまりん上永谷駅店
ファミリーマートサンズ上永谷L-ウィング店
の他に
ファミリーマート上永谷ニ丁目店
ファミリーマート丸山台一丁目店
などが徒歩圏にあります
もう少し範囲を広げると、
ファミリーマート上永谷駅前店
ファミリーマートはまりん上永谷駅店
ファミリーマートサンズ上永谷L-ウィング店
の他に
ファミリーマート上永谷ニ丁目店
ファミリーマート丸山台一丁目店
などが徒歩圏にあります
 このように、同一のチェーン店を集中的に出店することをドミナント戦略と表現します。
一見、過当競合のため、お互いに顧客を奪い合ったり経営効率が悪いように思えますが、︵本部にとっては︶地域内でのシェアを拡大し、競合他社と差別化したり、それぞれ店舗ごとに役割分担したり、在庫供給の効率化を高めることができたりする効果があります。
ただ、上永谷は住宅地なので、これだけ一つのチェーン店が集中して出店する状態が維持できるのか、今後の動向に注目していきたいと思います。
このように、同一のチェーン店を集中的に出店することをドミナント戦略と表現します。
一見、過当競合のため、お互いに顧客を奪い合ったり経営効率が悪いように思えますが、︵本部にとっては︶地域内でのシェアを拡大し、競合他社と差別化したり、それぞれ店舗ごとに役割分担したり、在庫供給の効率化を高めることができたりする効果があります。
ただ、上永谷は住宅地なので、これだけ一つのチェーン店が集中して出店する状態が維持できるのか、今後の動向に注目していきたいと思います。
 ファミリーマート上永谷駅前店
ところが、この出店場所のわずか30mほど先の上永谷駅構内にはファミリーマートがすでにあります。
さらに、その先、L-ウィングの広場にもファミリーマートがあります。
ファミリーマート上永谷駅前店
ところが、この出店場所のわずか30mほど先の上永谷駅構内にはファミリーマートがすでにあります。
さらに、その先、L-ウィングの広場にもファミリーマートがあります。
 ファミリーマートはまりん上永谷駅店
ファミリーマートサンズ上永谷L-ウィング店︵上写真の中央奥︶
ということで、おおよそ100mの間にファミリーマートが3店舗集中して出店していることになります。
このエリアに他系列のコンビニエンスストアは無し。
ファミリーマートはまりん上永谷駅店
ファミリーマートサンズ上永谷L-ウィング店︵上写真の中央奥︶
ということで、おおよそ100mの間にファミリーマートが3店舗集中して出店していることになります。
このエリアに他系列のコンビニエンスストアは無し。
 もう少し範囲を広げると、
ファミリーマート上永谷駅前店
ファミリーマートはまりん上永谷駅店
ファミリーマートサンズ上永谷L-ウィング店
の他に
ファミリーマート上永谷ニ丁目店
ファミリーマート丸山台一丁目店
などが徒歩圏にあります
もう少し範囲を広げると、
ファミリーマート上永谷駅前店
ファミリーマートはまりん上永谷駅店
ファミリーマートサンズ上永谷L-ウィング店
の他に
ファミリーマート上永谷ニ丁目店
ファミリーマート丸山台一丁目店
などが徒歩圏にあります
 このように、同一のチェーン店を集中的に出店することをドミナント戦略と表現します。
一見、過当競合のため、お互いに顧客を奪い合ったり経営効率が悪いように思えますが、︵本部にとっては︶地域内でのシェアを拡大し、競合他社と差別化したり、それぞれ店舗ごとに役割分担したり、在庫供給の効率化を高めることができたりする効果があります。
ただ、上永谷は住宅地なので、これだけ一つのチェーン店が集中して出店する状態が維持できるのか、今後の動向に注目していきたいと思います。
このように、同一のチェーン店を集中的に出店することをドミナント戦略と表現します。
一見、過当競合のため、お互いに顧客を奪い合ったり経営効率が悪いように思えますが、︵本部にとっては︶地域内でのシェアを拡大し、競合他社と差別化したり、それぞれ店舗ごとに役割分担したり、在庫供給の効率化を高めることができたりする効果があります。
ただ、上永谷は住宅地なので、これだけ一つのチェーン店が集中して出店する状態が維持できるのか、今後の動向に注目していきたいと思います。
2024年3月 6日
会計三昧も一区切り
今週前半、ある程度時間に余裕が出来たので、個人所得の確定申告を済ませました。

よく誤解をされるところではありますが、僧侶だからといって税金が軽減されることは無く、世間一般と同様に所得税が課税されます。 このあたりのところは、過去のブログ記事で言及していますので、そちらをご覧ください。 個人所得として計上されるうち、寺院からの給与は、寺院の法人会計からいただいており源泉徴収されています。 ︵寺院会計も、個人所得とは別に法人としての税務申告を行います︶ その他、寺院以外からの所得も雑所得等で漏れなく税務申告する必要があります。 最近では、YouTubeの収益が多少入るようになったので、その金額も雑所得として計上しています。
確定申告は3月15日まで。
個人所得について早めに申告することが出来たので、寺院会計の年度末決算作業も一気に進めました。 早めに作業を行っておくと、後々気が楽になります。

よく誤解をされるところではありますが、僧侶だからといって税金が軽減されることは無く、世間一般と同様に所得税が課税されます。 このあたりのところは、過去のブログ記事で言及していますので、そちらをご覧ください。 個人所得として計上されるうち、寺院からの給与は、寺院の法人会計からいただいており源泉徴収されています。 ︵寺院会計も、個人所得とは別に法人としての税務申告を行います︶ その他、寺院以外からの所得も雑所得等で漏れなく税務申告する必要があります。 最近では、YouTubeの収益が多少入るようになったので、その金額も雑所得として計上しています。
確定申告は3月15日まで。
個人所得について早めに申告することが出来たので、寺院会計の年度末決算作業も一気に進めました。 早めに作業を行っておくと、後々気が楽になります。
2024年1月10日
令和5年貞昌院の電力1年間の推移
令和5年︵2023年︶記録的な猛暑が続き、また円高や世界情勢に起因する燃料費の高騰の年でした。
貞昌院では電気料金の負担がどうだったかのまとめです。
結論としては、貞昌院の電気使用量は、ほぼ例年通り、電気料金は安くなっています。
令和5年1月から12月までの貞昌院の電力消費量、電気料金の推移は下記のとおりです。 東京電力の﹁ビジネスTEPCO﹂で、購入電力量の実績をグラフで表示しいます。
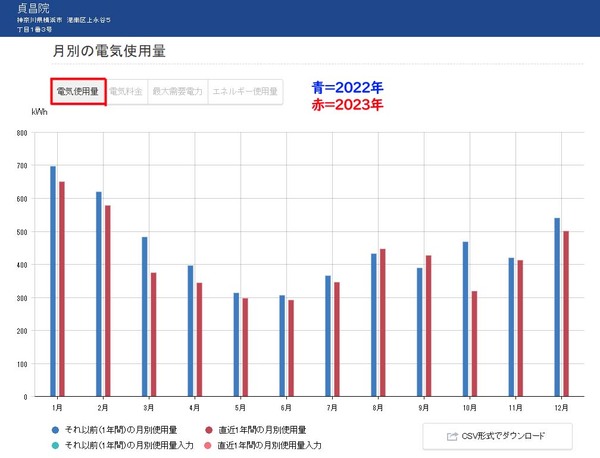 図1: 東京電力から購入した電力量の推移︵青=令和4年、赤=令和5年︶
図1: 東京電力から購入した電力量の推移︵青=令和4年、赤=令和5年︶
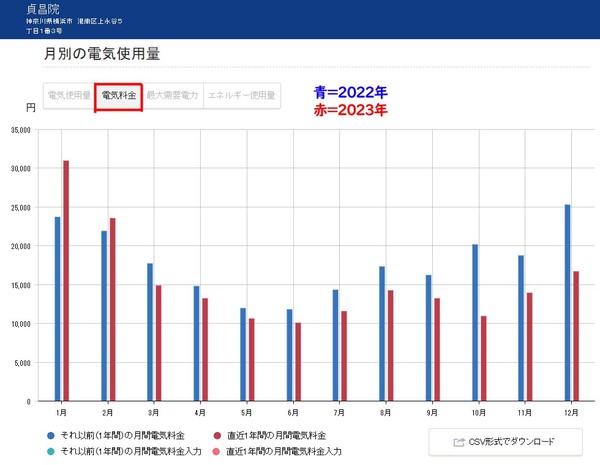 図2: 東京電力に支払った電気料金の推移︵青=令和4年、赤=令和5年︶
図2: 東京電力に支払った電気料金の推移︵青=令和4年、赤=令和5年︶
こうしてみると、令和4年と令和5年で、同月ではそれほど電力の使用量は変わらず推移していることが判ります。 対し、電気料金は、令和5年2月までは高騰していたことが判ります。 これは、燃料高騰による燃料調整額が反映されたことによります。 しかし、3月以降は、 国の電気およびガス料金軽減措置により、使用量に応じた値引き︵電気低圧▲3.5円/kWh、電気高圧▲1.8円/kWh、ガス▲15円/m3︶が含まれていることなどにより、結果、電気料金は昨年よりも下がっています。 なお、貞昌院では約10KWの太陽光発電設備を運用しているため、東京電力からの購入電力は、太陽光発電の発電量で賄えない分の購入電力量になります。 令和5年の冬至︵12月22日︶の一日の購入電力量の推移は下図のようになっています。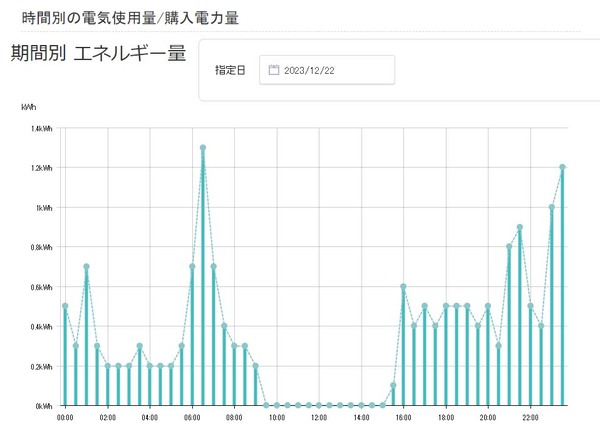 図3‥東京電力からの購入電力1日の推移︵令和5年12月22日の例︶
上図のように、日の出から日の入にかけての昼間は太陽光による発電量が、貞昌院の自己消費量を上回っていますので、完全に太陽光発電からの電力で賄うことができ、冬至であっても余剰電力を東京電力側に逆潮流させ電気を戻すことができています。
貞昌院における令和5年、1年間の電力に関する総括はこのような感じでした。
政府の補助政策があるにせよ、当面の間は燃料高騰の傾向は続くと思われますので、電力消費、電気料金の推移には引続き注視していくことが必要になりそうです。
図3‥東京電力からの購入電力1日の推移︵令和5年12月22日の例︶
上図のように、日の出から日の入にかけての昼間は太陽光による発電量が、貞昌院の自己消費量を上回っていますので、完全に太陽光発電からの電力で賄うことができ、冬至であっても余剰電力を東京電力側に逆潮流させ電気を戻すことができています。
貞昌院における令和5年、1年間の電力に関する総括はこのような感じでした。
政府の補助政策があるにせよ、当面の間は燃料高騰の傾向は続くと思われますので、電力消費、電気料金の推移には引続き注視していくことが必要になりそうです。
令和5年1月から12月までの貞昌院の電力消費量、電気料金の推移は下記のとおりです。 東京電力の﹁ビジネスTEPCO﹂で、購入電力量の実績をグラフで表示しいます。
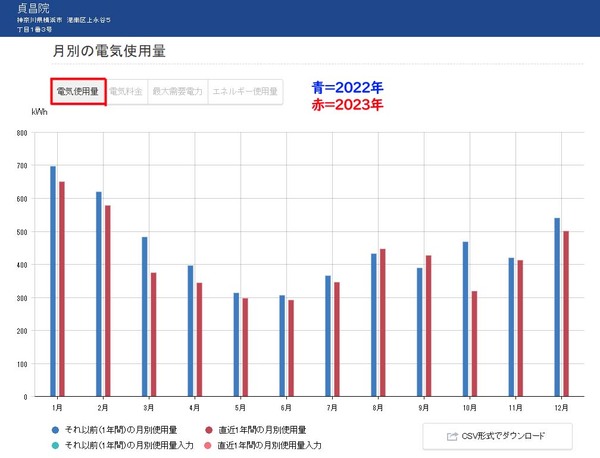 図1: 東京電力から購入した電力量の推移︵青=令和4年、赤=令和5年︶
図1: 東京電力から購入した電力量の推移︵青=令和4年、赤=令和5年︶
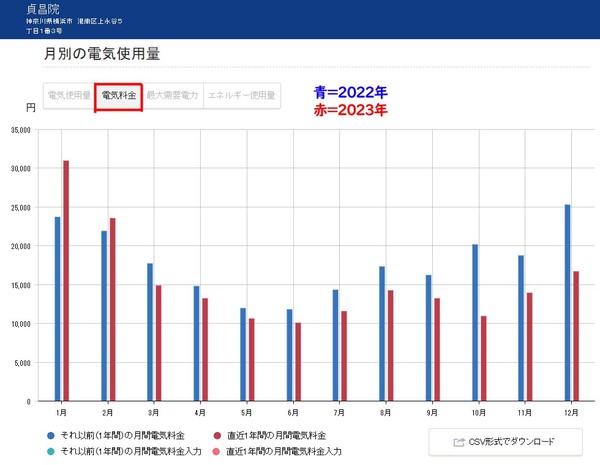 図2: 東京電力に支払った電気料金の推移︵青=令和4年、赤=令和5年︶
図2: 東京電力に支払った電気料金の推移︵青=令和4年、赤=令和5年︶
こうしてみると、令和4年と令和5年で、同月ではそれほど電力の使用量は変わらず推移していることが判ります。 対し、電気料金は、令和5年2月までは高騰していたことが判ります。 これは、燃料高騰による燃料調整額が反映されたことによります。 しかし、3月以降は、 国の電気およびガス料金軽減措置により、使用量に応じた値引き︵電気低圧▲3.5円/kWh、電気高圧▲1.8円/kWh、ガス▲15円/m3︶が含まれていることなどにより、結果、電気料金は昨年よりも下がっています。 なお、貞昌院では約10KWの太陽光発電設備を運用しているため、東京電力からの購入電力は、太陽光発電の発電量で賄えない分の購入電力量になります。 令和5年の冬至︵12月22日︶の一日の購入電力量の推移は下図のようになっています。
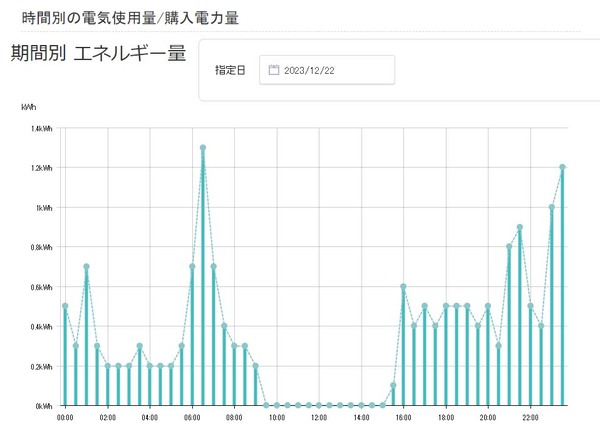 図3‥東京電力からの購入電力1日の推移︵令和5年12月22日の例︶
上図のように、日の出から日の入にかけての昼間は太陽光による発電量が、貞昌院の自己消費量を上回っていますので、完全に太陽光発電からの電力で賄うことができ、冬至であっても余剰電力を東京電力側に逆潮流させ電気を戻すことができています。
貞昌院における令和5年、1年間の電力に関する総括はこのような感じでした。
政府の補助政策があるにせよ、当面の間は燃料高騰の傾向は続くと思われますので、電力消費、電気料金の推移には引続き注視していくことが必要になりそうです。
図3‥東京電力からの購入電力1日の推移︵令和5年12月22日の例︶
上図のように、日の出から日の入にかけての昼間は太陽光による発電量が、貞昌院の自己消費量を上回っていますので、完全に太陽光発電からの電力で賄うことができ、冬至であっても余剰電力を東京電力側に逆潮流させ電気を戻すことができています。
貞昌院における令和5年、1年間の電力に関する総括はこのような感じでした。
政府の補助政策があるにせよ、当面の間は燃料高騰の傾向は続くと思われますので、電力消費、電気料金の推移には引続き注視していくことが必要になりそうです。
2022年3月 6日
iモードに感謝を込めて
NTTドコモの﹁iモード(i-mode)﹂は新規受付を2019年9月30日で既に終了、2026年3月31日のFOMA停波と共にサービス終了することになっています。
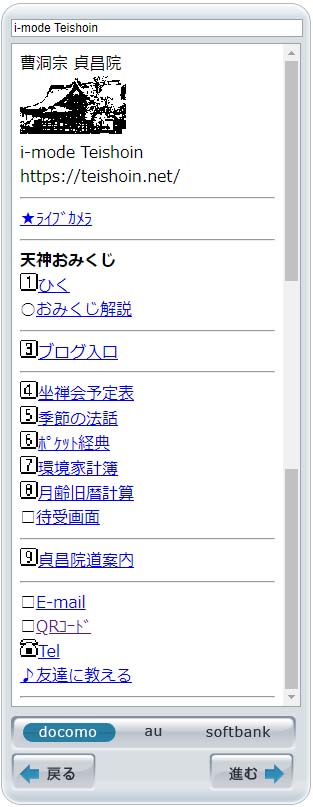 iモードは、ガラケーからインターネットに接続し、独自のブラウザを通して様々なサイトにアクセスできる日本が生み出した画期的な通信サービスでした。
インターネット黎明期は、通信料金が非常に高額で、その料金体系も通信時間で課金されていることも普通でした。
そこで、料金を通信時間ではなく、通信量としての﹁パケット﹂を単位として課金する制度が生みだされました。
この制度により、ガラケー側で情報のやり取りをするときだけ接続を行うことで、通信料金を抑えることができるようになったのです。
さらに、情報発信側も、﹁Compact HTML﹂に則り、かつ、パケット量が少なくて済むようなサイト作りを行うことで、パケット量を最小限にしつつも便利な機能が維持できる﹁iモード﹂の魅力を引出したことも大きな要因と言えます。
2010年7月には契約数が4900万件を突破し、まさにガラケーを利用してる方の大部分の方が利用していました。
さて、前置きは長くなりましたが、貞昌院のサイトにおいても、iモードサービス開始時から、iモード用のサイトを併設しております。
右メニューバーに i-mode の入口がありますので、クリックしてみてください。
i-mode入口
iモードは、ガラケーからインターネットに接続し、独自のブラウザを通して様々なサイトにアクセスできる日本が生み出した画期的な通信サービスでした。
インターネット黎明期は、通信料金が非常に高額で、その料金体系も通信時間で課金されていることも普通でした。
そこで、料金を通信時間ではなく、通信量としての﹁パケット﹂を単位として課金する制度が生みだされました。
この制度により、ガラケー側で情報のやり取りをするときだけ接続を行うことで、通信料金を抑えることができるようになったのです。
さらに、情報発信側も、﹁Compact HTML﹂に則り、かつ、パケット量が少なくて済むようなサイト作りを行うことで、パケット量を最小限にしつつも便利な機能が維持できる﹁iモード﹂の魅力を引出したことも大きな要因と言えます。
2010年7月には契約数が4900万件を突破し、まさにガラケーを利用してる方の大部分の方が利用していました。
さて、前置きは長くなりましたが、貞昌院のサイトにおいても、iモードサービス開始時から、iモード用のサイトを併設しております。
右メニューバーに i-mode の入口がありますので、クリックしてみてください。
i-mode入口
ただ、ガラケーからではないと、どのような表示になっているか分からないという方のために、見え方をスクリーンショットしてみました。
実際の動作を見たい方は、エミュレーター gooモバイルのサイトビューワ に https://teishoin.net/i を入力してみてください。 貞昌院のiモードサイトは、2026年3月31日のサ終までの間は設置しておく予定です。
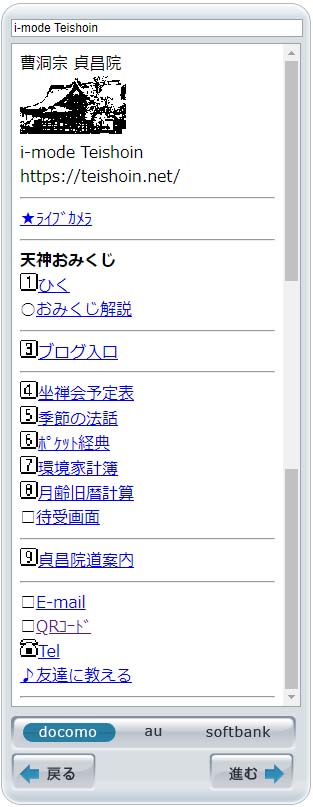 iモードは、ガラケーからインターネットに接続し、独自のブラウザを通して様々なサイトにアクセスできる日本が生み出した画期的な通信サービスでした。
インターネット黎明期は、通信料金が非常に高額で、その料金体系も通信時間で課金されていることも普通でした。
そこで、料金を通信時間ではなく、通信量としての﹁パケット﹂を単位として課金する制度が生みだされました。
この制度により、ガラケー側で情報のやり取りをするときだけ接続を行うことで、通信料金を抑えることができるようになったのです。
さらに、情報発信側も、﹁Compact HTML﹂に則り、かつ、パケット量が少なくて済むようなサイト作りを行うことで、パケット量を最小限にしつつも便利な機能が維持できる﹁iモード﹂の魅力を引出したことも大きな要因と言えます。
2010年7月には契約数が4900万件を突破し、まさにガラケーを利用してる方の大部分の方が利用していました。
さて、前置きは長くなりましたが、貞昌院のサイトにおいても、iモードサービス開始時から、iモード用のサイトを併設しております。
右メニューバーに i-mode の入口がありますので、クリックしてみてください。
i-mode入口
iモードは、ガラケーからインターネットに接続し、独自のブラウザを通して様々なサイトにアクセスできる日本が生み出した画期的な通信サービスでした。
インターネット黎明期は、通信料金が非常に高額で、その料金体系も通信時間で課金されていることも普通でした。
そこで、料金を通信時間ではなく、通信量としての﹁パケット﹂を単位として課金する制度が生みだされました。
この制度により、ガラケー側で情報のやり取りをするときだけ接続を行うことで、通信料金を抑えることができるようになったのです。
さらに、情報発信側も、﹁Compact HTML﹂に則り、かつ、パケット量が少なくて済むようなサイト作りを行うことで、パケット量を最小限にしつつも便利な機能が維持できる﹁iモード﹂の魅力を引出したことも大きな要因と言えます。
2010年7月には契約数が4900万件を突破し、まさにガラケーを利用してる方の大部分の方が利用していました。
さて、前置きは長くなりましたが、貞昌院のサイトにおいても、iモードサービス開始時から、iモード用のサイトを併設しております。
右メニューバーに i-mode の入口がありますので、クリックしてみてください。
i-mode入口
ただ、ガラケーからではないと、どのような表示になっているか分からないという方のために、見え方をスクリーンショットしてみました。
実際の動作を見たい方は、エミュレーター gooモバイルのサイトビューワ に https://teishoin.net/i を入力してみてください。 貞昌院のiモードサイトは、2026年3月31日のサ終までの間は設置しておく予定です。
2021年10月21日
MM21で電動キックボードの実証実験開始
横浜みなとみらい地区で、電動キックボードのシェアリング実証実験が開始されました。
期間は2021年10月21日から2022年3月31日まで。
みなとみらい地区内の5カ所に設置されたポートに電動キックボードが40台を設置され、専用アプリで免許証の登録をしアプリ内でのテストに合格すると利用ができます。
︵詳細は本記事下部に掲載︶
実証実験初日にドックヤードガーデンで説明会が行われていましたので参加してみました。

 社会実証実験初日ということもあって、神奈川県警察、事業主体Luup、横浜みなとみらい21、横浜市都市整備局などからの代表も参加され、意気込みを感じさせられます。
社会実証実験初日ということもあって、神奈川県警察、事業主体Luup、横浜みなとみらい21、横浜市都市整備局などからの代表も参加され、意気込みを感じさせられます。
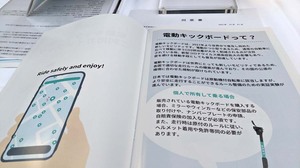
 まずは、簡単な説明を受けてドッグヤードガーデン内を試走します。
まずは、簡単な説明を受けてドッグヤードガーデン内を試走します。

30分の無料クーポンがもらえるので、早速公道に出て走ってきました。 音もなくス~っと走るので、気持ちよく街を巡ることができます。
なお、電動キックボードは小型特殊を運転することができる免許が必須となり、走行スピードは時速15kmに制限され、走行可能な区間はなとみらい21地区に限られています。 基本は車道の左側、または自転車専用区間を走行する必要があり、歩道では走行禁止。降りて押して歩くことになります。 また、通常はヘルメット着用が義務付けられますが、今回は産業競争力強化法に基づく﹁新事業特例制度﹂で認可された事業者が貸し出す﹁特例電動キックボード﹂にあたり、ヘルメット着用は任意となります。 その他、特別なルールもありますので、下記のアプリで確認の上の乗車が必要でしょう。 公道を走る際は、他の自動車との速度差が大きいため、お互いの安全確認は十分に行うことも大切です。
■プレスリリース
みなとみらい21地区で電動キックボードシェアリングサービスの実証実験がスタートします!(PDF)
︵都市整備局都心再生部横浜駅・みなとみらい推進課︶
 横浜市都市整備局や(一社)横浜みなとみらい21、(株)Luupは共同で、みなとみらい21地区で電動キックボードの利活用による地区の魅力や回遊性を高める交通ネットワークの充実やラストワンマイルの移動課題の軽減等を推進するため、電動キックボードシェアリングサービスの実証実験を2021年10月21日(木)から2022年3月31日(木)まで実施します。
同実験は、MM21地区内のポート︵停留所︶にある電動キックボードに乗車し、指定したポートに返せるシェアリングサービスです。
︻サービス期間︼
2021年10月21日(木)~2022年3月31日(木)
︻対象エリア︼
みなとみらい21地区
︻利用条件︼
専用スマートフォンアプリ﹁LUUP﹂をダウンロードの上、会員登録・免許証登録・走行ルールの確認テストに合格したのち、乗車可能
︻料 金︼
初乗り10分 110円、それ以降1分 16.5円︵税込︶
︻主要ポート候補地︼
横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、53街区︵新高島駅至近︶などを予定
※順次拡大予定
︻特例措置の内容(一部)︼
・ヘルメットの着用任意
・車道に加えて、普通自転車専用通行帯、自転車道、一方通行だが自転車が双方向通行可とされている車道の走行が可能
・道路交通法上は小型特殊自動車の扱いとなり、最高速度は15km/h
◆利用登録後の使用方法
①アプリ﹁LUUP﹂を開きライド開始したいポートを探す
②見つけて電動キックボードを選ぶ
③ポートに着いたらアプリを立ち上げて車体のQRコードをスキャンする
④目的地を設定したらライド開始!
横浜市都市整備局や(一社)横浜みなとみらい21、(株)Luupは共同で、みなとみらい21地区で電動キックボードの利活用による地区の魅力や回遊性を高める交通ネットワークの充実やラストワンマイルの移動課題の軽減等を推進するため、電動キックボードシェアリングサービスの実証実験を2021年10月21日(木)から2022年3月31日(木)まで実施します。
同実験は、MM21地区内のポート︵停留所︶にある電動キックボードに乗車し、指定したポートに返せるシェアリングサービスです。
︻サービス期間︼
2021年10月21日(木)~2022年3月31日(木)
︻対象エリア︼
みなとみらい21地区
︻利用条件︼
専用スマートフォンアプリ﹁LUUP﹂をダウンロードの上、会員登録・免許証登録・走行ルールの確認テストに合格したのち、乗車可能
︻料 金︼
初乗り10分 110円、それ以降1分 16.5円︵税込︶
︻主要ポート候補地︼
横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、53街区︵新高島駅至近︶などを予定
※順次拡大予定
︻特例措置の内容(一部)︼
・ヘルメットの着用任意
・車道に加えて、普通自転車専用通行帯、自転車道、一方通行だが自転車が双方向通行可とされている車道の走行が可能
・道路交通法上は小型特殊自動車の扱いとなり、最高速度は15km/h
◆利用登録後の使用方法
①アプリ﹁LUUP﹂を開きライド開始したいポートを探す
②見つけて電動キックボードを選ぶ
③ポートに着いたらアプリを立ち上げて車体のQRコードをスキャンする
④目的地を設定したらライド開始!

 社会実証実験初日ということもあって、神奈川県警察、事業主体Luup、横浜みなとみらい21、横浜市都市整備局などからの代表も参加され、意気込みを感じさせられます。
社会実証実験初日ということもあって、神奈川県警察、事業主体Luup、横浜みなとみらい21、横浜市都市整備局などからの代表も参加され、意気込みを感じさせられます。
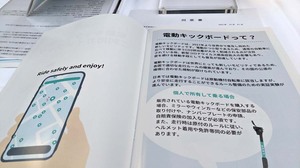
 まずは、簡単な説明を受けてドッグヤードガーデン内を試走します。
まずは、簡単な説明を受けてドッグヤードガーデン内を試走します。

30分の無料クーポンがもらえるので、早速公道に出て走ってきました。 音もなくス~っと走るので、気持ちよく街を巡ることができます。
なお、電動キックボードは小型特殊を運転することができる免許が必須となり、走行スピードは時速15kmに制限され、走行可能な区間はなとみらい21地区に限られています。 基本は車道の左側、または自転車専用区間を走行する必要があり、歩道では走行禁止。降りて押して歩くことになります。 また、通常はヘルメット着用が義務付けられますが、今回は産業競争力強化法に基づく﹁新事業特例制度﹂で認可された事業者が貸し出す﹁特例電動キックボード﹂にあたり、ヘルメット着用は任意となります。 その他、特別なルールもありますので、下記のアプリで確認の上の乗車が必要でしょう。 公道を走る際は、他の自動車との速度差が大きいため、お互いの安全確認は十分に行うことも大切です。
 横浜市都市整備局や(一社)横浜みなとみらい21、(株)Luupは共同で、みなとみらい21地区で電動キックボードの利活用による地区の魅力や回遊性を高める交通ネットワークの充実やラストワンマイルの移動課題の軽減等を推進するため、電動キックボードシェアリングサービスの実証実験を2021年10月21日(木)から2022年3月31日(木)まで実施します。
同実験は、MM21地区内のポート︵停留所︶にある電動キックボードに乗車し、指定したポートに返せるシェアリングサービスです。
︻サービス期間︼
2021年10月21日(木)~2022年3月31日(木)
︻対象エリア︼
みなとみらい21地区
︻利用条件︼
専用スマートフォンアプリ﹁LUUP﹂をダウンロードの上、会員登録・免許証登録・走行ルールの確認テストに合格したのち、乗車可能
︻料 金︼
初乗り10分 110円、それ以降1分 16.5円︵税込︶
︻主要ポート候補地︼
横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、53街区︵新高島駅至近︶などを予定
※順次拡大予定
︻特例措置の内容(一部)︼
・ヘルメットの着用任意
・車道に加えて、普通自転車専用通行帯、自転車道、一方通行だが自転車が双方向通行可とされている車道の走行が可能
・道路交通法上は小型特殊自動車の扱いとなり、最高速度は15km/h
◆利用登録後の使用方法
①アプリ﹁LUUP﹂を開きライド開始したいポートを探す
②見つけて電動キックボードを選ぶ
③ポートに着いたらアプリを立ち上げて車体のQRコードをスキャンする
④目的地を設定したらライド開始!
横浜市都市整備局や(一社)横浜みなとみらい21、(株)Luupは共同で、みなとみらい21地区で電動キックボードの利活用による地区の魅力や回遊性を高める交通ネットワークの充実やラストワンマイルの移動課題の軽減等を推進するため、電動キックボードシェアリングサービスの実証実験を2021年10月21日(木)から2022年3月31日(木)まで実施します。
同実験は、MM21地区内のポート︵停留所︶にある電動キックボードに乗車し、指定したポートに返せるシェアリングサービスです。
︻サービス期間︼
2021年10月21日(木)~2022年3月31日(木)
︻対象エリア︼
みなとみらい21地区
︻利用条件︼
専用スマートフォンアプリ﹁LUUP﹂をダウンロードの上、会員登録・免許証登録・走行ルールの確認テストに合格したのち、乗車可能
︻料 金︼
初乗り10分 110円、それ以降1分 16.5円︵税込︶
︻主要ポート候補地︼
横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、53街区︵新高島駅至近︶などを予定
※順次拡大予定
︻特例措置の内容(一部)︼
・ヘルメットの着用任意
・車道に加えて、普通自転車専用通行帯、自転車道、一方通行だが自転車が双方向通行可とされている車道の走行が可能
・道路交通法上は小型特殊自動車の扱いとなり、最高速度は15km/h
◆利用登録後の使用方法
①アプリ﹁LUUP﹂を開きライド開始したいポートを探す
②見つけて電動キックボードを選ぶ
③ポートに着いたらアプリを立ち上げて車体のQRコードをスキャンする
④目的地を設定したらライド開始!
2021年5月16日
「東神奈川駅」の改善案(横浜線ー京浜東北線)
今朝の神奈川新聞1面に次にような記事が掲載されていました。
ネットでも閲覧できますので、リンクを引用します。
横浜駅まで行かない横浜線︵上︶東神奈川駅の朝、まるで苦行
︵神奈川新聞 | 2021年5月16日︶
長い記事なので、引用は控えますが、要約するとJR﹁横浜線﹂︵東神奈川ー八王子︶の電車の大半が横浜駅まで到達しないのに、なぜ﹁横浜線﹂と名乗るのか?ということと、東神奈川から先の京浜東北線~横浜・桜木町方面に乗り入れることが難しい理由などが書かれています。
確かに、京浜東北線の過密ダイヤの隙間に横浜線を乗り入れることは難しいため、専用線を作らない限りこれ以上の乗り入れは難しいでしょう。
横浜駅、桜木町を通過する専用線を作ることも難しいでしょう。
けれども、横浜線の不便さは、むしろ、東神奈川での横浜線 ←→ 京浜東北線 の乗り換えのし難さが大きいのだと思います。
現状を見てみましょう。
 (JRのサイトから東神奈川駅の構内図を引用しました)
(JRのサイトから東神奈川駅の構内図を引用しました)
︻東神奈川駅の構造︼ 10両編成対応の島式ホーム2面4線を有し、橋上駅舎が設置されている地上駅である。ホームは北東から南西に延び、東口および西口を持つ。改札とホームは南側から階段・エレベーター・上下各1台のエスカレーターで連絡しているほか、北側に乗換え専用の階段がある。 当駅の北方で京浜東北線の複線の内側から横浜線の複線が分岐し、高架で東海道・横須賀・京浜東北の各線を乗り越えていく。外側2線を京浜東北線、内側2線を横浜線が使用する。また、横浜線および京浜東北線・根岸線の車両基地として鎌倉車両センター東神奈川派出所が北東側に併設されている。 東神奈川駅の番線は東から順に付番され、東側のホームに1・2番線、西側のホームに3・4番線を設置している。京浜東北線電車と横浜線電車で使用番線を分けているが、一部2番線から京浜東北線電車が発車する。 1番線 京浜東北線・根岸線 南行 横浜・関内・大船方面 2番線 横浜線からの直通列車 2・3番線 横浜線 下り 新横浜・町田・橋本・八王子方面 一部列車は4番線 4番線 京浜東北線 北行 品川・東京・上野・大宮方面 一部列車は2番線 ︵出典‥JR東日本:駅構内図︶ 京浜東北線においては、早朝と平日朝ラッシュ時に各1本横浜方面へ、平日夕方に1本東京方面へ、それぞれ当駅始発電車が設定されている。 留置線から4番線へは直接進入できない構造になっている。このため、京浜東北線北行︵東京方面︶の平日16時台の当駅始発は2番線を使用する。 ︵ウィキペディア東神奈川駅 項より引用︶
このような構造になっているため、京浜東北線に乗り入れず、東神奈川で折り返す横浜線は、2番線または3番線のどちらかに、ほぼ半々の確率で留まります。 このため、横浜から京浜東北線を使い、新横浜・八王子方面に向かう場合は、東神奈川で横浜線に乗り換える際、同じホームの反対側の横浜線に乗れるか、階段を登って向こう側のホームの横浜線に乗り換えるか、どちらかということになります。 八王子・新横浜方面から横浜に向かう際の東神奈川での乗り換えも同じです。 この、階段を登って向こうのホームへ渡るという部分が、特に通勤のラッシュアワーの際に混乱を招きます。
そこで、それほど費用をかけずに、この部分の問題を解決する方法を提示します。 それは ︵1︶東神奈川駅での2-3番線横浜線の停車位置を大口駅側にずらす。 ︵2︶東神奈川駅の横浜駅側に横浜線専用の折り返し用待避線を新設する。 という提案です。 これにより、
1番線 京浜東北線・根岸線 南行 横浜・関内・大船方面
2番線 横浜線 上り
3番線 横浜線 下り 新横浜・町田・橋本・八王子方面
4番線 京浜東北線 北行 品川・東京・上野・大宮方面
と固定することができます。
東神奈川で折り返す横浜線は、2番線に到着後、折り返し待避線に入り、折り返して3番線ホームへ。
東神奈川から京浜東北線に乗り入れる横浜線は、2番線に到着後、そのまま京浜東北線に乗り入れればよいのです。
これにより、京浜東北線と横浜線の乗り換えは、同じホームの反対側に行くだけで済みますから、階段の登り降りが不要になり、利便性が大幅に向上します。
Googleマップを見ても、折り返し用の待避線を設置するスペースは十分に確保できそうです。 ■現状︵クリックすると拡大します︶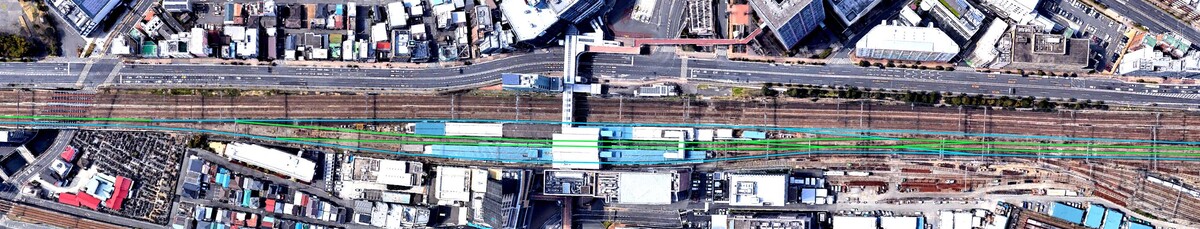
■折り返し待避線設置案︵クリックすると拡大します・下図だと待避線の長さがギリギリですが、横浜線は8両の短い編成なので横浜線ホーム停車位置を少し右側にずらすことにより解決できます。︶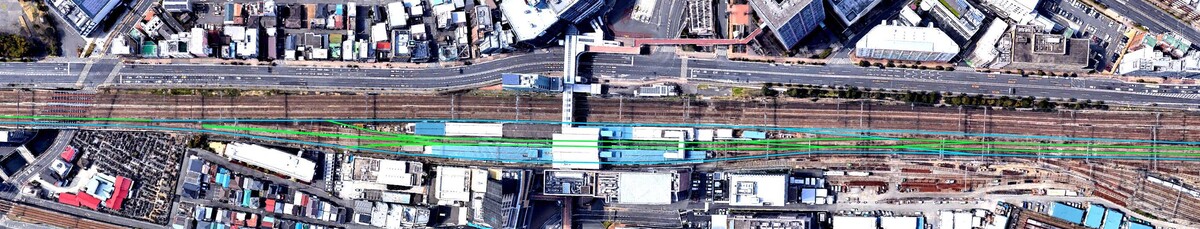
JR様、ご検討いただけないでしょうか。
けれども、横浜線の不便さは、むしろ、東神奈川での横浜線 ←→ 京浜東北線 の乗り換えのし難さが大きいのだと思います。
現状を見てみましょう。
 (JRのサイトから東神奈川駅の構内図を引用しました)
(JRのサイトから東神奈川駅の構内図を引用しました)
︻東神奈川駅の構造︼ 10両編成対応の島式ホーム2面4線を有し、橋上駅舎が設置されている地上駅である。ホームは北東から南西に延び、東口および西口を持つ。改札とホームは南側から階段・エレベーター・上下各1台のエスカレーターで連絡しているほか、北側に乗換え専用の階段がある。 当駅の北方で京浜東北線の複線の内側から横浜線の複線が分岐し、高架で東海道・横須賀・京浜東北の各線を乗り越えていく。外側2線を京浜東北線、内側2線を横浜線が使用する。また、横浜線および京浜東北線・根岸線の車両基地として鎌倉車両センター東神奈川派出所が北東側に併設されている。 東神奈川駅の番線は東から順に付番され、東側のホームに1・2番線、西側のホームに3・4番線を設置している。京浜東北線電車と横浜線電車で使用番線を分けているが、一部2番線から京浜東北線電車が発車する。 1番線 京浜東北線・根岸線 南行 横浜・関内・大船方面 2番線 横浜線からの直通列車 2・3番線 横浜線 下り 新横浜・町田・橋本・八王子方面 一部列車は4番線 4番線 京浜東北線 北行 品川・東京・上野・大宮方面 一部列車は2番線 ︵出典‥JR東日本:駅構内図︶ 京浜東北線においては、早朝と平日朝ラッシュ時に各1本横浜方面へ、平日夕方に1本東京方面へ、それぞれ当駅始発電車が設定されている。 留置線から4番線へは直接進入できない構造になっている。このため、京浜東北線北行︵東京方面︶の平日16時台の当駅始発は2番線を使用する。 ︵ウィキペディア東神奈川駅 項より引用︶
このような構造になっているため、京浜東北線に乗り入れず、東神奈川で折り返す横浜線は、2番線または3番線のどちらかに、ほぼ半々の確率で留まります。 このため、横浜から京浜東北線を使い、新横浜・八王子方面に向かう場合は、東神奈川で横浜線に乗り換える際、同じホームの反対側の横浜線に乗れるか、階段を登って向こう側のホームの横浜線に乗り換えるか、どちらかということになります。 八王子・新横浜方面から横浜に向かう際の東神奈川での乗り換えも同じです。 この、階段を登って向こうのホームへ渡るという部分が、特に通勤のラッシュアワーの際に混乱を招きます。
そこで、それほど費用をかけずに、この部分の問題を解決する方法を提示します。 それは ︵1︶東神奈川駅での2-3番線横浜線の停車位置を大口駅側にずらす。 ︵2︶東神奈川駅の横浜駅側に横浜線専用の折り返し用待避線を新設する。 という提案です。 これにより、
Googleマップを見ても、折り返し用の待避線を設置するスペースは十分に確保できそうです。 ■現状︵クリックすると拡大します︶
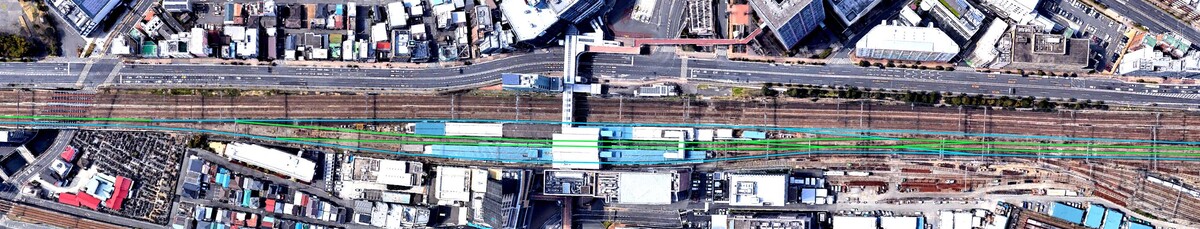
■折り返し待避線設置案︵クリックすると拡大します・下図だと待避線の長さがギリギリですが、横浜線は8両の短い編成なので横浜線ホーム停車位置を少し右側にずらすことにより解決できます。︶
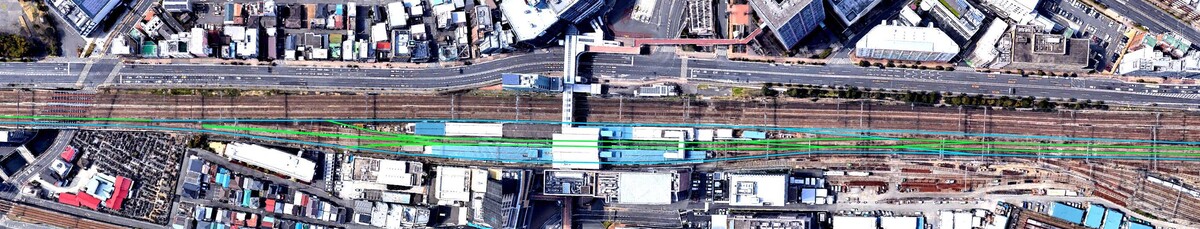
JR様、ご検討いただけないでしょうか。
2020年3月22日
首都高速・横浜北西線が開通
首都高速・横浜北西線が開通 東名~横浜港・羽田を直結
東名高速道路と第三京浜道路をつなぐ首都高速道路﹁横浜北西線﹂が22日午後、開通した。横浜港方面や羽田空港と東名高速が直結し、物流や観光の活性化が期待される。 北西線は、東名高速の横浜青葉インターチェンジ︵IC、横浜市青葉区︶と、第三京浜の港北IC︵同市都筑区︶を結ぶ片側2車線の延長7・1キロ。うち4・1キロがトンネル部となる。 港北ICでは2017年に開通した首都高﹁横浜北線﹂︵約8・2キロ︶と接続。東名高速から横浜港までの所要時間は、保土ケ谷バイパス︵BP︶を経由した場合の40~60分程度から20分程度に短縮し、アクセス性が改善した。 慢性的に混雑している保土ケ谷BPや、港北ニュータウン地区など周辺にある市道の渋滞緩和も見込まれる。災害時は東名高速から市内への救援物資の輸送網や、災害拠点病院への救急搬送網が充実する。 市によると、用地取得や工事が順調に進んだことで当初は22年だった開通予定を前倒しした。開通を前に予定していた記念イベントは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止された。 (カナロコ 2020/3/22配信)2020年3月22日午後4時、首都高速道路 横浜北西線が開通し、供用がはじまりました。 これまで開通していた首都高速道路 横浜北線・第三京浜の横浜港北JCTから、東名高速横浜青葉JCTまでが結ばれたことにより、東名高速道路から横浜市中心部、横浜港方面へのアクセス利便性が一気に向上することになります。 保土ヶ谷バイパスなど、複数のルートができたことにより、慢性的な交通渋滞解消や、災害時の緊急搬送への役割も期待されます。︵上図は首都高速道路公団のプレスリリースより引用︶
なお、今回開通したは延長約 7.1kmのうち、半分以上の 4.1kmはトンネル構造となっています。 横浜北西線の開通により、東名高速道路から大黒ふ頭までの所要時間が、これまでの約40~60分から約20分へと大幅に短縮されるということです。
開通初日、さっそくスバル360で走ってきました。 東名高速道路 青葉ICから横浜港まで20分程でアクセスできるので、利便性が飛躍的に向上しますね。ドライブレコーダによる前面展望動画です。
2019年12月17日
高輪ゲートウェイ駅と再開発
高輪ゲートウェイ駅の工事が進んでいます。
山手線・京浜東北線の新駅として設置される高輪ゲートウェイ駅は、は、品川駅ー田町駅間に位置し、来年・2020年春に開業予定となっています。
現在の様子です。
 新駅のデザインは、建築家・隈研吾氏が担当し、日本の伝統的な折り紙をモチーフにした屋根形状が特徴です。
だいぶ形が見えてきましたね。
2019年11月15日から17日に行われた線路切替工事によって、山手線・京浜東北線の線路が東側にずらされました。
かつての山手線・京浜東北線の線路部分は、これから撤去され、再開発の敷地に供されます。
新駅のデザインは、建築家・隈研吾氏が担当し、日本の伝統的な折り紙をモチーフにした屋根形状が特徴です。
だいぶ形が見えてきましたね。
2019年11月15日から17日に行われた線路切替工事によって、山手線・京浜東北線の線路が東側にずらされました。
かつての山手線・京浜東北線の線路部分は、これから撤去され、再開発の敷地に供されます。
 高輪ゲートウェイ駅周辺一帯は、品川開発プロジェクト1期(高輪ゲートウェイ駅周辺再開発)として、国道15号線から東側の一帯に広がる、山手線・京浜東北線のかつての線路部分および品川車両基地の跡地で進められています。。
完成すると、このような高層ビルが並ぶ光景に変貌します。
高輪ゲートウェイ駅周辺一帯は、品川開発プロジェクト1期(高輪ゲートウェイ駅周辺再開発)として、国道15号線から東側の一帯に広がる、山手線・京浜東北線のかつての線路部分および品川車両基地の跡地で進められています。。
完成すると、このような高層ビルが並ぶ光景に変貌します。
 ︵上図は都市計画素案より引用︶
詳細は、都市再生特別地区︵品川駅北周辺地区︶都市計画︵素案︶の概要 をご覧ください。
2019年11月15日から17日かけて行われた、山手線︵内回り・外回り︶および京浜東北線︵北行・大宮方面︶の線路切替工事によって、どのようにルートが変わったのか、比較動画を作成しました。
線路切替工事前後の京浜東北線前面展望の比較です。
東京オリンピックを契機に、東京都心のあちらこちらで大きなプロジェクトが進行しています。
︵上図は都市計画素案より引用︶
詳細は、都市再生特別地区︵品川駅北周辺地区︶都市計画︵素案︶の概要 をご覧ください。
2019年11月15日から17日かけて行われた、山手線︵内回り・外回り︶および京浜東北線︵北行・大宮方面︶の線路切替工事によって、どのようにルートが変わったのか、比較動画を作成しました。
線路切替工事前後の京浜東北線前面展望の比較です。
東京オリンピックを契機に、東京都心のあちらこちらで大きなプロジェクトが進行しています。
 新駅のデザインは、建築家・隈研吾氏が担当し、日本の伝統的な折り紙をモチーフにした屋根形状が特徴です。
だいぶ形が見えてきましたね。
2019年11月15日から17日に行われた線路切替工事によって、山手線・京浜東北線の線路が東側にずらされました。
かつての山手線・京浜東北線の線路部分は、これから撤去され、再開発の敷地に供されます。
新駅のデザインは、建築家・隈研吾氏が担当し、日本の伝統的な折り紙をモチーフにした屋根形状が特徴です。
だいぶ形が見えてきましたね。
2019年11月15日から17日に行われた線路切替工事によって、山手線・京浜東北線の線路が東側にずらされました。
かつての山手線・京浜東北線の線路部分は、これから撤去され、再開発の敷地に供されます。
 高輪ゲートウェイ駅周辺一帯は、品川開発プロジェクト1期(高輪ゲートウェイ駅周辺再開発)として、国道15号線から東側の一帯に広がる、山手線・京浜東北線のかつての線路部分および品川車両基地の跡地で進められています。。
完成すると、このような高層ビルが並ぶ光景に変貌します。
高輪ゲートウェイ駅周辺一帯は、品川開発プロジェクト1期(高輪ゲートウェイ駅周辺再開発)として、国道15号線から東側の一帯に広がる、山手線・京浜東北線のかつての線路部分および品川車両基地の跡地で進められています。。
完成すると、このような高層ビルが並ぶ光景に変貌します。
 ︵上図は都市計画素案より引用︶
詳細は、都市再生特別地区︵品川駅北周辺地区︶都市計画︵素案︶の概要 をご覧ください。
2019年11月15日から17日かけて行われた、山手線︵内回り・外回り︶および京浜東北線︵北行・大宮方面︶の線路切替工事によって、どのようにルートが変わったのか、比較動画を作成しました。
線路切替工事前後の京浜東北線前面展望の比較です。
東京オリンピックを契機に、東京都心のあちらこちらで大きなプロジェクトが進行しています。
︵上図は都市計画素案より引用︶
詳細は、都市再生特別地区︵品川駅北周辺地区︶都市計画︵素案︶の概要 をご覧ください。
2019年11月15日から17日かけて行われた、山手線︵内回り・外回り︶および京浜東北線︵北行・大宮方面︶の線路切替工事によって、どのようにルートが変わったのか、比較動画を作成しました。
線路切替工事前後の京浜東北線前面展望の比較です。
東京オリンピックを契機に、東京都心のあちらこちらで大きなプロジェクトが進行しています。
2019年6月27日
勝海舟会見之地の再開発
昨年春から平日昼間は東京都港区の事務所に通勤しています。
その通勤途中で通る、JR田町駅・都営三田線三田駅前では、現在再開発が進行中です。

再開発プロジェクトの一つ、第一京浜・芝五丁目交差点付近にある田町第一ビルが53年の歴史に幕を閉じ、新しいビルへ建て替えられることになりました。 第一田町ビルは、勝海舟会見之地に建てられたビルで昭和41︵1966︶年に竣工。三菱自動車本社が入っており、車のショールームが特徴でした。
 ︵左︶三菱自動車のショールームも ︵右︶移転によって、ビルは空になっています。
ビルの取り壊しに向けて、棟下式プロジェクトが4か月にわたり行われており、ビルの壁面や正面の路面にたくさんのメッセージやイラストが残されました。
︵左︶三菱自動車のショールームも ︵右︶移転によって、ビルは空になっています。
ビルの取り壊しに向けて、棟下式プロジェクトが4か月にわたり行われており、ビルの壁面や正面の路面にたくさんのメッセージやイラストが残されました。
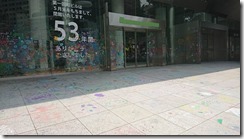
 鏡状の庇に反射することを計算して、鏡写しに書かれたメッセージやイラストもあります。
鏡状の庇に反射することを計算して、鏡写しに書かれたメッセージやイラストもあります。
 いよいよ取り壊しが始まり、(仮称)TTMプロジェクトが本格的に始動します。
この場所には、高さ約150m、延べ約131,000㎡の超高層ビルが建設され、2022年度頃に完成する見込みです。
高輪ゲートウェイから田町近辺の様相は、あと数年で一変することでしょう。
いよいよ取り壊しが始まり、(仮称)TTMプロジェクトが本格的に始動します。
この場所には、高さ約150m、延べ約131,000㎡の超高層ビルが建設され、2022年度頃に完成する見込みです。
高輪ゲートウェイから田町近辺の様相は、あと数年で一変することでしょう。


再開発プロジェクトの一つ、第一京浜・芝五丁目交差点付近にある田町第一ビルが53年の歴史に幕を閉じ、新しいビルへ建て替えられることになりました。 第一田町ビルは、勝海舟会見之地に建てられたビルで昭和41︵1966︶年に竣工。三菱自動車本社が入っており、車のショールームが特徴でした。

 ︵左︶三菱自動車のショールームも ︵右︶移転によって、ビルは空になっています。
ビルの取り壊しに向けて、棟下式プロジェクトが4か月にわたり行われており、ビルの壁面や正面の路面にたくさんのメッセージやイラストが残されました。
︵左︶三菱自動車のショールームも ︵右︶移転によって、ビルは空になっています。
ビルの取り壊しに向けて、棟下式プロジェクトが4か月にわたり行われており、ビルの壁面や正面の路面にたくさんのメッセージやイラストが残されました。
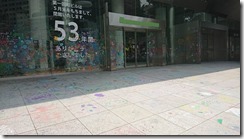
 鏡状の庇に反射することを計算して、鏡写しに書かれたメッセージやイラストもあります。
鏡状の庇に反射することを計算して、鏡写しに書かれたメッセージやイラストもあります。
 いよいよ取り壊しが始まり、(仮称)TTMプロジェクトが本格的に始動します。
この場所には、高さ約150m、延べ約131,000㎡の超高層ビルが建設され、2022年度頃に完成する見込みです。
高輪ゲートウェイから田町近辺の様相は、あと数年で一変することでしょう。
いよいよ取り壊しが始まり、(仮称)TTMプロジェクトが本格的に始動します。
この場所には、高さ約150m、延べ約131,000㎡の超高層ビルが建設され、2022年度頃に完成する見込みです。
高輪ゲートウェイから田町近辺の様相は、あと数年で一変することでしょう。

2019年6月20日
太陽光発電の買取制度がまもなく終了
太陽光発電など、新エネルギーから発電された電力の買取制度﹁エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律﹂︵平成21年法律第72号︶施行令は、新エネルギー普及促進の”国策”として2009年に始まりました。
当ブログでは、この買取制度がはじまった時期に記事を書いていますので、併せてご参照ください。
→太陽光発電の新買取制度
この買取制度は、10年間の買取期間が設定されておりますので、2019年以降順次、買取期間が満了を迎えることになります。
いわゆる新エネルギー買取制度の2019年問題です。
まずは、貞昌院での事例をもとに考えてみましょう。
貞昌院では、
・2003年に5kw規模の太陽光発電設備を設置、連携系統契約を東京電力と結ぶ。余剰電力買取約24円/kwh
・2009年に倍額買取制度開始。2010年より東京電力と余剰電力倍額買取約48円/kwh
・2014年太陽光発電設備を増設。合計9.9Kw規模となる
・2020年倍額買取契約終了予定
となっています。
この設置費用ー発電額をグラフにまとめたものを下図として示します。
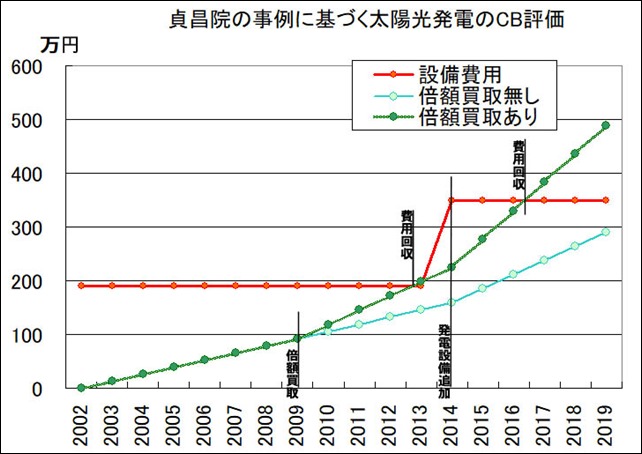 図中、太陽光発電設備の設置費用を赤線で引いています。
また、倍額買取を考慮した発電量を金額に置き換えたものを緑線で表しました。
緑線が赤線を上回った時点が、設置費用回収の時期と考えられます。
途中、設備増強のために費用が増えていますが、2013年、2016年には費用が回収できていることになります。
※参考のために、もしも倍額買取ができようされなかった場合を青線で付記しました。この場合、費用が回収できるのはおおむね2022年、つまり設置から約20年後ということになります。
では、買取制度が終了した後はどのようになるのでしょうか。
それについては、当ブログにおいては、昨年次のような記事を書きました。
→住宅用太陽光売電価格は11円/Kwhへ
図中、太陽光発電設備の設置費用を赤線で引いています。
また、倍額買取を考慮した発電量を金額に置き換えたものを緑線で表しました。
緑線が赤線を上回った時点が、設置費用回収の時期と考えられます。
途中、設備増強のために費用が増えていますが、2013年、2016年には費用が回収できていることになります。
※参考のために、もしも倍額買取ができようされなかった場合を青線で付記しました。この場合、費用が回収できるのはおおむね2022年、つまり設置から約20年後ということになります。
では、買取制度が終了した後はどのようになるのでしょうか。
それについては、当ブログにおいては、昨年次のような記事を書きました。
→住宅用太陽光売電価格は11円/Kwhへ
経済産業省のサイトでは、買取制度の終了についてのお知らせが掲載されています。 つまり、買取期間が終了した段階で、電力会社には法律に基づく買取義務がなくなり、発電した電力は
(1)自家消費
(2)相対・自由契約で余剰電力を売電
のどちらかを選択して適用することになります。
つまり、買取期間が終了した段階で、電力会社には法律に基づく買取義務がなくなり、発電した電力は
(1)自家消費
(2)相対・自由契約で余剰電力を売電
のどちらかを選択して適用することになります。
太陽光発電についての発電量と、自家消費のイメージは下図のようになります (1)では、買取にたよらず、発電した電力は、自家消費に充てるということ︵つまり、下図の青部分を無くす︶ことになります。 昼は発電の余剰が出る場合は、蓄電池などで蓄えて、夜間に使用するというイメージです。 (2)では、青部分の余剰電力を、これまでの単価からはかなり安くなるが、電力を買い取る業者と新たに契約を結んで余剰電力売電するというものです。 おそらく契約単価は10円/Kwh程度になるのではないかと考えています。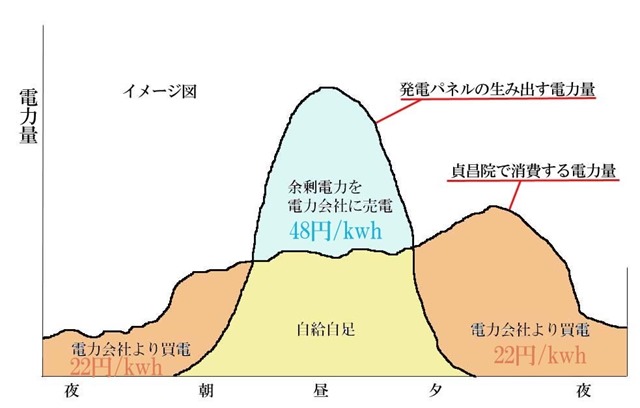 貞昌院の場合は、まだ買取制度終了まで1年間の余裕があるので、その間に情報を集めて、新たな契約を考えていきたいと思っています。
もう、すでに設置費用は回収できているので、買取価格がそれほど高くなくてもよいかとも思っています。
具体的になりましたらまたお知らせします。
ここで、買取制度終了の2019年問題に付け込んだ、悪徳なセールスもあるようなので、注意喚起がなされています。
具体的な悪徳業者のセールス内容と、それに対する経済産業省の回答は下記のとおりです。
︻悪徳業者︼これからは0円買取となるため、蓄電池を付けなければ損をすることになる。
︻経産省の回答︼蓄電池等と組み合わせて自家消費を拡大することは可能ですが、蓄電池を設置しなければ必ず損をするということはありません。
貞昌院の場合は、まだ買取制度終了まで1年間の余裕があるので、その間に情報を集めて、新たな契約を考えていきたいと思っています。
もう、すでに設置費用は回収できているので、買取価格がそれほど高くなくてもよいかとも思っています。
具体的になりましたらまたお知らせします。
ここで、買取制度終了の2019年問題に付け込んだ、悪徳なセールスもあるようなので、注意喚起がなされています。
具体的な悪徳業者のセールス内容と、それに対する経済産業省の回答は下記のとおりです。
︻悪徳業者︼これからは0円買取となるため、蓄電池を付けなければ損をすることになる。
︻経産省の回答︼蓄電池等と組み合わせて自家消費を拡大することは可能ですが、蓄電池を設置しなければ必ず損をするということはありません。
︻悪徳業者︼0円買取となるため、当社と売電契約しなければ損をすることになる。 ︻経産省の回答︼買取期間満了後、余剰電力の買取を表明している事業者は複数あり、また電気自動車や蓄電池と組み合わせて自家消費をすることもできますので、特定の1社と売電契約をしなければ必ず損をするということはありません。 ︻悪徳業者︼売電より、蓄電池と組み合わせて自家消費する方が絶対に得である。 ︻経産省の回答︼余剰電力の売電と、蓄電池と組み合わせた自家消費のどちらがお得かは、個々のケースによって異なります。 ︻悪徳業者︼現在買取を行う電力会社は買取終了のため、当社と契約しなければ損をする。 ︻経産省の回答︼電力会社の契約内容にもよりますので、必ずしも現在買取を行っている電力会社が買取をしないとは言えません。 買取制度終了のタイミングで、消費者心理を悪用するセールスには十分注意したいものです。
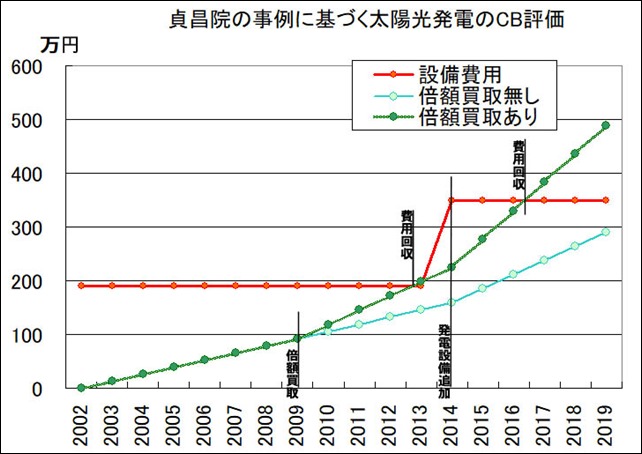 図中、太陽光発電設備の設置費用を赤線で引いています。
また、倍額買取を考慮した発電量を金額に置き換えたものを緑線で表しました。
緑線が赤線を上回った時点が、設置費用回収の時期と考えられます。
途中、設備増強のために費用が増えていますが、2013年、2016年には費用が回収できていることになります。
※参考のために、もしも倍額買取ができようされなかった場合を青線で付記しました。この場合、費用が回収できるのはおおむね2022年、つまり設置から約20年後ということになります。
では、買取制度が終了した後はどのようになるのでしょうか。
それについては、当ブログにおいては、昨年次のような記事を書きました。
→住宅用太陽光売電価格は11円/Kwhへ
図中、太陽光発電設備の設置費用を赤線で引いています。
また、倍額買取を考慮した発電量を金額に置き換えたものを緑線で表しました。
緑線が赤線を上回った時点が、設置費用回収の時期と考えられます。
途中、設備増強のために費用が増えていますが、2013年、2016年には費用が回収できていることになります。
※参考のために、もしも倍額買取ができようされなかった場合を青線で付記しました。この場合、費用が回収できるのはおおむね2022年、つまり設置から約20年後ということになります。
では、買取制度が終了した後はどのようになるのでしょうか。
それについては、当ブログにおいては、昨年次のような記事を書きました。
→住宅用太陽光売電価格は11円/Kwhへ
経済産業省のサイトでは、買取制度の終了についてのお知らせが掲載されています。
 つまり、買取期間が終了した段階で、電力会社には法律に基づく買取義務がなくなり、発電した電力は
(1)自家消費
(2)相対・自由契約で余剰電力を売電
のどちらかを選択して適用することになります。
つまり、買取期間が終了した段階で、電力会社には法律に基づく買取義務がなくなり、発電した電力は
(1)自家消費
(2)相対・自由契約で余剰電力を売電
のどちらかを選択して適用することになります。
太陽光発電についての発電量と、自家消費のイメージは下図のようになります (1)では、買取にたよらず、発電した電力は、自家消費に充てるということ︵つまり、下図の青部分を無くす︶ことになります。 昼は発電の余剰が出る場合は、蓄電池などで蓄えて、夜間に使用するというイメージです。 (2)では、青部分の余剰電力を、これまでの単価からはかなり安くなるが、電力を買い取る業者と新たに契約を結んで余剰電力売電するというものです。 おそらく契約単価は10円/Kwh程度になるのではないかと考えています。
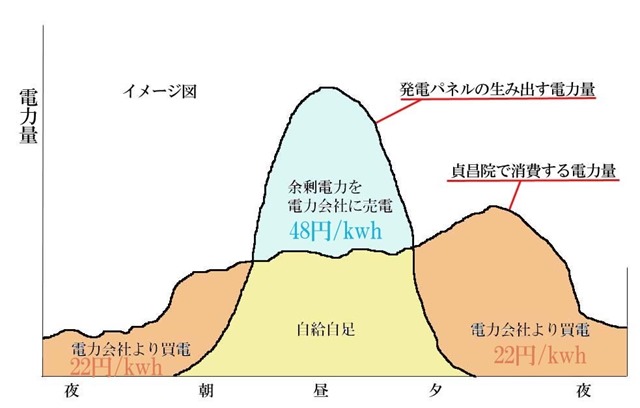 貞昌院の場合は、まだ買取制度終了まで1年間の余裕があるので、その間に情報を集めて、新たな契約を考えていきたいと思っています。
もう、すでに設置費用は回収できているので、買取価格がそれほど高くなくてもよいかとも思っています。
具体的になりましたらまたお知らせします。
ここで、買取制度終了の2019年問題に付け込んだ、悪徳なセールスもあるようなので、注意喚起がなされています。
具体的な悪徳業者のセールス内容と、それに対する経済産業省の回答は下記のとおりです。
︻悪徳業者︼これからは0円買取となるため、蓄電池を付けなければ損をすることになる。
︻経産省の回答︼蓄電池等と組み合わせて自家消費を拡大することは可能ですが、蓄電池を設置しなければ必ず損をするということはありません。
貞昌院の場合は、まだ買取制度終了まで1年間の余裕があるので、その間に情報を集めて、新たな契約を考えていきたいと思っています。
もう、すでに設置費用は回収できているので、買取価格がそれほど高くなくてもよいかとも思っています。
具体的になりましたらまたお知らせします。
ここで、買取制度終了の2019年問題に付け込んだ、悪徳なセールスもあるようなので、注意喚起がなされています。
具体的な悪徳業者のセールス内容と、それに対する経済産業省の回答は下記のとおりです。
︻悪徳業者︼これからは0円買取となるため、蓄電池を付けなければ損をすることになる。
︻経産省の回答︼蓄電池等と組み合わせて自家消費を拡大することは可能ですが、蓄電池を設置しなければ必ず損をするということはありません。
︻悪徳業者︼0円買取となるため、当社と売電契約しなければ損をすることになる。 ︻経産省の回答︼買取期間満了後、余剰電力の買取を表明している事業者は複数あり、また電気自動車や蓄電池と組み合わせて自家消費をすることもできますので、特定の1社と売電契約をしなければ必ず損をするということはありません。 ︻悪徳業者︼売電より、蓄電池と組み合わせて自家消費する方が絶対に得である。 ︻経産省の回答︼余剰電力の売電と、蓄電池と組み合わせた自家消費のどちらがお得かは、個々のケースによって異なります。 ︻悪徳業者︼現在買取を行う電力会社は買取終了のため、当社と契約しなければ損をする。 ︻経産省の回答︼電力会社の契約内容にもよりますので、必ずしも現在買取を行っている電力会社が買取をしないとは言えません。 買取制度終了のタイミングで、消費者心理を悪用するセールスには十分注意したいものです。
2019年2月18日
横浜港に2つのロープウエィ計画
会議のために横浜みなとみらいを見渡せる会議に出向きました。
景色の良い場所なので、スマートフォンを窓際に置いてタイムラプスで撮影してみました。
画面中央に見える道は、桜木町から赤レンガ倉庫方面を結ぶ、汽車道です。
かつては、ここに鉄道が通っており、歩道として整備されています。
※汽車道については、ブログ記事も併せてご覧ください。汽車道にまつわるエトセトラ シャンパンゴールドの汽車道
タイミングよく、この汽車道の上にロープウエーを敷設する計画がニュースになっていました。
しかも、
・桜木町~ワールドポーターズ
・横浜駅東口~山下ふ頭
という2つの計画が同時期にすすみ、東京オリンピック開業前には運行されるというものです。
横浜で2つのロープウエー案 桜木町駅-新港ふ頭 東京五輪前に開業へ
東京五輪・パラリンピックなどをにらみ、横浜市でロープウエーを建設する案が2つある。そのうちの一つが、横浜みなとみらい21︵MM21︶地区で、JR桜木町駅-新港ふ頭間を結ぶ計画案。もう一つは、横浜駅東口-山下ふ頭間を結ぶ構想案だ。実現すれば、開発が進む客船ターミナルの観光客受け入れ機能との連携が可能となるなど、観光促進や回遊性の向上にもつながりそうだ。
いずれの案も、市都市整備局が臨海部の回遊性を高めるために交通ネットワークを強化しようと、﹁まちを楽しむ多彩な交通の充実﹂を掲げて、平成29年度に募り、選定した事業案だ。企業側が設置費や運営費を負担する。
●最短2分半で
MM21地区のロープウエーの名称は﹁YOKOHAMA AIR CABIN︵仮称︶﹂。JR桜木町駅東口北改札から海上の遊歩道﹁汽車道﹂に沿って全長630メートルのロープウエーを整備して、新港ふ頭の運河パークと結ぶ。
停留所は、同駅東口北改札と商業施設﹁横浜ワールドポーターズ﹂の隣接地にそれぞれ設ける。運河パーク側の停留所は、横浜ワールドポーターズや歩道橋﹁サークルウォーク﹂の2階部分と接続することも検討中だ。同じルートを徒歩で移動すると、片道15~20分ほどかかるが、ロープウエーを利用すれば最短2分半ほどで移動できる。
支柱は、地上に2基︵高さ約10メートル︶、海上に3基︵高さ約30~40メートル︶を建設する。ゴンドラは36基作り、全基とも車いすの同乗が可能で、運行時間や運賃は未定という。
設置・運営を担うのは、同地区の遊園地﹁よこはまコスモワールド﹂を運営する泉陽興業︵大阪府︶。市は、3月末までに同社と協定を結び、夏ごろに着工する予定だ。
東京五輪・パラリンピック前の営業開始を目指している。観覧車やゴンドラの建設実績のある同社の広報担当者は﹁桜木町駅から横浜みなとみらい21地区への回遊性を高めることで、コスモワールドへの誘客効果や売り上げ向上にもつながれば﹂と話した。
●山下ふ頭にも
MM21地区は商業施設などが点在しており、内陸側と海側をつなぐ移動手段が乏しいことが課題となっていた。市はロープウエーを整備することで、新港ふ頭に今年秋、開業予定の﹁新港地区客船ターミナル﹂からの観光客受け入れ機能との連携や、ターミナル方面へのアクセス機能を強化することで、さらなる観光振興の促進を期待している。
横浜駅東口と再開発が進む山下ふ頭を結ぶロープウエーの構想案を提案したのは、YNP︵藤木幸太社長︶など一般社団法人﹁横浜港振興協会﹂を代表する共同体。YNPは同市を中心として港湾施設の管理・運営などを行う会社で、藤木企業︵同︶、小此木︵小此木歌蔵社長︶、川本工業︵川本守彦社長︶、横浜岡田屋︵岡田伸浩社長︶の計4社が出資している。横浜駅東口から市中央卸売市場、新港地区、山下公園・山下ふ頭をつなぐ。
再開発が予定される山下ふ頭は客船1、2隻の着岸が可能になり、着岸した客船をホテルとして使う計画もある。ロープウエーができることで、観光客誘致につなげる狙いもある。同局によると、現状はまだ検討が進められている段階といい、具体的な内容については今後、協議をしていくとしている。
︻新港ふ頭︼
開港160年を迎える横浜の内港地区のほぼ中央に位置し、明治後期から大正期に建設された埠頭。総面積は37・4ヘクタール。横浜市は、横浜みなとみらい21地区全体を一層活性化させようと、新たに﹁新港地区客船ターミナル﹂を整備している。同ターミナルは地上5階建て、延べ床面積約3万300平方メートル。10万トン程度までの国際クルーズ船が発着でき、CIQ︵税関、出入国管理、検疫︶施設のほかに、ホテルや商業施設などを備える。
︵産経新聞 2019/2/18配信︶
来年夏までに開業というのは、ずいぶん早いですね。
ロープウェイだからこそ、設置スピードが早くできるのでしょう。
桜木町~ワールドポーターズを結ぶロープウェーはこのようなルートを通るようです。 ︵Googleの航空写真に赤で線を描いてみました︶ 横浜港には、かつて、1989年︵平成元年︶に開催された横浜博覧会で横浜駅東口と博覧会会場を結んだロープウェーが運行されていました。
このときに、乗ったことがありますが、空中から見下ろすことができる乗り物はワクワクしますね。
開業が待ち遠しいものです。
横浜港には、かつて、1989年︵平成元年︶に開催された横浜博覧会で横浜駅東口と博覧会会場を結んだロープウェーが運行されていました。
このときに、乗ったことがありますが、空中から見下ろすことができる乗り物はワクワクしますね。
開業が待ち遠しいものです。
桜木町~ワールドポーターズを結ぶロープウェーはこのようなルートを通るようです。 ︵Googleの航空写真に赤で線を描いてみました︶
 横浜港には、かつて、1989年︵平成元年︶に開催された横浜博覧会で横浜駅東口と博覧会会場を結んだロープウェーが運行されていました。
このときに、乗ったことがありますが、空中から見下ろすことができる乗り物はワクワクしますね。
開業が待ち遠しいものです。
横浜港には、かつて、1989年︵平成元年︶に開催された横浜博覧会で横浜駅東口と博覧会会場を結んだロープウェーが運行されていました。
このときに、乗ったことがありますが、空中から見下ろすことができる乗り物はワクワクしますね。
開業が待ち遠しいものです。
2019年1月21日
相鉄JR直通線の工事が進む(2)
約1年前に書いた記事 相鉄JR直通線の工事が進む の続報です。
来年度︵2019年度︶下期に相模鉄道・西谷とJR東海道貨物線がつながり、海老名方面から武蔵小杉・渋谷・新宿方面への直通運転がはじまります。
それからさらに3年後、相模鉄道と東急東横線がつながり、海老名方面から新横浜・日吉・渋谷方面への直通運転がはじまります。
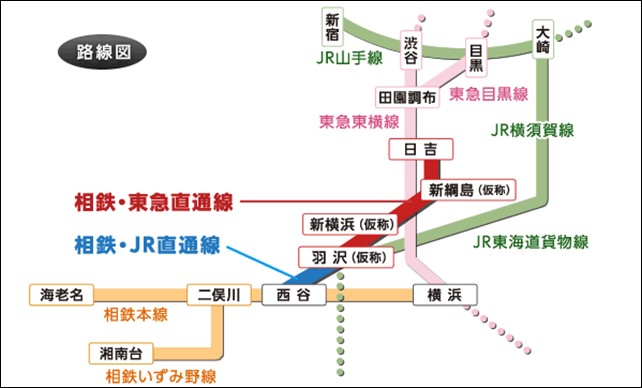 図は直通運転公式サイトより引用
その概要は下表のとおりです。
図は直通運転公式サイトより引用
その概要は下表のとおりです。
表‥相鉄・JR直通線および相鉄・東急直通線の概要 ︵参考・直通運転公式サイト︶
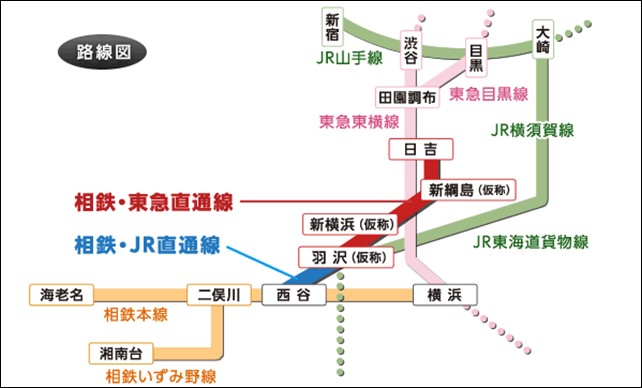 図は直通運転公式サイトより引用
その概要は下表のとおりです。
図は直通運転公式サイトより引用
その概要は下表のとおりです。
表‥相鉄・JR直通線および相鉄・東急直通線の概要 ︵参考・直通運転公式サイト︶
| 相鉄・JR 直通線 | 相鉄・東急 直通線 | |
| 整備区間 | 相鉄本線西谷駅~ JR東海道貨物線横浜羽沢駅付近(約2.7km) | JR東海道貨物線横浜羽沢駅付近~ 東急東横線・目黒線日吉駅(約10.0km) |
| 開業予定時期 | 2019年度下期 | 2022年度下期 |
| 営業主体 | 相模鉄道(株) | 相模鉄道(株)・東京急行電鉄(株) |
| 運行区間 | 海老名駅・湘南台駅~西谷駅~ 羽沢駅(仮称)~新宿方面 | 海老名駅・湘南台駅~西谷駅~羽沢駅(仮称)~新横浜駅(仮称)~新綱島駅(仮称)~日吉駅~渋谷方面・目黒方面 |
| 運行頻度 | 朝ラッシュ時間帯:4本/時 程度 その他時間帯:2~3本/時 程度 | 朝ラッシュ時間帯:10本~14本/時 程度 その他時間帯:4~6本/時 程度 |
直通運転の要となる、羽沢横浜国大駅の工事がだいぶ進んでいます。
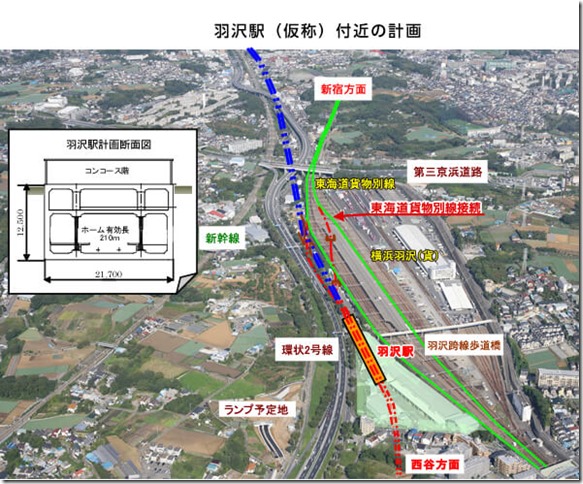 上図は直通運転公式サイトより引用
今日現在の羽沢横浜国大駅の状況です。
いろいろな角度から撮影してみました。
上図は直通運転公式サイトより引用
今日現在の羽沢横浜国大駅の状況です。
いろいろな角度から撮影してみました。


 貨物駅を横断する陸橋から上り方面を眺めると、地下から登ってJR貨物別線に接続する線路と、トンネルで新横浜を経由して東急東横線に接続する線路の工事状況もよくわかります。
貨物駅を横断する陸橋から上り方面を眺めると、地下から登ってJR貨物別線に接続する線路と、トンネルで新横浜を経由して東急東横線に接続する線路の工事状況もよくわかります。
 まずは、2019年度下期のJRとの接続まで1年ほどになりました。
完成すれば利便性はかなり向上することでしょう。
接続先のJR線は、貨物線を経由して、湘南新宿ライン・横須賀線の路線を通ります。
ただ、問題が全くないわけではなく、この路線はすでにダイヤがかなり過密化していて、そこの隙間に朝ラッシュ時間帯‥4本/時 程度、その他時間帯‥2~3本/時 程度を確保することはかなり難しい現状にあります。
その理由の一つが、旧蛇窪信号場の平面交差です。
旧蛇窪信号場は、JR西大井駅駅から先、品川方面に向かう横須賀線と、渋谷方面に向かう湘南新宿ラインの分岐点ですが、地図で示すと下図の2カ所ある赤着色のうち下の赤着色の部分にあたります。
まずは、2019年度下期のJRとの接続まで1年ほどになりました。
完成すれば利便性はかなり向上することでしょう。
接続先のJR線は、貨物線を経由して、湘南新宿ライン・横須賀線の路線を通ります。
ただ、問題が全くないわけではなく、この路線はすでにダイヤがかなり過密化していて、そこの隙間に朝ラッシュ時間帯‥4本/時 程度、その他時間帯‥2~3本/時 程度を確保することはかなり難しい現状にあります。
その理由の一つが、旧蛇窪信号場の平面交差です。
旧蛇窪信号場は、JR西大井駅駅から先、品川方面に向かう横須賀線と、渋谷方面に向かう湘南新宿ラインの分岐点ですが、地図で示すと下図の2カ所ある赤着色のうち下の赤着色の部分にあたります。
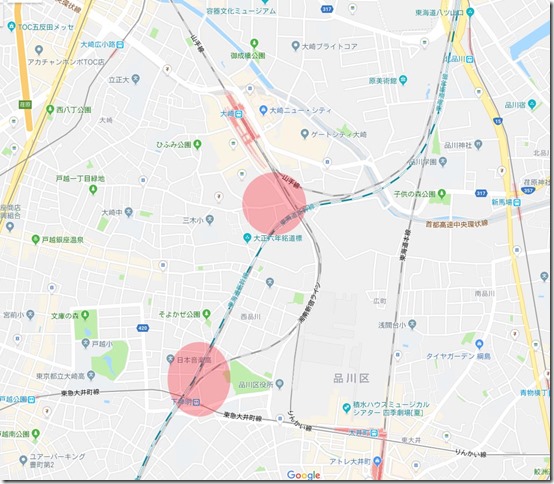 GooGleMapで見ると、この分岐点の線路は、平面交差していることがわかります。
︵下写真の着色部︶
GooGleMapで見ると、この分岐点の線路は、平面交差していることがわかります。
︵下写真の着色部︶

湘南新宿ラインに関わる平面交差支障の解消について(PDF) というJR東日本の報告書に、この部分を図式化していましたので、引用してみます。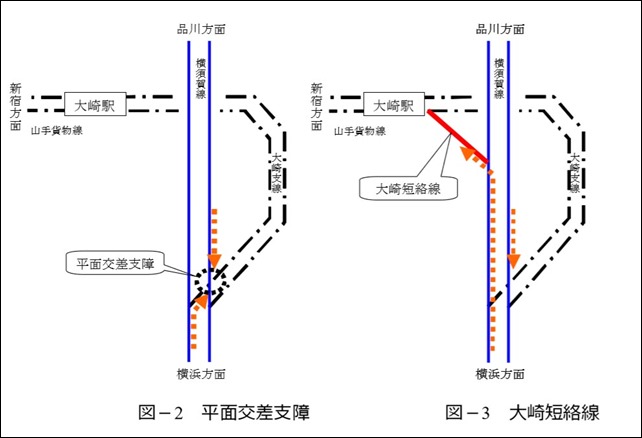 つまり、この平面交差があるために、西大井を出て大崎・渋谷方面に向かう湘南新宿ラインの北行き列車と、品川方面から西大井へ向かう横須賀線の南行き列車がお互い干渉しないようにダイヤ間隔を開けて運行する必要があるのです。
このために、数分刻みのダイヤを組むことができず、効率的な運行が出来ない問題があります。
この平面交差の問題を解決するための現実的な方法が、西大井を出て大崎・渋谷方面に向かう湘南新宿ラインの北行き列車をショートカットさせる短絡線を新規に敷設するというものです。
これを大崎短絡線構想といいます。
Googleの航空写真に大崎短絡線を描くとこのような感じになります。
つまり、この平面交差があるために、西大井を出て大崎・渋谷方面に向かう湘南新宿ラインの北行き列車と、品川方面から西大井へ向かう横須賀線の南行き列車がお互い干渉しないようにダイヤ間隔を開けて運行する必要があるのです。
このために、数分刻みのダイヤを組むことができず、効率的な運行が出来ない問題があります。
この平面交差の問題を解決するための現実的な方法が、西大井を出て大崎・渋谷方面に向かう湘南新宿ラインの北行き列車をショートカットさせる短絡線を新規に敷設するというものです。
これを大崎短絡線構想といいます。
Googleの航空写真に大崎短絡線を描くとこのような感じになります。
 ですので、相鉄・JR直通線は2019年度中に実現はするものの、本格的な運用ができるのは、大崎短絡線が完成してからということになりそうです。
ですので、相鉄・JR直通線は2019年度中に実現はするものの、本格的な運用ができるのは、大崎短絡線が完成してからということになりそうです。
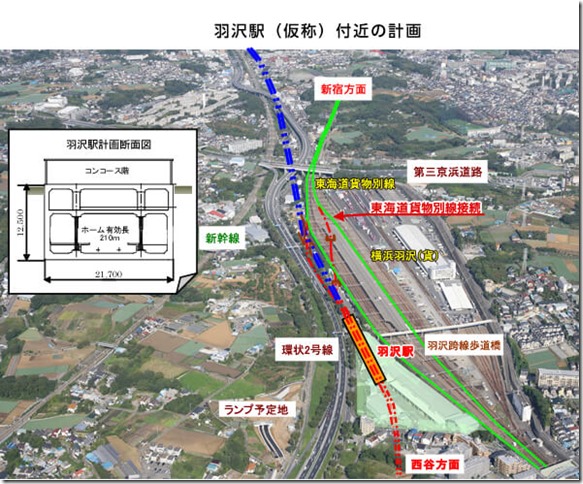 上図は直通運転公式サイトより引用
上図は直通運転公式サイトより引用


 貨物駅を横断する陸橋から上り方面を眺めると、地下から登ってJR貨物別線に接続する線路と、トンネルで新横浜を経由して東急東横線に接続する線路の工事状況もよくわかります。
貨物駅を横断する陸橋から上り方面を眺めると、地下から登ってJR貨物別線に接続する線路と、トンネルで新横浜を経由して東急東横線に接続する線路の工事状況もよくわかります。
 まずは、2019年度下期のJRとの接続まで1年ほどになりました。
完成すれば利便性はかなり向上することでしょう。
まずは、2019年度下期のJRとの接続まで1年ほどになりました。
完成すれば利便性はかなり向上することでしょう。
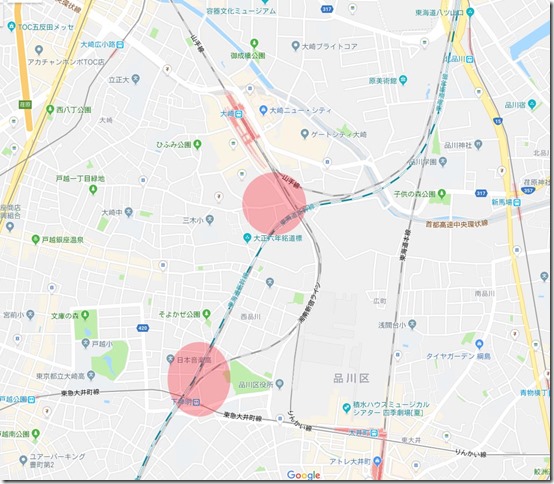 GooGleMapで見ると、この分岐点の線路は、平面交差していることがわかります。
︵下写真の着色部︶
GooGleMapで見ると、この分岐点の線路は、平面交差していることがわかります。
︵下写真の着色部︶

湘南新宿ラインに関わる平面交差支障の解消について(PDF) というJR東日本の報告書に、この部分を図式化していましたので、引用してみます。
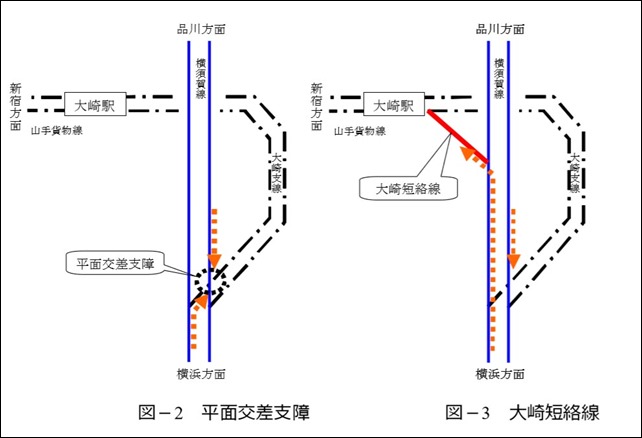 つまり、この平面交差があるために、西大井を出て大崎・渋谷方面に向かう湘南新宿ラインの北行き列車と、品川方面から西大井へ向かう横須賀線の南行き列車がお互い干渉しないようにダイヤ間隔を開けて運行する必要があるのです。
このために、数分刻みのダイヤを組むことができず、効率的な運行が出来ない問題があります。
この平面交差の問題を解決するための現実的な方法が、西大井を出て大崎・渋谷方面に向かう湘南新宿ラインの北行き列車をショートカットさせる短絡線を新規に敷設するというものです。
これを大崎短絡線構想といいます。
Googleの航空写真に大崎短絡線を描くとこのような感じになります。
つまり、この平面交差があるために、西大井を出て大崎・渋谷方面に向かう湘南新宿ラインの北行き列車と、品川方面から西大井へ向かう横須賀線の南行き列車がお互い干渉しないようにダイヤ間隔を開けて運行する必要があるのです。
このために、数分刻みのダイヤを組むことができず、効率的な運行が出来ない問題があります。
この平面交差の問題を解決するための現実的な方法が、西大井を出て大崎・渋谷方面に向かう湘南新宿ラインの北行き列車をショートカットさせる短絡線を新規に敷設するというものです。
これを大崎短絡線構想といいます。
Googleの航空写真に大崎短絡線を描くとこのような感じになります。
 ですので、相鉄・JR直通線は2019年度中に実現はするものの、本格的な運用ができるのは、大崎短絡線が完成してからということになりそうです。
ですので、相鉄・JR直通線は2019年度中に実現はするものの、本格的な運用ができるのは、大崎短絡線が完成してからということになりそうです。
2018年8月 6日
法人土地・建物基本調査
この夏、貞昌院に﹁平成30年 法人土地・建物基本調査﹂調査票が届きました。
 ﹁法人土地・建物基本調査﹂は、法人の土地や建物の所有状況や利用状況を総合的に把握するための調査で、平成5年に開始、5年おきに実施されています。
すなわち、今回は6回目に当たります。
調査対象は本年7~9月に、統計的手法により抽出された約49万法人を対象としているいうことです。
日本の法人数は、国税庁のサイトによれば、約260万社︵決算書を提出した法人︶ということなので、調査対象になる確率は20%程度ということでしょうか。
それにしても、貞昌院では平成10年、平成25年にも同調査に回答していますので、またか!という感じです。
これだけ毎回調査対象となっているということは、無作為というより、回答履歴のある法人を優先して調査対象にしているのでしょうか???
まあ、学術調査資料としても有用な調査だとは思いますので、今回もきっちり回答させていただきました。
前回はインターネット経由で回答しましたが、今回は前回の回答履歴が回答用紙に予め印字されているので、郵送にて回答書を送りました。
偶然にも、宗門でも同様の調査が進行しています。
回答内容自体はその調査とほぼ共通の内容となっていますので、簡単に回答することができました。
﹁法人土地・建物基本調査﹂は、法人の土地や建物の所有状況や利用状況を総合的に把握するための調査で、平成5年に開始、5年おきに実施されています。
すなわち、今回は6回目に当たります。
調査対象は本年7~9月に、統計的手法により抽出された約49万法人を対象としているいうことです。
日本の法人数は、国税庁のサイトによれば、約260万社︵決算書を提出した法人︶ということなので、調査対象になる確率は20%程度ということでしょうか。
それにしても、貞昌院では平成10年、平成25年にも同調査に回答していますので、またか!という感じです。
これだけ毎回調査対象となっているということは、無作為というより、回答履歴のある法人を優先して調査対象にしているのでしょうか???
まあ、学術調査資料としても有用な調査だとは思いますので、今回もきっちり回答させていただきました。
前回はインターネット経由で回答しましたが、今回は前回の回答履歴が回答用紙に予め印字されているので、郵送にて回答書を送りました。
偶然にも、宗門でも同様の調査が進行しています。
回答内容自体はその調査とほぼ共通の内容となっていますので、簡単に回答することができました。
 ﹁法人土地・建物基本調査﹂は、法人の土地や建物の所有状況や利用状況を総合的に把握するための調査で、平成5年に開始、5年おきに実施されています。
すなわち、今回は6回目に当たります。
調査対象は本年7~9月に、統計的手法により抽出された約49万法人を対象としているいうことです。
日本の法人数は、国税庁のサイトによれば、約260万社︵決算書を提出した法人︶ということなので、調査対象になる確率は20%程度ということでしょうか。
それにしても、貞昌院では平成10年、平成25年にも同調査に回答していますので、またか!という感じです。
これだけ毎回調査対象となっているということは、無作為というより、回答履歴のある法人を優先して調査対象にしているのでしょうか???
まあ、学術調査資料としても有用な調査だとは思いますので、今回もきっちり回答させていただきました。
前回はインターネット経由で回答しましたが、今回は前回の回答履歴が回答用紙に予め印字されているので、郵送にて回答書を送りました。
偶然にも、宗門でも同様の調査が進行しています。
回答内容自体はその調査とほぼ共通の内容となっていますので、簡単に回答することができました。
﹁法人土地・建物基本調査﹂は、法人の土地や建物の所有状況や利用状況を総合的に把握するための調査で、平成5年に開始、5年おきに実施されています。
すなわち、今回は6回目に当たります。
調査対象は本年7~9月に、統計的手法により抽出された約49万法人を対象としているいうことです。
日本の法人数は、国税庁のサイトによれば、約260万社︵決算書を提出した法人︶ということなので、調査対象になる確率は20%程度ということでしょうか。
それにしても、貞昌院では平成10年、平成25年にも同調査に回答していますので、またか!という感じです。
これだけ毎回調査対象となっているということは、無作為というより、回答履歴のある法人を優先して調査対象にしているのでしょうか???
まあ、学術調査資料としても有用な調査だとは思いますので、今回もきっちり回答させていただきました。
前回はインターネット経由で回答しましたが、今回は前回の回答履歴が回答用紙に予め印字されているので、郵送にて回答書を送りました。
偶然にも、宗門でも同様の調査が進行しています。
回答内容自体はその調査とほぼ共通の内容となっていますので、簡単に回答することができました。
2016年6月24日
イギリスのEU離脱が確実に
英、EU離脱へ=欧州分裂、大きな岐路に―国民投票 ︻ロンドン時事︼英国の欧州連合︵EU︶残留か離脱かを問う国民投票は、23日午後10時︵日本時間午前6時︶から開票が行われ、BBC放送によれば、離脱支持票が過半数となり、勝利する見通しとなった。 1973年に前身の欧州共同体︵EC︶参加以来、43年にわたる英国のEU加盟に終止符が打たれる。域内2位の経済大国である英国の離脱で欧州は分裂し、大きな岐路に立たされる。また、世界経済に大きな混乱を招くのは必至だ。 ︵時事通信6月24日(金)12時44分配信︶歴史的な国民投票結果について、イギリスのEU離脱がほぼ確実という速報が出ました。 午前中からイギリス各メディアをチェックしていたのですが、事前調査の残留がやや有利という報道に反し、票が拮抗するも離脱派がややリードを広げ、日本時間で12時半には離脱確実の報道となりました。 それだけ国民の移民流入に対する感情が強かったということでしょうか。 図は、速報が出た時刻のガーディアン紙開票状況を先取りして、為替市場、株式市場では大幅な円高・株安となっております。

︵左‥ポンド・円、 中‥ドル・円 右‥日経平均︶ この開票結果は、イギリスにとっては歴史的な岐路になることは間違いないでしょう。 また、世界経済のみならず、世界全体の構造の枠組みに及ぼす影響も計り知れません。 日本にとってはイギリスに大きな拠点を置く日立製作所、トヨタ、そして各金融機関にとっても打撃は大きいことでしょう。 まずは、今後の為替市場、株式市場の動向に注視する必要がありそうです。
2016年6月13日
電力自由化とスマートメーター
2016︵平成28︶年4月1日から、電力の自由化︵電気の小売業への参入が全面自由化︶されたことにより、電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになりました。
電力自由化によって、これまで寡占企業とされてきた電気事業において、市場参入規制の緩和や、市場競争が促されることになります。
結果として、電気料金の引き下げや電気事業における資源配分の効率化が進むことを期待します。
なお、貞昌院では、種々比較検討して、東京電力の2年契約プランとしました。
電力自由化には、電力量を測定するメーターを新しいスマートメーターに交換することが必要になったします。
これまでは、電力量の計測は、月一回の目視による検針でした。
それが、30分ごとに自動的に計測し、そのデータが自動的に電力会社に送られることとなります。
より詳細な電力料金プランが可能となるわけです。
貞昌院の電力メーターの交換が本日行われました。

 ↑これがこれまでの電力量メーターです。
連携系統の太陽光発電設備を設置しているので、買電、売電両方のメーターが設置されています。
このような型のメーターは珍しいようです。
メーターの本体↓
↑これがこれまでの電力量メーターです。
連携系統の太陽光発電設備を設置しているので、買電、売電両方のメーターが設置されています。
このような型のメーターは珍しいようです。
メーターの本体↓
 新型のスマートメーターでは、買電、売電が統合されて1台のメーターで済むこととなります。
まずは従来のメーター2つを取り外し。、スマートメーター1つを設置します。
新型のスマートメーターでは、買電、売電が統合されて1台のメーターで済むこととなります。
まずは従来のメーター2つを取り外し。、スマートメーター1つを設置します。
 設置まで。1時間ほどかかりました。
設置まで。1時間ほどかかりました。
 これがスマートメーターの表示パネル。
順動作、無計量、逆動作の表示がありますね。
7月からはインターネットで詳細な電力の使用状況、売電状況を確認できるようになります。
これがスマートメーターの表示パネル。
順動作、無計量、逆動作の表示がありますね。
7月からはインターネットで詳細な電力の使用状況、売電状況を確認できるようになります。

 ↑これがこれまでの電力量メーターです。
連携系統の太陽光発電設備を設置しているので、買電、売電両方のメーターが設置されています。
このような型のメーターは珍しいようです。
メーターの本体↓
↑これがこれまでの電力量メーターです。
連携系統の太陽光発電設備を設置しているので、買電、売電両方のメーターが設置されています。
このような型のメーターは珍しいようです。
メーターの本体↓
 新型のスマートメーターでは、買電、売電が統合されて1台のメーターで済むこととなります。
まずは従来のメーター2つを取り外し。、スマートメーター1つを設置します。
新型のスマートメーターでは、買電、売電が統合されて1台のメーターで済むこととなります。
まずは従来のメーター2つを取り外し。、スマートメーター1つを設置します。
 設置まで。1時間ほどかかりました。
設置まで。1時間ほどかかりました。
 これがスマートメーターの表示パネル。
順動作、無計量、逆動作の表示がありますね。
7月からはインターネットで詳細な電力の使用状況、売電状況を確認できるようになります。
これがスマートメーターの表示パネル。
順動作、無計量、逆動作の表示がありますね。
7月からはインターネットで詳細な電力の使用状況、売電状況を確認できるようになります。
2016年2月25日
シャープが外資傘下に
シャープ、鴻海が買収=外資傘下で再建へ
シャープは25日、臨時取締役会を開き、台湾の電子機器受託製造大手、鴻海︵ホンハイ︶精密工業の傘下で経営再建を目指すことを決めた。鴻海は7000億円規模の資金を投じ、シャープを事実上買収する。液晶など主要事業は売却せず、若手の雇用を維持しながら再建を目指す計画。月内に正式契約を結ぶ。国内電機大手が外資傘下に入るのは初めて。 シャープは鴻海と優先的に交渉する一方、政府系ファンドの産業革新機構に支援を仰ぐ案も検討してきた。再建の実現性やスピード、成長性、経済合理性などを比較し検討した結果、鴻海案が革新機構案より優れると判断した。 鴻海は、革新機構が示した3000億円を上回る5000億円の成長資金を投じると提案。再建策の実行を確約し、その保証金として1000億円を預けることにも同意した。主力取引銀行のみずほ銀行と三菱東京UFJ銀行が保有するシャープの優先株は半分程度を額面で買い取る。 ︵時事通信2月25日(木)11時15分配信︶ついにこの日がやってきてしまいました。 一時期は液晶や太陽光発電パネル、複合機などの分野で世界を牽引していくほどの技術力を誇っていた、それが遠い昔の事のようです。 技術力さを活かすことができなかった経営陣の会社運営能力の無さには残念です。
巨額な債権の負担を抱え、銀行からの債権放棄が無い状態で、少しでも︵今のところは︶好条件であろうと考えた経営陣の判断がこれからどのような結末をもたらすのかに注視していきたいところです。 せめて鴻海の提示している7000億円が約束通り履行され、社員たちにきちんとした対価が払われることを願うばかりです。 数年後、こんなはずではなかった・・・という結末だけは避けて欲しい。
シャープはこれまで応援してきた企業の一つでしたので、本当に残念な報道でした。
2016年1月31日
ガソリンが再びリッター100円割れ
昨年から原油価格の下落が続いており、近隣のガソリンスタンドではリッター100円を割ることが当たり前になってきました。
 このブログでも、時折ガソリンなど原油価格について言及してきました。
師走の値上げラッシュ(2007/12/1) リッター143円
原油高騰でもサンマは安値(2008/10/5) リッター180円
実態からかけ離れてしまった経済(2008/12/22) リッター99円
ガソリン価格下落傾向(2011/5/25) リッター137円
原油高騰が続く︵2014/6/26) リッター140円
改めて見ると、ここ10年の乱高下は激しいですね。
特に2008年︵平成20年︶10月から12月にかけての急激な下落は記憶に新しいところです。
総務省統計局﹁小売物価統計調査﹂資料を見ると、その乱高下の様子がグラフに如実に現れています。
このブログでも、時折ガソリンなど原油価格について言及してきました。
師走の値上げラッシュ(2007/12/1) リッター143円
原油高騰でもサンマは安値(2008/10/5) リッター180円
実態からかけ離れてしまった経済(2008/12/22) リッター99円
ガソリン価格下落傾向(2011/5/25) リッター137円
原油高騰が続く︵2014/6/26) リッター140円
改めて見ると、ここ10年の乱高下は激しいですね。
特に2008年︵平成20年︶10月から12月にかけての急激な下落は記憶に新しいところです。
総務省統計局﹁小売物価統計調査﹂資料を見ると、その乱高下の様子がグラフに如実に現れています。
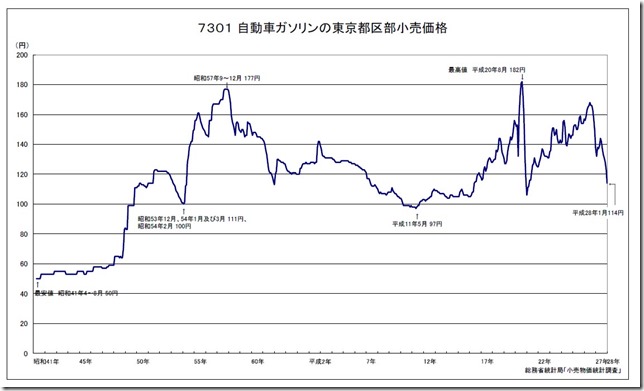 しかし、再びリッター100円を割る日が来るとは・・・・
しかし、再びリッター100円を割る日が来るとは・・・・
原油価格は、他の資源と同様、生産量と消費量の需給関係で価格が影響されます。 生産の面で言うと、OPECの減産見送りによる供給がある程度潤沢に保たれていること、シエールガス開発などエネルギーの多様化の方向性が期待できることなどが挙げられます。 また、消費の面で言うと、世界経済、特に中国経済の停滞による原油消費量の減少が原油価格の低下に拍車をかけているようです。 日本は資源を輸入して製品を輸出する貿易構造があるため、原油価格の下落はおおむねプラスの方向に働くと考えられます。 しかし、急激な原油価格下落は、世界経済全体の停滞による要因もあるため、結果的に輸出の減速等かならずしもプラスに働かない部分もあります。 いずれにしても、原油が投機的取引され価格が乱高下する状況は好ましくありません。 実態に即した経済であって欲しいものです。
 このブログでも、時折ガソリンなど原油価格について言及してきました。
師走の値上げラッシュ(2007/12/1) リッター143円
原油高騰でもサンマは安値(2008/10/5) リッター180円
実態からかけ離れてしまった経済(2008/12/22) リッター99円
ガソリン価格下落傾向(2011/5/25) リッター137円
原油高騰が続く︵2014/6/26) リッター140円
改めて見ると、ここ10年の乱高下は激しいですね。
特に2008年︵平成20年︶10月から12月にかけての急激な下落は記憶に新しいところです。
総務省統計局﹁小売物価統計調査﹂資料を見ると、その乱高下の様子がグラフに如実に現れています。
このブログでも、時折ガソリンなど原油価格について言及してきました。
師走の値上げラッシュ(2007/12/1) リッター143円
原油高騰でもサンマは安値(2008/10/5) リッター180円
実態からかけ離れてしまった経済(2008/12/22) リッター99円
ガソリン価格下落傾向(2011/5/25) リッター137円
原油高騰が続く︵2014/6/26) リッター140円
改めて見ると、ここ10年の乱高下は激しいですね。
特に2008年︵平成20年︶10月から12月にかけての急激な下落は記憶に新しいところです。
総務省統計局﹁小売物価統計調査﹂資料を見ると、その乱高下の様子がグラフに如実に現れています。
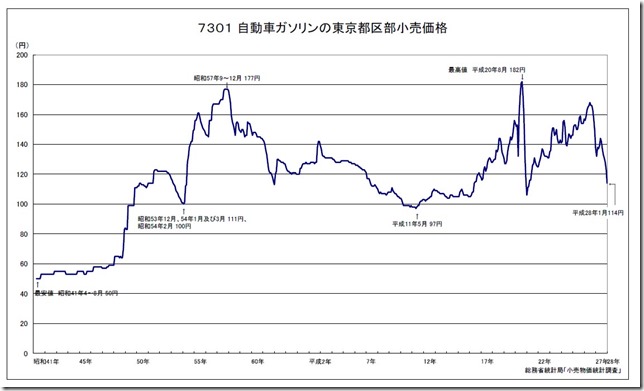 しかし、再びリッター100円を割る日が来るとは・・・・
しかし、再びリッター100円を割る日が来るとは・・・・
原油価格は、他の資源と同様、生産量と消費量の需給関係で価格が影響されます。 生産の面で言うと、OPECの減産見送りによる供給がある程度潤沢に保たれていること、シエールガス開発などエネルギーの多様化の方向性が期待できることなどが挙げられます。 また、消費の面で言うと、世界経済、特に中国経済の停滞による原油消費量の減少が原油価格の低下に拍車をかけているようです。 日本は資源を輸入して製品を輸出する貿易構造があるため、原油価格の下落はおおむねプラスの方向に働くと考えられます。 しかし、急激な原油価格下落は、世界経済全体の停滞による要因もあるため、結果的に輸出の減速等かならずしもプラスに働かない部分もあります。 いずれにしても、原油が投機的取引され価格が乱高下する状況は好ましくありません。 実態に即した経済であって欲しいものです。
2016年1月10日
お寺の年末調整事務
注︶本日のブログ記事は、ちょっと突っ込んだ内容となっております。お寺はそれぞれ独立の法人であり収支項目の内訳はそれぞれ異なります。
当ブログは﹁貞昌院についての内容﹂ですのでご留意下さい。
給与所得を何処からか得ている方は、年末の時期に﹁給与所得の源泉徴収票﹂をもらっていると思います。 また、従業員を雇っている法人であれば﹁給与所得の源泉徴収票﹂を作成して従業員に交付しているはずです。 今回はマイナンバー制度の実施で、ちょっと事務処理が煩雑になりました。 さて、お寺としては常識でも、意外に知られていないことですが、お寺も法人ですから当然に従業員︵住職・副住職・寺族等︶に給料が支払われている場合には、一般の会社と同じ所得税が課せられます。 お坊さんは税金を払わなくて良い、というのは大きな誤解であり、サラリーマンと同率の所得税の支払い義務があります。 ということで、貞昌院でも﹁給与所得の源泉徴収票﹂を発行しています。
年末調整がなぜ必要なのかといえば、副業や出費など、イレギュラーな部分を調整する必要があるからですね。 私の場合は、今年は本山の大遠忌局から給与所得︵出勤日に対し1日1万円程度のの日給制︶を得ましたので、その分も加味して申告しています。
それでは、なぜ ﹁お坊さんって、税金払わなくていいね﹂という誤解が生じるかというと、お寺という﹁宗教法人﹂は公益法人であり、一部の税金が免除、あるいは軽減されているということに原因があるのでしょう。 つまり、法人会計の一部は税金が免除、あるいは軽減されるといことです。
宗教法人としての宗教活動に係る収入は︵地方税法72条の4(1)︶により 公益法人等の非課税所得 次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外については、事業税が課されない。 (1) 法人税法別表第二第1号に規定する独立行政法人 (2) 日本赤十字社、商工会議所、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、職業訓練法人等 (3) 弁護士会等 (4) 労働組合等 (5) 漁船保険組合、信用保証協会、農業信用基金協会、国民健康保険組合、厚生年金基金等 (6) 市街地再開発組合等 (7) 日本自転車振興会等 (8) 中小企業総合事業団等 (9) 外国法人で法人税法別表第二第2号に規定する法人 (10) 管理組合法人等 (11) 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた団体 (12) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党又は政治団体 (13) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人 (14) 人格のない社団等 とされています。 この税金が免除、あるいは軽減されるという制度は、そのお寺の檀家さんにメリットがある制度であるということを理解いただけるとありがたいです。
具体的に、﹁貞昌院の法人としての収入、支出のグラフ﹂から説明します。 薄青色のグラフが収入項目、薄黄色のグラフが支出項目です。
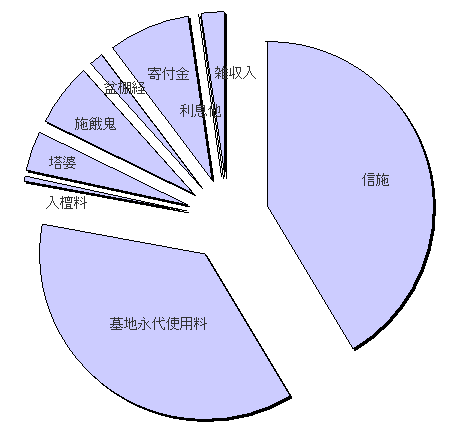
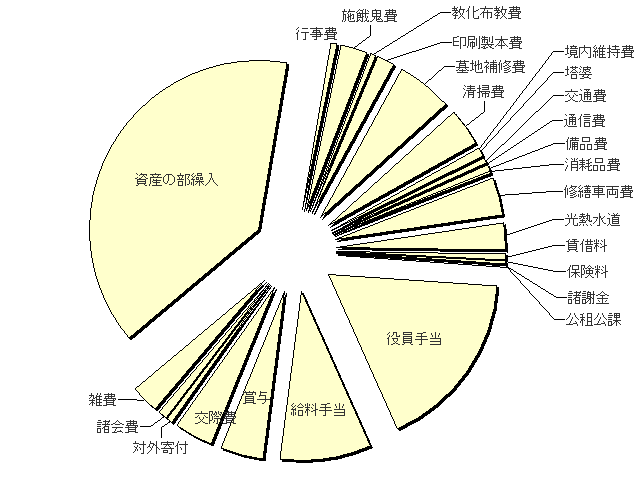
収入項目の﹁信施﹂は、葬儀、法事等で檀家さんからお預かりし寺院会計に入る﹁お布施﹂です。 これら様々な収入により寺院会計の収入が構成され、寺院の運営に資されることになります。 その使いみちが支出のグラフです。 うち、給与手当等従業員に支払われる部分が、住職など各従業員の給与となり、それぞれの給与所得者は源泉徴収により税金を払うということになります。 これが﹁給与所得の源泉徴収票﹂です。
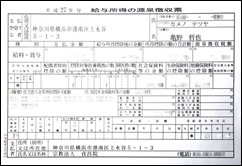 つまり、住職を含め従業員の個人所得には、所得税が一般のサラリーマンと同率にて課せられます。
そして、法人としての寺院会計の宗教活動に資される部分︵つまり、本堂や客殿など檀家さんなどの利用に資される共有部分︶については免除、あるいは軽減となっています。
これが、宗教法人の免除、あるいは軽減されることでメリットを享受するのは、お寺の檀家さんであるという理由です。
昨今は税金の財源を確保するために、公益法人への課税が検討されたりしていますが、公益法人への一律の課税は檀家さんにとっては税金の負担が増えることになるので、私としては賛成ではありません。
もし、公益法人への課税を行なうのであれば、一定以上の規模があり、余剰利益が相応にある法人のみを対象にしていただきたいものです。
税金に限らず、寺院を取りまく経済的な環境は、今後厳しい方向に進んでいくことでしょう。
そのような状況を見据えて、寺院運営については会計処理に関しても充分先を見据えた着実な運営が求められると感じます。
これからも気を引き締めて 寺院の果たすべき社会的責任 で提示した各項目を着実に実行していこうと考えています。
つまり、住職を含め従業員の個人所得には、所得税が一般のサラリーマンと同率にて課せられます。
そして、法人としての寺院会計の宗教活動に資される部分︵つまり、本堂や客殿など檀家さんなどの利用に資される共有部分︶については免除、あるいは軽減となっています。
これが、宗教法人の免除、あるいは軽減されることでメリットを享受するのは、お寺の檀家さんであるという理由です。
昨今は税金の財源を確保するために、公益法人への課税が検討されたりしていますが、公益法人への一律の課税は檀家さんにとっては税金の負担が増えることになるので、私としては賛成ではありません。
もし、公益法人への課税を行なうのであれば、一定以上の規模があり、余剰利益が相応にある法人のみを対象にしていただきたいものです。
税金に限らず、寺院を取りまく経済的な環境は、今後厳しい方向に進んでいくことでしょう。
そのような状況を見据えて、寺院運営については会計処理に関しても充分先を見据えた着実な運営が求められると感じます。
これからも気を引き締めて 寺院の果たすべき社会的責任 で提示した各項目を着実に実行していこうと考えています。
注︶本日のブログ記事は、ちょっと突っ込んだ内容となっており特に収支項目の内訳は﹁貞昌院についての内容﹂ですのでご留意下さい。大事なことなので2回書きました。 注2︶寺院会計の﹁資産の部繰入﹂は、この春に貞昌院で行なう予定の大きな行持のための繰入です。繰入は伽藍改修や法要費として使われ、檀家さんの負担が無いよう一時的に内部留保を増やしています。その行持については檀家さんには先月お知らせいたしました。
■関連ブログ記事
坊主は丸儲けかなぁ
経済学の視点から見たお寺
給与所得を何処からか得ている方は、年末の時期に﹁給与所得の源泉徴収票﹂をもらっていると思います。 また、従業員を雇っている法人であれば﹁給与所得の源泉徴収票﹂を作成して従業員に交付しているはずです。 今回はマイナンバー制度の実施で、ちょっと事務処理が煩雑になりました。 さて、お寺としては常識でも、意外に知られていないことですが、お寺も法人ですから当然に従業員︵住職・副住職・寺族等︶に給料が支払われている場合には、一般の会社と同じ所得税が課せられます。 お坊さんは税金を払わなくて良い、というのは大きな誤解であり、サラリーマンと同率の所得税の支払い義務があります。 ということで、貞昌院でも﹁給与所得の源泉徴収票﹂を発行しています。
年末調整がなぜ必要なのかといえば、副業や出費など、イレギュラーな部分を調整する必要があるからですね。 私の場合は、今年は本山の大遠忌局から給与所得︵出勤日に対し1日1万円程度のの日給制︶を得ましたので、その分も加味して申告しています。
それでは、なぜ ﹁お坊さんって、税金払わなくていいね﹂という誤解が生じるかというと、お寺という﹁宗教法人﹂は公益法人であり、一部の税金が免除、あるいは軽減されているということに原因があるのでしょう。 つまり、法人会計の一部は税金が免除、あるいは軽減されるといことです。
宗教法人としての宗教活動に係る収入は︵地方税法72条の4(1)︶により 公益法人等の非課税所得 次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外については、事業税が課されない。 (1) 法人税法別表第二第1号に規定する独立行政法人 (2) 日本赤十字社、商工会議所、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、職業訓練法人等 (3) 弁護士会等 (4) 労働組合等 (5) 漁船保険組合、信用保証協会、農業信用基金協会、国民健康保険組合、厚生年金基金等 (6) 市街地再開発組合等 (7) 日本自転車振興会等 (8) 中小企業総合事業団等 (9) 外国法人で法人税法別表第二第2号に規定する法人 (10) 管理組合法人等 (11) 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた団体 (12) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党又は政治団体 (13) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人 (14) 人格のない社団等 とされています。 この税金が免除、あるいは軽減されるという制度は、そのお寺の檀家さんにメリットがある制度であるということを理解いただけるとありがたいです。
具体的に、﹁貞昌院の法人としての収入、支出のグラフ﹂から説明します。 薄青色のグラフが収入項目、薄黄色のグラフが支出項目です。
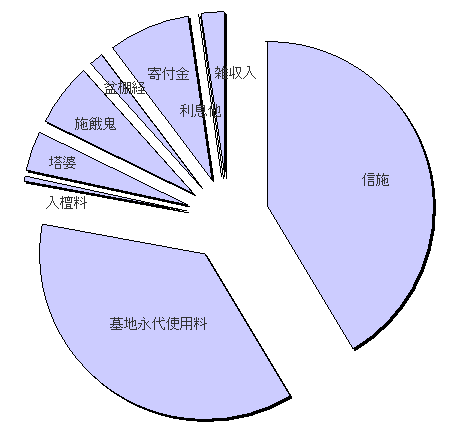
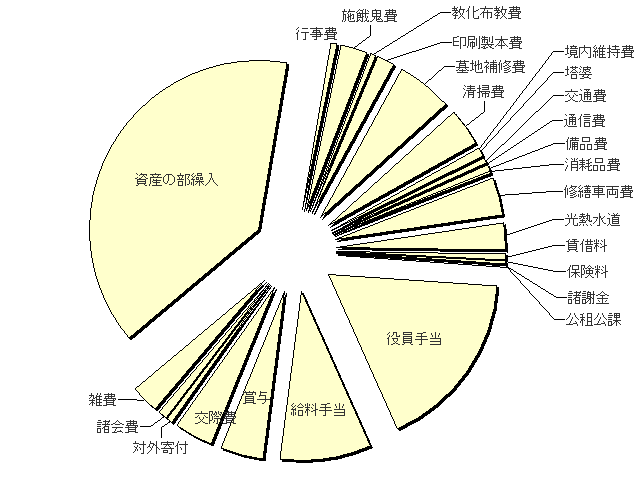
収入項目の﹁信施﹂は、葬儀、法事等で檀家さんからお預かりし寺院会計に入る﹁お布施﹂です。 これら様々な収入により寺院会計の収入が構成され、寺院の運営に資されることになります。 その使いみちが支出のグラフです。 うち、給与手当等従業員に支払われる部分が、住職など各従業員の給与となり、それぞれの給与所得者は源泉徴収により税金を払うということになります。 これが﹁給与所得の源泉徴収票﹂です。
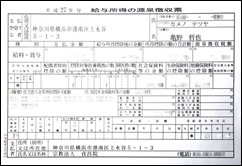 つまり、住職を含め従業員の個人所得には、所得税が一般のサラリーマンと同率にて課せられます。
そして、法人としての寺院会計の宗教活動に資される部分︵つまり、本堂や客殿など檀家さんなどの利用に資される共有部分︶については免除、あるいは軽減となっています。
これが、宗教法人の免除、あるいは軽減されることでメリットを享受するのは、お寺の檀家さんであるという理由です。
昨今は税金の財源を確保するために、公益法人への課税が検討されたりしていますが、公益法人への一律の課税は檀家さんにとっては税金の負担が増えることになるので、私としては賛成ではありません。
もし、公益法人への課税を行なうのであれば、一定以上の規模があり、余剰利益が相応にある法人のみを対象にしていただきたいものです。
税金に限らず、寺院を取りまく経済的な環境は、今後厳しい方向に進んでいくことでしょう。
そのような状況を見据えて、寺院運営については会計処理に関しても充分先を見据えた着実な運営が求められると感じます。
これからも気を引き締めて 寺院の果たすべき社会的責任 で提示した各項目を着実に実行していこうと考えています。
つまり、住職を含め従業員の個人所得には、所得税が一般のサラリーマンと同率にて課せられます。
そして、法人としての寺院会計の宗教活動に資される部分︵つまり、本堂や客殿など檀家さんなどの利用に資される共有部分︶については免除、あるいは軽減となっています。
これが、宗教法人の免除、あるいは軽減されることでメリットを享受するのは、お寺の檀家さんであるという理由です。
昨今は税金の財源を確保するために、公益法人への課税が検討されたりしていますが、公益法人への一律の課税は檀家さんにとっては税金の負担が増えることになるので、私としては賛成ではありません。
もし、公益法人への課税を行なうのであれば、一定以上の規模があり、余剰利益が相応にある法人のみを対象にしていただきたいものです。
税金に限らず、寺院を取りまく経済的な環境は、今後厳しい方向に進んでいくことでしょう。
そのような状況を見据えて、寺院運営については会計処理に関しても充分先を見据えた着実な運営が求められると感じます。
これからも気を引き締めて 寺院の果たすべき社会的責任 で提示した各項目を着実に実行していこうと考えています。
注︶本日のブログ記事は、ちょっと突っ込んだ内容となっており特に収支項目の内訳は﹁貞昌院についての内容﹂ですのでご留意下さい。大事なことなので2回書きました。 注2︶寺院会計の﹁資産の部繰入﹂は、この春に貞昌院で行なう予定の大きな行持のための繰入です。繰入は伽藍改修や法要費として使われ、檀家さんの負担が無いよう一時的に内部留保を増やしています。その行持については檀家さんには先月お知らせいたしました。
2015年5月19日
IT業界紙連載記事満了
2014年夏より、IT業界で購読されている新聞に記事を連載させていただいていておりましたが、今月で11回の連載が満了となりました。
読者はインターネット、コンピュータ、通信関連の関係者がほとんどということで、当該の連載記事もIT企業の社長さんや行政機関の責任者、研究者などが多いのですが、袈裟を掛けた写真付きで連載させていただています。
お寺とIT業界は、一見無関係、あるいは相反するようなイメージが有りますが、決してそうではないということから話を進めています。
連載は
寺院とはその場所にあり続け、その情報を受け継ぐ人がおり、地域における役割も大きい︵第1回︶
伝統とは時代や環境の変化に応じて変わり続けるものであり、伝統的と思われるものは意外に歴史が浅いこともある︵第2回︶
仏教とCMCはそもそも融合しやすい性格を持ち、情報技術の分野では宗教がそれを牽引してきた︵第3~5回︶
情報化社会だからこそ、その利便性に流されること無く、適度な距離を保ち、適度な間合いを取ることを学ぶことが必要︵第6回︶
災害時におけるネットワークの重要性︵第7・8回︶
地域活動の連携と情報大量消費の時代に向けて︵第9回︶
寺院への市場拡大の余地と課題︵第10回︶
観光立国﹁日本﹂の確立に向けて︵第11回︶
というような内容で展開いたしました。
このような機会を与えていただくことはありがたいことです。












2015年4月 4日
レモンジーナの情報作戦
サントリー食品﹁レモンジーナ﹂販売一時休止、年間目標を2日で出荷 サントリー食品インターナショナルは1日、果汁入り炭酸飲料﹁レモンジーナ﹂の販売を一時休止すると発表した。3月31日に発売したが、予想を超える販売量で、安定供給ができないため、生産体制が整うまで、出荷を休止する。 同社によると、今年12月末までの販売計画を100万ケースとしていたが、1日までに出荷が125万ケースと、2日間で、年間目標を超える異常事態となった。このため、420ミリリットル入りペットボトルと1.2リットル入りペットボトルともに休止した。自社の国内3工場と協力会社で生産する計画だが、生産体制を早急に確保したいとしている。 (Yahoo!ニュース 2015/4/1)ここのところ、このような需要と今日中バランスが極端な報道が多いですね。 東京駅開業100周年記念スイカの事例もまだ記憶に新しい中、冒頭のようなニュースがテレビ・新聞・ネットニュースなどで一斉に流されました。 ところが、今回のレモンジーナの件については他と少し様相が異なります。 今は情報化社会。 4月1日の報道から2日ほど経ったあたりからFacebookやTwitterではこんな画像がたくさん流れています。
ちなみに、近所のスーパーでもレモンジーナが潤沢に陳列されていました。 明日が貞昌院花まつり、護持会総会懇親会なので、参列の方にお出しする飲み物にもせっかくなのでレモンジーナを加えてみました。 レモンジーナは﹁土の味﹂という噂も検証してみたいものです。
しかし、これらの様子から判断するに、レモンジーナの件は在庫を掃くためのステマのようにも思えてきます。 もしくは、﹁2日間で、年間目標を超える異常事態となった﹂理由が、﹁人気があり需要が多かった﹂のではなく、﹁単に出荷数量をメーカー側で間違えた﹂のではないかと拝察します。 このため、冒頭のような情報を配信して出荷数量分をなんとか販売したいという思惑があるようにも見えるのです。 もしそうだとしたら今回の件がサントリーの企業イメージ低下につながる可能性も無きにしもあらず。
さらに、ヤフオクにはたくさんのレモンジーナが︻販売休止︼タグがつけられて出品されています。 販売休止に絡んで儲けようとする人も少なからずいるのでしょうか。 FacebookやTwitterなどが普及していない数年前であれば、﹁話題の商品﹂ということで、あっという間に売れるのでしょうけれども、近隣のスーパーやTwitter上ではどうやらそんなに売れているようには思えません。 しかし情報の裏の裏まで読まないと、後で痛い目にあうかもしれないですね。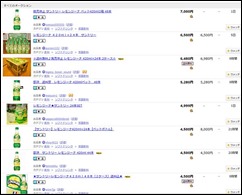
2014年12月17日
チョイモビにちょい乗り
2015年まで行なわれている﹁ワンウエイカーシェア﹂社会実証実験のチョイモビを便利に利用させて頂いています。
以前書いたブログ⇒ ワンウェイ型カーシェアリング﹁チョイモビ﹂
この日は宗務所役職員歓送迎会を開催いただいたこともあり、みなとみらい地区の会場までチョイモビに乗って行きました。
窓のない車で雨模様の天気を運転することが心配でしたが、走りだせば雨はほとんど入ってきません。
車両重量が軽いため、加速力はかなりあります。
 ちっちゃい車なのに2人乗りです。
ちっちゃい車なのに2人乗りです。
 無事会場に到着。
新旧役職員歓送迎会へは多くの皆様にご来駕いただきました。
4年間お世話になりました。
これからの新役職員の皆様↓よろしくお願いいたします。
無事会場に到着。
新旧役職員歓送迎会へは多くの皆様にご来駕いただきました。
4年間お世話になりました。
これからの新役職員の皆様↓よろしくお願いいたします。
 ■関連サイト
チョイモビ公式サイト
■関連サイト
チョイモビ公式サイト
 ちっちゃい車なのに2人乗りです。
ちっちゃい車なのに2人乗りです。
 無事会場に到着。
新旧役職員歓送迎会へは多くの皆様にご来駕いただきました。
4年間お世話になりました。
これからの新役職員の皆様↓よろしくお願いいたします。
無事会場に到着。
新旧役職員歓送迎会へは多くの皆様にご来駕いただきました。
4年間お世話になりました。
これからの新役職員の皆様↓よろしくお願いいたします。

2014年6月26日
原油高騰が続く
5年前にはレギュラーガソリン価格は100円を切っていたのに・・・・・・
 ここのところ、中東・イラクで起こっているイスラム教反政府勢力による内戦、ロシアとウクライナの問題など国際情勢が不安定な状態になっており、原油価格が高騰しています。
ここのところ、中東・イラクで起こっているイスラム教反政府勢力による内戦、ロシアとウクライナの問題など国際情勢が不安定な状態になっており、原油価格が高騰しています。
原油価格の国際指標となる米国産標準油種(WTI)のチャートはこんな感じで推移しています。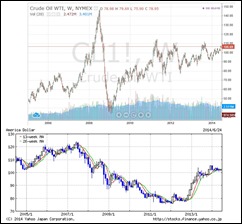
直近の米国産標準油種(WTI)価格は1バレル 106ドルを超え、9カ月ぶりの高水準となりました。 これにより、日本の原油の輸入価格上昇がレギュラーガソリン、重油や軽油に波及しています。 当然に関連の業種︵運輸業・漁業・製造業など︶燃料や石油を元にしる産業への影響は大きなものとなります。
冒頭の米国産標準油種(WTI)チャートと併せて、円ードルの為替チャートも併記してみました。 ガソリン価格の高等は円高の影響という印象はありますが、5年ほどの中期で観ても、決してそんなことはないということがわかります。 リーマン・ショック直前︵2008年︶までは、1ドル120円程度で推移しており、この時期、米国産標準油種(WTI)価格は1バレル 140ドルを超えていました。 このように、わずか5年間だけを取ってみても、原油価格や為替レートの変動が激しくなっています。 したがって、化石燃料だけというように、一つの原料に頼る社会構造は非常に脆弱な側面を持つということを心しておかなければなりません。 原油の高騰傾向は今後暫く続くと考えられます。 さて、東日本大震災をきっかけに、日本のエネルギー供給構造が一変しました。 一例として、電力がどのようなエネルギーにより供給されているのかを改めて考えてみます。 震災前は、石炭・LNG・石油等の化石燃料による発電は約60%でした。
震災直後の2012年は化石燃料が92%。
現在は原子力発電はゼロとなっていますから、化石燃料による発電が94%程度となっています。
すなわち、日本経済全体が﹁国際情勢による原油価格の影響を﹂まともに受ける形となっています。
高度経済成長期、日本の火力発電は化石燃料を活用してきました。
しかし、国際的には、1975年の第3回国際エネルギー機関閣僚理事会において﹁石炭利用拡大に関するIEA宣言﹂による﹁石油火力発電所の新設禁止﹂が採決され、それがスタンダードになっています。
震災前は、石炭・LNG・石油等の化石燃料による発電は約60%でした。
震災直後の2012年は化石燃料が92%。
現在は原子力発電はゼロとなっていますから、化石燃料による発電が94%程度となっています。
すなわち、日本経済全体が﹁国際情勢による原油価格の影響を﹂まともに受ける形となっています。
高度経済成長期、日本の火力発電は化石燃料を活用してきました。
しかし、国際的には、1975年の第3回国際エネルギー機関閣僚理事会において﹁石炭利用拡大に関するIEA宣言﹂による﹁石油火力発電所の新設禁止﹂が採決され、それがスタンダードになっています。
近年懸念される 原油価格の高騰により、火力発電コストは上昇しており、電力料金もさらに高騰傾向にあります。 原子力発電所の可動がゼロとなっている今は、その影響が顕著になっています。
少なくとも、現在の日本の経済が、原油価格の影響をまともに受ける状況にあることを認識しておき、今後の貿易収支の推移にも着目する必要があるでしょう。
■関連ブログ記事
実態からかけ離れてしまった経済(2008/12/22)
ディーゼルエンジン頑張れ (2008/12/17)
原油高騰でもサンマは安値(2008/10/5)
法事の盛籠からみるマクロ経済
 ここのところ、中東・イラクで起こっているイスラム教反政府勢力による内戦、ロシアとウクライナの問題など国際情勢が不安定な状態になっており、原油価格が高騰しています。
ここのところ、中東・イラクで起こっているイスラム教反政府勢力による内戦、ロシアとウクライナの問題など国際情勢が不安定な状態になっており、原油価格が高騰しています。
原油価格の国際指標となる米国産標準油種(WTI)のチャートはこんな感じで推移しています。
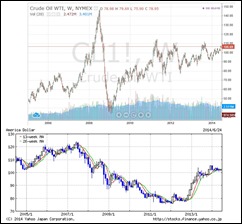
直近の米国産標準油種(WTI)価格は1バレル 106ドルを超え、9カ月ぶりの高水準となりました。 これにより、日本の原油の輸入価格上昇がレギュラーガソリン、重油や軽油に波及しています。 当然に関連の業種︵運輸業・漁業・製造業など︶燃料や石油を元にしる産業への影響は大きなものとなります。
冒頭の米国産標準油種(WTI)チャートと併せて、円ードルの為替チャートも併記してみました。 ガソリン価格の高等は円高の影響という印象はありますが、5年ほどの中期で観ても、決してそんなことはないということがわかります。 リーマン・ショック直前︵2008年︶までは、1ドル120円程度で推移しており、この時期、米国産標準油種(WTI)価格は1バレル 140ドルを超えていました。 このように、わずか5年間だけを取ってみても、原油価格や為替レートの変動が激しくなっています。 したがって、化石燃料だけというように、一つの原料に頼る社会構造は非常に脆弱な側面を持つということを心しておかなければなりません。 原油の高騰傾向は今後暫く続くと考えられます。 さて、東日本大震災をきっかけに、日本のエネルギー供給構造が一変しました。 一例として、電力がどのようなエネルギーにより供給されているのかを改めて考えてみます。
 震災前は、石炭・LNG・石油等の化石燃料による発電は約60%でした。
震災直後の2012年は化石燃料が92%。
現在は原子力発電はゼロとなっていますから、化石燃料による発電が94%程度となっています。
すなわち、日本経済全体が﹁国際情勢による原油価格の影響を﹂まともに受ける形となっています。
高度経済成長期、日本の火力発電は化石燃料を活用してきました。
しかし、国際的には、1975年の第3回国際エネルギー機関閣僚理事会において﹁石炭利用拡大に関するIEA宣言﹂による﹁石油火力発電所の新設禁止﹂が採決され、それがスタンダードになっています。
震災前は、石炭・LNG・石油等の化石燃料による発電は約60%でした。
震災直後の2012年は化石燃料が92%。
現在は原子力発電はゼロとなっていますから、化石燃料による発電が94%程度となっています。
すなわち、日本経済全体が﹁国際情勢による原油価格の影響を﹂まともに受ける形となっています。
高度経済成長期、日本の火力発電は化石燃料を活用してきました。
しかし、国際的には、1975年の第3回国際エネルギー機関閣僚理事会において﹁石炭利用拡大に関するIEA宣言﹂による﹁石油火力発電所の新設禁止﹂が採決され、それがスタンダードになっています。
近年懸念される 原油価格の高騰により、火力発電コストは上昇しており、電力料金もさらに高騰傾向にあります。 原子力発電所の可動がゼロとなっている今は、その影響が顕著になっています。
少なくとも、現在の日本の経済が、原油価格の影響をまともに受ける状況にあることを認識しておき、今後の貿易収支の推移にも着目する必要があるでしょう。
2014年6月14日
観光立国「日本」の確立へ(2)
今回のブログ記事は 観光立国﹁日本﹂の確立へ の続編です。
旅行情報を提供しているサイト﹁トリップアドバイザー﹂が、今月上旬に﹁口コミで選ぶ 行ってよかった!外国人に人気の日本の観光スポット 2014﹂のランキングを発表しました。
これは、日本を訪問した外国人の口コミ評価を元に、外国人の満足度を順位付けしたものです。
その結果がこちら。元データはこちらに有ります。
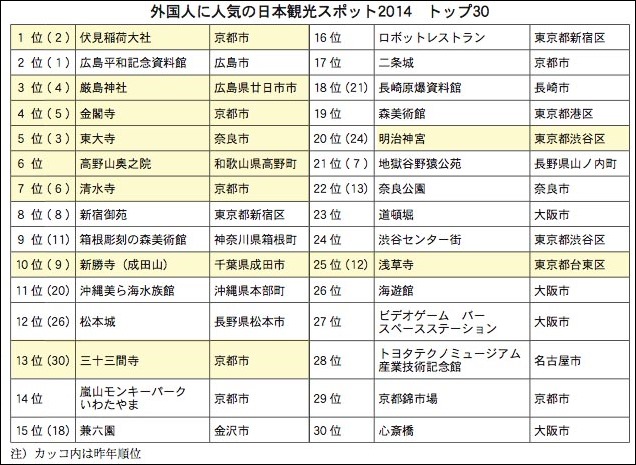
※ランキングはトリップアドバイザーによる。kamenoにより黄色着色を行った。
きっと、日本人が選ぶ国内の旅行先でランキングを行なうとTDLなどのアミューズメント施設が入るなど、全く違ったランキングになることでしょう。 しかし、この海外目線からのランキングはとても参考になります。 特筆すべきは、ランキングに寺社が多く入っているということです。 ランキングの中で、寺院・神社を黄色に着色してみました。
このランキングの傾向は、明治時代に行なわれた神奈川県名勝史蹟四十五佳選とも通じるものがあるような感じがします。 いずれにしても、日本の﹁アイコン﹂ともいえる鳥居の光景は、海外からの旅行者にとっては特に印象的なようです。 また、古来から培われてきた信仰や風習を体感できる場所は、日本を理解していただく上でとても重要な場所とも言えます。 特に日本文化の礎ともいえる ・日本庭園 ・茶の湯 ・坐禅 ・精進料理 ・木造建築 などに関しては、﹁寺院﹂、特に禅宗の寺院がその役割を担うことが期待されているのではないでしょうか。
何と言っても、日本には7万もの寺院、曹洞宗だけでも1万5千か寺もあります。 観光スポッットで有名な寺院ばかりではなく、ごく普通の寺院でも、いや、ごく普通の寺院だからこそきめ細かい受け入れや対応も可能となるでしょう。 例えば、坐禅をしてみたい、お寺の庭を見たい、本堂にお参りしたい、茶の湯をしてみたい・・・・・・ 海外からの旅行者のそのような要望に柔軟に対応できる体制づくりを︵理想的には︶宗門が連携して整えていくことが必要でしょう。 もちろん寺院によって得意な分野や苦手な分野があるでしょうから、その情報発信と共有も必要といえます。 寺院どうしが連携して﹁日本独自の文化﹂としての﹁禅﹂ブランドを活用していくことも有効でしょう。 まずは﹁多言語に依る情報発信﹂と﹁受入体制﹂。 この2つを整えることが早急かつ重要な課題です。 日本の貿易収支が過去最悪の赤字を更新する中、2014年4月中の国際収支状況︵速報︶では、﹁旅行収支﹂が44年ぶりに177億円の黒字となっりました。 4月の訪日外国人旅行者数は前年比33.4%増の123万1500人なのに対し、出国日本人数は4.4%減の119万0000人と、インバウンドとアウトバウンドが人数で逆転します。 旅行収支という結果にも、観光立国に向けての成果が少しづつ現れ始めています。 今後、東京オリンピック開催に向けて、海外からの旅行者はますます増えていくことでしょう。
その結果がこちら。元データはこちらに有ります。
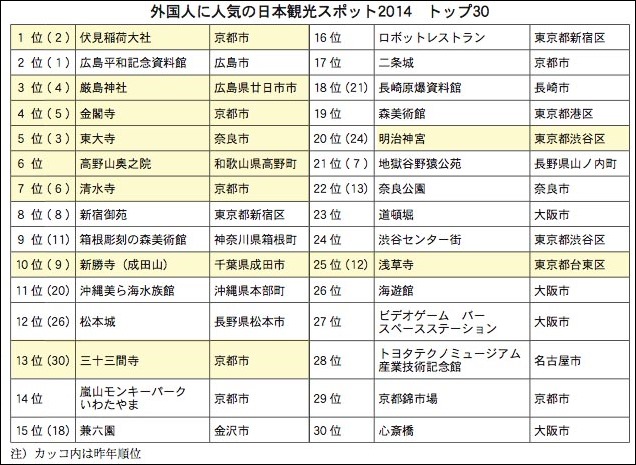
※ランキングはトリップアドバイザーによる。kamenoにより黄色着色を行った。
きっと、日本人が選ぶ国内の旅行先でランキングを行なうとTDLなどのアミューズメント施設が入るなど、全く違ったランキングになることでしょう。 しかし、この海外目線からのランキングはとても参考になります。 特筆すべきは、ランキングに寺社が多く入っているということです。 ランキングの中で、寺院・神社を黄色に着色してみました。
このランキングの傾向は、明治時代に行なわれた神奈川県名勝史蹟四十五佳選とも通じるものがあるような感じがします。 いずれにしても、日本の﹁アイコン﹂ともいえる鳥居の光景は、海外からの旅行者にとっては特に印象的なようです。 また、古来から培われてきた信仰や風習を体感できる場所は、日本を理解していただく上でとても重要な場所とも言えます。 特に日本文化の礎ともいえる ・日本庭園 ・茶の湯 ・坐禅 ・精進料理 ・木造建築 などに関しては、﹁寺院﹂、特に禅宗の寺院がその役割を担うことが期待されているのではないでしょうか。
何と言っても、日本には7万もの寺院、曹洞宗だけでも1万5千か寺もあります。 観光スポッットで有名な寺院ばかりではなく、ごく普通の寺院でも、いや、ごく普通の寺院だからこそきめ細かい受け入れや対応も可能となるでしょう。 例えば、坐禅をしてみたい、お寺の庭を見たい、本堂にお参りしたい、茶の湯をしてみたい・・・・・・ 海外からの旅行者のそのような要望に柔軟に対応できる体制づくりを︵理想的には︶宗門が連携して整えていくことが必要でしょう。 もちろん寺院によって得意な分野や苦手な分野があるでしょうから、その情報発信と共有も必要といえます。 寺院どうしが連携して﹁日本独自の文化﹂としての﹁禅﹂ブランドを活用していくことも有効でしょう。 まずは﹁多言語に依る情報発信﹂と﹁受入体制﹂。 この2つを整えることが早急かつ重要な課題です。 日本の貿易収支が過去最悪の赤字を更新する中、2014年4月中の国際収支状況︵速報︶では、﹁旅行収支﹂が44年ぶりに177億円の黒字となっりました。 4月の訪日外国人旅行者数は前年比33.4%増の123万1500人なのに対し、出国日本人数は4.4%減の119万0000人と、インバウンドとアウトバウンドが人数で逆転します。 旅行収支という結果にも、観光立国に向けての成果が少しづつ現れ始めています。 今後、東京オリンピック開催に向けて、海外からの旅行者はますます増えていくことでしょう。
2014年3月 7日
あべのアルカス本日オープン
これまで日本一の高さだった﹁横浜ランドマークタワー﹂を抜いて日本一のビルとなる﹁あべのハルカス﹂︵大阪市阿倍野区︶が本日全面開業しました。
ちょうど、この時期に人権学習で大阪方面に来ていたので、その熱気を少しなら感じることが出来ました。
■日本の高層ビルベスト3 第1位 あべのハルカス︵大阪府大阪市) 地上高 300m 60階 2014年竣工 第2位 横浜ランドマークタワー︵神奈川県横浜市︶ 地上高 295.8m 70階 1993年竣工 第3位 りんくうゲートタワービル︵大阪府泉佐野市︶ 地上高 256.1m 56階 1996年 大阪府泉佐野市 難波から眺めると、飛び抜けて高いビルが目につきます。 この高いビルが﹁あべのハルカス﹂です。 少し右に通天閣が見えます。
その高さの差は歴然ですね。
間近の天王寺から見上げると、迫力の光景です。
少し右に通天閣が見えます。
その高さの差は歴然ですね。
間近の天王寺から見上げると、迫力の光景です。
 先行営業している﹁あべのハルカス近鉄本店﹂は、営業面積10万平方メートルにも及ぶ日本最大の百貨店です。
圧倒的な広さで、様々な名店があつまり見ているだけで楽しいです。
先行営業している﹁あべのハルカス近鉄本店﹂は、営業面積10万平方メートルにも及ぶ日本最大の百貨店です。
圧倒的な広さで、様々な名店があつまり見ているだけで楽しいです。

 そして、本日︵3月7日︶の全面開業。
百貨店の入り口を起点に、ビル全体︵展望台・ホテルなど同ビル内の5会場とHoop、あべのキューズモール、新宿ごちそうビル︶をぐるりとテープが取り巻いています。
10時のオープニングセレモニーでは、この全長約3000メートルのテープを市民300人が参加して﹁日本一長い 街つなぎテープカット﹂が行われます。
そして、本日︵3月7日︶の全面開業。
百貨店の入り口を起点に、ビル全体︵展望台・ホテルなど同ビル内の5会場とHoop、あべのキューズモール、新宿ごちそうビル︶をぐるりとテープが取り巻いています。
10時のオープニングセレモニーでは、この全長約3000メートルのテープを市民300人が参加して﹁日本一長い 街つなぎテープカット﹂が行われます。



 オープニング直前の展望台入口
オープニング直前の展望台入口
 近鉄あべの駅では、記念入場券が売りだされていました。
近鉄あべの駅では、記念入場券が売りだされていました。
 あべのハルカス前の通りは、街路工事が進行しています。
あべのハルカス前の通りは、街路工事が進行しています。

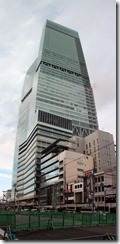 年間予想来店客数は4500万人、初年度目標売上高は1,450億円の﹁あべのハルカス﹂を中心に街並みが整備され、大阪の経済の中心もどんどん変化していくことでしょう。
大阪版﹁あべのミクス﹂ですね。
年間予想来店客数は4500万人、初年度目標売上高は1,450億円の﹁あべのハルカス﹂を中心に街並みが整備され、大阪の経済の中心もどんどん変化していくことでしょう。
大阪版﹁あべのミクス﹂ですね。
■日本の高層ビルベスト3 第1位 あべのハルカス︵大阪府大阪市) 地上高 300m 60階 2014年竣工 第2位 横浜ランドマークタワー︵神奈川県横浜市︶ 地上高 295.8m 70階 1993年竣工 第3位 りんくうゲートタワービル︵大阪府泉佐野市︶ 地上高 256.1m 56階 1996年 大阪府泉佐野市 難波から眺めると、飛び抜けて高いビルが目につきます。 この高いビルが﹁あべのハルカス﹂です。
 少し右に通天閣が見えます。
その高さの差は歴然ですね。
間近の天王寺から見上げると、迫力の光景です。
少し右に通天閣が見えます。
その高さの差は歴然ですね。
間近の天王寺から見上げると、迫力の光景です。
 先行営業している﹁あべのハルカス近鉄本店﹂は、営業面積10万平方メートルにも及ぶ日本最大の百貨店です。
圧倒的な広さで、様々な名店があつまり見ているだけで楽しいです。
先行営業している﹁あべのハルカス近鉄本店﹂は、営業面積10万平方メートルにも及ぶ日本最大の百貨店です。
圧倒的な広さで、様々な名店があつまり見ているだけで楽しいです。

 そして、本日︵3月7日︶の全面開業。
百貨店の入り口を起点に、ビル全体︵展望台・ホテルなど同ビル内の5会場とHoop、あべのキューズモール、新宿ごちそうビル︶をぐるりとテープが取り巻いています。
10時のオープニングセレモニーでは、この全長約3000メートルのテープを市民300人が参加して﹁日本一長い 街つなぎテープカット﹂が行われます。
そして、本日︵3月7日︶の全面開業。
百貨店の入り口を起点に、ビル全体︵展望台・ホテルなど同ビル内の5会場とHoop、あべのキューズモール、新宿ごちそうビル︶をぐるりとテープが取り巻いています。
10時のオープニングセレモニーでは、この全長約3000メートルのテープを市民300人が参加して﹁日本一長い 街つなぎテープカット﹂が行われます。



 オープニング直前の展望台入口
オープニング直前の展望台入口
 近鉄あべの駅では、記念入場券が売りだされていました。
近鉄あべの駅では、記念入場券が売りだされていました。
 あべのハルカス前の通りは、街路工事が進行しています。
あべのハルカス前の通りは、街路工事が進行しています。

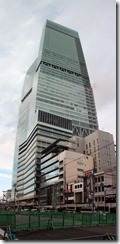 年間予想来店客数は4500万人、初年度目標売上高は1,450億円の﹁あべのハルカス﹂を中心に街並みが整備され、大阪の経済の中心もどんどん変化していくことでしょう。
大阪版﹁あべのミクス﹂ですね。
年間予想来店客数は4500万人、初年度目標売上高は1,450億円の﹁あべのハルカス﹂を中心に街並みが整備され、大阪の経済の中心もどんどん変化していくことでしょう。
大阪版﹁あべのミクス﹂ですね。
2013年12月23日
lenovoアウトレット
超宗派で電話相談を行なっている﹁仏教情報センター﹂の事務所が、このたび移転することになりました。
今回の移転は、入居しているビルが老朽化のため、オーナーが建替えを計画したことに寄ります。そのために移転先を探していました。
インターネットの時代、とても便利ですね。
条件をいろいろと入力すると、その条件に合致した物件が何件も出てきます。
その中から、とても良い物件を見つけることができました。
現在、事務所は文京区白山にありますが、1月27日より同じ文京区本郷1丁目に移ります。 白山通りに面し、都営三田線水道橋の真上という好立地です。 しかも、窓には東京ドームや、東京ドームシティーのアトラクションが広がります。 新事務所については、また後日ご報告させていただきます。
新事務所では、心機一転、古くなった什物類を一新しましょう、ということが理事会で決定され、事務員と相談員のパソコン︵現状はXP︶を探していました。 やはり信頼のおけるメーカーで使いやすいもの、かつ価格もできるだけ安くということで探していると、lenovoアウトレットモールにたどり着きました。

ちょうど、このページを開いた瞬間、ノートパソコンのアウトレット品が追加されたばかりだったようで、いくつか掘り出し物がありました。 残り台数がみるみる減っていきます。 開封整備品とはいえ、 Lenovo G580 (グロッシーブラウン) - 開封済み・新装整備品
主な構成製品番号: 2689XB8
プロセッサー インテル Celeron B830 プロセッサー1.8GHz
初期導入OS Windows 8 (64bit)
グラフィック インテルHDグラフィックス(CPU内蔵)
メモリー 4GB (空スロット:1)
ディスプレイ LED バックライト付 15.6 型HD液晶(1,366×768 ドット、1,677 万色)、光沢あり
内蔵カメラ:HD 720p カメラ
ハード・ディスク・ドライブ 320GB HDD 5400rpm
DVDスーパーマルチ ・ドライブ固定ベイ
このようなスペックの 2689XF9 とか 2689XB8 とかが送料無料で2万5千円前後ですよ。
これは買い!
ということで、なんとか目標の4台を買うことができました。
その直後には主だった掘り出し物が売り切れになりました。
Lenovo G580 (グロッシーブラウン) - 開封済み・新装整備品
主な構成製品番号: 2689XB8
プロセッサー インテル Celeron B830 プロセッサー1.8GHz
初期導入OS Windows 8 (64bit)
グラフィック インテルHDグラフィックス(CPU内蔵)
メモリー 4GB (空スロット:1)
ディスプレイ LED バックライト付 15.6 型HD液晶(1,366×768 ドット、1,677 万色)、光沢あり
内蔵カメラ:HD 720p カメラ
ハード・ディスク・ドライブ 320GB HDD 5400rpm
DVDスーパーマルチ ・ドライブ固定ベイ
このようなスペックの 2689XF9 とか 2689XB8 とかが送料無料で2万5千円前後ですよ。
これは買い!
ということで、なんとか目標の4台を買うことができました。
その直後には主だった掘り出し物が売り切れになりました。
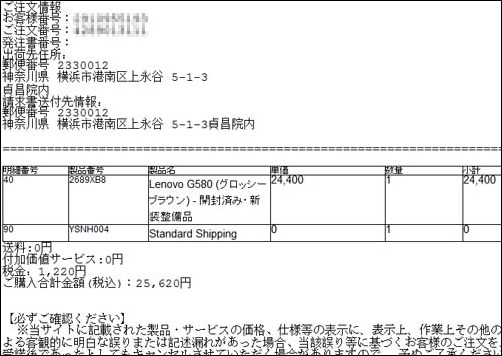 注文ステータスを見ると、12月24日配達予定になっています。
注文ステータスを見ると、12月24日配達予定になっています。

ちょっとしたクリスマスプレ・・・良い買い物になりました。
lenovoアウトレットモールは時々思わぬ掘り出し物が売り出されますので、時々チェックしてみることをお勧めします。
現在、事務所は文京区白山にありますが、1月27日より同じ文京区本郷1丁目に移ります。 白山通りに面し、都営三田線水道橋の真上という好立地です。 しかも、窓には東京ドームや、東京ドームシティーのアトラクションが広がります。 新事務所については、また後日ご報告させていただきます。
新事務所では、心機一転、古くなった什物類を一新しましょう、ということが理事会で決定され、事務員と相談員のパソコン︵現状はXP︶を探していました。 やはり信頼のおけるメーカーで使いやすいもの、かつ価格もできるだけ安くということで探していると、lenovoアウトレットモールにたどり着きました。

ちょうど、このページを開いた瞬間、ノートパソコンのアウトレット品が追加されたばかりだったようで、いくつか掘り出し物がありました。 残り台数がみるみる減っていきます。 開封整備品とはいえ、
 Lenovo G580 (グロッシーブラウン) - 開封済み・新装整備品
主な構成製品番号: 2689XB8
プロセッサー インテル Celeron B830 プロセッサー1.8GHz
初期導入OS Windows 8 (64bit)
グラフィック インテルHDグラフィックス(CPU内蔵)
メモリー 4GB (空スロット:1)
ディスプレイ LED バックライト付 15.6 型HD液晶(1,366×768 ドット、1,677 万色)、光沢あり
内蔵カメラ:HD 720p カメラ
ハード・ディスク・ドライブ 320GB HDD 5400rpm
DVDスーパーマルチ ・ドライブ固定ベイ
このようなスペックの 2689XF9 とか 2689XB8 とかが送料無料で2万5千円前後ですよ。
これは買い!
ということで、なんとか目標の4台を買うことができました。
その直後には主だった掘り出し物が売り切れになりました。
Lenovo G580 (グロッシーブラウン) - 開封済み・新装整備品
主な構成製品番号: 2689XB8
プロセッサー インテル Celeron B830 プロセッサー1.8GHz
初期導入OS Windows 8 (64bit)
グラフィック インテルHDグラフィックス(CPU内蔵)
メモリー 4GB (空スロット:1)
ディスプレイ LED バックライト付 15.6 型HD液晶(1,366×768 ドット、1,677 万色)、光沢あり
内蔵カメラ:HD 720p カメラ
ハード・ディスク・ドライブ 320GB HDD 5400rpm
DVDスーパーマルチ ・ドライブ固定ベイ
このようなスペックの 2689XF9 とか 2689XB8 とかが送料無料で2万5千円前後ですよ。
これは買い!
ということで、なんとか目標の4台を買うことができました。
その直後には主だった掘り出し物が売り切れになりました。
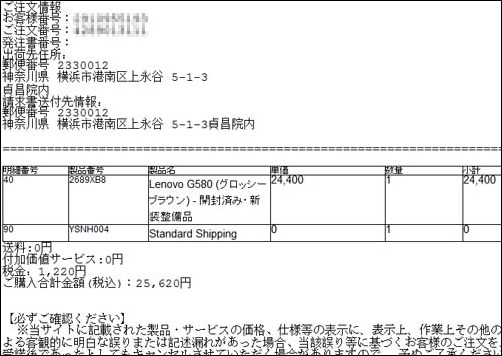 注文ステータスを見ると、12月24日配達予定になっています。
注文ステータスを見ると、12月24日配達予定になっています。

ちょっとしたクリスマスプレ・・・良い買い物になりました。
lenovoアウトレットモールは時々思わぬ掘り出し物が売り出されますので、時々チェックしてみることをお勧めします。
2013年12月22日
年末ジャンボ宝くじで夢を見る
先週金曜日まで﹁第651回 全国 年末ジャンボ宝くじ﹂が発売されておりました。
購入された方も多いと思います。
今年の﹁ウリ﹂は、1等、前後賞併せて7億円!
発表は大晦日︵2013年12月31日︶の午前11時58分頃︵4等~︶ということですので、年末に何人もの億万長者が生まれることでしょう。
今年のジャンボ宝くじの当せん金および本数は、次の通りです。
﹁年末ジャンボ宝くじ﹂︵第651回 全国︶の当せん金・本数
︵発売総額1,800億円・60ユニットの場合︶
1等 500,000,000円60本
1等の前後賞 100,000,000円 120本
1等の組違い賞 100,000円 5,940本
2等1,000,000円 1,800本
3等3,000円 6,000,000本
4等300円 60,000,000本
大晦日特別賞50,000円 180,000本
宝くじの1ユニットは、100,000~199,999番の10万枚を1組として、01組から100組までの1000万通です。 従って、1ユニット購入すると1000万枚=30億円となります。 ここで、︻成功率100%︼年末ジャンボ宝くじの1等に確実に当せんする方法をお教えします。 それは、宝くじ売り場に行き、連番で1000万枚購入するだけです。 しかも、前後賞もついてきます。 ︵某漫才のネタより︶ では、どれほどの当せん金が期待できるでしょうか。 その期待値を計算すると 1ユニット当たり 1等・・・・5億円×1本=5億円 1等前後賞・1億円×2本=2億円 1等組違章・10万円×99本=990万円 2等・・・・100万円×30本=3千万円 3等・・・・3千円×10万本=3億円 4等・・・・3百円×100万本=3億円 特別賞・・・5万円×3千本=1億5千万円 ---------------------------------- 合計15億7990万円
ということで、 15億7990万円÷30億円=0.5266︵52.7%︶となりました。 おおむね、日本の宝くじは購入金額の半分が期待値と考えれば間違いないでしょう。 宝くじの公式サイトでは、残りの半分の収益金をどのように使っているかが公表されています。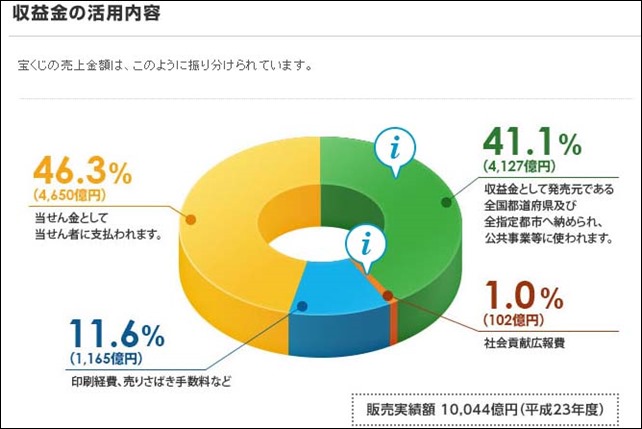 収益金の大部分は発売元各都道府県、指定都市の公共事業に使われています。
さて、今年の宝くじを購入されたかたも、買いそびれたかたも、年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる
宝くじシミュレーターで是非シミュレーションしてみることをお勧めします。
■今年︵2013年︶の年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる宝くじシミュレーター︹Trial版︺は、こちら
■同時発売の年末ジャンボミニ7000万の当せん本数で試せるシミュレーターはこちら
また、スマートフォン︵アンドロイド︶用のアプリもあります。
■当てろ2億円!宝くじシミュレーター
それにしても、今年︵2013年︶の年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる宝くじシミュレーター︹Trial版︺でシミュレートしてみたけれども、一等が全然当たらない><
収益金の大部分は発売元各都道府県、指定都市の公共事業に使われています。
さて、今年の宝くじを購入されたかたも、買いそびれたかたも、年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる
宝くじシミュレーターで是非シミュレーションしてみることをお勧めします。
■今年︵2013年︶の年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる宝くじシミュレーター︹Trial版︺は、こちら
■同時発売の年末ジャンボミニ7000万の当せん本数で試せるシミュレーターはこちら
また、スマートフォン︵アンドロイド︶用のアプリもあります。
■当てろ2億円!宝くじシミュレーター
それにしても、今年︵2013年︶の年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる宝くじシミュレーター︹Trial版︺でシミュレートしてみたけれども、一等が全然当たらない><
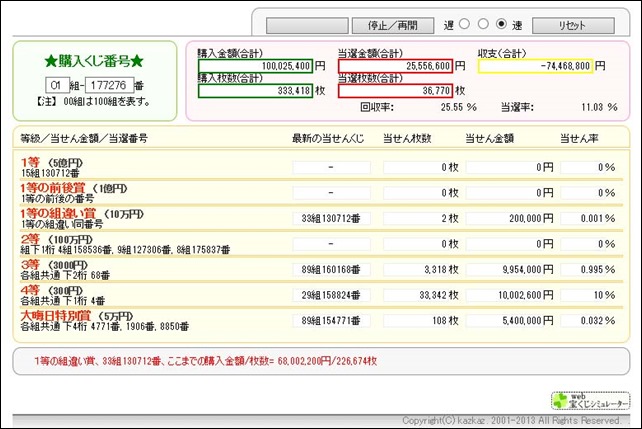
今年の年末ジャンボは、昨年に比べて、1等の金額が大幅に引き上げられました。 その分、昨年あった5等・6等が消え、中間層が大幅に削減されています。 つまり、ごくごく稀な確率の1等を引き当てると、回収率は極端に上がりますが、そこに行き当たらなければ購入し続けても回収率はどんどん下がっていきます。 それだけ﹁ギャンブル性﹂が強くなったといえましょう。 当せん金額は上昇傾向にありますから、そのうち何年かすると、1ユニット当たり 1等15億円1本 1等の前後賞1億円円2本 2等300円 100万本 などという、1等と2等のみの年末ジャンボ宝くじが発売されるかもしれません。。。。。 年末、ジャンボ宝くじの夢︵煩悩?︶を大いに楽しんで、大晦日夜の除夜の鐘でその煩悩をキレイサッパリ振り落として、新年を迎えましょう。
蛇足
宝くじの公式サイトにもジャンボ宝くじ 購入シミュレーター がありました。
■ジャンボ宝くじ 購入シミュレーター | 宝くじ公式サイト
ただし、こちらは、﹁実際の宝くじ﹂を購入するまでの手順を描いたものです。
さすがに、回収率の生々しいシミュレーションは行ないません。
宝くじの1ユニットは、100,000~199,999番の10万枚を1組として、01組から100組までの1000万通です。 従って、1ユニット購入すると1000万枚=30億円となります。 ここで、︻成功率100%︼年末ジャンボ宝くじの1等に確実に当せんする方法をお教えします。 それは、宝くじ売り場に行き、連番で1000万枚購入するだけです。 しかも、前後賞もついてきます。 ︵某漫才のネタより︶ では、どれほどの当せん金が期待できるでしょうか。 その期待値を計算すると 1ユニット当たり 1等・・・・5億円×1本=5億円 1等前後賞・1億円×2本=2億円 1等組違章・10万円×99本=990万円 2等・・・・100万円×30本=3千万円 3等・・・・3千円×10万本=3億円 4等・・・・3百円×100万本=3億円 特別賞・・・5万円×3千本=1億5千万円 ---------------------------------- 合計15億7990万円
ということで、 15億7990万円÷30億円=0.5266︵52.7%︶となりました。 おおむね、日本の宝くじは購入金額の半分が期待値と考えれば間違いないでしょう。 宝くじの公式サイトでは、残りの半分の収益金をどのように使っているかが公表されています。
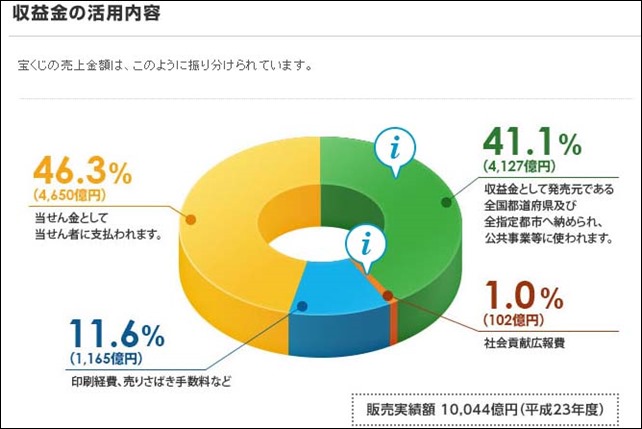 収益金の大部分は発売元各都道府県、指定都市の公共事業に使われています。
さて、今年の宝くじを購入されたかたも、買いそびれたかたも、年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる
宝くじシミュレーターで是非シミュレーションしてみることをお勧めします。
■今年︵2013年︶の年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる宝くじシミュレーター︹Trial版︺は、こちら
■同時発売の年末ジャンボミニ7000万の当せん本数で試せるシミュレーターはこちら
また、スマートフォン︵アンドロイド︶用のアプリもあります。
■当てろ2億円!宝くじシミュレーター
それにしても、今年︵2013年︶の年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる宝くじシミュレーター︹Trial版︺でシミュレートしてみたけれども、一等が全然当たらない><
収益金の大部分は発売元各都道府県、指定都市の公共事業に使われています。
さて、今年の宝くじを購入されたかたも、買いそびれたかたも、年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる
宝くじシミュレーターで是非シミュレーションしてみることをお勧めします。
■今年︵2013年︶の年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる宝くじシミュレーター︹Trial版︺は、こちら
■同時発売の年末ジャンボミニ7000万の当せん本数で試せるシミュレーターはこちら
また、スマートフォン︵アンドロイド︶用のアプリもあります。
■当てろ2億円!宝くじシミュレーター
それにしても、今年︵2013年︶の年末ジャンボ宝くじの当せん本数で試せる宝くじシミュレーター︹Trial版︺でシミュレートしてみたけれども、一等が全然当たらない><
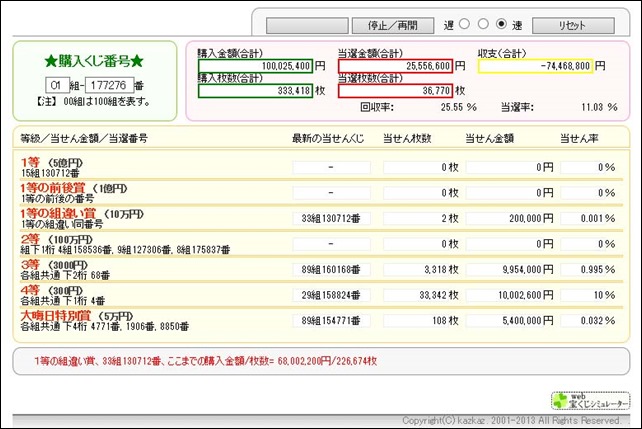
今年の年末ジャンボは、昨年に比べて、1等の金額が大幅に引き上げられました。 その分、昨年あった5等・6等が消え、中間層が大幅に削減されています。 つまり、ごくごく稀な確率の1等を引き当てると、回収率は極端に上がりますが、そこに行き当たらなければ購入し続けても回収率はどんどん下がっていきます。 それだけ﹁ギャンブル性﹂が強くなったといえましょう。 当せん金額は上昇傾向にありますから、そのうち何年かすると、1ユニット当たり 1等15億円1本 1等の前後賞1億円円2本 2等300円 100万本 などという、1等と2等のみの年末ジャンボ宝くじが発売されるかもしれません。。。。。 年末、ジャンボ宝くじの夢︵煩悩?︶を大いに楽しんで、大晦日夜の除夜の鐘でその煩悩をキレイサッパリ振り落として、新年を迎えましょう。
2013年12月17日
剃刀と刃のビジネスモデル
2年前からCanonのインクジェットプリンタip2700を使っています。
このプリンタ、コンパクトで小回りが利くなかなかの優れものです。

なんといっても、プリンタ本体のの安さは特筆ものです。 4000円もしませんでした。 除夜の鐘の整理券や年賀状印刷などに重宝しています。 また、封筒印刷や郵便振替用紙の印刷にも、インクジェットプリンタは重宝します。 ところが、コンパクトな分、インクの減りが早いのことがネックですね。 写真画質で何枚も印刷すると、途中でインクが切れてしまいます。 気づかないで印刷をほうっておくと、このようになっています。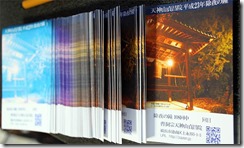 ︵↑一昨年の除夜の鐘整理券印刷時の状況︶
︵↑一昨年の除夜の鐘整理券印刷時の状況︶
インクが切れると、慌てて買いに行くわけですが、このインクがかなり高い。 純正インクで、ブラック300が2000円強、カラー311が2500円程度ですから、合計で3500円ほどです。 なんと、本体︵インクも同梱︶を新規に買うのとほとんど変わりません。 このように、﹁本体﹂を安く売り、継続的に使用しなければならない﹁消耗品﹂を高く売るビジネスモデルを Razor and blades business model ︵剃刀と刃のビジネスモデル︶といいます。 アメリカの剃刀メーカー、ジレット社が確立して有名になりました。 剃刀と刃のビジネスモデルは、携帯電話、コピー機、コーヒーマシンなどなど、同様の事例は最近特に多くなりました。 新しい機械を導入する際には、初期投資金額だけではなく、ランニングコストがどの程度になるのかをよくよく考えておく必要があります。 そんなにうまい話は転がってはいないのです。 ところで、インクジェットプリンタには、詰め替えインクというサードパーティーの製品が出ています。 プリンタメーカーとしては面白くない話なので、訴訟問題になったり純正しか使えないよう機能設定したりと、いたちごっこの様相がありますが、最近の詰め替えインクの進化は驚くばかりです。
数年前の詰め替えインクは、詰め替えるのに相当な手間をかけなければならなかったり、手を汚してしまったり、インク自体の品質が悪かったり、といった欠点がありました。 ところが、今年の詰め替えインクは、インクボトル、インクボトルノズル、穴あけ専用のニードル、ハンドドリル、詰め替え穴の位置を正確にガイドするホルダー、ホルダーキャップ、シール、ポリ手袋、ワイパークロスなどがセットになっていて、手軽に詰め替えることが出来るようになっています。
今年はこれを利用させていただきました。 除夜の鐘の整理券も、このインクで印刷します。 個人的な考えとして、剃刀と刃のビジネスモデルはあまり好ましくないと感じますので、ささやかな抵抗です。

なんといっても、プリンタ本体のの安さは特筆ものです。 4000円もしませんでした。 除夜の鐘の整理券や年賀状印刷などに重宝しています。 また、封筒印刷や郵便振替用紙の印刷にも、インクジェットプリンタは重宝します。 ところが、コンパクトな分、インクの減りが早いのことがネックですね。 写真画質で何枚も印刷すると、途中でインクが切れてしまいます。 気づかないで印刷をほうっておくと、このようになっています。
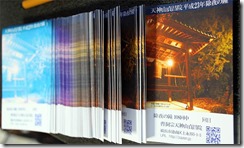 ︵↑一昨年の除夜の鐘整理券印刷時の状況︶
︵↑一昨年の除夜の鐘整理券印刷時の状況︶
インクが切れると、慌てて買いに行くわけですが、このインクがかなり高い。 純正インクで、ブラック300が2000円強、カラー311が2500円程度ですから、合計で3500円ほどです。 なんと、本体︵インクも同梱︶を新規に買うのとほとんど変わりません。 このように、﹁本体﹂を安く売り、継続的に使用しなければならない﹁消耗品﹂を高く売るビジネスモデルを Razor and blades business model ︵剃刀と刃のビジネスモデル︶といいます。 アメリカの剃刀メーカー、ジレット社が確立して有名になりました。 剃刀と刃のビジネスモデルは、携帯電話、コピー機、コーヒーマシンなどなど、同様の事例は最近特に多くなりました。 新しい機械を導入する際には、初期投資金額だけではなく、ランニングコストがどの程度になるのかをよくよく考えておく必要があります。 そんなにうまい話は転がってはいないのです。 ところで、インクジェットプリンタには、詰め替えインクというサードパーティーの製品が出ています。 プリンタメーカーとしては面白くない話なので、訴訟問題になったり純正しか使えないよう機能設定したりと、いたちごっこの様相がありますが、最近の詰め替えインクの進化は驚くばかりです。
数年前の詰め替えインクは、詰め替えるのに相当な手間をかけなければならなかったり、手を汚してしまったり、インク自体の品質が悪かったり、といった欠点がありました。 ところが、今年の詰め替えインクは、インクボトル、インクボトルノズル、穴あけ専用のニードル、ハンドドリル、詰め替え穴の位置を正確にガイドするホルダー、ホルダーキャップ、シール、ポリ手袋、ワイパークロスなどがセットになっていて、手軽に詰め替えることが出来るようになっています。

今年はこれを利用させていただきました。 除夜の鐘の整理券も、このインクで印刷します。 個人的な考えとして、剃刀と刃のビジネスモデルはあまり好ましくないと感じますので、ささやかな抵抗です。
2013年11月 2日
超高速モバイルネットの時代へ
ニュースリリース 超速モバイルネット﹁WiMAX 2+﹂の提供開始および取扱MVNOについて -2013年10月31日からUQおよびMVNO各社でスタート- UQコミュニケーションズ株式会社︵本社‥東京都港区、代表取締役社長野坂章雄、以下UQ︶およびMVNO各社は、超速モバイルネット﹁WiMAX 2+︵ワイマックスツープラス︶﹂を2013年10月31日︵木︶より提供開始いたします。 ﹁WiMAX 2+﹂は下り最大110Mbpsを実現する超高速モバイルインターネットサービスです。対応エリアは、当初、環状7号線︵東京都道318号線︶内の一部から開始し、2013年度末には東名阪、2014年度末には全国へ拡大する予定です。 ︵UQコミュニケーションズ株式会社 2013年10月30日︶ここのところ、通信各社がしのぎを削って通信エリアの拡大とと高速通信の整備をすすめています。 中でも、UQの本気度は一歩抜け出ているような感じがします。
UQコミュニケーションズのエリアマップを見ると、下り最大110Mbpsを実現するWiMAX 2+のエリアは、既に都心部から始まっています。 ︵下記エリア地図の濃いピンク部分︶
首都圏近郊も今年度中にはサービスが始まる見込みとなっています。 貞昌院境内にもUQコミュニケーションズのアンテナが設置されています。 貞昌院への設置工事は東日本大震災発生直後の2011年4月に行なわれました。 設置工事のブログ記事⇒ UQ Wimax がやってきた 今年度末までに新しいアンテナへの交換増設工事が行なわれる設計図面が届きました。 貞昌院近辺の方は、今年度中に超速モバイルネットのエリアになることでしょう。光ファイバーケーブルによるインターネット通信と遜色ない環境が無線で実現されるという時代になりました。 UQのみならず、通信各社の追随もあり、ますます競争が激しくなっていくことが予想されます。 そして、今後数年間で、モバイルインターネット環境は大きく変貌していくはずです。 データを端末に溜め込んで持ち運ぶ必要は無くなり、アプリケーションですらその都度ダウンロードすれば良いという時代もそう遠くは無いでしょう。
2013年10月17日
スパムメールの経済学
サクラ利用“出会えない”系サイト…1000万円支払った客も 会社社長ら逮捕 出会い系サイトで﹁サクラ﹂とやり取りさせ、料金をだまし取ったとして、京都府警と大分県警の合同捜査班は16日、詐欺の疑いで、大分県別府市の出会い系サイト運営会社﹁ラパン﹂の元会長、同市駅前町の立石正彰容疑者︵59︶=不正指令電磁的記録保管・同供用容疑で逮捕、処分保留で釈放=ら3人を再逮捕、同社社長の佐伯照美容疑者︵62︶=同市鶴見=ら3人を逮捕した。府警によると、うち2人は容疑を認めているが、立石容疑者ら4人は﹁よくわからない﹂などと容疑を否認している。 逮捕容疑は今年8月1~15日、同社が経営する出会い系サイト﹁おしゃべり広場﹂で、実際には利用者同士のやり取りはできないのに、異性をかたったサクラとやり取りをさせ、大阪府高槻市の男性︵74︶ら2人からサイトの利用料現金約6万円をだまし取ったとしている。 府警サイバー犯罪対策課によると6人は、同社が不正に取得した約36億件のメールアドレスから無作為にサイトの勧誘メールを送信。サクラのアルバイト約10人に利用者とやり取りをさせ、サイト内でのメールの送受信などに必要なポイントを購入させていた。課金した利用者は全国で約5600人で、同サイトは平成19年2月の開設以来、約8億4千万円の売り上げがあった。1千万円以上を支払った利用者もいたが、少なくとも合同捜査班が調べた2週間の間は、すべてサクラとのやり取りだったという。 ︵産経新聞10月16日配信︶毎日のように大量に届く迷惑メール。 一向に減る気配はありません。 冒頭のニュースを元に、迷惑メールを送信することで、どれだけの利益が出るのかを計算してみましょう。 京都府警サイバー犯罪対策課による、この事件の概要は次の通りです。
■出会い系サイト運営会社が不正に取得したメールアドレス 3,600,000,000 件 ■メールを送りつけられ、サイトを利用し、料金を支払った人 5,600 人 ■出会い系サイトの売り上げ 840,000,000 円
3,600,000,000 件のメールアドレスがどの程度の金額で売られているかをざっと検索してみると、ある程度質の良いメールアドレスで30万円程度。 1件あたり大体 0.0001円弱といったところでしょうか。 不正に入手したアドレスということなので、さらに格安の二束三文で入手したのでしょう。
3,600,000,000 件 のスパムメールに対して、サイトを利用し、料金を払った人は 5,600人ですから、 642,857 人に1人の割合で料金が支払われました。 0.00015% の確率です。 おそらく、ただサイトを覗いただけという人の数はその10倍、あるいは100倍居るのではないでしょうか。 仮に100倍とすると、0.015% の反応率です。
さらに注目すべきは、その粗利率の高さ。 支払った人一人あたりの料金は、何と 150,000円です。 二束三文で取得したメールアドレスを送りつけた結果、スパムメール1通当たり 0.23 円もの収入を得ていたのです。 そのうち、1割程度を経費︵サクラのアルバイト料支弁等︶と仮定しても、粗利率9割の丸儲け。 当然、法人税や所得税は真っ当には支払っていないでしょう。 迷惑な上に、実に悪質な犯罪です。
以前、[コメントスパムには困ったものだ] のブログ記事で メール1万通を送信するコストは約1ドルで、迷惑メール100万通につき約15通程度の返信が来る。 100万通につき15通のリアクションなので0.0015%という恐ろしく低い返信率ですが、メールアドレスやメールを送信するコストが低いためビジネスとして成り立ってしまいます。例えば、100万通の迷惑メールを送信した場合、必要なコストは約100ドルで15通程度の返信が期待できるので、1通につき10ドルの利益しか上がらなくても全体としては、50ドルの純利益となります。 や、 ﹁スパムメールの採算ベースは返信率が0.001%﹂ スパムメールは返信率が0.001%を超えれば採算に合うため、コストがかからない。 例えば、PCが10万円、プロバイダー料金が月額4,000円、1億件のメールアドレスの相場価格が10,000円、その他の経費を含めて20万円を初期投資金額と想定する。アダルトサイトを運営している業者が2-3万円の課金請求することを目的にスパムメールを送った場合、7-10人が騙されて料金を支払えば初期投資分は回収できるという。
ということを書きました。 冒頭の記事から具体的な検証を行なってみましたが、これでは、スパムメールは無くなりませんね。 やれやれ。■関連ブログ記事 スパムメールには困ったものだ SPAMメールと仲良く付き合う方法 コメントスパムには困ったものだ SPAMメールと仲良く付き合う方法その2
2013年10月 6日
レアメタルが「レア」ではなくなる日
昭電の産業ロボ向け磁石合金、中国産の希少材料不要に 昭和電工はレアアース︵希土類︶の一種、ジスプロシウムを使わない産業用ロボット向け 磁石合金を開発した。高価なジスプロが不要になり磁石合金の価格を約3割安くできる。 中国産レアアースの使用量削減で需給が緩和すれば、まだジスプロを必要とするハイブリッド車 ︵HV︶向け高性能磁石の価格低下にもつながりそうだ。 ジスプロは磁石の耐熱性を高めるため、ネオジムや鉄などからつくる磁石合金に添加する。 添加率を上げると耐熱性が高まる。産業用ロボットのモーターに組み込まれている磁石は、 重量ベースで3.5%程度のジスプロを含む。特殊な熱処理で結晶構造を変えることで、 ジスプロをゼロにした磁石合金を初めて量産できる体制を整えた。 昭和電工によると、ネオジムや鉄を主原料にした高性能磁石の2013年の世界生産量は2万3千トンの見込み。16年には高性能磁石の世界生産量に占める産業用ロボット向けの比率は3割強の約1万5000トンにのぼると予想されている。これに比例して磁石合金の市場も拡大する。 昭和電工が今回開発した磁石合金の採用拡大で、9割が中国産といわれるジスプロの 需給も緩和する見通し。その結果、現時点では添加率が6~8%と高く、 まだジスプロをゼロにできていないHV向けの高性能磁石の価格も下げることができる。 ジスプロの価格は1キログラム当たり6万~7万円。鉄︵同100円前後︶やネオジム︵同1万円前後︶ を大きく上回る。産業用ロボット向け磁石合金の価格は1万円弱。 今回、昭和電工が開発した磁石合金を使えば3割程度安くなる。今後も風力発電機や産業用ロボット向けを 中心に高性能磁石の需要が高まるとみて、来春にも秩父事業所︵埼玉県秩父市︶で量産を始める。 高性能磁石合金で世界シェアの約25%を持つ同社は現在、耐熱性のより高い磁石合金の研究を進めている。 日立金属は2%添加相当の磁石を販売し、さらに多くのジスプロをゼロにできる技術を研究しており、 磁石メーカーもレアアース削減を急いでいる。 ︵日経新聞 2013/10/3︶このようなニュースを目にするにつけ、日本は本当にピンチを生かしてチャンスに転換することができる技術大国だと実感します。 以前、尖閣諸島沖で逮捕の中国人船長を釈放へというブログ記事の中で ■脱中国経済にむけて (1)資源を中国以外の国から調達できるように他国との交渉を進める。 (2)都市鉱山からの再資源化の仕組みをさらに強化する。 (3)レアメタルの代用品を作る技術の開発、実用化のための研究に重点を置く。 という提言を掲げました。 3年前の2010年9月、まだ民主党政権だった頃の記事です。 日本の工業製品、特に磁石用合金などに欠かせないレアメタルは、当時、日本向け輸出の大半が中国からの輸入でした。 2010年9月に尖閣諸島で中国漁船衝突事件が発生すると、中国は日本に対する経済政策措置としてレアメタルの輸出規制へと踏み出しました。 日本の産業界は中国の横暴に対して黙っては居ません。 数年前から起こっているチャイナリスクを踏み台に、レアメタルの新たな輸入先の開拓、レアメタルの徹底的なリサイクル、レアメタルを使わない技術を続々と開発していきました。 結果、中国から日本へのレアアース輸出量は2011年には前年比34%減となり、その後も大幅な減少傾向が続いています。 中国国内のレアメタル業者は減産や生産停止に追い込まれているそうですが、まさに自業自得といえましょう。 そして、ついに日本は冒頭の報道のように、産業用ロボット向け磁石合金を生産する際に、全くレアメタルの一種であるジスプロシウムを使用しない技術を開発してしまいました。 ジスプロシウムの価格は、益々暴落していくことは確実です。
脱レアメタルの技術確立は、中国からの資源に依存しきっている日本のために重要な事項といえます。 日立製作所は酸化鉄を使った脱レアメタルモーターの製品化が具体化しています。 また、帝人と東北大学は鉄と窒素による新材料を開発しています。 これらはほんの一例です。
レアメタルに限らず、石油資源にしても、他のどのような資源にしても、埋蔵量に制約されない原料の確保やリサイクルシステム、代用品技術の確立を進めていくこと。 ﹁ピンチをチャンスに変える﹂ことを可能に出来るのが日本の技術力の強みであるといえましょう。

※上写真ははぐれメタルです。本文とは関係ありません (C)SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
2013年6月 2日
電気料金が大幅黒字に
貞昌院では平成15年11月より太陽光発電設備を運用しています。
太陽光発電設備から発電された電力は寺院内電力の消費に回され、使い切れなかった余剰電力が東京電力側が購入してくれる仕組みとなっています。
毎年、発電電力量のピークは5月に現われます。
平成25年5月分の電気料金請求書がこちら。
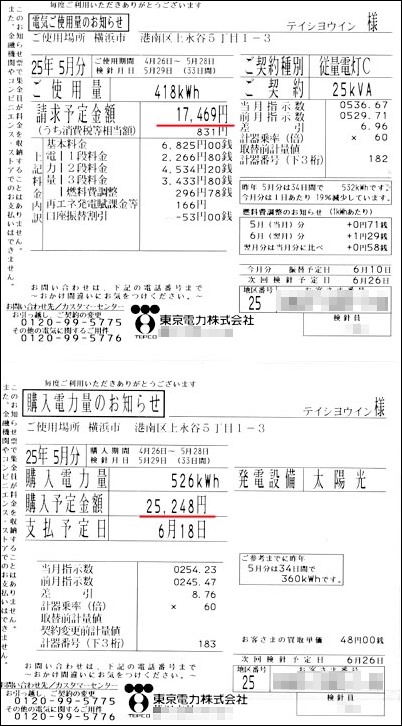 このように、東京電力からの請求予定金額が17,469円、東京電力の購入予定金額が25,248円となっています。
つまり、5月は7,779円の黒字となりました。
黒字額がこれだけ大きな金額になるのは初めてのことです。
基本料金6,825円を加味しての黒字額ですよ、念のため。
このように、東京電力からの請求予定金額が17,469円、東京電力の購入予定金額が25,248円となっています。
つまり、5月は7,779円の黒字となりました。
黒字額がこれだけ大きな金額になるのは初めてのことです。
基本料金6,825円を加味しての黒字額ですよ、念のため。
振り返ってみればそれだけ日射量が多かったということにもなります。 本当に雨が少ない月でした。 月ごとの発電電力量の推移がこちら。 発電電力量も過去最高を記録しました。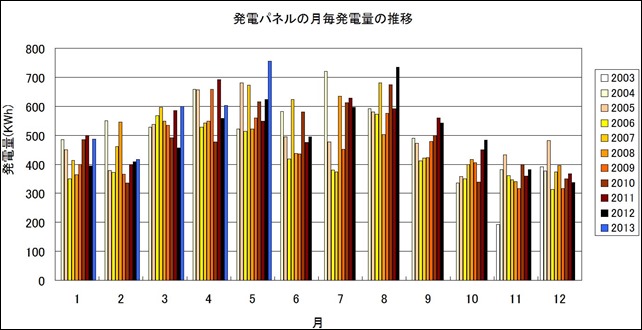 余剰電力量をグラフにしてみると・・・・・
余剰電力量をグラフにしてみると・・・・・
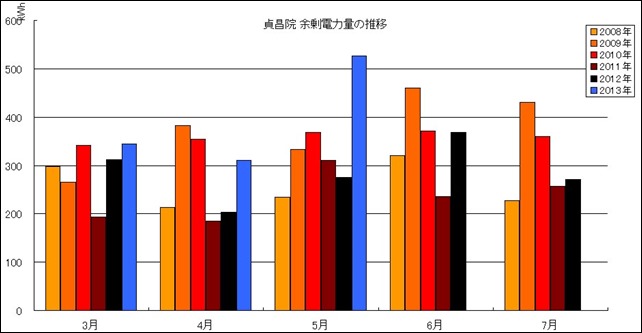 平成25年︵2013年︶だけ突出しています。
これだけ余剰電力︵つまり、貞昌院で使い切れずに東京電力に売った余剰分︶が多かったということです。
また、節電につとめた結果も少なからず影響しています。
平成25年︵2013年︶だけ突出しています。
これだけ余剰電力︵つまり、貞昌院で使い切れずに東京電力に売った余剰分︶が多かったということです。
また、節電につとめた結果も少なからず影響しています。
5月の大幅黒字は、日照時間が長かったこと、そして貞昌院で消費する電力量が少なかったこと、この両者によるものといえます。 経済的にムリをせずに環境貢献できる制度は良いですね。
■関連ブログ記事
電気料金がマイナスに
太陽光発電の醍醐味は5月にあり
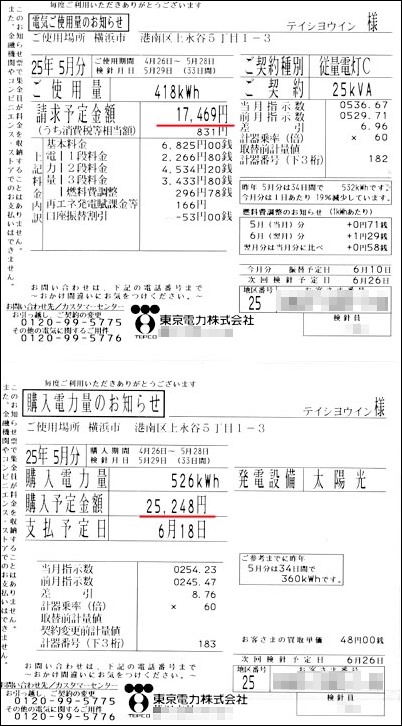 このように、東京電力からの請求予定金額が17,469円、東京電力の購入予定金額が25,248円となっています。
つまり、5月は7,779円の黒字となりました。
黒字額がこれだけ大きな金額になるのは初めてのことです。
基本料金6,825円を加味しての黒字額ですよ、念のため。
このように、東京電力からの請求予定金額が17,469円、東京電力の購入予定金額が25,248円となっています。
つまり、5月は7,779円の黒字となりました。
黒字額がこれだけ大きな金額になるのは初めてのことです。
基本料金6,825円を加味しての黒字額ですよ、念のため。
振り返ってみればそれだけ日射量が多かったということにもなります。 本当に雨が少ない月でした。 月ごとの発電電力量の推移がこちら。 発電電力量も過去最高を記録しました。
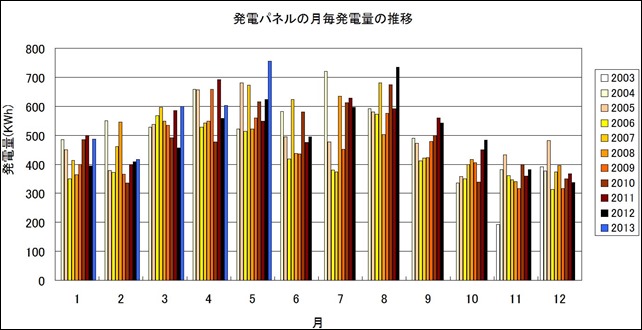 余剰電力量をグラフにしてみると・・・・・
余剰電力量をグラフにしてみると・・・・・
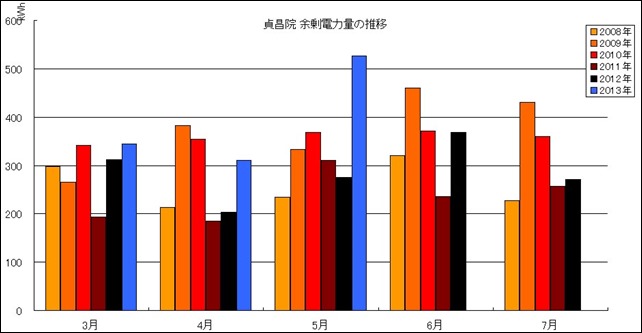 平成25年︵2013年︶だけ突出しています。
これだけ余剰電力︵つまり、貞昌院で使い切れずに東京電力に売った余剰分︶が多かったということです。
また、節電につとめた結果も少なからず影響しています。
平成25年︵2013年︶だけ突出しています。
これだけ余剰電力︵つまり、貞昌院で使い切れずに東京電力に売った余剰分︶が多かったということです。
また、節電につとめた結果も少なからず影響しています。
5月の大幅黒字は、日照時間が長かったこと、そして貞昌院で消費する電力量が少なかったこと、この両者によるものといえます。 経済的にムリをせずに環境貢献できる制度は良いですね。
2012年12月12日
日の出町駅前が大変貌
日常、京浜急行を利用しています。
車窓の光景を眺めていると、この秋口から日の出町駅近辺の光景が激変していることに気づきます。
 これは、﹁日ノ出町駅前A地区市街地再開発﹂という再開発事業です。
日の出町駅から大岡川に至る大岡川沿いに至る0.7haの区域を、今年夏から平成27年にかけて地上21階建ての複合ビルを中心として開発される予定です。
仮囲いゲートの隙間からのぞいてみると、そこにあったはずのビルはすっかり取り壊されてしまい、ほぼ更地になっていました。
これは、﹁日ノ出町駅前A地区市街地再開発﹂という再開発事業です。
日の出町駅から大岡川に至る大岡川沿いに至る0.7haの区域を、今年夏から平成27年にかけて地上21階建ての複合ビルを中心として開発される予定です。
仮囲いゲートの隙間からのぞいてみると、そこにあったはずのビルはすっかり取り壊されてしまい、ほぼ更地になっていました。

今日現在の様子と、取り壊し前の様子を並べてみました。 取り壊し前はGoogleMapによる画像です。
 ︵左︶2012年12月12日の様子 ︵右︶GoogleMapによる取り壊し前の様子
︵左︶2012年12月12日の様子 ︵右︶GoogleMapによる取り壊し前の様子

 ︵左︶2012年12月12日の様子 ︵右︶GoogleMapによる取り壊し前の様子
︵左︶2012年12月12日の様子 ︵右︶GoogleMapによる取り壊し前の様子
ところで、再開発事業が進んでいるこの場所は、かつて、鉄道が通る計画︵桜木町~蒔田間︶がありました。 ﹁湘南電鉄︵現在の京浜急行︶の当初の計画︵大正6年に免許申請︶では鉄道の起点は蒔田町で、当時鉄道省︵現在のJR︶が桜木町より横浜市内をを通り抜け保土ヶ谷へ通じる電車路線の敷設を計画し、蒔田町に停車場を予定していた﹂︵﹃港南の歴史﹄より引用︶とあり、その計画上の土地の買収も進んでいました。 鉄道計画路線の名残りは現在でもはっきりと見て取れます。 地図上で、鉄道計画の部分を青く着色してみました。
細長い区画が、黄金町から桜木町に掛けて残っています。この部分に鉄道が通る筈でした。
この計画が実行されていれば、桜木町から省電の路線が日の出町、黄金町を通り、蒔田ターミナルへ繋がる・・・ということになっていたことでしょう。
しかし、この鉄道計画は、昭和9年、鉄道免許返納により頓挫します。
戦争の影響が濃厚となった昭和12年には、再度、東横電鉄同区間の鉄道計画をし、鉄道免許を申請しますが、これも昭和19年に免許返納されています。
地図上で、鉄道計画の部分を青く着色してみました。
細長い区画が、黄金町から桜木町に掛けて残っています。この部分に鉄道が通る筈でした。
この計画が実行されていれば、桜木町から省電の路線が日の出町、黄金町を通り、蒔田ターミナルへ繋がる・・・ということになっていたことでしょう。
しかし、この鉄道計画は、昭和9年、鉄道免許返納により頓挫します。
戦争の影響が濃厚となった昭和12年には、再度、東横電鉄同区間の鉄道計画をし、鉄道免許を申請しますが、これも昭和19年に免許返納されています。
時代背景により街づくりの計画は変わっていきます。 数年後、日の出町駅前の様相も激変していることでしょう。
■関連ブログ記事 とつか再開発くん
 これは、﹁日ノ出町駅前A地区市街地再開発﹂という再開発事業です。
日の出町駅から大岡川に至る大岡川沿いに至る0.7haの区域を、今年夏から平成27年にかけて地上21階建ての複合ビルを中心として開発される予定です。
仮囲いゲートの隙間からのぞいてみると、そこにあったはずのビルはすっかり取り壊されてしまい、ほぼ更地になっていました。
これは、﹁日ノ出町駅前A地区市街地再開発﹂という再開発事業です。
日の出町駅から大岡川に至る大岡川沿いに至る0.7haの区域を、今年夏から平成27年にかけて地上21階建ての複合ビルを中心として開発される予定です。
仮囲いゲートの隙間からのぞいてみると、そこにあったはずのビルはすっかり取り壊されてしまい、ほぼ更地になっていました。

今日現在の様子と、取り壊し前の様子を並べてみました。 取り壊し前はGoogleMapによる画像です。

 ︵左︶2012年12月12日の様子 ︵右︶GoogleMapによる取り壊し前の様子
︵左︶2012年12月12日の様子 ︵右︶GoogleMapによる取り壊し前の様子

 ︵左︶2012年12月12日の様子 ︵右︶GoogleMapによる取り壊し前の様子
︵左︶2012年12月12日の様子 ︵右︶GoogleMapによる取り壊し前の様子
ところで、再開発事業が進んでいるこの場所は、かつて、鉄道が通る計画︵桜木町~蒔田間︶がありました。 ﹁湘南電鉄︵現在の京浜急行︶の当初の計画︵大正6年に免許申請︶では鉄道の起点は蒔田町で、当時鉄道省︵現在のJR︶が桜木町より横浜市内をを通り抜け保土ヶ谷へ通じる電車路線の敷設を計画し、蒔田町に停車場を予定していた﹂︵﹃港南の歴史﹄より引用︶とあり、その計画上の土地の買収も進んでいました。 鉄道計画路線の名残りは現在でもはっきりと見て取れます。
 地図上で、鉄道計画の部分を青く着色してみました。
細長い区画が、黄金町から桜木町に掛けて残っています。この部分に鉄道が通る筈でした。
この計画が実行されていれば、桜木町から省電の路線が日の出町、黄金町を通り、蒔田ターミナルへ繋がる・・・ということになっていたことでしょう。
しかし、この鉄道計画は、昭和9年、鉄道免許返納により頓挫します。
戦争の影響が濃厚となった昭和12年には、再度、東横電鉄同区間の鉄道計画をし、鉄道免許を申請しますが、これも昭和19年に免許返納されています。
地図上で、鉄道計画の部分を青く着色してみました。
細長い区画が、黄金町から桜木町に掛けて残っています。この部分に鉄道が通る筈でした。
この計画が実行されていれば、桜木町から省電の路線が日の出町、黄金町を通り、蒔田ターミナルへ繋がる・・・ということになっていたことでしょう。
しかし、この鉄道計画は、昭和9年、鉄道免許返納により頓挫します。
戦争の影響が濃厚となった昭和12年には、再度、東横電鉄同区間の鉄道計画をし、鉄道免許を申請しますが、これも昭和19年に免許返納されています。
時代背景により街づくりの計画は変わっていきます。 数年後、日の出町駅前の様相も激変していることでしょう。
■関連ブログ記事 とつか再開発くん
2012年7月 6日
電力需給と節電効果
まもなく梅雨明け。
梅雨が開けると本格的な夏を迎えます。
東日本大震災以降、電力需給が逼迫し、昨年は関東地方を中心に計画停電が行なわれました。
2011年を中心に、一時間分の電力需要のデータが東京電力から公表されています。
そのデータをもとに、2010年、2011年、2012年の電力需要︵東京電力管内でどれだけの電力が消費されているか︶をグラフにしてみました。
︵データ量が膨大なため、私の非力なパソコンでは処理に時間を要しました><︶
まずは、こちらを御覧ください。
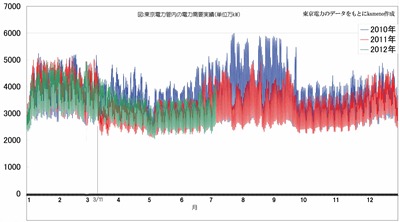 図をクリックすると拡大します。
電力需要の大まかな流れとしては、電力消費のピークが夏場にくることがわかります。
グラフを細かく見ていくと、1日毎に、深夜から早朝にかけて下振れし、昼間にピークを迎える変動を繰り返しています。
青︵2010年︶、赤︵2011年︶、青︵2012年︶の幅をもった線に見えるのは、一日の需要最小値と最大値の幅ということになります。
図をクリックすると拡大します。
電力需要の大まかな流れとしては、電力消費のピークが夏場にくることがわかります。
グラフを細かく見ていくと、1日毎に、深夜から早朝にかけて下振れし、昼間にピークを迎える変動を繰り返しています。
青︵2010年︶、赤︵2011年︶、青︵2012年︶の幅をもった線に見えるのは、一日の需要最小値と最大値の幅ということになります。
電力会社は、夏場の最大需要時間にあわせて発電所を計画します。 東日本大震災の前、2010年には、6000万KWの最大需要がありましたので、これを賄うだけの発電設備が稼働していました。 赤︵2011年︶グラフに着目すると、3月11日以降、前年︵青︶よりも電力需要がかなり低下しています。 災害による工場の操業停止、計画停電、企業や家庭が取り組んだ節電の結果によるものです。 また、それほど暑い夏ではなかったことも幸いし、電力需要のピークが5000万KWを少し上回る程度で済んでいます。 さて、今年はどうでしょうか。 東日本大震災以降初めて迎えた冬︵2012年の緑グラフ1月1日~3月31日︶は、2010年、2011年に比べて低い値で推移しています。 これは、節電効果によるものが大と考えられます。 3月の部分を取り出して拡大したグラフがこちらです。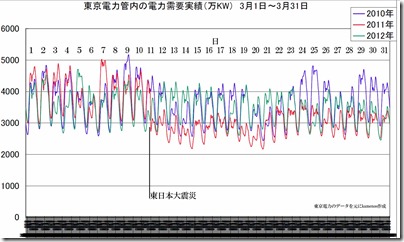 第1図のごちゃごちゃした部分がよりはっきりして、一日の電力需要の変化がよくわかります。
第1図のごちゃごちゃした部分がよりはっきりして、一日の電力需要の変化がよくわかります。
さて、問題はこれからです。 梅雨が開けた後、本格的な夏を迎える7月半ばから8月が正念場です。 下のグラフは7月1日から7月31日までの部分を拡大したものです。 東京電力のデータは一日前まで出されていますので、今年のデータは7月5日分までを盛り込みました。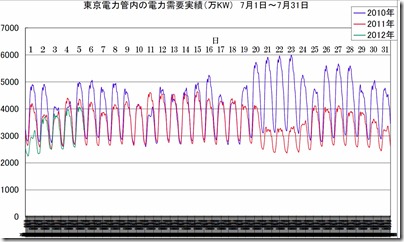 2010年には、7月23日の午後2時ぐらいに電力需要のピークを迎えています。
グラフを見て分かるとおり、この昼前後数時間の間にグーンと電力需要が高まり、2時前後にピークを迎え、夕方に向けてグーンと下がっていきます。
夏場のこの時間帯の節電が重要であることがよくわかります。
今年は、赤い線と緑の線がほぼ同一のカーブを描いていますので、昨年並みの需要動向のまま推移しているようです。
節電行動が定着している証拠です。
ただ、昨年は稼働していた原子力発電所は、次々と停止し、現在は東京電力エリアでは、原子力発電所の稼働がゼロとなっています。
より一層の節電行動が求められます。
2010年には、7月23日の午後2時ぐらいに電力需要のピークを迎えています。
グラフを見て分かるとおり、この昼前後数時間の間にグーンと電力需要が高まり、2時前後にピークを迎え、夕方に向けてグーンと下がっていきます。
夏場のこの時間帯の節電が重要であることがよくわかります。
今年は、赤い線と緑の線がほぼ同一のカーブを描いていますので、昨年並みの需要動向のまま推移しているようです。
節電行動が定着している証拠です。
ただ、昨年は稼働していた原子力発電所は、次々と停止し、現在は東京電力エリアでは、原子力発電所の稼働がゼロとなっています。
より一層の節電行動が求められます。
○夏の節電は、7月~8月の平日の午前9時から午後8時の節電につとめる。 ○その時間帯のうち、午後1時から午後4時の節電が特に重要。 ○それ以外の時間帯は無理に節電する必要はない。 とにかく、電力需要の状況をリアルタイムに把握して、効率良い節電行動を無理なく行うことが大切でしょう。 具体的な節電行動として、政府のポータルサイトに判りやすい取り組み事例が紹介されています。
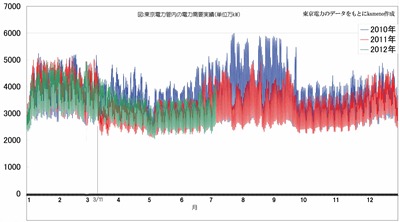 図をクリックすると拡大します。
電力需要の大まかな流れとしては、電力消費のピークが夏場にくることがわかります。
グラフを細かく見ていくと、1日毎に、深夜から早朝にかけて下振れし、昼間にピークを迎える変動を繰り返しています。
青︵2010年︶、赤︵2011年︶、青︵2012年︶の幅をもった線に見えるのは、一日の需要最小値と最大値の幅ということになります。
図をクリックすると拡大します。
電力需要の大まかな流れとしては、電力消費のピークが夏場にくることがわかります。
グラフを細かく見ていくと、1日毎に、深夜から早朝にかけて下振れし、昼間にピークを迎える変動を繰り返しています。
青︵2010年︶、赤︵2011年︶、青︵2012年︶の幅をもった線に見えるのは、一日の需要最小値と最大値の幅ということになります。
電力会社は、夏場の最大需要時間にあわせて発電所を計画します。 東日本大震災の前、2010年には、6000万KWの最大需要がありましたので、これを賄うだけの発電設備が稼働していました。 赤︵2011年︶グラフに着目すると、3月11日以降、前年︵青︶よりも電力需要がかなり低下しています。 災害による工場の操業停止、計画停電、企業や家庭が取り組んだ節電の結果によるものです。 また、それほど暑い夏ではなかったことも幸いし、電力需要のピークが5000万KWを少し上回る程度で済んでいます。 さて、今年はどうでしょうか。 東日本大震災以降初めて迎えた冬︵2012年の緑グラフ1月1日~3月31日︶は、2010年、2011年に比べて低い値で推移しています。 これは、節電効果によるものが大と考えられます。 3月の部分を取り出して拡大したグラフがこちらです。
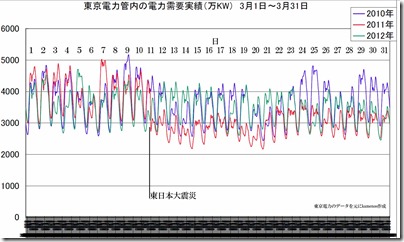 第1図のごちゃごちゃした部分がよりはっきりして、一日の電力需要の変化がよくわかります。
第1図のごちゃごちゃした部分がよりはっきりして、一日の電力需要の変化がよくわかります。
さて、問題はこれからです。 梅雨が開けた後、本格的な夏を迎える7月半ばから8月が正念場です。 下のグラフは7月1日から7月31日までの部分を拡大したものです。 東京電力のデータは一日前まで出されていますので、今年のデータは7月5日分までを盛り込みました。
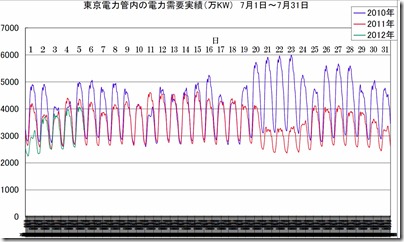 2010年には、7月23日の午後2時ぐらいに電力需要のピークを迎えています。
グラフを見て分かるとおり、この昼前後数時間の間にグーンと電力需要が高まり、2時前後にピークを迎え、夕方に向けてグーンと下がっていきます。
夏場のこの時間帯の節電が重要であることがよくわかります。
今年は、赤い線と緑の線がほぼ同一のカーブを描いていますので、昨年並みの需要動向のまま推移しているようです。
節電行動が定着している証拠です。
ただ、昨年は稼働していた原子力発電所は、次々と停止し、現在は東京電力エリアでは、原子力発電所の稼働がゼロとなっています。
より一層の節電行動が求められます。
2010年には、7月23日の午後2時ぐらいに電力需要のピークを迎えています。
グラフを見て分かるとおり、この昼前後数時間の間にグーンと電力需要が高まり、2時前後にピークを迎え、夕方に向けてグーンと下がっていきます。
夏場のこの時間帯の節電が重要であることがよくわかります。
今年は、赤い線と緑の線がほぼ同一のカーブを描いていますので、昨年並みの需要動向のまま推移しているようです。
節電行動が定着している証拠です。
ただ、昨年は稼働していた原子力発電所は、次々と停止し、現在は東京電力エリアでは、原子力発電所の稼働がゼロとなっています。
より一層の節電行動が求められます。
○夏の節電は、7月~8月の平日の午前9時から午後8時の節電につとめる。 ○その時間帯のうち、午後1時から午後4時の節電が特に重要。 ○それ以外の時間帯は無理に節電する必要はない。 とにかく、電力需要の状況をリアルタイムに把握して、効率良い節電行動を無理なく行うことが大切でしょう。 具体的な節電行動として、政府のポータルサイトに判りやすい取り組み事例が紹介されています。

2012年6月27日
昨年並の節電維持は難しい
貞昌院の電気電力計の検診日は毎月27日に行なわれ、検針票が投函されます。
24年6月分︵5月29日~6月26日︶の使用量のお知らせは次のとおりでした。
使用量は444kWh。
︵庫裏と本堂、客殿を合わせた貞昌院全体の使用量です︶
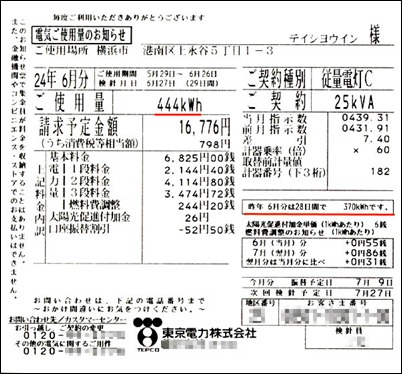 なお、赤線で示したように、昨年同月の使用量が参考値として記載されています。
昨年は東日本大震災直後ということもあり、計画停電と徹底的な節電を行った結果、370kWhでした。
今年も節電を心がけてはいますが、昨年の水準を維持することは難しいと感じています。
74kWh増えてしまいました。
なお、赤線で示したように、昨年同月の使用量が参考値として記載されています。
昨年は東日本大震災直後ということもあり、計画停電と徹底的な節電を行った結果、370kWhでした。
今年も節電を心がけてはいますが、昨年の水準を維持することは難しいと感じています。
74kWh増えてしまいました。
この傾向は貞昌院だけでは無いような気がします。 ︵是非、皆様も電力会社からの検針票に着目してみてください︶
街中には昨年よりも明らかに光が溢れています。 止められていたエスカレーターやエレベーターも、平常通り動いています。 昨年同時期よりも原子力発電所の稼働率が極端に低下してる中、これからの本格的な夏に向けて、考えなければならないことはたくさんありそうです。
貞昌院の太陽光発電による余剰電力は、昨年よりも多い結果が出ました。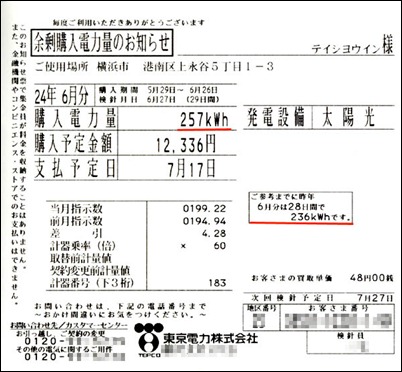 太陽光発電の余剰電力は、太陽が高い位置にある時間帯に生じます。
すなわち、日本中の消費電力がピークを迎える時間帯に電力を生み出しているということを意味します。
消費電力のピークカット、ピークシフトに太陽光発電が大きく寄与しています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
毎月の使用電力のお知らせを集めることが面倒でも、電力会社では過去2年間ほどの電力使用量を表やグラフにまとめてくれるサービスを提供しています。
このようなシステムを利用することもおすすめします。
太陽光発電の余剰電力は、太陽が高い位置にある時間帯に生じます。
すなわち、日本中の消費電力がピークを迎える時間帯に電力を生み出しているということを意味します。
消費電力のピークカット、ピークシフトに太陽光発電が大きく寄与しています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
毎月の使用電力のお知らせを集めることが面倒でも、電力会社では過去2年間ほどの電力使用量を表やグラフにまとめてくれるサービスを提供しています。
このようなシステムを利用することもおすすめします。
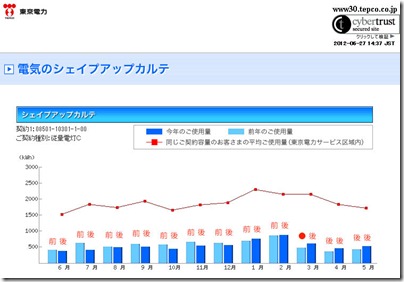 このグラフは、貞昌院の電力使用量の推移を表示したものです。
棒グラフの上に、前︵=震災前︶、●︵=震災の月︶、後︵=震災後︶を記しました。
同月の比較で、6月~2月は、震災前ー震災後の比較となっている月は、使用量を削減できていることがわかります。
3~5月は、同月の部分が震災後、および、その一年後の月ということになりますので、使用量が昨年同月よりも使用量が増えてしまっています。
このことからも、震災直後に行った徹底的な節電を維持することが難しいということが良くわかります。
皆さんのところはいかがでしょうか?
このグラフは、貞昌院の電力使用量の推移を表示したものです。
棒グラフの上に、前︵=震災前︶、●︵=震災の月︶、後︵=震災後︶を記しました。
同月の比較で、6月~2月は、震災前ー震災後の比較となっている月は、使用量を削減できていることがわかります。
3~5月は、同月の部分が震災後、および、その一年後の月ということになりますので、使用量が昨年同月よりも使用量が増えてしまっています。
このことからも、震災直後に行った徹底的な節電を維持することが難しいということが良くわかります。
皆さんのところはいかがでしょうか?
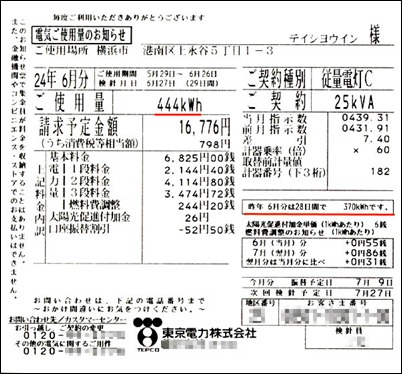 なお、赤線で示したように、昨年同月の使用量が参考値として記載されています。
昨年は東日本大震災直後ということもあり、計画停電と徹底的な節電を行った結果、370kWhでした。
今年も節電を心がけてはいますが、昨年の水準を維持することは難しいと感じています。
74kWh増えてしまいました。
なお、赤線で示したように、昨年同月の使用量が参考値として記載されています。
昨年は東日本大震災直後ということもあり、計画停電と徹底的な節電を行った結果、370kWhでした。
今年も節電を心がけてはいますが、昨年の水準を維持することは難しいと感じています。
74kWh増えてしまいました。
この傾向は貞昌院だけでは無いような気がします。 ︵是非、皆様も電力会社からの検針票に着目してみてください︶
街中には昨年よりも明らかに光が溢れています。 止められていたエスカレーターやエレベーターも、平常通り動いています。 昨年同時期よりも原子力発電所の稼働率が極端に低下してる中、これからの本格的な夏に向けて、考えなければならないことはたくさんありそうです。
貞昌院の太陽光発電による余剰電力は、昨年よりも多い結果が出ました。
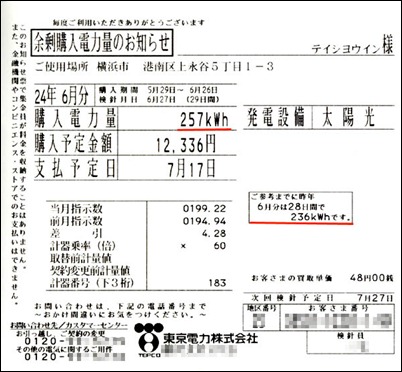 太陽光発電の余剰電力は、太陽が高い位置にある時間帯に生じます。
すなわち、日本中の消費電力がピークを迎える時間帯に電力を生み出しているということを意味します。
消費電力のピークカット、ピークシフトに太陽光発電が大きく寄与しています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
毎月の使用電力のお知らせを集めることが面倒でも、電力会社では過去2年間ほどの電力使用量を表やグラフにまとめてくれるサービスを提供しています。
このようなシステムを利用することもおすすめします。
太陽光発電の余剰電力は、太陽が高い位置にある時間帯に生じます。
すなわち、日本中の消費電力がピークを迎える時間帯に電力を生み出しているということを意味します。
消費電力のピークカット、ピークシフトに太陽光発電が大きく寄与しています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
毎月の使用電力のお知らせを集めることが面倒でも、電力会社では過去2年間ほどの電力使用量を表やグラフにまとめてくれるサービスを提供しています。
このようなシステムを利用することもおすすめします。
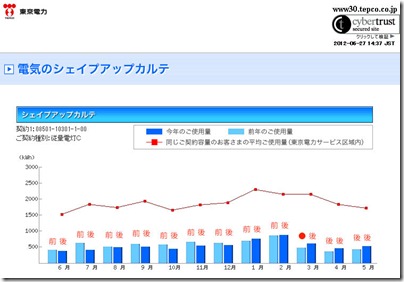 このグラフは、貞昌院の電力使用量の推移を表示したものです。
棒グラフの上に、前︵=震災前︶、●︵=震災の月︶、後︵=震災後︶を記しました。
同月の比較で、6月~2月は、震災前ー震災後の比較となっている月は、使用量を削減できていることがわかります。
3~5月は、同月の部分が震災後、および、その一年後の月ということになりますので、使用量が昨年同月よりも使用量が増えてしまっています。
このことからも、震災直後に行った徹底的な節電を維持することが難しいということが良くわかります。
皆さんのところはいかがでしょうか?
このグラフは、貞昌院の電力使用量の推移を表示したものです。
棒グラフの上に、前︵=震災前︶、●︵=震災の月︶、後︵=震災後︶を記しました。
同月の比較で、6月~2月は、震災前ー震災後の比較となっている月は、使用量を削減できていることがわかります。
3~5月は、同月の部分が震災後、および、その一年後の月ということになりますので、使用量が昨年同月よりも使用量が増えてしまっています。
このことからも、震災直後に行った徹底的な節電を維持することが難しいということが良くわかります。
皆さんのところはいかがでしょうか?
■関連ブログ記事
電力の自由化は安定供給と価格の低下をもたらすか
電気料金32年ぶり値上げ申請
屋根貸し制度と曹洞宗メガソーラー
2012年5月26日
電力の自由化は安定供給と価格の低下をもたらすか
北海道電力泊原子力発電所が定期検査に入り、停止となったことで、現在の日本では﹁原発ゼロ﹂の状態となっています。
原発再稼動についての論議は、賛否両論ありましょうが、これまで少なからず電力供給を原子力発電に頼っていたという事実は事実としてあります。
そのことを踏まえ、このまま原子力発電所の再稼動が無い状態が続くとどのような影響が生じるかを、まず纏めてみます。
これは昨年度︵2011年度︶から既に始まっている事象ですので、原発再稼動反対論者も、再稼動容認論者もしっかりと認識しておく必要があります。
︵1︶東日本大震災前に発電電力量の約3割を占めていた原子力発電が停止しているため、その不足分が火力発電で補われている。燃料輸入増加により、例年よりも毎年3兆円を超える国富が海外に流出している。この値は、実に日本のGDPの0.6%に当たる。
︵2︶燃料費の輸入単価の高騰により、電力料金は上昇傾向にある。このことは、家計を圧迫し、企業の利益をも減少させることとなる。
︵3︶計画停電、あるいは節電を強いられることにより、企業活動が計画通りに行なえなくなる。
︵4︶火力発電所は、寿命を迎えたものを含めてフル稼働しているが、火力発電所を新設するためには10年程必要。再生可能エネルギーの普及も時間がかかるだろう。したがって、慢性的な電力不足は向こう10年は続く。
︵5︶結果として、設備投資の減少や、生産拠点を海外にシフトするなど、雇用条件の悪化、産業空洞化を引き起こす。
などなど、東日本大震災から復旧復興する段階にある日本にとっては、悪い条件が重なっているのです。
だから、即、全ての原子力発電所を再稼動すべきとは言いませんし、そのような意見を押し付けたりもしません。
ただ上記︵1︶~︵5︶は実際問題として起こっている事象であり、では実際にどのようにこの困難を乗り越えていくかを、真剣かつ早急に意思決定していく必要があります。
総合資源エネルギー調査会の試算によると、今から約20年後、2030年に原発がゼロとなった場合、2人以上世帯の月額電気料金は、現在の電源構成を維持したケース︵約9900円︶より77~133%上昇し、17600~23100円に跳ね上がるとされています。
これにより、企業の生産活動が制約を受け、消費の落込みと併せて、2030年の国内総生産(GDP)は、5%程度下押しされます。
仮に2030年まで原子力発電所の不足を火力発電所で補い、その間に再生可能エネルギーの普及拡大を進めるというシナリオを考えると、毎年3兆円を超える︵原油・LNGの価格動向によってはそれ以上︶国富が海外に流出する状況が約20年続いた上に、水力を含む再生可能エネルギーの比率を現状の9%から35%程度まで高める必要があります。
このようなことが本当に可能でしょうか。
可能だとしても、それまで日本経済が持続するのかどうか。
政府主導により、一時の﹁脱原発﹂の風潮に流されないで、中長期的な景気影響や安定供給を見据えたエネルギー戦略を打ち出すことが必要だと、個人的には考えます。
さて、ブログタイトルに記載した、﹁電力の自由化は安定供給と価格の低下をもたらすか﹂について考えてみます。 いまの日本の世論は、電力を自由化することにより、価格競争が進み、電気料金が安くなる。 だから、自由化を進めるべきだ・・・というものが大勢を占めているように感じます。 まずは、電気料金の国際比較を見てみましょう。 単位は米ドル/MWhですから、ここ数年の極端な円高も併せて考慮すると良いと思います。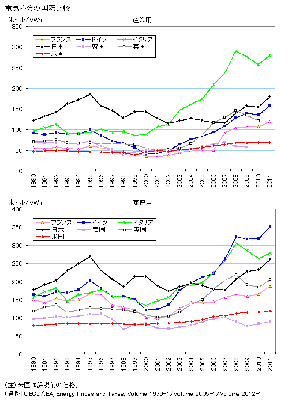 家庭用電力料金でいうと、1990年代の日本は、高めであったことがわかります。
しかし、2000年を越えてから、イタリア、ドイツが急上昇しています。
日本は200~250米ドル/MWhで安定しています。
円高を考慮すると、むしろ下落傾向にさえあることが分かります。
イタリアは慢性的な電力不足による電力輸入超過が響いて、産業用、家庭用ともに価格が上昇しています。
日本も今後、このような推移を辿るのかもしれません。
着目すべきはドイツです。
環境先進国というイメージがありますが。電力料金はやはり上昇傾向にあります。
ドイツ・ドレスデンのサイトより資料を引用してもう少し詳細にみてみましょう。
家庭用電力料金でいうと、1990年代の日本は、高めであったことがわかります。
しかし、2000年を越えてから、イタリア、ドイツが急上昇しています。
日本は200~250米ドル/MWhで安定しています。
円高を考慮すると、むしろ下落傾向にさえあることが分かります。
イタリアは慢性的な電力不足による電力輸入超過が響いて、産業用、家庭用ともに価格が上昇しています。
日本も今後、このような推移を辿るのかもしれません。
着目すべきはドイツです。
環境先進国というイメージがありますが。電力料金はやはり上昇傾向にあります。
ドイツ・ドレスデンのサイトより資料を引用してもう少し詳細にみてみましょう。
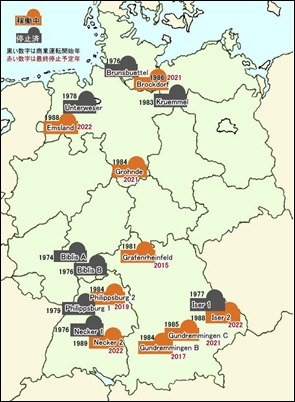 ドイツ国内には現在図のような原子力発電所があります。
うち、2012年までに稼動停止した発電所がグレーで塗られています。
オレンジの発電所はまだまだ稼働中で寿命まで運用した上で、赤数字の年に停止する予定となっています。
したがって、ドイツでは脱原発を進めているとはいえ、現在、あるいは今後も相当の割合を原子力発電所に頼ることとなります。
ドイツ国内には現在図のような原子力発電所があります。
うち、2012年までに稼動停止した発電所がグレーで塗られています。
オレンジの発電所はまだまだ稼働中で寿命まで運用した上で、赤数字の年に停止する予定となっています。
したがって、ドイツでは脱原発を進めているとはいえ、現在、あるいは今後も相当の割合を原子力発電所に頼ることとなります。
また、ドイツの電気料金は、電気料金の国際比較で見たとおり、2000年から2010年にかけてのかなりの上昇が見られます。 その内訳は下図のとおりです。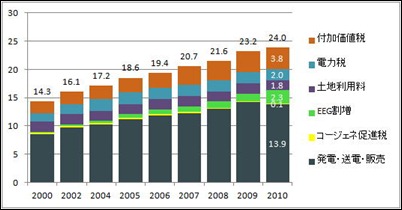 図・ドイツの電力価格の構成と推移 単位‥ セント
出所‥連邦環境・自然保護・原子炉安全省 "Erneuerbare Energien in Zahlen"
図・ドイツの電力価格の構成と推移 単位‥ セント
出所‥連邦環境・自然保護・原子炉安全省 "Erneuerbare Energien in Zahlen"
注1︶﹁電力税﹂は環境税の一種 注2︶﹁土地利用料﹂は送配・電のための道路等使用料としてエネルギー事業法に基づいて市町村が課す。 注3︶﹁EEG割増﹂は再生可能エネルギー割増 注4︶﹁コージェネ促進税﹂はEEG割増と同様にコージェネ助成費用を電力価格に上乗せするもの。 原子力発電所の不足分を火力発電所で補い、その間に再生可能エネルギーの普及拡大を勧めるということは、やはり相当の価格上昇を覚悟する必要がありそうです。
さらに、ヨーロッパ各国の電力料金推移の図をもう一つ提示します。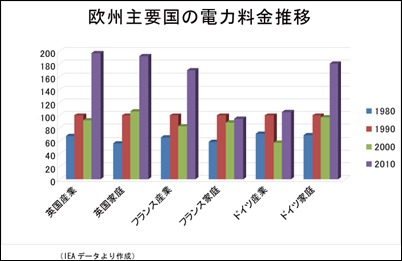 上図は、ヨーロッパ各国の電力料金の推移です。
上図は、ヨーロッパ各国の電力料金の推移です。
﹁電力を自由化すれば料金が下がるということ﹂を、必ずしも期待できないということです。 期待するだけ、後で失望感が大きくやってきます ヨーロッパ諸国の中で、特に電力の自由化を進めたのが英国です。 しかし、結果として、2000年から2010年に掛けての上昇は約2倍となっています。 発電設備は、巨大な規模になるほど単価が安くなるという規模の経済が顕著に働きますので、競争により小型の多くの発電所が乱立する状況よりも、大型の発電所に集約する供給システムのほうがコストが安くなる性質があります。 さらに、﹁品質の良い電力を安定供給する﹂という命題が課せられるために、自然独占が認められてきた市場なのです。 もちろん天下りや献金、癒着といった問題は改善されなければなりませんが、場合によっては自然独占、寡占が必要な市場もあるということです。 また、記憶に新しいカリフォルニア州の例では、自由化後、電力価格が急騰し始め、小売価格が凍結されなかったサンディエゴ地区では僅か3ヵ月間で標準家庭の電力料金は月間50ドルから120ドルになり、その他の地区でも大規模な停電や電力料金の高騰と供給不安が発生しています。 電力という市場が、自由化に向かない市場であるという論議があるため、よほど制度を周到に準備して厳格に適用しないとないと自由化の成果は生み出されないでしょう。 ︵はたしてそのような制度の厳格な適用が自由化と呼べるかどうかは疑問ですが︶ 今後日本の電力市場が健全な自由化を進めることが出来るかどうか分かりませんが、少なくとも自由化が進めば競争原理が働き、電力料金は安くなると短絡的に考えないほうが良さそうです。 これらの基礎資料を踏まえた上で、日本のエネルギー政策の方向性を冷静に考える必要があります。
■関連ブログ記事 電気料金32年ぶり値上げ申請
さて、ブログタイトルに記載した、﹁電力の自由化は安定供給と価格の低下をもたらすか﹂について考えてみます。 いまの日本の世論は、電力を自由化することにより、価格競争が進み、電気料金が安くなる。 だから、自由化を進めるべきだ・・・というものが大勢を占めているように感じます。 まずは、電気料金の国際比較を見てみましょう。 単位は米ドル/MWhですから、ここ数年の極端な円高も併せて考慮すると良いと思います。
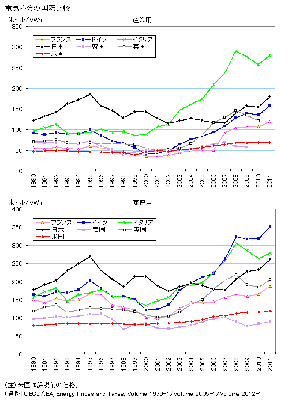 家庭用電力料金でいうと、1990年代の日本は、高めであったことがわかります。
しかし、2000年を越えてから、イタリア、ドイツが急上昇しています。
日本は200~250米ドル/MWhで安定しています。
円高を考慮すると、むしろ下落傾向にさえあることが分かります。
イタリアは慢性的な電力不足による電力輸入超過が響いて、産業用、家庭用ともに価格が上昇しています。
日本も今後、このような推移を辿るのかもしれません。
着目すべきはドイツです。
環境先進国というイメージがありますが。電力料金はやはり上昇傾向にあります。
ドイツ・ドレスデンのサイトより資料を引用してもう少し詳細にみてみましょう。
家庭用電力料金でいうと、1990年代の日本は、高めであったことがわかります。
しかし、2000年を越えてから、イタリア、ドイツが急上昇しています。
日本は200~250米ドル/MWhで安定しています。
円高を考慮すると、むしろ下落傾向にさえあることが分かります。
イタリアは慢性的な電力不足による電力輸入超過が響いて、産業用、家庭用ともに価格が上昇しています。
日本も今後、このような推移を辿るのかもしれません。
着目すべきはドイツです。
環境先進国というイメージがありますが。電力料金はやはり上昇傾向にあります。
ドイツ・ドレスデンのサイトより資料を引用してもう少し詳細にみてみましょう。
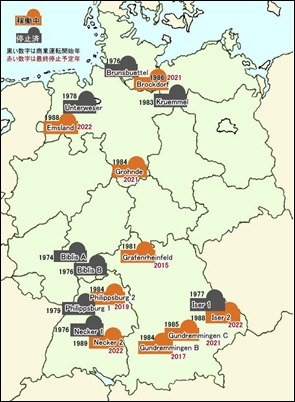 ドイツ国内には現在図のような原子力発電所があります。
うち、2012年までに稼動停止した発電所がグレーで塗られています。
オレンジの発電所はまだまだ稼働中で寿命まで運用した上で、赤数字の年に停止する予定となっています。
したがって、ドイツでは脱原発を進めているとはいえ、現在、あるいは今後も相当の割合を原子力発電所に頼ることとなります。
ドイツ国内には現在図のような原子力発電所があります。
うち、2012年までに稼動停止した発電所がグレーで塗られています。
オレンジの発電所はまだまだ稼働中で寿命まで運用した上で、赤数字の年に停止する予定となっています。
したがって、ドイツでは脱原発を進めているとはいえ、現在、あるいは今後も相当の割合を原子力発電所に頼ることとなります。
また、ドイツの電気料金は、電気料金の国際比較で見たとおり、2000年から2010年にかけてのかなりの上昇が見られます。 その内訳は下図のとおりです。
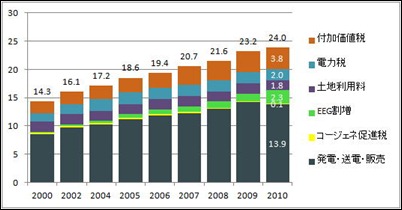 図・ドイツの電力価格の構成と推移 単位‥ セント
出所‥連邦環境・自然保護・原子炉安全省 "Erneuerbare Energien in Zahlen"
図・ドイツの電力価格の構成と推移 単位‥ セント
出所‥連邦環境・自然保護・原子炉安全省 "Erneuerbare Energien in Zahlen"
注1︶﹁電力税﹂は環境税の一種 注2︶﹁土地利用料﹂は送配・電のための道路等使用料としてエネルギー事業法に基づいて市町村が課す。 注3︶﹁EEG割増﹂は再生可能エネルギー割増 注4︶﹁コージェネ促進税﹂はEEG割増と同様にコージェネ助成費用を電力価格に上乗せするもの。 原子力発電所の不足分を火力発電所で補い、その間に再生可能エネルギーの普及拡大を勧めるということは、やはり相当の価格上昇を覚悟する必要がありそうです。
さらに、ヨーロッパ各国の電力料金推移の図をもう一つ提示します。
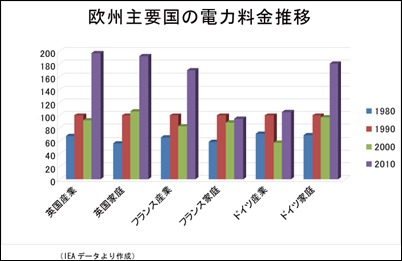 上図は、ヨーロッパ各国の電力料金の推移です。
上図は、ヨーロッパ各国の電力料金の推移です。
﹁電力を自由化すれば料金が下がるということ﹂を、必ずしも期待できないということです。 期待するだけ、後で失望感が大きくやってきます ヨーロッパ諸国の中で、特に電力の自由化を進めたのが英国です。 しかし、結果として、2000年から2010年に掛けての上昇は約2倍となっています。 発電設備は、巨大な規模になるほど単価が安くなるという規模の経済が顕著に働きますので、競争により小型の多くの発電所が乱立する状況よりも、大型の発電所に集約する供給システムのほうがコストが安くなる性質があります。 さらに、﹁品質の良い電力を安定供給する﹂という命題が課せられるために、自然独占が認められてきた市場なのです。 もちろん天下りや献金、癒着といった問題は改善されなければなりませんが、場合によっては自然独占、寡占が必要な市場もあるということです。 また、記憶に新しいカリフォルニア州の例では、自由化後、電力価格が急騰し始め、小売価格が凍結されなかったサンディエゴ地区では僅か3ヵ月間で標準家庭の電力料金は月間50ドルから120ドルになり、その他の地区でも大規模な停電や電力料金の高騰と供給不安が発生しています。 電力という市場が、自由化に向かない市場であるという論議があるため、よほど制度を周到に準備して厳格に適用しないとないと自由化の成果は生み出されないでしょう。 ︵はたしてそのような制度の厳格な適用が自由化と呼べるかどうかは疑問ですが︶ 今後日本の電力市場が健全な自由化を進めることが出来るかどうか分かりませんが、少なくとも自由化が進めば競争原理が働き、電力料金は安くなると短絡的に考えないほうが良さそうです。 これらの基礎資料を踏まえた上で、日本のエネルギー政策の方向性を冷静に考える必要があります。
■関連ブログ記事 電気料金32年ぶり値上げ申請
2012年5月12日
電気料金32年ぶり値上げ申請
5月11日、東京電力は家庭・個人商店等の小口契約の電気料金を約10%値上げする申請を経済産業省に出しました。
電気料金の値上げは32年ぶりです。
日本の電気料金は高いというイメージがありますが、それでも日本の経済成長を支えてきた電力を、そして精密産業を支えてきた世界一安定した電力を、私たちは享受してきたという事実をまず認識しておく必要があるでしょう。
32年間値上げが無かったという理由はなぜだったのか、ということも併せて考えておく必要があります。
さて、本題に入ります。 今回の値上げ申請の内容は、使用量の少ない契約者では値上げ額が小なく、使用電力量が大きいほど値上げの幅が大きくなっています。 実際に、個別にどれほどの負担増になるかについては 電気料金シミュレーション で確認できます。 電力料金値上げの根拠が東京電力のサイトに 徹底した経営合理化に取り組んでいます。 一方で、火力発電の燃料費等が大きく増加しています。 そのため、やむを得ず料金値上げをお願いしています。 というように纏められておりますので、まずは一読されることをお薦めします。
東日本大震災前に日本の電力全体の約3割を賄っていた原子力発電所は、順次点検のため停止し、再稼動しないまま今月全ての発電所が停止しました。 このまま全国の全原子力発電所を停止したまま全て廃炉することも選択肢の一つでしょう。 しかし、それを実現するためには、私たちは相当の覚悟が必要です。 原子力発電所反対論者も含めて、世間一般的にその覚悟がされているとはとても思えないのです。 振り返って、一年前の今頃は、私たちは計画停電を強いられ、自主的にもかなりの電気使用削減に努めていました。 街の明かりは可能な限り落とされ、店舗、駅構内の照明は薄暗く、エレベーター、エスカレーターも最低限の稼動、電車の間引き運転・・・・ その中で、なんとか夏を乗り切ることができました。 昨年は夏は一昨年のような猛暑で無かったことも幸いしました。 しかし、現在、一年前のちょうど今頃に比べて如何でしょうか。 照明はかなり明るく灯されています。エレベーター、エスカレーターの稼動も制限がかなり解除されました。 電車も通常通り運行しています。 工場も、観光地も震災直後から相当復旧復興し、電力需要は総じて伸びています。 さらに、今年、あるいは来年、再来年のうちには必ず猛暑がやって来るはずです。
両者を考え合わせるにつけて、今後の電力需給バランスは、状況次第で電力不足に陥る可能性が高く、安定した電力供給が望めないことは明白です。 今のところは老朽化して寿命を迎えた火力発電所を含めてフル稼働して凌いでいますが、余裕・ゆとりの無い発電所稼動は、万が一の場合重大な事故を引き起こしかねません。 さらに悪いことに、中東の政情不安も重なって、原油、LNGの料金は高騰しています。 つまり、急に原子力発電に頼らない方向に舵を切り替えるためには ・これまで以上の節電 ・電気料金値上げの容認 ・経済的に後退した状況への覚悟 等々が必要不可欠であるにもかかわらず、それがなされているようには到底感じられないのです。 ここまでの結論は、節電に頼った電力需給対策は、一時的には凌げるかもしれないけれども、持続性に欠ける施策である ということです。 さらに、電気料金の値上げによって私たちが負担する電気料金の増分のほとんどは、重油やLNGなど火力発電所の燃料輸入として、日本国外に流出してしまうという事実も重く認識しておく必要があります。 原子力発電所代替の火力発電所焚き増しによる燃料費の増加は一昨年に比べて2~3兆円の増加と試算され、その分、日本の貿易収支の支出増に燃料費が重く圧し掛かっていることがわかります。 その年間何兆円ものお金を被災地復興のため、或いは放射能汚染地域除染のために使ったほうが、どれだけ有用なのでしょうか。 これら全てが日本経済復興の大きな足かせになっていることを考え合わせて、現実的な着地点として、事故を起こした原子力発電所の原因を踏まえ、この経験を生かし、適切なストレステストを経た上で安全性が確認された電子力発電所の再稼動を行うこと が必要であると考えます。 これまで少なからず原子力発電施策を容認してきた私たちの暮らしを、いきなり原子力発電に頼らない社会構造に移行することは無理です。
しかし、原子力発電に頼る社会構造からの緩やかな脱却は可能でしょう。 今後、原子力発電所の新設を行わないこととすれば、数十年のうちに自ずと原子力発電所の割合は減少していきます。 寿命を全うした発電所設備は廃炉になるからです。 その間に、原子力発電に頼らない社会構造に移行していけば良いのです。 廃炉を行うにしても、向こう数十年、あるいは数百年単位のプロセスが必要であることも勘案する必要があります。 廃炉に向けた安全なステップで、日本は世界をリードする技術を培うことができればさらに良いでしょう。 やみくもに﹁値上げ反対﹂﹁原子力発電所再稼動反対﹂を唱えるだけでではなく、その場合にどのような対案があるのかを提示して、真剣に考えていくことが大切です。
東京電力は、夜間の電気料金が安くなる新料金プランを6月から導入することを併せて発表しました。
この料金体系は﹁電気ジョーズ﹂として、これまでもあったのですが、それはオール電化の設備を設置した場合に限られていました。
しかし、その選択肢が全ての家庭、事業所に広がったことにより、太陽光発電を含めた新エネルギー普及の原動力となりそうです。
また、特に太陽光発電を設置している家庭・事業所にとっては、直接的な料金のメリットを受けることができそうです。
新たなピーク抑制型料金︵選択約款︶の設定
ピーク時間︵夏季の13時~16時︶に割高な料金を設定し、ピーク時の節電インセンティブとさせていただくとともに、夜間時間の料金を安く設定し、電気のご使用をピーク時間から昼間時間・夜間時間に、または昼間時間から夜間時間に移行していただくことにより、電気料金の低減が可能となる新たな料金メニューとして、ピーク抑制型季節別時間帯別電灯︵以下﹁ピークシフトプラン﹂︶を設定することといたしました。
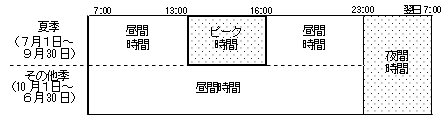 ピークシフトプランにおいて料金が高くなる時間帯は、晴天時の太陽光発電の発電ピーク時と重なります。
︵この発電ピークは、日本の電力使用のピーク時間帯とも重なります︶
貞昌院でも、このプランでの契約変更を具体的に検討してみたいと考えています。
地球温暖化対策としての太陽光発電設備が、原子力発電に頼る社会からの脱却に貢献できるということも大きな意味を持ちます。
■関連ブログ記事
ソーラー作戦、地球温暖化対策として大展開 ︵2005年の記事︶
全国の寺院に太陽光発電があると︵2007年の記事︶
エネルギー源分散のメリット︵2011年の記事︶
屋根貸し制度と曹洞宗メガソーラー︵2012年の記事︶
ピークシフトプランにおいて料金が高くなる時間帯は、晴天時の太陽光発電の発電ピーク時と重なります。
︵この発電ピークは、日本の電力使用のピーク時間帯とも重なります︶
貞昌院でも、このプランでの契約変更を具体的に検討してみたいと考えています。
地球温暖化対策としての太陽光発電設備が、原子力発電に頼る社会からの脱却に貢献できるということも大きな意味を持ちます。
■関連ブログ記事
ソーラー作戦、地球温暖化対策として大展開 ︵2005年の記事︶
全国の寺院に太陽光発電があると︵2007年の記事︶
エネルギー源分散のメリット︵2011年の記事︶
屋根貸し制度と曹洞宗メガソーラー︵2012年の記事︶
さて、本題に入ります。 今回の値上げ申請の内容は、使用量の少ない契約者では値上げ額が小なく、使用電力量が大きいほど値上げの幅が大きくなっています。 実際に、個別にどれほどの負担増になるかについては 電気料金シミュレーション で確認できます。 電力料金値上げの根拠が東京電力のサイトに 徹底した経営合理化に取り組んでいます。 一方で、火力発電の燃料費等が大きく増加しています。 そのため、やむを得ず料金値上げをお願いしています。 というように纏められておりますので、まずは一読されることをお薦めします。
東日本大震災前に日本の電力全体の約3割を賄っていた原子力発電所は、順次点検のため停止し、再稼動しないまま今月全ての発電所が停止しました。 このまま全国の全原子力発電所を停止したまま全て廃炉することも選択肢の一つでしょう。 しかし、それを実現するためには、私たちは相当の覚悟が必要です。 原子力発電所反対論者も含めて、世間一般的にその覚悟がされているとはとても思えないのです。 振り返って、一年前の今頃は、私たちは計画停電を強いられ、自主的にもかなりの電気使用削減に努めていました。 街の明かりは可能な限り落とされ、店舗、駅構内の照明は薄暗く、エレベーター、エスカレーターも最低限の稼動、電車の間引き運転・・・・ その中で、なんとか夏を乗り切ることができました。 昨年は夏は一昨年のような猛暑で無かったことも幸いしました。 しかし、現在、一年前のちょうど今頃に比べて如何でしょうか。 照明はかなり明るく灯されています。エレベーター、エスカレーターの稼動も制限がかなり解除されました。 電車も通常通り運行しています。 工場も、観光地も震災直後から相当復旧復興し、電力需要は総じて伸びています。 さらに、今年、あるいは来年、再来年のうちには必ず猛暑がやって来るはずです。
両者を考え合わせるにつけて、今後の電力需給バランスは、状況次第で電力不足に陥る可能性が高く、安定した電力供給が望めないことは明白です。 今のところは老朽化して寿命を迎えた火力発電所を含めてフル稼働して凌いでいますが、余裕・ゆとりの無い発電所稼動は、万が一の場合重大な事故を引き起こしかねません。 さらに悪いことに、中東の政情不安も重なって、原油、LNGの料金は高騰しています。 つまり、急に原子力発電に頼らない方向に舵を切り替えるためには ・これまで以上の節電 ・電気料金値上げの容認 ・経済的に後退した状況への覚悟 等々が必要不可欠であるにもかかわらず、それがなされているようには到底感じられないのです。 ここまでの結論は、節電に頼った電力需給対策は、一時的には凌げるかもしれないけれども、持続性に欠ける施策である ということです。 さらに、電気料金の値上げによって私たちが負担する電気料金の増分のほとんどは、重油やLNGなど火力発電所の燃料輸入として、日本国外に流出してしまうという事実も重く認識しておく必要があります。 原子力発電所代替の火力発電所焚き増しによる燃料費の増加は一昨年に比べて2~3兆円の増加と試算され、その分、日本の貿易収支の支出増に燃料費が重く圧し掛かっていることがわかります。 その年間何兆円ものお金を被災地復興のため、或いは放射能汚染地域除染のために使ったほうが、どれだけ有用なのでしょうか。 これら全てが日本経済復興の大きな足かせになっていることを考え合わせて、現実的な着地点として、事故を起こした原子力発電所の原因を踏まえ、この経験を生かし、適切なストレステストを経た上で安全性が確認された電子力発電所の再稼動を行うこと が必要であると考えます。 これまで少なからず原子力発電施策を容認してきた私たちの暮らしを、いきなり原子力発電に頼らない社会構造に移行することは無理です。
しかし、原子力発電に頼る社会構造からの緩やかな脱却は可能でしょう。 今後、原子力発電所の新設を行わないこととすれば、数十年のうちに自ずと原子力発電所の割合は減少していきます。 寿命を全うした発電所設備は廃炉になるからです。 その間に、原子力発電に頼らない社会構造に移行していけば良いのです。 廃炉を行うにしても、向こう数十年、あるいは数百年単位のプロセスが必要であることも勘案する必要があります。 廃炉に向けた安全なステップで、日本は世界をリードする技術を培うことができればさらに良いでしょう。 やみくもに﹁値上げ反対﹂﹁原子力発電所再稼動反対﹂を唱えるだけでではなく、その場合にどのような対案があるのかを提示して、真剣に考えていくことが大切です。
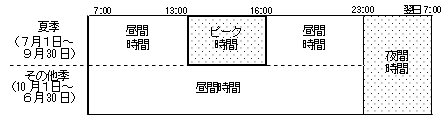
2012年4月27日
日本のICT お寺がアーカイブを推進
先日、電経新聞社から取材を受け、その記事が電経新聞4月23日号に掲載されました。
 取材内容は、日本のICT︵Information and Communication Technology︶の実践事例として、寺院や地域がどのようにデジタルアーカイブを推進していくことができるかという可能性を探るものでした。
それにしても、こちらの言いたいことをよく纏めてくださっています。
ありがたいことです。
ご縁に感謝したいと思います。
■関連ブログ記事
横浜の記憶を写真で残すためのシンポジウム報告
関東ICT推進NPO連絡協議会記念フォーラム報告
フォーラム@横浜赤レンガ倉庫
横浜的電脳18区の本
映像の持つ力を生かす取組み
みんなでつくる横濱写真アルバムシンポジウム
取材内容は、日本のICT︵Information and Communication Technology︶の実践事例として、寺院や地域がどのようにデジタルアーカイブを推進していくことができるかという可能性を探るものでした。
それにしても、こちらの言いたいことをよく纏めてくださっています。
ありがたいことです。
ご縁に感謝したいと思います。
■関連ブログ記事
横浜の記憶を写真で残すためのシンポジウム報告
関東ICT推進NPO連絡協議会記念フォーラム報告
フォーラム@横浜赤レンガ倉庫
横浜的電脳18区の本
映像の持つ力を生かす取組み
みんなでつくる横濱写真アルバムシンポジウム
 取材内容は、日本のICT︵Information and Communication Technology︶の実践事例として、寺院や地域がどのようにデジタルアーカイブを推進していくことができるかという可能性を探るものでした。
それにしても、こちらの言いたいことをよく纏めてくださっています。
ありがたいことです。
ご縁に感謝したいと思います。
取材内容は、日本のICT︵Information and Communication Technology︶の実践事例として、寺院や地域がどのようにデジタルアーカイブを推進していくことができるかという可能性を探るものでした。
それにしても、こちらの言いたいことをよく纏めてくださっています。
ありがたいことです。
ご縁に感謝したいと思います。
2012年4月 2日
長谷寺でSuiaca導入
長谷寺といっても、永平寺東京別院ではなく、鎌倉の長谷寺の話です。
昨日から電子マネーSuicaでの入山参拝が出来るようになりました。
スイカで古刹・長谷寺へ 入山券用の券売機で使用可能に
JR東日本横浜支社︵横浜市西区︶は1日、鎌倉の古刹︵こさつ︶、長谷寺︵神奈川県鎌倉市長谷︶の入山券販売用の券売機で電子マネー﹁Suica︵スイカ︶﹂を使えるサービスを始めた。鎌倉の神社仏閣では初の導入。
券売機は長谷寺の入り口に2台設置され、外国人の観光客も多く訪れるため、券売機のタッチパネルには日本語以外に英語、中国語、韓国語の3カ国の外国語でも文字が表記されている。同社の担当者は﹁長谷寺観光がより便利になるはず﹂と話している。
︵産経新聞 2012.4.1︶
鎌倉の寺社では初の試みです。
調べてみると、電子マネーで参拝可能になった寺社では、奈良県の阿部文殊院が2007年に導入したというニュースがありました。
寺の拝観料など電子マネーOK
奈良県桜井市の﹁安倍文殊院﹂は、2007年4月に入りプリペイド電子マネー﹁Edy﹂を使って拝観料やお守りなどの支払いができるようにした。同院では﹁若い人たちに対し、寺院や仏教への敷居を低くしたい﹂と狙いを説明している。他にも電子マネー﹁PiTaPaカード﹂などにも対応するという。
(J-CASTニュース 2007/4/17 ︶
お寺と電子マネー、一見まったく無縁であるような感じがしますが、海外に目を向ければ、クレジット決裁の寄附だとか、会費納入という事例は当たり前のようにあります。
日本がようやくその流れに追いついてきたのでしょう。
特に長谷寺は、台湾やタイ、ベトナムなど東南アジアからの団体参拝客が多く参拝に訪れ、在日本の方々も鎌倉観音巡礼を定期的にされています。 同じく鎌倉市にある曹洞宗寺院、大船観音寺でも、年間7万人の参拝客のうち、約3割はやはり東南アジアを中心とした日本人以外の方々です。 長谷寺と併せて参拝される方々も多いので、大船観音寺もSuicaなど電子マネー対応になると参拝客にとっては便利になるでしょう。 以前、お寺とポイントカードについて記事を書きました。 ⇒お墓参りにマイリポイント その記事の中で神社仏閣共通の地域通貨の性格を盛り込んでみては、という提案をさせていただきました。 すなわち、単純な法定通貨だけではなく、寺院共通の﹁地域通過﹂として還元する仕組みを付与するのです。 このことにより、さらに一歩進んだシステムとなると考えます。
例えばですが、﹁テラマイル﹂というマイルポイントを新に設定します。 この﹁テラマイル﹂ポイントを神社仏閣の地域通貨に還元させるようにするのです。 ・長谷寺、大船観音寺にお参りして50テラマイル ・菩提寺のお墓参りをして50テラマイル ・寺社の境内清掃に参加して1000テラマイル ・菩提寺の責任役員会に出席して500テラマイル ・・・・とか。 法定通貨よりも地域通過の方がよほど﹁お布施﹂の概念に適合するとさえ言ってもよいでしょう。 砕けた言い方をすれば、神様、ご本尊さまからのプレゼントです。
数年後には通貨の概念がガラッと変わっている、ということになるかもしれませんね。
特に長谷寺は、台湾やタイ、ベトナムなど東南アジアからの団体参拝客が多く参拝に訪れ、在日本の方々も鎌倉観音巡礼を定期的にされています。 同じく鎌倉市にある曹洞宗寺院、大船観音寺でも、年間7万人の参拝客のうち、約3割はやはり東南アジアを中心とした日本人以外の方々です。 長谷寺と併せて参拝される方々も多いので、大船観音寺もSuicaなど電子マネー対応になると参拝客にとっては便利になるでしょう。 以前、お寺とポイントカードについて記事を書きました。 ⇒お墓参りにマイリポイント その記事の中で神社仏閣共通の地域通貨の性格を盛り込んでみては、という提案をさせていただきました。 すなわち、単純な法定通貨だけではなく、寺院共通の﹁地域通過﹂として還元する仕組みを付与するのです。 このことにより、さらに一歩進んだシステムとなると考えます。
例えばですが、﹁テラマイル﹂というマイルポイントを新に設定します。 この﹁テラマイル﹂ポイントを神社仏閣の地域通貨に還元させるようにするのです。 ・長谷寺、大船観音寺にお参りして50テラマイル ・菩提寺のお墓参りをして50テラマイル ・寺社の境内清掃に参加して1000テラマイル ・菩提寺の責任役員会に出席して500テラマイル ・・・・とか。 法定通貨よりも地域通過の方がよほど﹁お布施﹂の概念に適合するとさえ言ってもよいでしょう。 砕けた言い方をすれば、神様、ご本尊さまからのプレゼントです。
数年後には通貨の概念がガラッと変わっている、ということになるかもしれませんね。
2012年2月10日
おはぎが売れ続ける理由
仙台の山奥にありながら
全国からお客様が
ひっきりなしにやってくる店がある・・・・・・
大きな地図で見る 山間の温泉地、秋保にあるごく普通の店構えの商店ですが、おそらく日本で一番有名なおはぎ屋さん。 それが主婦の店﹁佐市︵さいち︶﹂です。 何と、毎日おはぎが5000個、彼岸の時期は15000個も売れるそうです。
店に入ると、陳列棚に並べられたおはぎ、おはぎ、おはぎ、惣菜、おはぎ・・・・ それが瞬く間に売れていきます。 そのおはぎがこちら。
佐市の売り上げの殆んどは、おはぎと、お惣菜だそうです。 なぜ、この店の商品がこんなにも売れるのでしょうか。 その秘密を求めて、全国の百貨店やスーパーから研修や見学にも来るそうです。
遠くにあっても、山の中にあっても、それが良いものであれば人はそれを求めて集まってくる。 心理的距離 < 物理的距離 を実現するヒントは佐市の企業理念にありそうです。
■佐市の3つの心
・どの家庭の味よりさらにおいしい事。
・毎日食べても飽きが来ない事。
・時間がたっても、そのおいしさが失われない事
------------------------------------------------
■さいちの企業理念
私たちは、さいちでの仕事を通じて、地域の皆様に物心とものの豊かさを提供します。
■行動指針
・商品サービス・・・ 私たちは常に新鮮な食品と情報を提供します。
・固定客作り・・・・ わたくしたちは、常にお客様の立場に立って考え、真心を持ってサービスします
・チームワーク・・・ わたしたちは和と協調と思いやりの精神で仕事をします。
■誓いの言葉
私たちは、お客様に笑顔で、心をこめて﹁いらっしゃいませ﹂﹁ありがとうございました﹂の挨拶をすることを誓います。
ごくごく当たり前の企業理念ですね。
けれども、佐市のようなお店が他にほとんど見当たらないということが、それを真摯に実行することが実はとても難しいということを如実に物語っています。
この企業理念は、寺院にも当てはめることができますし、学ぶことも多いと感じます。
佐市取締役社長執筆による本も企業経営者を中心に売れているようです。
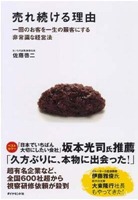
大きな地図で見る 山間の温泉地、秋保にあるごく普通の店構えの商店ですが、おそらく日本で一番有名なおはぎ屋さん。 それが主婦の店﹁佐市︵さいち︶﹂です。 何と、毎日おはぎが5000個、彼岸の時期は15000個も売れるそうです。
店に入ると、陳列棚に並べられたおはぎ、おはぎ、おはぎ、惣菜、おはぎ・・・・ それが瞬く間に売れていきます。 そのおはぎがこちら。

佐市の売り上げの殆んどは、おはぎと、お惣菜だそうです。 なぜ、この店の商品がこんなにも売れるのでしょうか。 その秘密を求めて、全国の百貨店やスーパーから研修や見学にも来るそうです。
遠くにあっても、山の中にあっても、それが良いものであれば人はそれを求めて集まってくる。 心理的距離 < 物理的距離 を実現するヒントは佐市の企業理念にありそうです。
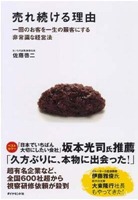
売れ続ける理由 一回のお客を一生の顧客にする非常識な経営法
佐藤啓二‥著 価格︵税込︶‥¥ 1,500 ISBN‥978-4-478-01322-9内容紹介 イトーヨーカドー創業者・伊藤雅俊氏、﹁餃子の王将﹂大東社長など、なぜ、全国600社超が仙台駅から車で30分強・人口4700人の山奥にあるお店に視察にくるのか? ﹁惣菜をつくる姿勢をつくる﹂がお客様がひっきりなしに押しかけてくる秘密。 日本人が忘れた宝物がここにある。75歳にして著者の処女作!
2011年12月18日
シャンパンゴールドの汽車道
この時期、お釈迦様の成道を祝う︵違いましたっけ?︶イルミネーションが街を鮮やかに彩っています。
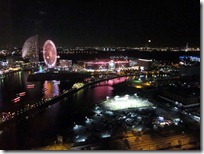
 みなとみらい地区では、汽車道の橋脚をシャンパンゴールドに照らすなど、様々な社会実験が行われています。
社会実験は、新たな制度・施策導入にあたって場所や期間を限定して試行することですので、これが良しとされれば定着することになるのでしょう。
みなとみらい地区では、汽車道の橋脚をシャンパンゴールドに照らすなど、様々な社会実験が行われています。
社会実験は、新たな制度・施策導入にあたって場所や期間を限定して試行することですので、これが良しとされれば定着することになるのでしょう。
 節電にも配慮し、光源にはLED︵発光ダイオード︶が使用されています。
このように、赤・緑・青などが並んでいて、内側の色が時間と共に変化するようになっています。
節電にも配慮し、光源にはLED︵発光ダイオード︶が使用されています。
このように、赤・緑・青などが並んでいて、内側の色が時間と共に変化するようになっています。
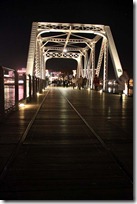
 イルミネーションと共に、成道の菩提樹を模ったツリー︵違いましたっけ?︶が街を彩ります。
ランドマークプラザでは、様々なコンサートが開催されていて、この日は全国大会に出場した横浜創英中高の吹奏楽部の演奏やワンピースのツリー、
イルミネーションと共に、成道の菩提樹を模ったツリー︵違いましたっけ?︶が街を彩ります。
ランドマークプラザでは、様々なコンサートが開催されていて、この日は全国大会に出場した横浜創英中高の吹奏楽部の演奏やワンピースのツリー、

 クイーンズスクエアでは﹁勇気の輝﹂をテーマにしたシンギングツリーなど。
クイーンズスクエアでは﹁勇気の輝﹂をテーマにしたシンギングツリーなど。


 ライトアップは来年の2月17日まで、16時~24時まで行われています。
ライトアップは来年の2月17日まで、16時~24時まで行われています。
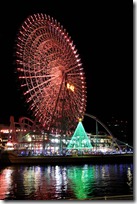
 ■関連ブログ記事
汽車道にまつわるエトセトラ
被災者のみなさまに届きますように2
■関連ブログ記事
汽車道にまつわるエトセトラ
被災者のみなさまに届きますように2
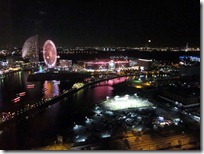
 みなとみらい地区では、汽車道の橋脚をシャンパンゴールドに照らすなど、様々な社会実験が行われています。
社会実験は、新たな制度・施策導入にあたって場所や期間を限定して試行することですので、これが良しとされれば定着することになるのでしょう。
みなとみらい地区では、汽車道の橋脚をシャンパンゴールドに照らすなど、様々な社会実験が行われています。
社会実験は、新たな制度・施策導入にあたって場所や期間を限定して試行することですので、これが良しとされれば定着することになるのでしょう。
 節電にも配慮し、光源にはLED︵発光ダイオード︶が使用されています。
このように、赤・緑・青などが並んでいて、内側の色が時間と共に変化するようになっています。
節電にも配慮し、光源にはLED︵発光ダイオード︶が使用されています。
このように、赤・緑・青などが並んでいて、内側の色が時間と共に変化するようになっています。
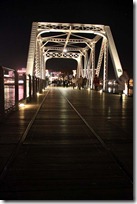
 イルミネーションと共に、成道の菩提樹を模ったツリー︵違いましたっけ?︶が街を彩ります。
ランドマークプラザでは、様々なコンサートが開催されていて、この日は全国大会に出場した横浜創英中高の吹奏楽部の演奏やワンピースのツリー、
イルミネーションと共に、成道の菩提樹を模ったツリー︵違いましたっけ?︶が街を彩ります。
ランドマークプラザでは、様々なコンサートが開催されていて、この日は全国大会に出場した横浜創英中高の吹奏楽部の演奏やワンピースのツリー、

 クイーンズスクエアでは﹁勇気の輝﹂をテーマにしたシンギングツリーなど。
クイーンズスクエアでは﹁勇気の輝﹂をテーマにしたシンギングツリーなど。


 ライトアップは来年の2月17日まで、16時~24時まで行われています。
ライトアップは来年の2月17日まで、16時~24時まで行われています。
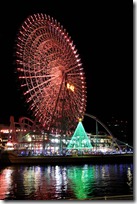

2011年6月18日
フランスで日本産茶葉から規制値を超える放射性物質

Du thé vert japonais radioactif intercepté à l'aéroport de Roissy
NUCLÉAIRE - Le produit a été mis en quarantaine et fera l'objet d'une destruction par une entreprise spécialisée...Un lot de thé vert en provenance du Japon, contenant deux fois plus de césium que le niveau maximal admissible, a été intercepté à l'aéroport parisien de Roissy, et doit être détruit, a annoncé ce vendredi la direction de la consommation (DGCCRF) dans un communiqué. Il s'agit d'un lot de 162 kg de feuilles séchées, en provenance de la préfecture de Shizuoka (centre). C'est la première fois que des produits radioactifs sont détectés en France dans le cadre des contrôles mis en place à la suite de l'accident de Fukushima. Contamination au césium supérieure au niveau maximal Les analyses en laboratoire ont mis en évidence une contamination en césium de 1.038 Bq/kg, supérieure au niveau maximal admissible défini au niveau européen, qui est de 500 Bq/kg pour ce type de produit, précise la DGCCRF. Le produit a été mis en quarantaine et fera l'objet d'une destruction par une entreprise spécialisée. La DGCCRF a décidé de «mettre en place un contrôle systématique de tous les végétaux en provenance de la même préfecture japonaise» et «va saisir la Commission européenne pour ajouter la préfecture de Shizuoka à la liste des préfectures pour lesquelles la réglementation européenne impose un contrôle systématique au départ du Japon». ︵AFP 17/06/2011 à 19h30︶日本からフランスに輸出された静岡県の緑茶茶葉から、規制値の2倍もの放射性セシウムが検出されたというニュースが入っています。 福島第一原発事故を受け、仏政府が日本からの輸入品の放射能検査を開始して以降、基準値を超える放射性セシウムが初めて検出されました。 汚染量は1.038のBq/kgで、ヨーロッパの基準値500のBqkgの2倍を超えています。
この報道はとても大きな意味を持っています。 日本からの輸出段階でチェックできなかったことの重い意味と、静岡県のお茶だけでなく、日本製の全ての製品に対する風評被害へと拡大することへの懸念です。 ﹁ニッポン﹂ブランドの崩壊が決定的になりかねない、本当に残念なニュースです。
2011年5月28日
ガソリン価格下落傾向
ここのところ、ガソリン価格が下落傾向にあります。
昨日横浜市内で給油した時は@137円でした。
 一時期は160円台となり、さらに震災での供給不足によりどうなることか心配していましたが、ガソリンに限っては、今後これから述べる理由によりさらなる安定供給と低価格化が見込まれます。
一時期は160円台となり、さらに震災での供給不足によりどうなることか心配していましたが、ガソリンに限っては、今後これから述べる理由によりさらなる安定供給と低価格化が見込まれます。
東日本大震災直後は、国内原油処理能力︵1日あたり450万バレル︶の約30%が稼働停止となってしまいました。 原油の緊急輸入、被災しなかった地域の製油所の稼働率の引上げ、備蓄日数の引下げににより、原油製品の生産に関しては余裕が生じつつあります。 稼動停止となっていた内の半数以上が既に回復し、これからも逐次製油所の復旧が進んでいくでしょう。 ガソリンの安定供給につながるもう一つの要因は、この夏に向けて火力発電所のフル稼働に伴う重油需要量の増大です。 電力不足を補うためにガスタービン発電や火力発電所の増強など緊急的に電力供給源を確保しなければなりません。 火力発電は、燃料として重油を使用します。 その重油を確保するために原油から重油のみを精製することはできません。 伴って、さまざまな副産物が生じます。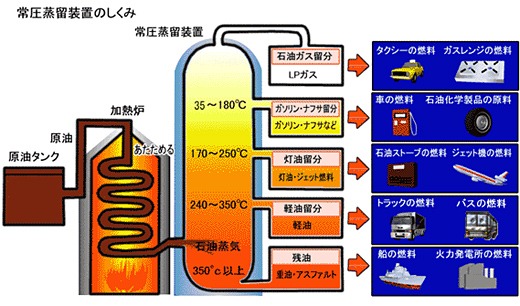 ︵図は石油情報センターより引用︶
︵図は石油情報センターより引用︶
LPガス、ガソリン、ナフサ、ジェット燃料、トラックやバスなどの軽油、アスファルトの原料となる残油などが副産物として生じていくわけです。
これらの副産物は、震災復興のために必要なものでもあります。 石油消費が増加して、結果としてCO2排出量が増大する、これは今後2-3年間に限っては震災からの復興という免罪符の下に許してもらうしかないですね。
さらに、円高の影響もあり、ガソリン価格はさらに下落していくことでしょう。 個人的にはガソリン価格は今年夏には120円位になるのではないかと考えています。 車の使用者としては嬉しいことでしょうけれど、復興税としての消費税増税が論議されるのであれば、それと併せてガソリン価格下落分を︵被災地以外の場所で︶復興税として徴収するということを検討してもよいのではないでしょうか。
■関連ブログ記事
実態からかけ離れてしまった経済
原油高騰でもサンマは安値
 一時期は160円台となり、さらに震災での供給不足によりどうなることか心配していましたが、ガソリンに限っては、今後これから述べる理由によりさらなる安定供給と低価格化が見込まれます。
一時期は160円台となり、さらに震災での供給不足によりどうなることか心配していましたが、ガソリンに限っては、今後これから述べる理由によりさらなる安定供給と低価格化が見込まれます。
東日本大震災直後は、国内原油処理能力︵1日あたり450万バレル︶の約30%が稼働停止となってしまいました。 原油の緊急輸入、被災しなかった地域の製油所の稼働率の引上げ、備蓄日数の引下げににより、原油製品の生産に関しては余裕が生じつつあります。 稼動停止となっていた内の半数以上が既に回復し、これからも逐次製油所の復旧が進んでいくでしょう。 ガソリンの安定供給につながるもう一つの要因は、この夏に向けて火力発電所のフル稼働に伴う重油需要量の増大です。 電力不足を補うためにガスタービン発電や火力発電所の増強など緊急的に電力供給源を確保しなければなりません。 火力発電は、燃料として重油を使用します。 その重油を確保するために原油から重油のみを精製することはできません。 伴って、さまざまな副産物が生じます。
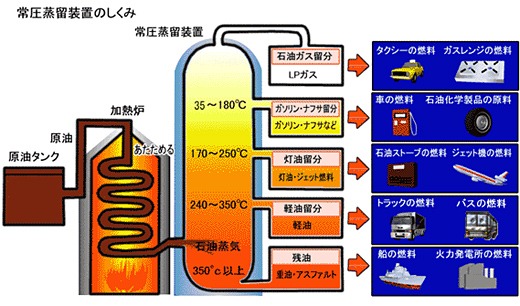 ︵図は石油情報センターより引用︶
︵図は石油情報センターより引用︶
LPガス、ガソリン、ナフサ、ジェット燃料、トラックやバスなどの軽油、アスファルトの原料となる残油などが副産物として生じていくわけです。
これらの副産物は、震災復興のために必要なものでもあります。 石油消費が増加して、結果としてCO2排出量が増大する、これは今後2-3年間に限っては震災からの復興という免罪符の下に許してもらうしかないですね。
さらに、円高の影響もあり、ガソリン価格はさらに下落していくことでしょう。 個人的にはガソリン価格は今年夏には120円位になるのではないかと考えています。 車の使用者としては嬉しいことでしょうけれど、復興税としての消費税増税が論議されるのであれば、それと併せてガソリン価格下落分を︵被災地以外の場所で︶復興税として徴収するということを検討してもよいのではないでしょうか。
2011年3月26日
過剰な自粛は必要か
東日本大震災の影響で、日本全体が﹁自粛﹂ムードになっています。
震災直後、大阪、道頓堀のグリコの看板が、節電に協力するために当分の間点灯を取りやめたというニュースがありました。 おそらく、今も消灯しているのではないでしょうか。 さらにいろいろと話を伺うと、関西のみならず、九州の方々にも、節電ムード、さまざまな行事の自粛ムードが広がっています。 しかし、日本全体が自粛ムードということは、あまり好ましく無いことだと考えます。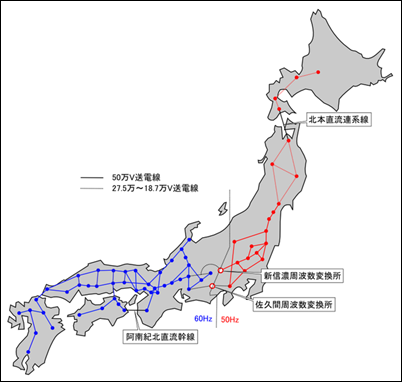 ︵図はウィキメディアより︶
︵図はウィキメディアより︶
今回の震災で、東日本エリアを賄う発電所が損壊してしまい、需要量を賄うだけの発電能力が失われてしまったため、本州東半分では計画節電の実施が長引きそうです。 国内での交流電源の周波数が、東日本と西日本での50ヘルツと60ヘルツと異なることは、西日本の電力を大々的に東日本に融通する障壁となっています。 一つの国の中に複数の周波数が明確に混在している国は、日本くらいでしょう。 しかし、この障壁を逆に考えると、西日本は電気に関しては震災の影響をほとんど受けず、節電を気にせずに﹁平常どおり﹂産業活動を行なうことが可能である地域であるとも考えることができます。 西日本の皆様には、こんな時だからこそ、﹁元気の無くなっている﹂東日本の分まで活発に︵派手にということではないですよ︶経済活動を行なって欲しいと考えています。 それが回りまわって、結局は被災地復興支援の大きな原動力になります。 ひとことで言うと、現段階では北海道を除く東日本では﹁節電﹂が復興支援、西日本では﹁電気を使うこと﹂が復興支援 ということでしょう。
追記 宗門行事の梅花流全国奉詠大会︵島根県開催︶も中止が検討されています。
これも、上記の理由で、また、被災された方々へのメッセージを込めた大会として開催するべきではないかと考え、神奈川県第二宗務所としての意見書を本庁に提出いたしました。
震災直後、大阪、道頓堀のグリコの看板が、節電に協力するために当分の間点灯を取りやめたというニュースがありました。 おそらく、今も消灯しているのではないでしょうか。 さらにいろいろと話を伺うと、関西のみならず、九州の方々にも、節電ムード、さまざまな行事の自粛ムードが広がっています。 しかし、日本全体が自粛ムードということは、あまり好ましく無いことだと考えます。
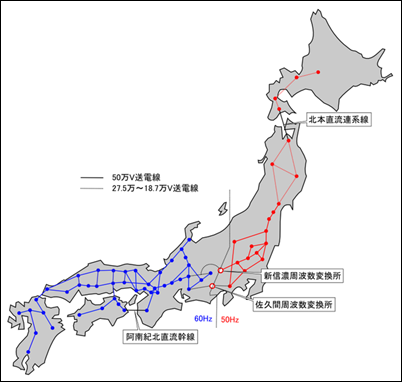 ︵図はウィキメディアより︶
︵図はウィキメディアより︶
今回の震災で、東日本エリアを賄う発電所が損壊してしまい、需要量を賄うだけの発電能力が失われてしまったため、本州東半分では計画節電の実施が長引きそうです。 国内での交流電源の周波数が、東日本と西日本での50ヘルツと60ヘルツと異なることは、西日本の電力を大々的に東日本に融通する障壁となっています。 一つの国の中に複数の周波数が明確に混在している国は、日本くらいでしょう。 しかし、この障壁を逆に考えると、西日本は電気に関しては震災の影響をほとんど受けず、節電を気にせずに﹁平常どおり﹂産業活動を行なうことが可能である地域であるとも考えることができます。 西日本の皆様には、こんな時だからこそ、﹁元気の無くなっている﹂東日本の分まで活発に︵派手にということではないですよ︶経済活動を行なって欲しいと考えています。 それが回りまわって、結局は被災地復興支援の大きな原動力になります。 ひとことで言うと、現段階では北海道を除く東日本では﹁節電﹂が復興支援、西日本では﹁電気を使うこと﹂が復興支援 ということでしょう。
2011年2月 4日
大相撲を統計的に検証
米学者が八百長証明!﹁7勝﹂対﹁8勝﹂千秋楽の勝率は? ケータイメールが動かぬ証拠となった大相撲の八百長問題。相撲協会の放駒理事長は﹁過去には一切なかったこと﹂と言うが、実は米名門大の経済学教授が過去の膨大な取組を分析し、八百長の存在を経済学的に証明している。その気になる中身は-。 大相撲の八百長を分析したのは、米シカゴ大のスティーヴン・D・レヴィット教授。ジャーナリストのスティーヴン・J・ダブナー氏との共著で2006年に出版、07年に増補改訂版が出た﹃ヤバい経済学﹄︵東洋経済新報社刊︶で、ヤクの売人や出会い系サイトなどを経済学的に解き明かし、ベストセラーとなった。その第1章で大相撲も取り上げている。 レヴィット教授は1989年1月から2000年1月までに開かれた本場所の上位力士281人による3万2000番の取組から、14日目まで7勝7敗と勝ち越しがかかる力士と、8勝6敗と勝ち越している力士の千秋楽での対戦をピックアップした。 過去の対戦成績では、7勝7敗の力士の8勝6敗の力士に対する勝率は48・7%と5割を少し下回る。ところが、これが千秋楽の対戦になると7勝7敗の力士の8勝6敗の力士に対する勝率は79・6%と大きくはね上がるというのだ。 これだけなら7勝7敗の力士のモチベーションが高い結果といえなくもないが、次の場所での取組︵どちらも7勝7敗でない場合︶では、前の場所で勝った7勝7敗の力士の勝率は約40%と大幅に落ち込む。この2人の力士が次の次の場所で対戦すると勝率は約50%に戻ると指摘する。 同書では﹁一番理屈に合う説明は、力士たちの間で取引が成立しているというものだ﹂とする。 興味深いことには、日本のマスコミで八百長報道が出たすぐ後に開かれた本場所千秋楽では、7勝7敗の力士の8勝6敗の力士に対する勝率はいつもの80%ではなく、約50%に下落。﹁データをどういじっても出てくる答えはいつも同じだ。相撲に八百長なんかないとはとても言い張れない﹂と結論づけた。 レヴィット氏は米紙ワシントン・ポストで相撲の八百長に関するコラムを読んだのをきっかけに分析を始め、英語の相撲雑誌﹁スモウ・ワールド﹂のバックナンバーを15~20年分取り寄せたという。放駒理事長は反論できるのだろうか。 ︵朝日新聞2011/2/4)話題の本がこちらです。 ﹃ヤバい経済学﹄ [増補改訂版] [単行本] スティーヴン・D・レヴィット/スティーヴン・J・ダブナー (著), 望月衛 (翻訳)
この﹃ヤバい経済学﹄︵内容は全然ヤバくないです︶では、﹁常識﹂だと考えられがちなことに﹁本当にそうなのか?﹂と疑問を持ち、先入観無しの視点から物事を検証しています。 例えば、酔っ払って歩くのと飲酒運転と、どっちが危険なのでしょうか。 一般常識では、飲酒運転のほうが重大な結果をもたらし、危険であると考えられています。 ですから飲酒運転には厳罰が設けられていますし、酔っ払って歩くことには特にペナルティーは科せられていません。 しかし、統計学的に検証すると、酔っ払って歩くことは、飲酒運転に比べて死ぬ可能性が8倍の危険性があるそうです。 まあ、その真偽は各項目検証していく必要があるとしても、とにかく﹁ものの見方﹂として、固定概念に捕らわれない視点を持つことが大切でしょう。 相撲界が今回の八百長問題にどのように取り組んでいくのか、注目されるところです。 徹底的に自浄できる組織にならなければいけないですね。 さて、こんな統計データもあります。 平成15年から八百長疑惑が表面化する平成21年夏までの期間、7勝7敗で千秋楽を迎えた大関の勝敗の記録です。
平成15年9月 秋場所 平成16年9月 秋場所 平成18年3月 春場所 平成18年5月 夏場所 平成18年7月 名古屋場所 平成19年1月 初場所 平成19年3月 春場所 平成19年3月 春場所 平成20年1月 初場所 平成20年3月 春場所 平成20年5月 夏場所 平成20年9月 秋場所 平成20年11月 九州場所 平成21年1月 初場所 平成21年5月 夏場所 平成21年5月 夏場所 平成21年7月 名古屋場所
2011年1月31日
お墓参りにマイリポイント
前に地域通過の特徴と、お寺にも適用するべきとしたブログ記事を書きました。
⇒元気をもたらす地域通貨(2) これに関連して、今はやりの﹁ポイント制﹂を墓参に導入している霊園も出ています。
お墓参りするごとに貯まるマイルならぬ“マイリ” ﹁マイリポイントカード﹂
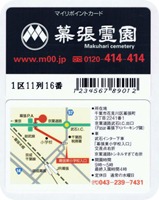 ポイントカードは馬鹿にならない。普段、何気なく通っている行きつけの店で、不意に﹁現在、ポイントが○○円分溜まっております﹂と教えられる、あの瞬間。その額の思いも寄らない溜まりっぷりが、実に嬉しいのだ。“ポイント額”も、ひとつの財産です。
話は変わって、“お墓参り”。ぶっちゃけ、自分でもキチンと通っているとは言い難い。なるべく顔を出して、ご挨拶するべきだとはわかっているのだが……。
そんな時、気になる情報を耳にした。千葉市にある﹁幕張霊園﹂では、非常に斬新なサービスを開始したそうなのだ。その名も﹁マイリポイントカード﹂。
﹁マイル﹂ではない。﹁マイリ﹂である。要するに、お墓“参り”をすることでポイントが加算されていくカードのこと。
システムは、こうだ。たとえば、お墓参りに訪れたとする。その際は、霊園の受付にカードを提示。すると、1回につき30マイリ︵30円︶のポイントが加算されていく。他にも、買い物をした場合。お供えのお花だったりを購入すると、価格の3%がマイリとして上積みされていく。そして、霊園で一番大きな買い物といえば“お墓”。このお墓が100万円するとしたら、3万マイリ︵3万円︶がカードに蓄えられるのだ。そうすると、しばらくはマイリでお花などが購入できるというワケ。マイリがなくなれば、現金で商品を購入することになるが、それはそれでマイリが溜まっていくことになる。
ハッキリ言って、お墓参りでこんなサービスは今までなかったと思う。どうして、このような試みを始めたのか? 直接、霊園に伺ってみた。
﹁普通の人がお墓に訪れる機会と言えば、春と秋のお彼岸と、お盆、そして命日。多くても、この年4回だと思うんです。しかし、幕張霊園は高速道路のパーキングエリアから歩いて行ける場所にあるので、通常の日でもお越しいただける立地なんですね﹂
ゴルフに行くついでにプレイに関する知恵をもらいに来たり、デイリーやウイクリーにお墓参りをしてもらいたい。そしてご提供するポイントを、またご先祖様に使ってほしい。そんな風に、同霊園は考えているのだ。
また、ポイントカードを始めたことで、もう一つのメリットが。
﹁お墓参りの際、マイリを加算するには受付に寄っていただくことになります。そこでお顔を見せていただくことで、皆さんとお話をさせていただけますよね。﹃今度、こういうイベントをやりますよ﹄なんて会話が弾めば、明るい霊園づくりにつながるんです﹂
また、大事なのはポイントカードにお墓の区画番号を記載していること。霊園にあまり来る機会がない方は、お墓の場所を忘れることだって珍しくない。
実際、﹁佐藤﹂さんが隣の﹁佐藤﹂さんのお墓に訪れていた、なんてケースもあったそうで……。そんなトラブルを防ぐための、お墓の名刺代わりの役割も果たす。
そんな﹁マイリポイントカード﹂のサービスは、今月︵※2010年4月︶の1日からスタートしたばかり。﹁幕張霊園﹂自体、開園したのは今年︵※2010年︶の4月28日で、できたてホヤホヤなのだ。
キレイで明るい霊園にある、斬新なポイントサービス。気軽に足を運んで、是非とも“マイリ”を貯め込んでいただきたい。
お墓参り=参り⇒マイリ・・・・・
ネーミングの妙もありますが、そのサービス内容には注目すべき事項も含まれています。
﹁マイリポイントカード﹂のサービスがどのように推移していくのかに注目していきたいと思います。
さて、この制度を、お寺に導入した場合はどのようなことが考えられるでしょうか。
お寺のお墓にお参りいただいく際に、必ずしも全檀家さんが本堂の本尊様に参拝し、玄関にご挨拶に来られるとは限りません。
記事中にあった﹁お墓参りの際、マイリを加算するには受付に寄っていただくことになります。そこでお顔を見せていただくことで、皆さんとお話をさせていただけますよね。﹃今度、こういうイベントをやりますよ﹄なんて会話が弾めば、明るい霊園づくりにつながるんです﹂という部分は大きいと思います。
墓参が楽しくなり、墓参の数が増えることによってお墓を綺麗に維持できるという効果も期待できるでしょう。
寺院で導入する場合には提案事項があります。
法定通貨ではなく、寺院共通の﹁地域通過﹂に還元する仕組みにするのです。
このことにより、さらに一歩進んだシステムとなります。
﹁幕張霊園﹂の事例では、1マイリ1円に換算というように、法定通貨に換算されていきます。
ここを法定通貨ではなく、地域通貨に還元させるようにするのです。
・お墓参りをして100テラマイル
・境内清掃に参加して1000テラマイル
・責任役員会に出席して500テラマイル
・・・・とか。
法定通貨よりも地域通過の方がよほど﹁お布施﹂の概念に適合するとさえ言ってもよいでしょう。
砕けた言い方をすれば、ご本尊さまからのプレゼントです。
ポイントカードは馬鹿にならない。普段、何気なく通っている行きつけの店で、不意に﹁現在、ポイントが○○円分溜まっております﹂と教えられる、あの瞬間。その額の思いも寄らない溜まりっぷりが、実に嬉しいのだ。“ポイント額”も、ひとつの財産です。
話は変わって、“お墓参り”。ぶっちゃけ、自分でもキチンと通っているとは言い難い。なるべく顔を出して、ご挨拶するべきだとはわかっているのだが……。
そんな時、気になる情報を耳にした。千葉市にある﹁幕張霊園﹂では、非常に斬新なサービスを開始したそうなのだ。その名も﹁マイリポイントカード﹂。
﹁マイル﹂ではない。﹁マイリ﹂である。要するに、お墓“参り”をすることでポイントが加算されていくカードのこと。
システムは、こうだ。たとえば、お墓参りに訪れたとする。その際は、霊園の受付にカードを提示。すると、1回につき30マイリ︵30円︶のポイントが加算されていく。他にも、買い物をした場合。お供えのお花だったりを購入すると、価格の3%がマイリとして上積みされていく。そして、霊園で一番大きな買い物といえば“お墓”。このお墓が100万円するとしたら、3万マイリ︵3万円︶がカードに蓄えられるのだ。そうすると、しばらくはマイリでお花などが購入できるというワケ。マイリがなくなれば、現金で商品を購入することになるが、それはそれでマイリが溜まっていくことになる。
ハッキリ言って、お墓参りでこんなサービスは今までなかったと思う。どうして、このような試みを始めたのか? 直接、霊園に伺ってみた。
﹁普通の人がお墓に訪れる機会と言えば、春と秋のお彼岸と、お盆、そして命日。多くても、この年4回だと思うんです。しかし、幕張霊園は高速道路のパーキングエリアから歩いて行ける場所にあるので、通常の日でもお越しいただける立地なんですね﹂
ゴルフに行くついでにプレイに関する知恵をもらいに来たり、デイリーやウイクリーにお墓参りをしてもらいたい。そしてご提供するポイントを、またご先祖様に使ってほしい。そんな風に、同霊園は考えているのだ。
また、ポイントカードを始めたことで、もう一つのメリットが。
﹁お墓参りの際、マイリを加算するには受付に寄っていただくことになります。そこでお顔を見せていただくことで、皆さんとお話をさせていただけますよね。﹃今度、こういうイベントをやりますよ﹄なんて会話が弾めば、明るい霊園づくりにつながるんです﹂
また、大事なのはポイントカードにお墓の区画番号を記載していること。霊園にあまり来る機会がない方は、お墓の場所を忘れることだって珍しくない。
実際、﹁佐藤﹂さんが隣の﹁佐藤﹂さんのお墓に訪れていた、なんてケースもあったそうで……。そんなトラブルを防ぐための、お墓の名刺代わりの役割も果たす。
そんな﹁マイリポイントカード﹂のサービスは、今月︵※2010年4月︶の1日からスタートしたばかり。﹁幕張霊園﹂自体、開園したのは今年︵※2010年︶の4月28日で、できたてホヤホヤなのだ。
キレイで明るい霊園にある、斬新なポイントサービス。気軽に足を運んで、是非とも“マイリ”を貯め込んでいただきたい。
お墓参り=参り⇒マイリ・・・・・
ネーミングの妙もありますが、そのサービス内容には注目すべき事項も含まれています。
﹁マイリポイントカード﹂のサービスがどのように推移していくのかに注目していきたいと思います。
さて、この制度を、お寺に導入した場合はどのようなことが考えられるでしょうか。
お寺のお墓にお参りいただいく際に、必ずしも全檀家さんが本堂の本尊様に参拝し、玄関にご挨拶に来られるとは限りません。
記事中にあった﹁お墓参りの際、マイリを加算するには受付に寄っていただくことになります。そこでお顔を見せていただくことで、皆さんとお話をさせていただけますよね。﹃今度、こういうイベントをやりますよ﹄なんて会話が弾めば、明るい霊園づくりにつながるんです﹂という部分は大きいと思います。
墓参が楽しくなり、墓参の数が増えることによってお墓を綺麗に維持できるという効果も期待できるでしょう。
寺院で導入する場合には提案事項があります。
法定通貨ではなく、寺院共通の﹁地域通過﹂に還元する仕組みにするのです。
このことにより、さらに一歩進んだシステムとなります。
﹁幕張霊園﹂の事例では、1マイリ1円に換算というように、法定通貨に換算されていきます。
ここを法定通貨ではなく、地域通貨に還元させるようにするのです。
・お墓参りをして100テラマイル
・境内清掃に参加して1000テラマイル
・責任役員会に出席して500テラマイル
・・・・とか。
法定通貨よりも地域通過の方がよほど﹁お布施﹂の概念に適合するとさえ言ってもよいでしょう。
砕けた言い方をすれば、ご本尊さまからのプレゼントです。
何よりも、地域通貨のシステムでは、通帳に記載されている﹁黒字﹂や﹁赤字﹂は、特定の人に対する債務とはなりません。 そして地域通貨の流通するコミュニティー全体へのコミットメントにもなります。 数年後には通貨の概念がガラッと変わっている、ということになるかもしれませんね。
⇒元気をもたらす地域通貨(2) これに関連して、今はやりの﹁ポイント制﹂を墓参に導入している霊園も出ています。
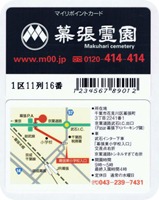 ポイントカードは馬鹿にならない。普段、何気なく通っている行きつけの店で、不意に﹁現在、ポイントが○○円分溜まっております﹂と教えられる、あの瞬間。その額の思いも寄らない溜まりっぷりが、実に嬉しいのだ。“ポイント額”も、ひとつの財産です。
話は変わって、“お墓参り”。ぶっちゃけ、自分でもキチンと通っているとは言い難い。なるべく顔を出して、ご挨拶するべきだとはわかっているのだが……。
そんな時、気になる情報を耳にした。千葉市にある﹁幕張霊園﹂では、非常に斬新なサービスを開始したそうなのだ。その名も﹁マイリポイントカード﹂。
﹁マイル﹂ではない。﹁マイリ﹂である。要するに、お墓“参り”をすることでポイントが加算されていくカードのこと。
システムは、こうだ。たとえば、お墓参りに訪れたとする。その際は、霊園の受付にカードを提示。すると、1回につき30マイリ︵30円︶のポイントが加算されていく。他にも、買い物をした場合。お供えのお花だったりを購入すると、価格の3%がマイリとして上積みされていく。そして、霊園で一番大きな買い物といえば“お墓”。このお墓が100万円するとしたら、3万マイリ︵3万円︶がカードに蓄えられるのだ。そうすると、しばらくはマイリでお花などが購入できるというワケ。マイリがなくなれば、現金で商品を購入することになるが、それはそれでマイリが溜まっていくことになる。
ハッキリ言って、お墓参りでこんなサービスは今までなかったと思う。どうして、このような試みを始めたのか? 直接、霊園に伺ってみた。
﹁普通の人がお墓に訪れる機会と言えば、春と秋のお彼岸と、お盆、そして命日。多くても、この年4回だと思うんです。しかし、幕張霊園は高速道路のパーキングエリアから歩いて行ける場所にあるので、通常の日でもお越しいただける立地なんですね﹂
ゴルフに行くついでにプレイに関する知恵をもらいに来たり、デイリーやウイクリーにお墓参りをしてもらいたい。そしてご提供するポイントを、またご先祖様に使ってほしい。そんな風に、同霊園は考えているのだ。
また、ポイントカードを始めたことで、もう一つのメリットが。
﹁お墓参りの際、マイリを加算するには受付に寄っていただくことになります。そこでお顔を見せていただくことで、皆さんとお話をさせていただけますよね。﹃今度、こういうイベントをやりますよ﹄なんて会話が弾めば、明るい霊園づくりにつながるんです﹂
また、大事なのはポイントカードにお墓の区画番号を記載していること。霊園にあまり来る機会がない方は、お墓の場所を忘れることだって珍しくない。
実際、﹁佐藤﹂さんが隣の﹁佐藤﹂さんのお墓に訪れていた、なんてケースもあったそうで……。そんなトラブルを防ぐための、お墓の名刺代わりの役割も果たす。
そんな﹁マイリポイントカード﹂のサービスは、今月︵※2010年4月︶の1日からスタートしたばかり。﹁幕張霊園﹂自体、開園したのは今年︵※2010年︶の4月28日で、できたてホヤホヤなのだ。
キレイで明るい霊園にある、斬新なポイントサービス。気軽に足を運んで、是非とも“マイリ”を貯め込んでいただきたい。
ポイントカードは馬鹿にならない。普段、何気なく通っている行きつけの店で、不意に﹁現在、ポイントが○○円分溜まっております﹂と教えられる、あの瞬間。その額の思いも寄らない溜まりっぷりが、実に嬉しいのだ。“ポイント額”も、ひとつの財産です。
話は変わって、“お墓参り”。ぶっちゃけ、自分でもキチンと通っているとは言い難い。なるべく顔を出して、ご挨拶するべきだとはわかっているのだが……。
そんな時、気になる情報を耳にした。千葉市にある﹁幕張霊園﹂では、非常に斬新なサービスを開始したそうなのだ。その名も﹁マイリポイントカード﹂。
﹁マイル﹂ではない。﹁マイリ﹂である。要するに、お墓“参り”をすることでポイントが加算されていくカードのこと。
システムは、こうだ。たとえば、お墓参りに訪れたとする。その際は、霊園の受付にカードを提示。すると、1回につき30マイリ︵30円︶のポイントが加算されていく。他にも、買い物をした場合。お供えのお花だったりを購入すると、価格の3%がマイリとして上積みされていく。そして、霊園で一番大きな買い物といえば“お墓”。このお墓が100万円するとしたら、3万マイリ︵3万円︶がカードに蓄えられるのだ。そうすると、しばらくはマイリでお花などが購入できるというワケ。マイリがなくなれば、現金で商品を購入することになるが、それはそれでマイリが溜まっていくことになる。
ハッキリ言って、お墓参りでこんなサービスは今までなかったと思う。どうして、このような試みを始めたのか? 直接、霊園に伺ってみた。
﹁普通の人がお墓に訪れる機会と言えば、春と秋のお彼岸と、お盆、そして命日。多くても、この年4回だと思うんです。しかし、幕張霊園は高速道路のパーキングエリアから歩いて行ける場所にあるので、通常の日でもお越しいただける立地なんですね﹂
ゴルフに行くついでにプレイに関する知恵をもらいに来たり、デイリーやウイクリーにお墓参りをしてもらいたい。そしてご提供するポイントを、またご先祖様に使ってほしい。そんな風に、同霊園は考えているのだ。
また、ポイントカードを始めたことで、もう一つのメリットが。
﹁お墓参りの際、マイリを加算するには受付に寄っていただくことになります。そこでお顔を見せていただくことで、皆さんとお話をさせていただけますよね。﹃今度、こういうイベントをやりますよ﹄なんて会話が弾めば、明るい霊園づくりにつながるんです﹂
また、大事なのはポイントカードにお墓の区画番号を記載していること。霊園にあまり来る機会がない方は、お墓の場所を忘れることだって珍しくない。
実際、﹁佐藤﹂さんが隣の﹁佐藤﹂さんのお墓に訪れていた、なんてケースもあったそうで……。そんなトラブルを防ぐための、お墓の名刺代わりの役割も果たす。
そんな﹁マイリポイントカード﹂のサービスは、今月︵※2010年4月︶の1日からスタートしたばかり。﹁幕張霊園﹂自体、開園したのは今年︵※2010年︶の4月28日で、できたてホヤホヤなのだ。
キレイで明るい霊園にある、斬新なポイントサービス。気軽に足を運んで、是非とも“マイリ”を貯め込んでいただきたい。
何よりも、地域通貨のシステムでは、通帳に記載されている﹁黒字﹂や﹁赤字﹂は、特定の人に対する債務とはなりません。 そして地域通貨の流通するコミュニティー全体へのコミットメントにもなります。 数年後には通貨の概念がガラッと変わっている、ということになるかもしれませんね。
2010年12月22日
タダほど高いものは無い
携帯ゲームGREE﹁無料﹂CM取りやめ 消費者団体﹁アイテム有料で法抵触﹂申し入れで 一律に﹁無料﹂の音声が流れていた携帯電話向けゲームサイト﹁GREE︵グリー︶﹂のテレビCMについて、運営会社の﹁グリー﹂︵東京都︶が一部のCMで、﹁無料﹂音声を取りやめていたことが20日、分かった。GREEのCMをめぐっては﹁無料で利用できる範囲は限定されており、景品表示法に抵触する﹂として消費者団体﹁消費者支援機構関西﹂︵大阪市︶が10月、﹁無料﹂音声の停止を申し入れていた。 CM総合研究所によると、10月までの1年間でGREEのCM回数︵関東地域︶は、全業種中最多の約2万4600回。一方、ライバルサイトの﹁モバゲータウン﹂も3位︵約1万回︶につけ、業界内のCM合戦が過熱している。 グリーによると、全国的にテレビCMを変更したのは今月に入ってから。プレー開始時には利用料がかからないが、進めていくうちに有料の道具︵アイテム︶などが登場するゲームについて順次、﹁無料です﹂という音声をなくしている。それ以外のゲームのCMでは、これまで通り﹁無料﹂音声を流している。 従来のCMでも﹁一部コンテンツは有料﹂という表示をしていることなどから、グリーは﹁違法性があったとは考えていない﹂︵広報担当者︶としながら、消費者に、より適切な理解を促す必要があると判断した。今回の変更については﹁社内検証の結果﹂で、消費者団体の指摘とは﹁関係ない﹂としている。 急成長する携帯向けゲーム市場をめぐっては、GREEとモバゲーがシェアをほぼ二分する一方で、モバゲー運営会社の﹁ディー・エヌ・エー︵DeNA︶﹂が今月8日、ゲームソフト開発業者の﹁囲い込み﹂をした独占禁止法違反の疑いで、公正取引委員会の立ち入り検査を受けるなど、熾烈︵しれつ︶なシェア争いの弊害が問題視されている。 ︵産経新聞 2010.12.21︶
ようやく・・・といった感がありますが、テレビのCMで耳にタコができるくらい繰り返し流されていたGREEの﹁無料です﹂という音声案内がついに景品表示法に抵触するということで、中止になるようです。 モバゲーのCMでも同じような流れになるでしょう。 ただ単に﹁無料です﹂を中止するだけでなく、﹁初めは無料ですが、ゲームを進めるためには有料となります﹂と案内することを義務付けるべきだと感じます。
それにしても、GREE、モバゲーの勢いたるや凄まじいものがあります。 2010年7月末の会員数は、 ■GREE 2,125万人 ■mixi 2,102万人 ■モバゲー 2,048万人 それぞれ2千万人を超え、GREEが一歩抜きん出て国内最大のSNSとなっています。 ページビューの数を見ると、同じ2010年7月末時点で ■GREE パソコン経由4億PV、携帯経由 354憶PV ■mixi パソコン経由52億PV、携帯経由 245憶PV ■モバゲー パソコン経由 0PV 、携帯経由 740億PV 圧倒的に携帯端末経由での利用が多いですね。 パソコン経由が多いmixiでも、携帯経由のほうが圧倒的に上回っています。
さらにその利益構造をみると驚愕の事実がわかります。 2010年4-6月期 ■GREE 売上高 109憶︵広告売上18%、課金売上82%)、営業利益53憶、利益率 48.4% ■mixi 売上高40憶︵広告売上85%、課金売上15%)、営業利益11憶、利益率 26.8% ■モバゲー 売上高 242憶︵広告売上9%、課金売上91%)、営業利益 120憶、利益率 49.6%
GREE、モバゲー共に売上高の多さもさることながら、その高利益率に着目です。 世の中に様々な業種あれど、これだけ効率的に稼ぐことのできる業種はそうそう無いですよ。 さらに売上高の内訳を見ていくとGREE、モバゲー共に課金売上げがほとんどです。
実際に利用者がどのようなSNSソーシャルゲームをどのように利用しているかという利用実態調査結果をグラフにしてみました。 SNSソーシャルゲーム利用実態調査︵1︶ 調査概要 ・調査手法‥ モバイルリサーチ ・調査地域‥ 全国・調査対象‥13~59歳の男女︵モッピーモニター︶ ‥SNSのソーシャルゲームを利用している人・調査期間‥ 2010/8/24 ・有効回答数‥ 1,063サンプル︵年代内訳‥10代 19.8%、20代 20.3%、30代 20.0%、40代 20.0%、50代 19.9%︶ソーシャルゲーム利用者のうち、課金をしないでゲームをしている割合は多いのですが、少額の課金をして利用している割合も意外に多いことがわかります。また、5千円以上お金をかけている割合も少なからずありますね。 塵も積もれば山となる。会員数を乗じてみると数十億もの莫大な課金金額となるわけです。
SNSソーシャルゲーム利用者も、業界のビジネスモデル ■一般広告収入︵広告代理店を通じて販売される広告枠︶ ■成果報酬型広告収入︵アフィリエイト︶ ■有料会員料金︵GREEプラス、GREEプレミアムなど︶ ■コンテンツ売上︵アバターの着せ替えアイテム、ゲームの技、アイテム販売など︶ それぞれがどのような仕組みになっているかをよく学んでから利用するべきであると思いますし、その判断がまだ出来ない子ども相手に﹁無料釣りゲームで利用者を釣り上げる﹂ような状況も好ましくないでしょう。
さらに、SNSソーシャルゲームにはユーザー間の直接コンタクト︵出会い系など︶の問題もあり、近年急速な伸びを示しているソーシャルゲーム市場の動向には注意していかなければならないと思います。
2010年12月18日
オーランチオキトリウムが日本を救う
一昨年 ホンダワラが日本を救う という記事を書きましたが、それに勝るとも劣らない画期的な発見がありました。
生産能力10倍 「石油」つくる藻類、日本で有望株発見
藻類に﹁石油﹂を作らせる研究で、筑波大のチームが従来より10倍以上も油の生産能力が高いタイプを沖縄の海で発見した。チームは工業利用に向けて特許を申請している。将来は燃料油としての利用が期待され、資源小国の日本にとって朗報となりそうだ。茨城県で開かれた国際会議で14日に発表した。
筑波大の渡邉信教授、彼谷邦光特任教授らの研究チーム。海水や泥の中などにすむ﹁オーランチオキトリウム﹂という単細胞の藻類に注目し、東京湾やベトナムの海などで計150株を採った。これらの性質を調べたところ、沖縄の海で採れた株が極めて高い油の生産能力を持つことが分かった。 球形で直径は5~15マイクロメートル︵マイクロは100万分の1︶。水中の有機物をもとに、化石燃料の重油に相当する炭化水素を作り、細胞内にため込む性質がある。同じ温度条件で培養すると、これまで有望だとされていた藻類のボトリオコッカスに比べて、10~12倍の量の炭化水素を作ることが分かった。 研究チームの試算では、深さ1メートルのプールで培養すれば面積1ヘクタールあたり年間約1万トン作り出せる。﹁国内の耕作放棄地などを利用して生産施設を約2万ヘクタールにすれば、日本の石油輸入量に匹敵する生産量になる﹂としている。 炭化水素をつくる藻類は複数の種類が知られているが生産効率の低さが課題だった。 渡邉教授は﹁大規模なプラントで大量培養すれば、自動車の燃料用に1リットル50円以下で供給できるようになるだろう﹂と話している。 また、この藻類は水中の有機物を吸収して増殖するため、生活排水などを浄化しながら油を生産するプラントをつくる一石二鳥の構想もある。︵朝日新聞 2010年12月15日︶これまでの10倍の効率で重油に近い炭化水素が生産されるということで、コストの面が一気に解決されそうです。 実用化に要する時間も現実的です。 ただし、ホンダワラは光合成によるカーボンニュートラルとなるのに対し、オーランチオキトリウムは光合成では無いのでCO2排出量は石油と変わらないということになります。 日本海はホンダワラ、暖かい沖縄や九州近海ではオーランチオキトリウムという使い分けもできますね。 また、品種改良によって更なる効率化や水温の低い場所への対応などが期待できます。 こういう技術こそ、躊躇することなく国家主導でどんどん進めていくことが必要でしょう。 他の国に先行されないよう適切な施策をとることが出来れば日本の未来は明るいと思います。 問題は今の政権でそのような判断が出来るだろうか、ということですね。 さらに突っ込んだ提言をするならば、国の愚策により水質が悪化している九州・諫早湾の潮受堤防調整池を大規模なプラントとして活用するのはいかがでしょうか。 つい最近、国の上告断念によって潮受堤防開門への道筋が出来ています。しかし、干拓農家にとっては調整池に海水が流入することを手放しに喜んでばかりは居られません。 諫早の愚作は漁民も農家も振り回す結果となってしまいました。 そこでオーランチオキトリウム養殖池として利用することを提案します。 改めてプラントを建設する手間は省けますし、水中の有機物も﹁豊富﹂です。塩分濃度調整もそれこそ自由にできます。
これは一つの提案ですが、﹁創エネルギー﹂+﹁省エネルギー﹂によって日本がエネルギー大国になることも決して夢物語では無いのです。
2010年9月 7日
エコカー補助金狂想曲
 テレビCMで﹁減税、補助金も・・・・﹂というキャッチフレーズが盛んに流されていますが、今日の記事はこれからきっと大問題になろうかと懸念されることです。
︵これからフェアやっている場合じゃないですよ>ダイハツさん︶
エコカー補助金は予算総額が決まっていたため、8月の段階では少なくとも9月中旬位までは大丈夫だろうと誰もが考えていたはずです。
テレビCMで﹁減税、補助金も・・・・﹂というキャッチフレーズが盛んに流されていますが、今日の記事はこれからきっと大問題になろうかと懸念されることです。
︵これからフェアやっている場合じゃないですよ>ダイハツさん︶
エコカー補助金は予算総額が決まっていたため、8月の段階では少なくとも9月中旬位までは大丈夫だろうと誰もが考えていたはずです。
 ↑8月26日発表の申請状況。
残額593億円に対し、1日あたり35億円と考えても約17日分の予算がありました。
しかし、エコカー補助金のエコノミー﹁経済﹂効果は予想以上となり、駆け込み需要の増加で補助金を支給する次世代自動車振興センター処理能力をオーバーし、一昨日になって申請を受理していながら受理金額に反映できていなかったデータが大量に発覚するという事態に陥っています。
↑8月26日発表の申請状況。
残額593億円に対し、1日あたり35億円と考えても約17日分の予算がありました。
しかし、エコカー補助金のエコノミー﹁経済﹂効果は予想以上となり、駆け込み需要の増加で補助金を支給する次世代自動車振興センター処理能力をオーバーし、一昨日になって申請を受理していながら受理金額に反映できていなかったデータが大量に発覚するという事態に陥っています。
 ↑は一昨日の次世代自動車振興センターのデータです。
修正分130億円が、この日初めて発覚した未処理分。なんというずさんな処理でしょう。
一気に130億円の予算消化となりました。
このため、本日︵9月7日︶発表された申請状況は
↑は一昨日の次世代自動車振興センターのデータです。
修正分130億円が、この日初めて発覚した未処理分。なんというずさんな処理でしょう。
一気に130億円の予算消化となりました。
このため、本日︵9月7日︶発表された申請状況は
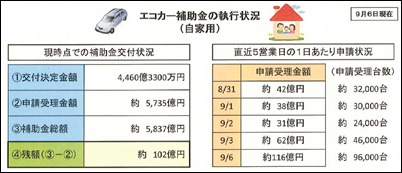 このようになり、予算残額は僅か102億円。
︵あれ?前日の修正130億円は何処へいっちゃったの?︶
ルールとして予算残高を上回る申請があった場合、その日の申請分は一律に補助金が支給されない仕組みとなっておりますので、9月7日に102億円以上の申請があった場合は、7日受付け分は支給対象外となり、6日申請分を最後に補助が打ち切られることになります。
このようになり、予算残額は僅か102億円。
︵あれ?前日の修正130億円は何処へいっちゃったの?︶
ルールとして予算残高を上回る申請があった場合、その日の申請分は一律に補助金が支給されない仕組みとなっておりますので、9月7日に102億円以上の申請があった場合は、7日受付け分は支給対象外となり、6日申請分を最後に補助が打ち切られることになります。
これってかなり問題になると思います。 車の契約から登録、エコカー補助金申請までにはどんなに早くても7日以上掛かります。 つまり、8月末から9月初旬にかけてエコカー補助金対象車期待してを購入した人にとっては思いがけず補助金を得る機会を失ってしまうこととなり、それを知ってからでは後の祭りとなるからです。 一日あたり5万~10万台の申請ペースがあることから、百万人単位でエコカー補助金難民が発生するはずです。 とにかく、明日にはエコカー補助金終了が発表されることでしょう。 ディーラーの営業マンが可愛そうです。 どうなることやら。
2010年7月24日
地デジ完全移行まで365日
地上デジタル放送‥移行へ﹁最終年総合対策﹂公表...総務省 地上デジタル放送への完全移行︵11年7月24日︶まで残り約1年になったことを受け、総務省は23日、﹁地デジ最終年総合対策﹂を公表した。デジタル放送が届かない山間地などにケーブルテレビの幹線を整備したり、自治体が新たに経済弱者の地デジ対応策に乗り出す場合には特別交付税を措置するなど公的支援を拡充する。予算額は未定。 経済的に地デジ対応が困難な世帯や、ビル陰や山間地などの難視聴世帯などで対応が遅れていることから、これらの層に重点的に対策を講じる。高層マンションなどの陰で電波環境が悪い周辺住民とマンション住民の補償に関する話し合いが進まない問題に対しては、うまく解決した事例を﹁虎の巻︵仮称︶﹂として8月にも公表し、参考にしてもらう。 高齢者世帯対策としては、ボランティアや郵便配達員による声掛けや、﹁地デジ対策﹂と称して金をだまし取る悪質商法の相談事例を公表したりする。 総務省のコールセンターは現在の75回線から地デジ移行時までに1000回線に増強する。ただ、地デジ移行が遅れれば相談件数は1日最大60万件に上ると予想されるため、移行促進を急ぐ。 ︵毎日新聞2010/7/24)地上デジタル放送への移行の日まであと365日、つまり来年のこの日が地上デジタルへの完全移行の日とされています。 では、現行のアナログ放送は来年の7月24日まで視聴できるのか、というと、そうでもないようです。アナログ放送は2011年6月から画面は上のような﹁お知らせ画面﹂の固定表示となり、音声のみの放送になってしまいます。 そして7月24日に砂嵐へ。 ︵このことはあまり知られていないようですが、7月24日以前に約1ヶ月間の空白期間が生じるということです︶ デジタル放送受信機器普及の遅れや、都市部のビル陰問題、山村部への対策など期限までに地デジに100%対応できていない状況が考えられ、さらにこのようなアナログ放送前倒し打切りを行なうと、少なからず混乱が起こりそうです。 さらにもう一つ考えられる問題は東京タワーから東京スカイツリーへの移行問題です。 地上デジタルへの完全移行の日には、まだ東京スカイツリーは完成しておらず、竣工予定は2011年12月、それから試験放送を行なって、実際に放送が開始されるのは2012年春以降となります。 それと同時に東京タワーの地上デジタル放送が終了し、東京スカイツリーに移行されるわけですので、東京タワーを基準に合せているUHFアンテナの方向調整が必要になります。 東京スカイツリーからの送信開始︵=東京タワーからの送信終了︶に伴い、それほど大きなUHFアンテナを使わなくても映るようになったり、東京タワーではエリア外の地域でも受信できるようになる場合もあるでしょう。 逆に、急に映りが悪くなったという苦情も殺到するはずです。 特に都心部の場合にはビル反射波などの影響も考慮しなければならないので、単純にタワーの方向に向ければ良いというわけにはいかず、放送が始まってみないと調整ができない。そこが難しいところです。 つまり ︵1) 地上アナログから地上デジタルへの移行の時期︵2011年6月~7月24日︶ ︵2) 東京タワーから東京スカイツリーへの移行の時期︵2012年春~夏︶ この2つの時点それぞれで少なからず混乱が予想されます。 混乱を最小限に留めるという意味で、少なくとも 地上アナログ放送を東京スカイツリーが営業開始するまでの2012年春まで延長させるべき ではないかと思います。
■関連ブログ記事 地デジカ騒動
2010年7月19日
資源大国 日本
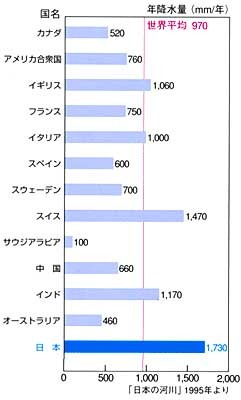 今年の梅雨の時期には全国各地で記録的な豪雨があり大きな被害がもたらされました。
特に岐阜県八百津町では大規模な土砂崩れにより激甚災害に相当する規模となっています。
被災者の皆様方には心よりお見舞い申し上げます。
時には災害を引き起こす豪雨ですが、各国の年間降雨量︵右図︶を見ても改めて日本は降雨の多い国であることを感じます。
世界を見渡してみても、降雨量がこれだけ多い国はまれであり、しかも︵コンクリートダムへの批判はあるものの︶全国各地に設置されているダムにより淡水の貯留、制御がきちんとなされている国はほとんどありません。
新鮮で綺麗な淡水を気兼ねなく使えるという﹁あたりまえ﹂の事は、世界の中では﹁あたりまえではない﹂ことなのです。
蛇口を捻ればそのまま安全に飲める水が流れてくる国は他にどれだけあるでしょうか。
さらに、お風呂の水、トイレの水、庭に撒く水、洗濯の水、車を洗う水・・・・・飲用できる水を私たち日本人は何のためらいも無く使っています。
資源が無いと言われる日本ですが、﹁淡水﹂という貴重な資源を豊富に有しているということを忘れてはなりません。
いや、日本は実は資源大国であるといっても過言ではないでしょう。
この、水を資源として輸出しようという試みがようやく具体化してきました。
今年の梅雨の時期には全国各地で記録的な豪雨があり大きな被害がもたらされました。
特に岐阜県八百津町では大規模な土砂崩れにより激甚災害に相当する規模となっています。
被災者の皆様方には心よりお見舞い申し上げます。
時には災害を引き起こす豪雨ですが、各国の年間降雨量︵右図︶を見ても改めて日本は降雨の多い国であることを感じます。
世界を見渡してみても、降雨量がこれだけ多い国はまれであり、しかも︵コンクリートダムへの批判はあるものの︶全国各地に設置されているダムにより淡水の貯留、制御がきちんとなされている国はほとんどありません。
新鮮で綺麗な淡水を気兼ねなく使えるという﹁あたりまえ﹂の事は、世界の中では﹁あたりまえではない﹂ことなのです。
蛇口を捻ればそのまま安全に飲める水が流れてくる国は他にどれだけあるでしょうか。
さらに、お風呂の水、トイレの水、庭に撒く水、洗濯の水、車を洗う水・・・・・飲用できる水を私たち日本人は何のためらいも無く使っています。
資源が無いと言われる日本ですが、﹁淡水﹂という貴重な資源を豊富に有しているということを忘れてはなりません。
いや、日本は実は資源大国であるといっても過言ではないでしょう。
この、水を資源として輸出しようという試みがようやく具体化してきました。
2010年7月 5日
自宅葬が増えている
近隣寺院で会合があった際に、雑談の中でここ1,2年で﹁自宅葬﹂の割合が急速に増えた、という話題が出ました。
これまでは自宅で葬儀をあげる方は年々減少傾向にあると思われがちでした。
図・葬儀施行場所の割合︵%︶左H8年、右H13年
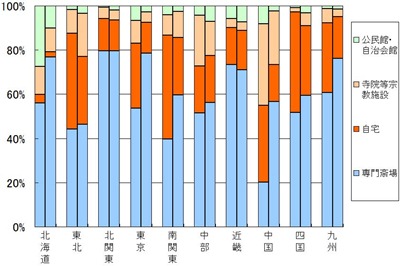 ︵︵社︶全日本冠婚葬祭互助協会調査・平成8年度調査の回答=2,169件、平成13年度調査の回答=4,536件︶
上の調査結果では平成8年から13年の間に、自宅で葬儀を行う割合が急速に減って、斎場での葬儀が増えていることがわかります。特に東京、南関東、中国、九州地方で顕著です。
統計上はまだ自宅葬が減少傾向にあるということしか見えてきません。
専門斎場が増加した理由を考えると、次のようなことが考えられます。
︵︵社︶全日本冠婚葬祭互助協会調査・平成8年度調査の回答=2,169件、平成13年度調査の回答=4,536件︶
上の調査結果では平成8年から13年の間に、自宅で葬儀を行う割合が急速に減って、斎場での葬儀が増えていることがわかります。特に東京、南関東、中国、九州地方で顕著です。
統計上はまだ自宅葬が減少傾向にあるということしか見えてきません。
専門斎場が増加した理由を考えると、次のようなことが考えられます。
︵1︶ 参列者に対応するためのスペースや、接客対応の人手、食事の用意、祭壇などを手配する手間が不要となる。 ︵2︶地域コミュニティーの機能喪失、近所付き合いの減少、核家族化、少子高齢化などの社会的変化。 ︵3︶葬儀社にとっては、自宅葬よりも自前の斎場のほうが利益が多いため、斎場を勧める傾向にある。 など。
では、最近﹁自宅葬﹂が増えているということはどういうことなのでしょうか。 地域コミュニティーの機能喪失、近所付き合いの減少、核家族化、少子高齢化などの社会的変化により、葬儀の規模自体が縮小傾向にあることは間違いありません。 もちろん、従来の通り多くの生前関係された皆様に見送っていただくという葬儀形式もありますが、一般に案内はせずに、家族やごく親しい身内のみだけで行なうという葬儀も増えています。一般焼香にいらっしゃる方が殆ど居ない葬儀です。 葬儀規模多様化の傾向はこれからも進んでいくでしょう。 家族葬を希望する場合には、葬儀社の専門斎場で行なうという理由が無くなってきます。 つまり、上で挙げた︵1︶の理由が無くなるということです。
家族葬であれば、自宅の一室で行なうことで充分なのです。 例えば、自宅︵あるいはマンションなど︶の一室で、ほぼ枕飾りに準じた簡単な祭壇を設けた中で行なう葬儀です。 規模は小さいのですが、きちんと菩提寺の僧侶が出向いて枕経、通夜、葬儀、出棺、火葬場でのご供養、初七日の法要・・・と、葬儀の規模の大小に関らず何ら変わらずに執り行います。 ところが、葬儀社の立場からすれば、基本的にはこのような自宅葬はあまり行いたくないというのが本音でしょう。 理由は︵3︶で挙げたとおり、自前の斎場で行なう葬儀のほうが葬儀業者としては利益を挙げることができるからです。 葬祭業者の葬儀費用一式への﹁葬儀費用明示化の流れ﹂は、ブラックボックス化された葬儀費用一式を明瞭にしていく試みの一つといえます。 今後、家族葬が増えていく中で、さらに自宅葬が増えていくことになれば、葬祭業者としては死活問題でしょう。実は、寺院の危機というよりは、葬祭業者の危機のほうが深刻なのだと考えています。 数年後に葬儀施行場所の調査結果が出れば、専門斎場から自宅葬への回帰の状況が結果として表れてくるはずですので、もう少し状況の推移に着目していきたいと思います。
■関連ブログ記事
葬儀費用明示化の流れ
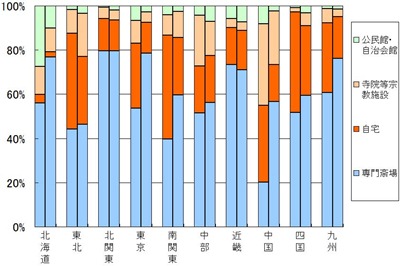 ︵︵社︶全日本冠婚葬祭互助協会調査・平成8年度調査の回答=2,169件、平成13年度調査の回答=4,536件︶
上の調査結果では平成8年から13年の間に、自宅で葬儀を行う割合が急速に減って、斎場での葬儀が増えていることがわかります。特に東京、南関東、中国、九州地方で顕著です。
統計上はまだ自宅葬が減少傾向にあるということしか見えてきません。
専門斎場が増加した理由を考えると、次のようなことが考えられます。
︵︵社︶全日本冠婚葬祭互助協会調査・平成8年度調査の回答=2,169件、平成13年度調査の回答=4,536件︶
上の調査結果では平成8年から13年の間に、自宅で葬儀を行う割合が急速に減って、斎場での葬儀が増えていることがわかります。特に東京、南関東、中国、九州地方で顕著です。
統計上はまだ自宅葬が減少傾向にあるということしか見えてきません。
専門斎場が増加した理由を考えると、次のようなことが考えられます。
︵1︶ 参列者に対応するためのスペースや、接客対応の人手、食事の用意、祭壇などを手配する手間が不要となる。 ︵2︶地域コミュニティーの機能喪失、近所付き合いの減少、核家族化、少子高齢化などの社会的変化。 ︵3︶葬儀社にとっては、自宅葬よりも自前の斎場のほうが利益が多いため、斎場を勧める傾向にある。 など。
では、最近﹁自宅葬﹂が増えているということはどういうことなのでしょうか。 地域コミュニティーの機能喪失、近所付き合いの減少、核家族化、少子高齢化などの社会的変化により、葬儀の規模自体が縮小傾向にあることは間違いありません。 もちろん、従来の通り多くの生前関係された皆様に見送っていただくという葬儀形式もありますが、一般に案内はせずに、家族やごく親しい身内のみだけで行なうという葬儀も増えています。一般焼香にいらっしゃる方が殆ど居ない葬儀です。 葬儀規模多様化の傾向はこれからも進んでいくでしょう。 家族葬を希望する場合には、葬儀社の専門斎場で行なうという理由が無くなってきます。 つまり、上で挙げた︵1︶の理由が無くなるということです。
家族葬であれば、自宅の一室で行なうことで充分なのです。 例えば、自宅︵あるいはマンションなど︶の一室で、ほぼ枕飾りに準じた簡単な祭壇を設けた中で行なう葬儀です。 規模は小さいのですが、きちんと菩提寺の僧侶が出向いて枕経、通夜、葬儀、出棺、火葬場でのご供養、初七日の法要・・・と、葬儀の規模の大小に関らず何ら変わらずに執り行います。 ところが、葬儀社の立場からすれば、基本的にはこのような自宅葬はあまり行いたくないというのが本音でしょう。 理由は︵3︶で挙げたとおり、自前の斎場で行なう葬儀のほうが葬儀業者としては利益を挙げることができるからです。 葬祭業者の葬儀費用一式への﹁葬儀費用明示化の流れ﹂は、ブラックボックス化された葬儀費用一式を明瞭にしていく試みの一つといえます。 今後、家族葬が増えていく中で、さらに自宅葬が増えていくことになれば、葬祭業者としては死活問題でしょう。実は、寺院の危機というよりは、葬祭業者の危機のほうが深刻なのだと考えています。 数年後に葬儀施行場所の調査結果が出れば、専門斎場から自宅葬への回帰の状況が結果として表れてくるはずですので、もう少し状況の推移に着目していきたいと思います。
2010年6月 4日
富山の路面電車
ご縁のあった老師様の本葬儀準備のため前日より富山に来ております。
現在、日本では約20ヶ所で路面電車が存在していますが、ここ富山でも元気に活躍しています。

富山地方鉄道富山市内軌道線では、昨年末より超低床式のCENTRAM︵セントラム︶が運行開始となりました。 平成26年には、北陸新幹線改行にあわせ、富山ライトレールと地鉄市内軌道線のレールが接続され、駅を挟んだ南北の直通運転がされるそうです。 路面電車のために道路上に張り巡らされる架線も﹁目立たなく﹂なるように工夫されており、景観も損なっていません。 このような交通システムが各都市で拡充されると良いと思います。
例えば、横浜市の環状二号線にニュートラムを運行しては如何でしょうか。
磯子?上永谷?東戸塚?西谷?新横浜?鶴見

富山地方鉄道富山市内軌道線では、昨年末より超低床式のCENTRAM︵セントラム︶が運行開始となりました。 平成26年には、北陸新幹線改行にあわせ、富山ライトレールと地鉄市内軌道線のレールが接続され、駅を挟んだ南北の直通運転がされるそうです。 路面電車のために道路上に張り巡らされる架線も﹁目立たなく﹂なるように工夫されており、景観も損なっていません。 このような交通システムが各都市で拡充されると良いと思います。
2010年1月25日
葬儀費用明示化の流れ
イオン﹁葬儀ビジネス﹂に参入 ﹁ブラックボックス﹂業界大変化 豪華な祭壇、たくさんの生花、おいしい料理と追加していくと、知らず知らずのうちに葬儀が高額になり、後日送られてきた請求書を見て青ざめるというのはよくある話だ。それもこれも料金が不透明なためで、なかでも祭壇は﹁ブラックボックス﹂と言われている。ようやく最近、わかりやすい料金体系を売りにしたベンチャー企業もいくつか出現。さらに大手小売のイオンも葬儀ビジネスに参入し、葬儀業界が大きく変わりそうだ。 (J-CASTニュース︶
大手スーパー﹁イオン﹂の葬儀に対する取り組みが注目されているようです。 これまで、この手の葬儀費用明示化はいろいろと為されてきつつありますが、大手スーパーがこの業界に参入したということは着目すべきことだと思います。 ﹁3年後には年間葬儀件数の10%を手がけたい﹂という意気込みもまんざら大げさではなさそうです。 今後はこのような流れとともに、葬儀業者、寺院、僧侶のグループ化が加速していくものと思われます。
その背景には冒頭のニュースに書かれているようなことがあることは確かでしょう。 まず、一般的に葬儀にどれほどの金額が掛かるかという統計をみると、
葬儀一式費用+別途立替費用︵145.3万円︶ + 通夜からの飲食接待費︵40.1万円︶ ↓ 平均総費用︵182.4万円︶ ※葬儀費用の全国平均 出典‥2007年 財団法人 日本消費者協会 第8回﹁葬儀についてのアンケート調査﹂報告書 ※宗教費用︵お経料、戒名、お布施等︶は除く となります。 これに対し、イオンの葬儀の場合の試算は、
葬儀費用︵29.8万円 39.8万円 59.8万円 79.8万円 108万円 148万円︶より選択 + おもてなし費用︵参列者100名、遺族親戚20名の場合︶25.0万円 + 別途費用︵15.9万円︶ ↓ お葬式にかかる総費用 100.7万円︵葬儀費用59.8万円の場合︶
となり、全国平均費用に比べて安く、透明化された費用にて葬儀ができることをアピールしています。
葬儀費用には、これにプラス、宗教費用︵この表現はあまり好きではありませんが︶があり、例えば仏式の場合は寺院へのお布施がこれにあたります。 なお、寺院へのお布施は僧侶への謝礼ではないこと、あくまでも﹁宗教法人﹂たる﹁寺院﹂の会計に入るものであり、寺院護持に欠かせないものであるということ を予めご理解ください。
さて、既に菩提寺をお持ちの場合は別として、イオンの葬儀の中には菩提寺を持たない方にはお坊さんの紹介 というシステムまであり、﹁お布施は本来﹁喜捨﹂であり﹁標準﹂や﹁統一﹂すべきものではありませんが、お客さまにご安心いただけるように目安を表示しました﹂という前置きはあるにせよ目安価格が提示されています。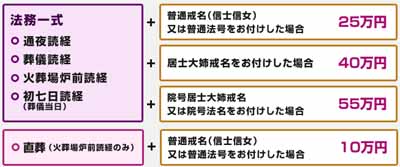
ですから、標準的なプランで標準的な参列者︵参列100名、遺族親族20名の規模︶、普通戒名の葬儀の場合にはお葬式に掛かる総費用は 100.7万円+25万円=125.7万円ということになります。
確かに施主にとってみれば料金がある程度明示化されることは嬉しいことだと思います。 けれども布施はあくまでも布施です。 ここに挙げられている数字は参考程度に位置づけると良いと思います。 懸念すべきは、戒名によるお布施の料金目安が提示されたことによる寺院側とのトラブルです。 地域・宗派にもよりますし、別の基準を目安としている寺院もあります。 例えばイオンのこのプランで葬儀が執行された場合、既存の菩提寺へ目安金額でのお布施を持っていった時に寺院側で﹁この金額では葬儀をお受けできない﹂とされた場合はどうなるのでしょうか。 心配です。 良く聞くのですよ、この手のトラブル。
この寺院費用の基準を見て﹁やたら安いな?﹂と感じるご寺院様がいらっしゃったら、きっと要注意です。 全国的に、スーパーでこのような金額が明記されたパンフレットが配布され、インターネットでも情報が出されていることを念頭においておく必要があります。
<ここから先の話は貞昌院でのことでありますので、そのことを念頭においてお読みください> なお、貞昌院としては、このイオンで提示されているお布施の目安はだいたい﹁平均すると﹂このようなものか、という感じです。︵あくまで、一寺院、一僧侶としての感覚です︶ このイオンの取組みは、ブラックボックスになりがちな葬祭業者の葬儀費用の内訳を明示化するという意味では評価できるものであります。 檀家さんがもし、イオンを通して葬儀を行なうとして、上記金額の通りの葬儀をお考えであっても問題はないと考えます。もちろん、お布施はイオンの費用よりも多くしていただいてもまったく問題はありません。 また、菩提寺をお持ちでない方が、イオンを通して貞昌院をご希望であればお受けさせていただきます。
このブログをお読みの方に、もっと取っておきの情報をお知らせいたします。 それは、意外と思われるかもしれませんが、﹁お寺で葬儀を﹂行なうことが一番費用削減なるということです。 客殿を使った葬儀も可能ですし、なんとなれば、祭壇は﹁須弥檀﹂という形でも可能です。 冒頭の試算の中の葬儀費用の大部分の削減に繋げることも可能でしょう。
イオンの葬儀プランナーに相談されるのもよいですが、まずはお寺に相談して、ざっくばらんに相談されるということも宜しいのではないかと思います。 葬儀費用について疑問等ありましたら、そのままにしておかないことが、結果的に費用削減に繋がるということになります。
■関連リンク 護持会費・墓地管理費などのごあんない︵貞昌院Web site︶
2009年1月19日
60兆円産業に再編・買収の嵐
本日発売された﹃週刊ダイヤモンド﹄1月24日号で ﹁寺・墓・葬儀にかかるカネ﹂ ? 60兆円産業に再編・買収の嵐が吹き荒れる? が特集として取り上げられています。
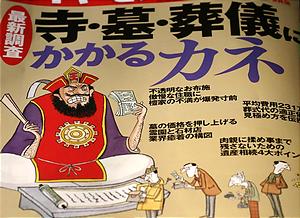
昨年も1月早々から﹁寺と墓-誰も知らない巨大ビジネス﹂が特集化されておりましたので、新年恒例の特集記事になるかもしれません。 どんなにカネ持ちでも﹁死﹂だけは避けて通れないが、カネがあれば盛大な供養を営むことは可能だ。しかし、その多くは寺や業者などの思惑が優先し、故人の思いが本当に反映されているとは限らない。現状の問題点を明らかにするとともに、従来型とは一線を画した新たな動きも取り上げた。 なるほど・・・・・・早速購入して読んでみました。
■序章 ムダなカネを払っていないか 今から考えたい供養のあり方 葬儀の準備を事前に進めておくことは、これまでタブーとされる傾向にありました。 結果、死を迎え、家族近親者がなんだか分からないままに、葬儀社の言うがままに葬儀を進めてしまい、振り返って考えると﹁こうしておけば良かった﹂と反省する事例が増えています。 超宗派の僧侶で設立した団体の相談窓口には ﹁葬儀社の請求にびっくりした﹂ ﹁葬儀に来てもらった僧侶と連絡が取れなくなった﹂ など、葬儀にまつわる不安が多数寄せられています。 寺・墓・葬儀の考え方として、 ︵1︶どんな供養をして欲しいのか ---﹁寺﹂ ︵2︶どんな墓に眠りたいのか ---﹁墓﹂ ︵3︶どんな葬儀にしてほしいか ---﹁葬儀﹂ ということを前もって真剣に考えておく必要があると指摘しています。 このキーワードをもとに、特集の項目が並べられています。
■Part1 ﹁寺﹂ 加速する仏教離れ、寺離れ 檀家依存の収入基盤は崩壊 ここで目を引くのは﹁︻大図解︼数字で見る数字で見る、寺の収入モデルと迫り来る危機﹂という図です。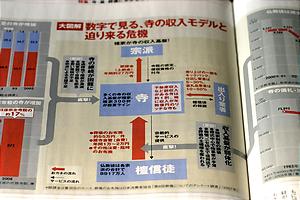 寺を中心に、お金がどのように動いているのかということを図解しています。
寺の収入として、その大部分を占める檀信徒からの布施収入、そして、出入業者からのキックバックが描かれてます。
ここで、注意するべきは、出入業者からのキックバックです。
例えば仕出し業者から寺に5?30%のキックバックが寺に入るとしています。
返礼品業者は10?50%、このほか石材店、葬儀業者など…
このキックバックは次のColumnと関係してきますが、檀信徒の信頼関係を損なうものです。
もし、キックバックを平然と受け取るような寺院なり僧侶がいるとすれば、それは問題です。
逆に、お寺や僧侶の見極めをするのであれば、この辺りがキーワードになって来るでしょう。
次のColumnへと続きます。
寺を中心に、お金がどのように動いているのかということを図解しています。
寺の収入として、その大部分を占める檀信徒からの布施収入、そして、出入業者からのキックバックが描かれてます。
ここで、注意するべきは、出入業者からのキックバックです。
例えば仕出し業者から寺に5?30%のキックバックが寺に入るとしています。
返礼品業者は10?50%、このほか石材店、葬儀業者など…
このキックバックは次のColumnと関係してきますが、檀信徒の信頼関係を損なうものです。
もし、キックバックを平然と受け取るような寺院なり僧侶がいるとすれば、それは問題です。
逆に、お寺や僧侶の見極めをするのであれば、この辺りがキーワードになって来るでしょう。
次のColumnへと続きます。
◆Column 資格なしの﹁ニセ坊主﹂も跋扈 僧侶の質の低下でクレーム多発 特に都市部に多いのですが、地方から都市部に越してきた方の多くは菩提寺を持っていません。 そこで、葬儀社や霊園、専門の僧侶派遣会社に頼むことになることがあり、その場合いい加減な僧侶が少なからずま紛れているという指摘です。酷いケースでは、葬儀社が実質的に僧侶を社員として抱え込んでいる場合もあるようです。 ニセ坊主の見分け方として ︵1︶自分の寺を持っていない ︵2︶何宗の僧侶資格を持っているか言わない ︵3︶どんな宗派の葬儀でも執り行えると明言 ︵4︶自分の連絡先を言わない ︵5︶戒名をつけるために事前に連絡を取らない ︵6︶読経、法話が下手くそ ︵7︶袈裟が着られない などをポイントして列挙しています。 まさに、これは葬儀費用の不透明化、質の低下の最たる原因となるものです。 菩提寺を未だ持っていらっしゃらない方は時間のあるときに近くの寺院を実際に巡って、そのお寺の住職・僧侶と話をしてみると宜しいと存じます。 お寺めぐりは伽藍を眺めるだけでなく、その寺院の僧侶とお話しする楽しみもあるのです。周囲にはきっと様々なお寺があります。新たな発見も多いことでしょう。 そのような信頼関係を予め作っておくことがトラブルを防ぐ基本的なこととなります。 記事は、いくら多くの僧侶がちゃんと活動しても、こうした構造にメスを入れなければ仏教界全体の信頼は落ちていくだろうと指摘しています。 次の特集では﹁寺が変わる!﹂としての寺の取組みの具体例です。 ◆取り組み 本来の機能・役割を取り戻せ 始まった原点回帰への模索 知多四国霊場会︵愛知県︶/喝破道場︵香川県︶/宝蔵寺︵茨城県︶/ビハーラ21︵大阪府︶/超光寺︵埼玉県︶ Column 生と死を歌で伝える女性僧侶/都会人の心癒やす﹁坊主バー﹂ ここに、知人の関わる取組みも紹介されています。 特に5日間で2万人の参拝者を集めた霊場サミットの例は、保守的な寺院からは反対の声もあったものの、時代に即し社会から支持を集める活動をどのように進め、成功に導いていったのかが特集されています。
特集は、この後、Part2﹁墓﹂ Part3﹁葬儀﹂と続きます。 ■Part2 ﹁墓﹂ 継承者難で家墓が崩壊? 変貌を遂げる終の棲家 Diagram 墓の価格を押し上げる石材店儲けのカラクリ Column 墓石のベンツと呼ばれる庵治が高い理由は希少性 弔い方 墓を作らない人が急増中 安さと自然回帰に人気集まる 永代供養/納骨堂/散骨/樹木葬/手元供養 Column CO2排出量基に森林保護に寄付 供養の場でも広がるエコロジー 改葬 意を尽くして住職に説明必要 費用は200万円前後覚悟を ペット供養 同居墓から出張火葬まで 愛好家につけ込む業者に注意
■Part 3 ﹁葬儀﹂ 不透明な価格の裏に潜む闇 悪徳業者の手口と見分け方 Diagram 遺族を悩ます不明朗な葬儀費用のカラクリ 新潮流 生花祭壇や高級死装束も人気 簡素化・こだわりがキーワード オフィスシオン/ニチリョク/日比谷花壇/ビューティ花壇/リコルド田園調布︵メモリアルアートの大野屋︶/一文 Column 専門学校で葬儀のプロ育成 数少ない有望市場に人材送る 戒名料 ﹁高額﹂﹁不透明﹂と槍玉に挙がる寺院関連費用の相場を公開 遺産相続 肉親には揉め事を残さない! 相続で気をつけたい4ヵ条 時代の変化は墓、葬儀のあり方にも大きな影響を及ぼしています。 特集記事は﹁価格﹂面からのアプローチを行っていますが、一つの手法として客観的に物事を捉える上で知っておくことは必要だと思います。 不明朗な費用にはきちんと説明を求める姿勢も必要でしょう。 特に、P.61の﹁こんな葬儀社には要注意!﹂というチェックリストはここでは列挙いたしませんが必読です。 これまで供養に関するしきたりや習慣は小さな共同体の中で共有・継承されてきた。暗黙のなかで伝わっていく場合も多く、わからなければ知恵者に聞けば教えてくれた。 その中心にいたのが菩提寺や住職であり、檀家との寺檀関係を通じてしっかりと結び付けられていた。 ところが地方から都会に移り住む人が増え、そこに住みつくなど人口の流動化で地域コミュニティーが希薄化したり、少子高齢化で後継者がいなくなったりしたことで透明性を求める動きが強まっているのだ。 とりわけ不満が強いのが金銭面での大きな負担である。 普段はなにもしてくれない寺が事があると急に擦り寄ってきたり、悲嘆に暮れている遺族が知識不足と見るや、それにつけ込んで寺や業者が結託し、ぼろ儲けを図ろうとすることも珍しくない。 ︵P.32より引用、下線はkameno︶ 菩提寺をお持ちの方は、生前から寺院の僧侶と話をして疑問点があれば遠慮なくぶつける 菩提寺を持っていない方は、生前に出来るだけ多くの寺院を巡り、僧侶と話をしてみる そして、信頼の置ける寺院、葬儀社、石材店を予め見つけておく。 ちょっとしたことが無駄な出費を抑えトラブルを防止するきっかけになるのです。
週刊ダイヤモンドの記事がきっかけで寺・墓・葬儀を取り巻く問題が改善の方向に進むことを期待しています。
追記
特集の一つ P.53﹁CO2排出量基に森林保護に寄付・供養の場でも広がるエコロジー﹂に、SOTO禅インターナショナルで進めている﹁塔婆供養で植林支援﹂の紹介が掲載されていました。
■関連リンク
貞昌院檀信徒向け情報
寺と墓-誰も知らない巨大ビジネス
寺院の果たすべき社会的責任
寺院の数はコンビニの数よりもずっと多い
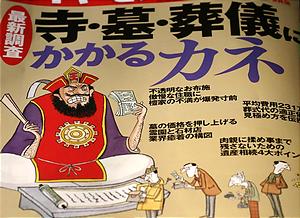
昨年も1月早々から﹁寺と墓-誰も知らない巨大ビジネス﹂が特集化されておりましたので、新年恒例の特集記事になるかもしれません。 どんなにカネ持ちでも﹁死﹂だけは避けて通れないが、カネがあれば盛大な供養を営むことは可能だ。しかし、その多くは寺や業者などの思惑が優先し、故人の思いが本当に反映されているとは限らない。現状の問題点を明らかにするとともに、従来型とは一線を画した新たな動きも取り上げた。 なるほど・・・・・・早速購入して読んでみました。
■序章 ムダなカネを払っていないか 今から考えたい供養のあり方 葬儀の準備を事前に進めておくことは、これまでタブーとされる傾向にありました。 結果、死を迎え、家族近親者がなんだか分からないままに、葬儀社の言うがままに葬儀を進めてしまい、振り返って考えると﹁こうしておけば良かった﹂と反省する事例が増えています。 超宗派の僧侶で設立した団体の相談窓口には ﹁葬儀社の請求にびっくりした﹂ ﹁葬儀に来てもらった僧侶と連絡が取れなくなった﹂ など、葬儀にまつわる不安が多数寄せられています。 寺・墓・葬儀の考え方として、 ︵1︶どんな供養をして欲しいのか ---﹁寺﹂ ︵2︶どんな墓に眠りたいのか ---﹁墓﹂ ︵3︶どんな葬儀にしてほしいか ---﹁葬儀﹂ ということを前もって真剣に考えておく必要があると指摘しています。 このキーワードをもとに、特集の項目が並べられています。
■Part1 ﹁寺﹂ 加速する仏教離れ、寺離れ 檀家依存の収入基盤は崩壊 ここで目を引くのは﹁︻大図解︼数字で見る数字で見る、寺の収入モデルと迫り来る危機﹂という図です。
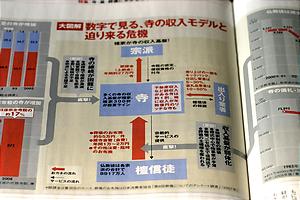 寺を中心に、お金がどのように動いているのかということを図解しています。
寺の収入として、その大部分を占める檀信徒からの布施収入、そして、出入業者からのキックバックが描かれてます。
ここで、注意するべきは、出入業者からのキックバックです。
例えば仕出し業者から寺に5?30%のキックバックが寺に入るとしています。
返礼品業者は10?50%、このほか石材店、葬儀業者など…
このキックバックは次のColumnと関係してきますが、檀信徒の信頼関係を損なうものです。
もし、キックバックを平然と受け取るような寺院なり僧侶がいるとすれば、それは問題です。
逆に、お寺や僧侶の見極めをするのであれば、この辺りがキーワードになって来るでしょう。
次のColumnへと続きます。
寺を中心に、お金がどのように動いているのかということを図解しています。
寺の収入として、その大部分を占める檀信徒からの布施収入、そして、出入業者からのキックバックが描かれてます。
ここで、注意するべきは、出入業者からのキックバックです。
例えば仕出し業者から寺に5?30%のキックバックが寺に入るとしています。
返礼品業者は10?50%、このほか石材店、葬儀業者など…
このキックバックは次のColumnと関係してきますが、檀信徒の信頼関係を損なうものです。
もし、キックバックを平然と受け取るような寺院なり僧侶がいるとすれば、それは問題です。
逆に、お寺や僧侶の見極めをするのであれば、この辺りがキーワードになって来るでしょう。
次のColumnへと続きます。
◆Column 資格なしの﹁ニセ坊主﹂も跋扈 僧侶の質の低下でクレーム多発 特に都市部に多いのですが、地方から都市部に越してきた方の多くは菩提寺を持っていません。 そこで、葬儀社や霊園、専門の僧侶派遣会社に頼むことになることがあり、その場合いい加減な僧侶が少なからずま紛れているという指摘です。酷いケースでは、葬儀社が実質的に僧侶を社員として抱え込んでいる場合もあるようです。 ニセ坊主の見分け方として ︵1︶自分の寺を持っていない ︵2︶何宗の僧侶資格を持っているか言わない ︵3︶どんな宗派の葬儀でも執り行えると明言 ︵4︶自分の連絡先を言わない ︵5︶戒名をつけるために事前に連絡を取らない ︵6︶読経、法話が下手くそ ︵7︶袈裟が着られない などをポイントして列挙しています。 まさに、これは葬儀費用の不透明化、質の低下の最たる原因となるものです。 菩提寺を未だ持っていらっしゃらない方は時間のあるときに近くの寺院を実際に巡って、そのお寺の住職・僧侶と話をしてみると宜しいと存じます。 お寺めぐりは伽藍を眺めるだけでなく、その寺院の僧侶とお話しする楽しみもあるのです。周囲にはきっと様々なお寺があります。新たな発見も多いことでしょう。 そのような信頼関係を予め作っておくことがトラブルを防ぐ基本的なこととなります。 記事は、いくら多くの僧侶がちゃんと活動しても、こうした構造にメスを入れなければ仏教界全体の信頼は落ちていくだろうと指摘しています。 次の特集では﹁寺が変わる!﹂としての寺の取組みの具体例です。 ◆取り組み 本来の機能・役割を取り戻せ 始まった原点回帰への模索 知多四国霊場会︵愛知県︶/喝破道場︵香川県︶/宝蔵寺︵茨城県︶/ビハーラ21︵大阪府︶/超光寺︵埼玉県︶ Column 生と死を歌で伝える女性僧侶/都会人の心癒やす﹁坊主バー﹂ ここに、知人の関わる取組みも紹介されています。 特に5日間で2万人の参拝者を集めた霊場サミットの例は、保守的な寺院からは反対の声もあったものの、時代に即し社会から支持を集める活動をどのように進め、成功に導いていったのかが特集されています。
特集は、この後、Part2﹁墓﹂ Part3﹁葬儀﹂と続きます。 ■Part2 ﹁墓﹂ 継承者難で家墓が崩壊? 変貌を遂げる終の棲家 Diagram 墓の価格を押し上げる石材店儲けのカラクリ Column 墓石のベンツと呼ばれる庵治が高い理由は希少性 弔い方 墓を作らない人が急増中 安さと自然回帰に人気集まる 永代供養/納骨堂/散骨/樹木葬/手元供養 Column CO2排出量基に森林保護に寄付 供養の場でも広がるエコロジー 改葬 意を尽くして住職に説明必要 費用は200万円前後覚悟を ペット供養 同居墓から出張火葬まで 愛好家につけ込む業者に注意
■Part 3 ﹁葬儀﹂ 不透明な価格の裏に潜む闇 悪徳業者の手口と見分け方 Diagram 遺族を悩ます不明朗な葬儀費用のカラクリ 新潮流 生花祭壇や高級死装束も人気 簡素化・こだわりがキーワード オフィスシオン/ニチリョク/日比谷花壇/ビューティ花壇/リコルド田園調布︵メモリアルアートの大野屋︶/一文 Column 専門学校で葬儀のプロ育成 数少ない有望市場に人材送る 戒名料 ﹁高額﹂﹁不透明﹂と槍玉に挙がる寺院関連費用の相場を公開 遺産相続 肉親には揉め事を残さない! 相続で気をつけたい4ヵ条 時代の変化は墓、葬儀のあり方にも大きな影響を及ぼしています。 特集記事は﹁価格﹂面からのアプローチを行っていますが、一つの手法として客観的に物事を捉える上で知っておくことは必要だと思います。 不明朗な費用にはきちんと説明を求める姿勢も必要でしょう。 特に、P.61の﹁こんな葬儀社には要注意!﹂というチェックリストはここでは列挙いたしませんが必読です。 これまで供養に関するしきたりや習慣は小さな共同体の中で共有・継承されてきた。暗黙のなかで伝わっていく場合も多く、わからなければ知恵者に聞けば教えてくれた。 その中心にいたのが菩提寺や住職であり、檀家との寺檀関係を通じてしっかりと結び付けられていた。 ところが地方から都会に移り住む人が増え、そこに住みつくなど人口の流動化で地域コミュニティーが希薄化したり、少子高齢化で後継者がいなくなったりしたことで透明性を求める動きが強まっているのだ。 とりわけ不満が強いのが金銭面での大きな負担である。 普段はなにもしてくれない寺が事があると急に擦り寄ってきたり、悲嘆に暮れている遺族が知識不足と見るや、それにつけ込んで寺や業者が結託し、ぼろ儲けを図ろうとすることも珍しくない。 ︵P.32より引用、下線はkameno︶ 菩提寺をお持ちの方は、生前から寺院の僧侶と話をして疑問点があれば遠慮なくぶつける 菩提寺を持っていない方は、生前に出来るだけ多くの寺院を巡り、僧侶と話をしてみる そして、信頼の置ける寺院、葬儀社、石材店を予め見つけておく。 ちょっとしたことが無駄な出費を抑えトラブルを防止するきっかけになるのです。
週刊ダイヤモンドの記事がきっかけで寺・墓・葬儀を取り巻く問題が改善の方向に進むことを期待しています。
2009年1月16日
ビュートついに生産終了
光岡﹁ビュート﹂年内で生産終了 光岡自動車︵本社・富山市︶は15日、16年間販売していた小型車﹁ビュート﹂の生産を年内で終えると発表した。同車のクラシックなデザインが保安基準の改正で適合しなくなるためという。年内に60台を生産し、うち20台はシートに刺繍︵ししゅう︶を入れるなどした特別仕様車として16日から予約を受け付ける。 ビュートは日産自動車の﹁マーチ﹂の外観を仕立て直した改造車で、﹁美しく遊ぶ人﹂から﹁美遊人︵ビュート︶﹂と名付けられた。16年間で約9300台を手作業で生産。単一の外観モデルとしては異例の長さだ。同社は﹁今後も景気に左右されない手作りの車を販売する﹂としている。 ︵朝日新聞2009年1月15日︶
光岡自動車は富山県の自動車メーカーで、日本で第10番目に設立された国内認可で一番新しい自動車会社です。 今回生産終了となるビュートは以前乗っていたこともありますので、とても残念なニュースです。
⇒ビュートの特設サイト︵光岡自動車︶ ビュートは、1993年に生産が開始され、発売された当時、雑誌の広告を見て、そのコンセプトに惚れ込み、また﹁小さな工場には、夢がある﹂という光岡自動車のキャッチフレーズにも大いに感銘を受け、直ぐに世田谷のショールームに見に行ったものです。 そして即決。 手作りのため、確か生産台数が月数十台ほどで、しかも発売されたばかりだったため、納車に半年以上も掛かりました。 念願のビュートが届いたのは1994年春。
今でこそ数はそれなりに増えてきましたが、当時は珍しい上にインパクトがあったためか、街で運転していると様々な人に﹁これは何という車?﹂と興味深そうによく尋ねられました。 この車を見て、ビュートを購入されたかたも何人か居たり。エンジンは日産のものですから、走りは全く問題ありません。 車検も日産の工場でできますので維持費も安い。 しいて言えば、初期型はバックライトが下向きに付いていたため、ちょっとした段差があるとバックライトの底部を擦ってしまうという欠点がありました。これは次のマイナーチェンジで上向きに改善されたようです。 こういう乗っていて楽しい車というのは珍しいと思います。 ビュートは3年間愛用し、現在のミニバンに変更するために中古車で売ってしまいました。 ︵当時はまだまだ珍しかったためか、売却査定額は購入時と殆ど変わらない価格でした!︶
車は乗り換えてしまいましたが、街でビュートを見かけると思わず微笑んでしまいます。 16年間生産が続いたビュートもついに生産終了。 バンパーが保安基準に適合しなくなったことが理由のようですが、本当に残念です。 以下、光岡自動車のサイトより引用大企業になることが目標じゃない 納得するまでとことんこだわり続ける 私達のクルマ作りは、 ﹁今までに見た事も無いようなクルマ﹂ ﹁みんながびっくりするクルマ﹂ ﹁日々の生活が楽しくなるクルマ﹂ ﹁ワクワクするクルマ﹂ ﹁世界が広がるクルマ﹂ などと、常にいろいろな事を考えて企画しデザインを描きます。 紙の上に描かれたデザインを忠実に形にする事は、 限界への挑戦でもあります。 時には、常識では考えられない工法を取り入れる事さえあります。 出来上がった形は、デザインを優先するので大量生産には不向きな形になります。 FRP成形、スチールのたたき出し、溶接、ボディの接合など、全て手作業で行っています。 太陽が降り注ぐ暑い夏でも手で汗を拭い、雪が降り続ける厳しい冬でも、かじかんだ手を温めながら、一台一台クラフトマン︵職人︶の手によって仕上げられていきます。 しかし、そんな時でもクラフトマン︵職人︶の瞳は、少年のように輝いています。 また、私達は﹁質﹂へのこだわりも決して忘れません。 私達が求めている﹁質﹂とは、私達の自分勝手なクルマ作りへの思いに賛同していただき、ユーザーとなってくださった皆様が、購入後数年経った後に ﹁光岡自動車にしてよかった!﹂ と思っていただける﹁質﹂を目標として、これからも﹁質﹂を極め続けていきます。 ミツオカが一味違って見えるのは、こうした遊び心を大切にしている気持ちと、物作りへのこだわりからかもしれません。 こうして誕生するクルマは、技と感性が作り上げた、希少で味わい深い私達の自信作です。 誰もが不可能に思う事でも、それに立ち向かい、もっと楽しいクルマ、もっと夢のあるクルマを。
歴史的な不況の中にあっても、それをものともしない元気な企業のもつ原動力は、こうところにあるのでしょう。 学ぶべきことはたくさんあります。
2008年12月22日
実態からかけ離れてしまった経済
ついに近所のガソリンスタンドでレギュラーガソリンが100円を切りました。

 給油中の金額の上昇の仕方が半年前とまるで異なります。
給油中の金額の上昇の仕方が半年前とまるで異なります。
今年の異常なほどの原油高は、経済全体に大きな影響を及ぼしました。 第一次産業従事者にあっては、コストの上昇があまりにも急激過ぎて経営が成り立たないという状況も多く見られました。 そこで急遽考えられたことの一つが、オイルサーチャージ制だったと思います。 農林水産物の生産コストの内の、原油の価格を価格に反映させるというものです。 一見、そのシステムは生産者の生活を保護するかのように思えました。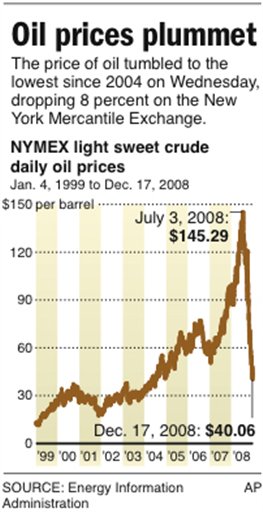
しかし、夏過ぎからの原油価格崩落は、その甘い考えを打ち砕くものになってしまうのではないでしょうか。 オイルサーチャージ制を取り入れたとすると、価格を下げて販売しなければなりません。 市場はは国内のみではありませんから、ここ数ヶ月の円高により、海外から安い農作物が入ってくる上に、輸出環境は悪化する一方です。 また、国内消費も経済環境の悪化により需要も減少しています。 大丈夫なのでしょうか。
そういえば、春先には投資会社から、原油や農作物の先物取引に関するセールスの電話がかなり頻繁に掛かってきました。 相手は電話帳を片っ端から掛けているようです。 セールストークは決って﹁これまでにない価格の上昇が見られます。今投資しておかないと損ですよ﹂云々・・・・・ このようなときには、電話の相手に﹁では、半年後に価格がいくらになるか予測してみてください。もし、半年後にその価格が当たっていたら検討します﹂と対応していました。 それから半年、予測された価格は全く大外れです。︵というより、半年前に下落を予想した人は皆無︶ きっと、セールストークに踊らされて投資してしまった人も多いのでしょうね。 有名大学ですら、巨大な損失を蒙ってしまっていますから。
明中に当って暗あり、暗相をもって遇うことなかれ、 暗中に当って明あり、明相をもって覩ることなかれ、 明暗おのおの相対して、比するに前後の歩みのごとし ﹃参同契︵さんどうかい︶﹄
今日の托鉢では参同契もたくさん読経してきます。 そして夕方は鎌倉でのキャンドルナイト。 何も背伸びする必要はありません。 自分のペースで進んでいけばいいのです。

 給油中の金額の上昇の仕方が半年前とまるで異なります。
給油中の金額の上昇の仕方が半年前とまるで異なります。
今年の異常なほどの原油高は、経済全体に大きな影響を及ぼしました。 第一次産業従事者にあっては、コストの上昇があまりにも急激過ぎて経営が成り立たないという状況も多く見られました。 そこで急遽考えられたことの一つが、オイルサーチャージ制だったと思います。 農林水産物の生産コストの内の、原油の価格を価格に反映させるというものです。 一見、そのシステムは生産者の生活を保護するかのように思えました。
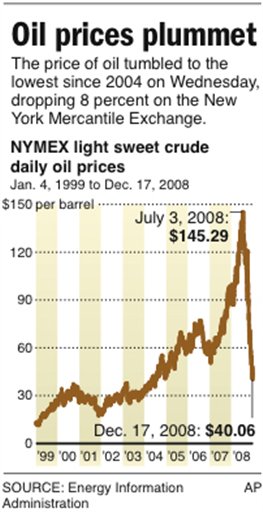
しかし、夏過ぎからの原油価格崩落は、その甘い考えを打ち砕くものになってしまうのではないでしょうか。 オイルサーチャージ制を取り入れたとすると、価格を下げて販売しなければなりません。 市場はは国内のみではありませんから、ここ数ヶ月の円高により、海外から安い農作物が入ってくる上に、輸出環境は悪化する一方です。 また、国内消費も経済環境の悪化により需要も減少しています。 大丈夫なのでしょうか。
そういえば、春先には投資会社から、原油や農作物の先物取引に関するセールスの電話がかなり頻繁に掛かってきました。 相手は電話帳を片っ端から掛けているようです。 セールストークは決って﹁これまでにない価格の上昇が見られます。今投資しておかないと損ですよ﹂云々・・・・・ このようなときには、電話の相手に﹁では、半年後に価格がいくらになるか予測してみてください。もし、半年後にその価格が当たっていたら検討します﹂と対応していました。 それから半年、予測された価格は全く大外れです。︵というより、半年前に下落を予想した人は皆無︶ きっと、セールストークに踊らされて投資してしまった人も多いのでしょうね。 有名大学ですら、巨大な損失を蒙ってしまっていますから。
明中に当って暗あり、暗相をもって遇うことなかれ、 暗中に当って明あり、明相をもって覩ることなかれ、 明暗おのおの相対して、比するに前後の歩みのごとし ﹃参同契︵さんどうかい︶﹄
今日の托鉢では参同契もたくさん読経してきます。 そして夕方は鎌倉でのキャンドルナイト。 何も背伸びする必要はありません。 自分のペースで進んでいけばいいのです。
2008年12月16日
サンタクロース+禅=?
﹁Buy Nothing Day﹂という日をご存知でしょうか。
これは、1992年カナダから始まったカルチャー・ジャミングのエコ・ムーブメントです。
毎年11月終わりに開催されるイベントで、今年で15年回目を迎え、62か国150万人以上が関わりました。
日本では﹁無買日﹂として広まっています。
﹁Buy Nothing Day﹂・・・﹁無買日﹂とは、1年に1日だけ、必要なのもの以外は買わずに過ごそうとする日です。 考えてみれば当たりまえのことですが、たくさんの商品が陳列されたスーパーに行ったり、ネットサーフィンをしたり、コマーシャルに接したり、私たちの周りには購買意欲を掻き立てるものに囲まれています。 ついつい、後で振り返ると必要のないものを買ってしまったという経験も少なくないはずです。 そこで、自戒を込めて、﹁無買﹂を誓い、消費行動を見直そうとするのが﹁無買日﹂の目指すところです。 今年、日本、デンマーク、フランス、イタリア、スェーデン、ドイツ、イスラエル、イギリスなどでは11月29日に行われました。 アメリカは一日早く、11月28日金曜日から行われました。アメリカでは、Thanks Giving Day の後の金曜日をBlack Fridayといい、大々的なバーゲンセールが行われ大量消費がなされる日でもあります。 だからこそ、やみくもに買い物をするのではなく、消費行動を見直すという行動が広がったのです。 さて、日本での﹁無買日﹂に、近年サンタクロースのパフォーマンスが見られるようになりました。 ﹁禅タクロース﹂と呼ばれるものです。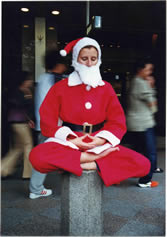
︵写真はBNDより︶
なぜ、﹁禅﹂+﹁サンタクロース﹂なのでしょうか。 公式ページからその理由を抜粋してみます。 禅タクロース伝説 インスピレーション それはゴミ置き場にサンタの衣装が捨てられていたのを見つけた時です。私の住む京都は日本でも間違いなく有数のゴミの量が多い都市です︵人口1人当たり換算︶。私、ガブリエレ・ハードは、1999年の﹁無買デー﹂に、どんなイベントを打とうか考えあぐねていました。そして、そのゴミ置き場を見た瞬間、全てが一つになったのです。 以前、禅をしている知人が﹁あなたが居る処から大改革が始まるんだ﹂、﹁買い物をする人たちの心の平穏を祈って瞑想しよう﹂と言っていたのを思い出しました。そこには捨てられたサンタの衣装があり、何かやりたいと人々が集まり、そして、ほら、禅タクロースができあがりました。阪急デパートのショウウィンドウでサンタの人形がダンスをしているその前で、禅タクロースはデビューしたのです。 ︵禅タクロース伝説、BND Japanのサイトより︶
単なる一人の禅タクロースとしての行動が雑誌やメディアに取り上げられ、世界中に発信されることにより、禅タクロースは世界中にひろがりました。 禅とサンタクロースのコラボレーションという発想が面白いですね。 ﹁禅タクロース﹂は、街頭での坐禅を行うことにより、﹁買い物という欲望﹂に疑問を投げかけ、禅定を通して現代社会のの消費について問題を提起しています。 サンタクロースには﹁子どもたちに夢を与える、西欧の伝統﹂という誤った先入観が植えつけられています。西洋的な消費主義の象徴であるサンタクロースが東洋の﹁禅﹂と結びついてこのような形になりました。
きっと道行く人々は思わず足を止め、何事かと思うことでしょう。 なぜサンタクロースが坐禅をしているのだろう! その奥には、ここでご紹介したようなメッセージが隠されているのです。
ただし・・・・・ ﹁カルチャー・ジャミング﹂は、﹁文化破壊﹂と直訳されますが、それを額面どおりに受け取ってしまい、単なる破壊行動となってしまっては本末転倒です。 せっかく﹁禅﹂と結びつけるのであれば、本来の﹁禅﹂についての学びを深め、﹁禅﹂の教えから消費行動を振り返ってみるということも大切です。 ﹁ジャミング﹂が、単なる﹁破壊﹂ではなく、新しく﹁創造﹂を生み出す﹁既成概念の破壊﹂でなければならないと思います。
関連リンク
■カルチャー・ジャミング︵ウィキペディア Wikipedia︶
■
﹁Buy Nothing Day﹂・・・﹁無買日﹂とは、1年に1日だけ、必要なのもの以外は買わずに過ごそうとする日です。 考えてみれば当たりまえのことですが、たくさんの商品が陳列されたスーパーに行ったり、ネットサーフィンをしたり、コマーシャルに接したり、私たちの周りには購買意欲を掻き立てるものに囲まれています。 ついつい、後で振り返ると必要のないものを買ってしまったという経験も少なくないはずです。 そこで、自戒を込めて、﹁無買﹂を誓い、消費行動を見直そうとするのが﹁無買日﹂の目指すところです。 今年、日本、デンマーク、フランス、イタリア、スェーデン、ドイツ、イスラエル、イギリスなどでは11月29日に行われました。 アメリカは一日早く、11月28日金曜日から行われました。アメリカでは、Thanks Giving Day の後の金曜日をBlack Fridayといい、大々的なバーゲンセールが行われ大量消費がなされる日でもあります。 だからこそ、やみくもに買い物をするのではなく、消費行動を見直すという行動が広がったのです。 さて、日本での﹁無買日﹂に、近年サンタクロースのパフォーマンスが見られるようになりました。 ﹁禅タクロース﹂と呼ばれるものです。
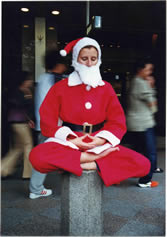
︵写真はBNDより︶
なぜ、﹁禅﹂+﹁サンタクロース﹂なのでしょうか。 公式ページからその理由を抜粋してみます。 禅タクロース伝説 インスピレーション それはゴミ置き場にサンタの衣装が捨てられていたのを見つけた時です。私の住む京都は日本でも間違いなく有数のゴミの量が多い都市です︵人口1人当たり換算︶。私、ガブリエレ・ハードは、1999年の﹁無買デー﹂に、どんなイベントを打とうか考えあぐねていました。そして、そのゴミ置き場を見た瞬間、全てが一つになったのです。 以前、禅をしている知人が﹁あなたが居る処から大改革が始まるんだ﹂、﹁買い物をする人たちの心の平穏を祈って瞑想しよう﹂と言っていたのを思い出しました。そこには捨てられたサンタの衣装があり、何かやりたいと人々が集まり、そして、ほら、禅タクロースができあがりました。阪急デパートのショウウィンドウでサンタの人形がダンスをしているその前で、禅タクロースはデビューしたのです。 ︵禅タクロース伝説、BND Japanのサイトより︶
単なる一人の禅タクロースとしての行動が雑誌やメディアに取り上げられ、世界中に発信されることにより、禅タクロースは世界中にひろがりました。 禅とサンタクロースのコラボレーションという発想が面白いですね。 ﹁禅タクロース﹂は、街頭での坐禅を行うことにより、﹁買い物という欲望﹂に疑問を投げかけ、禅定を通して現代社会のの消費について問題を提起しています。 サンタクロースには﹁子どもたちに夢を与える、西欧の伝統﹂という誤った先入観が植えつけられています。西洋的な消費主義の象徴であるサンタクロースが東洋の﹁禅﹂と結びついてこのような形になりました。
きっと道行く人々は思わず足を止め、何事かと思うことでしょう。 なぜサンタクロースが坐禅をしているのだろう! その奥には、ここでご紹介したようなメッセージが隠されているのです。
ただし・・・・・ ﹁カルチャー・ジャミング﹂は、﹁文化破壊﹂と直訳されますが、それを額面どおりに受け取ってしまい、単なる破壊行動となってしまっては本末転倒です。 せっかく﹁禅﹂と結びつけるのであれば、本来の﹁禅﹂についての学びを深め、﹁禅﹂の教えから消費行動を振り返ってみるということも大切です。 ﹁ジャミング﹂が、単なる﹁破壊﹂ではなく、新しく﹁創造﹂を生み出す﹁既成概念の破壊﹂でなければならないと思います。

2008年11月11日
経済学の視点から見たお寺
神奈川県仏教会釈尊成道会記念講演会
﹃経済学の視点から見たお寺の現代的課題﹄が、横浜市・西有寺専門僧堂を会場に開催されました。
講師は慶応大学中島隆信先生。
講師先生の著書﹃お寺の経済学﹄︵文末で紹介︶を読んだこともありますので、直接講演を聴くことが出来ることを楽しみにしていました。
講演内容は主に﹃お寺の経済学﹄を掘り下げたものとなりました。
記録として書き記しておきます。
(kameno個人メモであることを予めご了承ください︶
 ■経済学の基本
世の中には必要ないものは存在しない。
ゆえに、お寺は少なくとも現在は世の中のニーズがあると考えられる。
経済学的視点からの一般的法則は、買う側と売る側のサービスのやり取りであり、両面が必要である。片方だけでは成立しない。
これを寺院に当てはめると、人々にいかに仏教の教えを伝え︵サービスの提供︶それをいかに人々が受けとめるか︵サービスの受容︶ということになる。
■信仰市場という解釈
<経済学のものの見方=需要と供給はどちらが重要だろうか>
消費者を大切にする。
商品が売れなかった場合に、なぜ売れなかったか原因を考える。
その際に、物を売る側に問題があるのか、買う側に問題があるのかのどちらかであるとすると、ほとんどの場合、売る側に問題があると考えるべきである。
たとえば大学の授業でテストの成績・結果が悪い場合、学生が悪いのではなく、教える側の教え方が悪い、良い授業が出来なかったと考える。
仏教に当てはめると、仏教の教えが一般に浸透していないとすれば、それは寺院・僧侶側に問題があると考えるべきである。
私自分もお寺の経済学の本を書くまでは、自分の所属する浄土真宗の教えについてほとんど知らなかった。
日常生活において、お寺との接点は法事や葬儀の際の関わりしかなかった。
法事法要の際の法話の際に、話を聞かない参列者が増えている原因が、参列者にあると考えているうちは進歩がない。どうしたら話を聞いてくれるのかを考えることにより進歩があるのである。
社会問題となっている食品偽装︵=消費者を騙す悪徳な業者︶については、買う側も何処産か、ということはわからない。消費者にも責任の一端があるが、賢い消費者を育ててこないことにも問題がある。
どの市場においても賢い消費者を育てる努力が必要である。
■経済学の基本
世の中には必要ないものは存在しない。
ゆえに、お寺は少なくとも現在は世の中のニーズがあると考えられる。
経済学的視点からの一般的法則は、買う側と売る側のサービスのやり取りであり、両面が必要である。片方だけでは成立しない。
これを寺院に当てはめると、人々にいかに仏教の教えを伝え︵サービスの提供︶それをいかに人々が受けとめるか︵サービスの受容︶ということになる。
■信仰市場という解釈
<経済学のものの見方=需要と供給はどちらが重要だろうか>
消費者を大切にする。
商品が売れなかった場合に、なぜ売れなかったか原因を考える。
その際に、物を売る側に問題があるのか、買う側に問題があるのかのどちらかであるとすると、ほとんどの場合、売る側に問題があると考えるべきである。
たとえば大学の授業でテストの成績・結果が悪い場合、学生が悪いのではなく、教える側の教え方が悪い、良い授業が出来なかったと考える。
仏教に当てはめると、仏教の教えが一般に浸透していないとすれば、それは寺院・僧侶側に問題があると考えるべきである。
私自分もお寺の経済学の本を書くまでは、自分の所属する浄土真宗の教えについてほとんど知らなかった。
日常生活において、お寺との接点は法事や葬儀の際の関わりしかなかった。
法事法要の際の法話の際に、話を聞かない参列者が増えている原因が、参列者にあると考えているうちは進歩がない。どうしたら話を聞いてくれるのかを考えることにより進歩があるのである。
社会問題となっている食品偽装︵=消費者を騙す悪徳な業者︶については、買う側も何処産か、ということはわからない。消費者にも責任の一端があるが、賢い消費者を育ててこないことにも問題がある。
どの市場においても賢い消費者を育てる努力が必要である。
■長期計画の重要性 現代に宗教は必要ないのだろうかという問題を考えてみる。 科学や医療のの発達していない時代においては、宗教がその役割を担っていた。 では、例えば医療が発達し、薬が病気を治療する時代になったとすれば宗教は不要になるのだろうか。 現代に宗教が排除されている状況、宗教に関心がない状況は、前段の考えに基づき、現代社会に宗教が不要であるということではなく、それを伝える側に問題があると考える。 経済学的に考えると、﹁顧客﹂を大切にしてこなかった、努力を怠ってきた結果であるといえる。 長期計画を持って﹁顧客﹂を育てていく必要がある 顧客︵=檀信徒︶が、後々に、寺院や仏教会を護持していくことも結びついていく。
檀信徒 宗教=信仰 寺院 <市場> ■観光寺、信者寺、檀家寺の違いとは? お寺市場には大別して次の三種類がある。 ・観光寺 例えば鎌倉大仏。 外からは見えない仕組みになっている。参拝者が信仰心をどれだけ持っているか。金閣寺を拝観する人は、そこが何宗か、住職は誰かについてはほとんど感心がない。行って写真を撮れば満足する。 宗教施設としての寺院というよりは、立ち食い蕎麦屋の感覚で、立ち寄って一回行けば満足するような寺である。 ・信者寺 浅草寺、善光寺、川崎大師など。初詣などでにぎわう寺院。行って手を合わせる点で、少なくとも観光寺よりは信仰心がある。祈願を行う=信仰。 ただし、信仰心がどれだけあるかは多少疑問が残る。 ・檀家寺 例えば価格表を出していないすし屋のようなもの。一見さんお断り。客のことを良くわかっている店。かといってぼったくりをするわけではない。そこには﹁信頼関係﹂が存在する。 医者と患者の信頼関係、教師と生徒の信頼関係。そのような信頼関係がなければファストフード店的な付き合いとなる⇒一回限りの取引。 例えば、駅前のトラックで売っている果物を大切な人への贈り物として購入するか? 檀家寺では、一回限りのサービスではなく、長い間付き合っていくという信頼関係が必要となる。老舗の信頼関係。逆に言えば、信頼関係が失われた場合には檀家寺である意味がない。 ■沖縄の寺院 檀家制度を排除した鹿児島藩が実効支配していたため、寺院の数が極端に少ない。 宗教法人格を未だ取れていなく、他の建物を流用する寺院が多い。祈祷、悩み相談。 なぜ沖縄に寺院が浸透しないのか 沖縄は信仰が100年遅れているといわれるが、実は100年進んでいるのではないか。 信頼関係=信仰=墓地 信頼関係の元である墓地の基盤が崩れると、信頼関係も崩壊する。
■信仰サービスの非営利性 信頼関係とお金のやり取り どのようにお金を受け取るべきか。 先生、医者・・・お金を受け取る側が人助けをし、お金を出す側が御礼をする。 御礼が先にあり、その後にお金を受け取る。 道ばたに人が倒れている状況を見て、通行人たちは受け取る料金を念頭に人助けをするだろうか。答えはNOだろう。とすれば、人助けをする際に料金を提示してはならない。 学校、病院は補助金があるがゆえに、料金提示が出来ても制限がある。 対し、寺院は唯一何の制約もなくできる業種である。 非営利であるということは、料金的提示がなされていないということが担保されていることが必要である。 経験上の例を挙げれば、ある山にハイキングに行ったときのこと。神社敷地の上山口に賽銭箱が設置されていた。賽銭箱には、道中の無事を祈るために﹁100円﹂記載されている。そのような場合は営利事業とみなすべきである。 非営利とみなされるようにするのであれば、下山口に設置し、料金提示をするべきではない。
■タイの寺院はなぜ存在しうるのか 布施を行うことにより<徳>が積みあがっていく。 何らかの価値を産み、その対価を得る。=徳を売る。 ■これから先の寺院はどのようにして生き残っていくべきか。 現代人にとって心の悩み苦しみは切っても切り離せないものである。 今後は、いかに苦しみと共存していくかが重要な課題であろう。 私自身、重い病気の家族と暮らす経験から、仏教の発想、教えに触れることができた。 なぜ彼が生まれてきたか、これから苦労して育てていかなければならないこと、回りからの視線など、そのような苦しみと如何に共存するべきなのか。 重い病気の家族が仏様であると考えることができるようになって、負担が軽減されるばかりではなく、ありがたい感情まで生じた。 何の薬も使わず、手術を施すこともなく、発想の転換のみで救われることが出来るのである。 これが檀家寺が長い間かけて育んできた、信頼関係の礎となるものである。 寺院は徐々に淘汰されていくかもれないが、賢い消費者を育てることのできる寺院は生き残っていくだろう。
講演の内容は﹃お寺の経済学﹄がベースになっています。
改めて先生の著書をご紹介いたします。
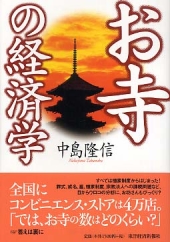 ﹃お寺の経済学﹄で坊主丸儲けは許しません
経済学者がつきつけたお寺業界の規制緩和策
﹃お寺の経済学﹄で坊主丸儲けは許しません
経済学者がつきつけたお寺業界の規制緩和策
お寺の経済学
中島 隆信 著 ■発行日 ‥ 2005年03月10日 ■ISBN ‥ 4-492-31345-1 C33 ■サイズ ‥ 四六判 並製 ■ページ ‥ 244頁 ■価格︵税込︶ ‥ 1,575円
 ■経済学の基本
世の中には必要ないものは存在しない。
ゆえに、お寺は少なくとも現在は世の中のニーズがあると考えられる。
経済学的視点からの一般的法則は、買う側と売る側のサービスのやり取りであり、両面が必要である。片方だけでは成立しない。
これを寺院に当てはめると、人々にいかに仏教の教えを伝え︵サービスの提供︶それをいかに人々が受けとめるか︵サービスの受容︶ということになる。
■信仰市場という解釈
<経済学のものの見方=需要と供給はどちらが重要だろうか>
消費者を大切にする。
商品が売れなかった場合に、なぜ売れなかったか原因を考える。
その際に、物を売る側に問題があるのか、買う側に問題があるのかのどちらかであるとすると、ほとんどの場合、売る側に問題があると考えるべきである。
たとえば大学の授業でテストの成績・結果が悪い場合、学生が悪いのではなく、教える側の教え方が悪い、良い授業が出来なかったと考える。
仏教に当てはめると、仏教の教えが一般に浸透していないとすれば、それは寺院・僧侶側に問題があると考えるべきである。
私自分もお寺の経済学の本を書くまでは、自分の所属する浄土真宗の教えについてほとんど知らなかった。
日常生活において、お寺との接点は法事や葬儀の際の関わりしかなかった。
法事法要の際の法話の際に、話を聞かない参列者が増えている原因が、参列者にあると考えているうちは進歩がない。どうしたら話を聞いてくれるのかを考えることにより進歩があるのである。
社会問題となっている食品偽装︵=消費者を騙す悪徳な業者︶については、買う側も何処産か、ということはわからない。消費者にも責任の一端があるが、賢い消費者を育ててこないことにも問題がある。
どの市場においても賢い消費者を育てる努力が必要である。
■経済学の基本
世の中には必要ないものは存在しない。
ゆえに、お寺は少なくとも現在は世の中のニーズがあると考えられる。
経済学的視点からの一般的法則は、買う側と売る側のサービスのやり取りであり、両面が必要である。片方だけでは成立しない。
これを寺院に当てはめると、人々にいかに仏教の教えを伝え︵サービスの提供︶それをいかに人々が受けとめるか︵サービスの受容︶ということになる。
■信仰市場という解釈
<経済学のものの見方=需要と供給はどちらが重要だろうか>
消費者を大切にする。
商品が売れなかった場合に、なぜ売れなかったか原因を考える。
その際に、物を売る側に問題があるのか、買う側に問題があるのかのどちらかであるとすると、ほとんどの場合、売る側に問題があると考えるべきである。
たとえば大学の授業でテストの成績・結果が悪い場合、学生が悪いのではなく、教える側の教え方が悪い、良い授業が出来なかったと考える。
仏教に当てはめると、仏教の教えが一般に浸透していないとすれば、それは寺院・僧侶側に問題があると考えるべきである。
私自分もお寺の経済学の本を書くまでは、自分の所属する浄土真宗の教えについてほとんど知らなかった。
日常生活において、お寺との接点は法事や葬儀の際の関わりしかなかった。
法事法要の際の法話の際に、話を聞かない参列者が増えている原因が、参列者にあると考えているうちは進歩がない。どうしたら話を聞いてくれるのかを考えることにより進歩があるのである。
社会問題となっている食品偽装︵=消費者を騙す悪徳な業者︶については、買う側も何処産か、ということはわからない。消費者にも責任の一端があるが、賢い消費者を育ててこないことにも問題がある。
どの市場においても賢い消費者を育てる努力が必要である。
■長期計画の重要性 現代に宗教は必要ないのだろうかという問題を考えてみる。 科学や医療のの発達していない時代においては、宗教がその役割を担っていた。 では、例えば医療が発達し、薬が病気を治療する時代になったとすれば宗教は不要になるのだろうか。 現代に宗教が排除されている状況、宗教に関心がない状況は、前段の考えに基づき、現代社会に宗教が不要であるということではなく、それを伝える側に問題があると考える。 経済学的に考えると、﹁顧客﹂を大切にしてこなかった、努力を怠ってきた結果であるといえる。 長期計画を持って﹁顧客﹂を育てていく必要がある 顧客︵=檀信徒︶が、後々に、寺院や仏教会を護持していくことも結びついていく。
檀信徒 宗教=信仰 寺院 <市場> ■観光寺、信者寺、檀家寺の違いとは? お寺市場には大別して次の三種類がある。 ・観光寺 例えば鎌倉大仏。 外からは見えない仕組みになっている。参拝者が信仰心をどれだけ持っているか。金閣寺を拝観する人は、そこが何宗か、住職は誰かについてはほとんど感心がない。行って写真を撮れば満足する。 宗教施設としての寺院というよりは、立ち食い蕎麦屋の感覚で、立ち寄って一回行けば満足するような寺である。 ・信者寺 浅草寺、善光寺、川崎大師など。初詣などでにぎわう寺院。行って手を合わせる点で、少なくとも観光寺よりは信仰心がある。祈願を行う=信仰。 ただし、信仰心がどれだけあるかは多少疑問が残る。 ・檀家寺 例えば価格表を出していないすし屋のようなもの。一見さんお断り。客のことを良くわかっている店。かといってぼったくりをするわけではない。そこには﹁信頼関係﹂が存在する。 医者と患者の信頼関係、教師と生徒の信頼関係。そのような信頼関係がなければファストフード店的な付き合いとなる⇒一回限りの取引。 例えば、駅前のトラックで売っている果物を大切な人への贈り物として購入するか? 檀家寺では、一回限りのサービスではなく、長い間付き合っていくという信頼関係が必要となる。老舗の信頼関係。逆に言えば、信頼関係が失われた場合には檀家寺である意味がない。 ■沖縄の寺院 檀家制度を排除した鹿児島藩が実効支配していたため、寺院の数が極端に少ない。 宗教法人格を未だ取れていなく、他の建物を流用する寺院が多い。祈祷、悩み相談。 なぜ沖縄に寺院が浸透しないのか 沖縄は信仰が100年遅れているといわれるが、実は100年進んでいるのではないか。 信頼関係=信仰=墓地 信頼関係の元である墓地の基盤が崩れると、信頼関係も崩壊する。
■信仰サービスの非営利性 信頼関係とお金のやり取り どのようにお金を受け取るべきか。 先生、医者・・・お金を受け取る側が人助けをし、お金を出す側が御礼をする。 御礼が先にあり、その後にお金を受け取る。 道ばたに人が倒れている状況を見て、通行人たちは受け取る料金を念頭に人助けをするだろうか。答えはNOだろう。とすれば、人助けをする際に料金を提示してはならない。 学校、病院は補助金があるがゆえに、料金提示が出来ても制限がある。 対し、寺院は唯一何の制約もなくできる業種である。 非営利であるということは、料金的提示がなされていないということが担保されていることが必要である。 経験上の例を挙げれば、ある山にハイキングに行ったときのこと。神社敷地の上山口に賽銭箱が設置されていた。賽銭箱には、道中の無事を祈るために﹁100円﹂記載されている。そのような場合は営利事業とみなすべきである。 非営利とみなされるようにするのであれば、下山口に設置し、料金提示をするべきではない。
■タイの寺院はなぜ存在しうるのか 布施を行うことにより<徳>が積みあがっていく。 何らかの価値を産み、その対価を得る。=徳を売る。 ■これから先の寺院はどのようにして生き残っていくべきか。 現代人にとって心の悩み苦しみは切っても切り離せないものである。 今後は、いかに苦しみと共存していくかが重要な課題であろう。 私自身、重い病気の家族と暮らす経験から、仏教の発想、教えに触れることができた。 なぜ彼が生まれてきたか、これから苦労して育てていかなければならないこと、回りからの視線など、そのような苦しみと如何に共存するべきなのか。 重い病気の家族が仏様であると考えることができるようになって、負担が軽減されるばかりではなく、ありがたい感情まで生じた。 何の薬も使わず、手術を施すこともなく、発想の転換のみで救われることが出来るのである。 これが檀家寺が長い間かけて育んできた、信頼関係の礎となるものである。 寺院は徐々に淘汰されていくかもれないが、賢い消費者を育てることのできる寺院は生き残っていくだろう。
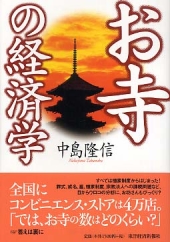 ﹃お寺の経済学﹄で坊主丸儲けは許しません
経済学者がつきつけたお寺業界の規制緩和策
﹃お寺の経済学﹄で坊主丸儲けは許しません
経済学者がつきつけたお寺業界の規制緩和策
お寺の経済学
中島 隆信 著 ■発行日 ‥ 2005年03月10日 ■ISBN ‥ 4-492-31345-1 C33 ■サイズ ‥ 四六判 並製 ■ページ ‥ 244頁 ■価格︵税込︶ ‥ 1,575円
2008年11月 3日
寺院会計の疑念を払拭するために
去年の春に城山三郎さんが亡くなったとき、五木寛之さんが本紙に寄せた追悼文に、こんなくだりがあった。︿︵先に亡くなった︶奥さんの葬式にきてくれた浄土真宗の僧侶が、リーズナブルな金額を申しでたうえに、ちゃんと領収書をくれたことを感心して話されていた﹀▼そのときの城山さんの表情が五木さんは印象深かったそうだ。ささやかな一コマだが、筋の通らぬことを嫌った故人らしい話だと思って読んだ▼葬儀などの際、包んだお布施に釈然としなかった人は1人や2人ではあるまい。数十万円、ときにはそれ以上が領収書もなく渡される。いまどき政治の世界でもない話だ。﹁相場﹂と言われる額の当否も外部には分かりづらい▼不透明さが仏教界への不信を招いているのではないか。憂える青年僧ら約20人が、東京で﹁寺ネット・サンガ﹂なる団体を旗揚げした。お布施について、施主に十分説明し、使途も明示するなどして、信頼を得る道を探るそうだ▼代表の中下大樹さん︵33︶によれば、近年、葬祭業者から仕事を回してもらった僧が、謝礼にお布施の何割かを渡す﹁キックバック﹂も見られる。そして戒名は金次第。すべての寺ではないにせよ、あれやこれやの算盤︵そろばん︶が﹁葬式仏教﹂などと批判されて久しい▼﹁宗教は死者を弔うばかりではなく、生者の心を救うもの﹂。そう語る中下さんは、これまでにホスピスで多くの人を看取︵みと︶ってもきた。青年僧たちは、受け取ったお布施を様々な社会貢献にも充てるという。旧弊をゆさぶって吹く、新しい風になれ。
︵﹁天声人語﹂2008年10月20日・朝日新聞︶
下線はkameno付記
問題を提起していただいたことはありがたいのですが、﹃天声人語﹄で書くのであれば、個人的な思い入れではなく、十分な検証を行ったうえで書いていただきたいところです。 葬儀に際し、僧侶側からリーズナブルな金額を申し出たとの点ですが、布施というものは僧侶側から申し出されるべきものでしょうか。 領収書を発行したことについて感心されたとのことですが、領収書を発行することは、法人として当然のことです。 もしも領収書を発行しないことが社会通念として常識となっているとすれば、それは逆に問題だと感じます。 寺院の会計はどんぶり勘定であったり、公私が混同されたりしてはなりません。 定期的に税務調査等が入り、会計処理に関する指導が適宜なされる現在では、不正処理を行うことは困難であるといえます。 ただし、収支決算書、貸借対照表、キャッシュフローをきちんと処理し、外部監査機関によるチェックを受けて、利害関係人に公表まで行う寺院はまだ多くないと思います。 このあたりは、他の公益法人と同様に基準を定めて会計処理を行うことは必要でありましょう。 本日、冒頭の﹁天声人語﹂に対する﹁読者の声﹂が掲載されていました。
高額のお布施 思いもよらぬ
住職 ****︵三重県***町 73︶
10月20日の﹁天声人語﹂で葬儀の布施についてふれてありました。数十万円などという額の布施に驚きました。
きっと都会の富裕層なのでしょう。当方では、そんな高額な布施やお礼を手にしたことはありません。過疎地では求めもしませんし、出して頂く余裕もないと思いますから。
戒名に金でランクをつけるなど、あってはならないことです。寺の経営上、仏教本来の精神を離れて、お金に振り回されている実情もあるようです。
内部から改革の声は上がりにくいので、今回のように、外部から素直な意見を聞かせて頂けば刺激になるでしょう。
辺地の寺を守っていくのは容易でありません。
兼職で支えていますが、それも困難になっています。住職は高齢化で亡くなり、無住・兼務が増えて葬式を出す人手も足りない集落もあります。人々の心のよりどころとして安らぎの求めにこたえる。それが僧侶の仕事と考え、檀家と苦労を共にし、出来るだけのことをしたいと思っています。
︵﹁声﹂ 2008年11月3日・朝日新聞︶
全国に分布する寺院は、ごく一部の大規模寺院と、大部分の中小寺院により構成されています。
﹁声﹂に投稿されたようなご寺院様が大部分です。
このあたりは、以前ブログでも書きましたが、いわゆる赤字の寺院が過半数を占めています。
たとえ、過疎地の小さな寺院であっても、会計処理を行うことにより、運営上の問題点が明確化となります。
赤字の寺院であれば、ただ漠然と運営が苦しいと訴えるのではなく、どの程度の赤字であるのかを具体的にきちんと把握できます。
檀家さんと苦労を共にする一つの拠り所ともなるでしょう。
貞昌院では次のように檀家の皆さまに提示しています。
貞昌院の護持会費・墓地管理費など
これから、寺院を取り巻く環境はますます厳しくなることは間違いありません。 読者の声に投稿されたご意見のように、外部からの声を真摯に受け止めていくことは大切なことであると考えています。 最後に、﹁天声人語﹂で紹介されていた﹁寺ネット・サンガ﹂に関する記事をご紹介します。
﹁寺ネット・サンガ﹂発足 葬儀・法要など 現代の仏教界や社会の抱える諸問題に危機感を抱き、包括的に対処していくことを目指す超宗派の僧侶・寺院のネットワーク﹁寺ネット・サンガ﹂の発足会が十七日、東京の浄土真宗本願寺派築地別院第二伝道会館で開催された。同会に賛同する仏教者、葬儀業者、NPO関係者らが一堂に会し、今後の展望などについて語り合った。 任意団体﹁寺ネット・サンガ﹂は、菩提寺がない人の葬儀・法要・納骨、セミナーや法話会などの情報発信、看取りの段階からかかわるターミナルケアなどを事業内容としている。特徴的なのは、会の活動を通じて得たお布施から葬儀社などへのキックバックは一切行なわないこと。組織内にはファンド︵基金︶を設立、正会員はお布施の半額を納め、公益性の高い団体など社会に還元していく方針を打ち出している。 事務所は東京都新宿区に置かれ﹁駆け込み寺﹂としての役割を担い、定期的に﹁サンガの会﹂を開き、業種の枠を超えて"いのち"のあり方について議論する。会員の優良な葬儀社・石材店・関連企業を同会のホームページで紹介するなど業者との連携も図っていく計画だ。 同会の代表は、ビハーラ僧としての経験も豊富な真宗大谷派僧侶の中下大樹氏が務め、全国青少年教化協議会主幹の神仁氏、浄土真宗本願寺派延立寺住職の松本智量氏をはじめ約十人の僧侶らが世話人となる。 発足会では、神氏の導師による法要の後、事業計画の説明などがあり、中下代表は﹁われわれは次の世代に何を訴えられるか、自分たちは何を受け継いできたのかが問われている。言葉だけではなく実践を通じて伝えていきたい。次世代に誇れる仕事をし、道なき荒野に道をつくっていきたい﹂と抱負を語った。 ︵中外日報情 2008年9月20日より︶
葬儀社などへのキックバックについては、ホント問題です。
寺院の問題というよりは、都市部に多い寺院を持たない僧侶が増えていることと非常に関連します。
この問題については、日を改めて考えていきたいと思います。
問題を提起していただいたことはありがたいのですが、﹃天声人語﹄で書くのであれば、個人的な思い入れではなく、十分な検証を行ったうえで書いていただきたいところです。 葬儀に際し、僧侶側からリーズナブルな金額を申し出たとの点ですが、布施というものは僧侶側から申し出されるべきものでしょうか。 領収書を発行したことについて感心されたとのことですが、領収書を発行することは、法人として当然のことです。 もしも領収書を発行しないことが社会通念として常識となっているとすれば、それは逆に問題だと感じます。 寺院の会計はどんぶり勘定であったり、公私が混同されたりしてはなりません。 定期的に税務調査等が入り、会計処理に関する指導が適宜なされる現在では、不正処理を行うことは困難であるといえます。 ただし、収支決算書、貸借対照表、キャッシュフローをきちんと処理し、外部監査機関によるチェックを受けて、利害関係人に公表まで行う寺院はまだ多くないと思います。 このあたりは、他の公益法人と同様に基準を定めて会計処理を行うことは必要でありましょう。 本日、冒頭の﹁天声人語﹂に対する﹁読者の声﹂が掲載されていました。
これから、寺院を取り巻く環境はますます厳しくなることは間違いありません。 読者の声に投稿されたご意見のように、外部からの声を真摯に受け止めていくことは大切なことであると考えています。 最後に、﹁天声人語﹂で紹介されていた﹁寺ネット・サンガ﹂に関する記事をご紹介します。
﹁寺ネット・サンガ﹂発足 葬儀・法要など 現代の仏教界や社会の抱える諸問題に危機感を抱き、包括的に対処していくことを目指す超宗派の僧侶・寺院のネットワーク﹁寺ネット・サンガ﹂の発足会が十七日、東京の浄土真宗本願寺派築地別院第二伝道会館で開催された。同会に賛同する仏教者、葬儀業者、NPO関係者らが一堂に会し、今後の展望などについて語り合った。 任意団体﹁寺ネット・サンガ﹂は、菩提寺がない人の葬儀・法要・納骨、セミナーや法話会などの情報発信、看取りの段階からかかわるターミナルケアなどを事業内容としている。特徴的なのは、会の活動を通じて得たお布施から葬儀社などへのキックバックは一切行なわないこと。組織内にはファンド︵基金︶を設立、正会員はお布施の半額を納め、公益性の高い団体など社会に還元していく方針を打ち出している。 事務所は東京都新宿区に置かれ﹁駆け込み寺﹂としての役割を担い、定期的に﹁サンガの会﹂を開き、業種の枠を超えて"いのち"のあり方について議論する。会員の優良な葬儀社・石材店・関連企業を同会のホームページで紹介するなど業者との連携も図っていく計画だ。 同会の代表は、ビハーラ僧としての経験も豊富な真宗大谷派僧侶の中下大樹氏が務め、全国青少年教化協議会主幹の神仁氏、浄土真宗本願寺派延立寺住職の松本智量氏をはじめ約十人の僧侶らが世話人となる。 発足会では、神氏の導師による法要の後、事業計画の説明などがあり、中下代表は﹁われわれは次の世代に何を訴えられるか、自分たちは何を受け継いできたのかが問われている。言葉だけではなく実践を通じて伝えていきたい。次世代に誇れる仕事をし、道なき荒野に道をつくっていきたい﹂と抱負を語った。 ︵中外日報情 2008年9月20日より︶
2008年10月26日
功の多少を計り 彼の来処を量る
 コーヒーを専門ショップで注文すると、大体1杯 330円くらい。
その売上げは
︵1︶コーヒー農家
︵2︶輸出業者、地元の貿易会社
︵3︶カフェ、小売業者、輸入業者
にそれぞれどれくらい配分されているのでしょうか。
コーヒーを専門ショップで注文すると、大体1杯 330円くらい。
その売上げは
︵1︶コーヒー農家
︵2︶輸出業者、地元の貿易会社
︵3︶カフェ、小売業者、輸入業者
にそれぞれどれくらい配分されているのでしょうか。
私たちがコーヒーを飲むときには、あまり頭に浮かばない問題ですね。 しかし、改めて考えてみると、消費者には生産者の姿がほとんどといって良いほど見えないことに気づかされます。 逆に、生産国のコーヒー農園で働く人にとって、目の前のコーヒーがどのように飲まれているかということを想像することも困難なことなのでしょう。 後に紹介する映画﹃おいしいコーヒーの真実﹄の中では、コーヒーを消費する先進国と、コーヒーの原産国の生活の光景とが同時進行で淡々と映しだされていきます。 同じコーヒーで結ばれた始点と終点の光景が、なぜ別世界となってしまっているのでしょうか。 その答えは ﹁私たちは経済的な援助ではなく公正な貿易取引を求めている﹂ というコーヒー生産国代表の言葉に集約されています。
例えば、コーヒー豆がエチオピアから輸入国の焙煎業者に渡るまでには、6業種ほどの中間業者が取引の段階に関わります。 各段階で、業者は利益を上るために、仕入れ単価を可能な限り下げようとします。 結果、産地農園の労働者たちは、日給0.5ドルという不当に安い価格で、しかもその状況に不信感すら抱くことも無く働かざるを得ない状況に追い込まれています。 エチオピアでは、緊急支援を必要とする人々が年間700万人も生み出されているともいわれます。 全世界で毎日20億杯も飲まれているコーヒーですが、飲まれれば飲まれるほど貧困を生み出すという構図です。 それを解決する手段の一つが公正な貿易取引、フェアトレードです。 きちんと生産者に正当な代価が届くシステムを作り上げることにより、問題は少しづつ解決の方向に進むはずです。 映画﹃おいしいコーヒーの真実﹄では、スターバックスが名指しで批判の対象にあげられていますが、スターバックスでもフェアトレード製品の選択肢があります。 ⇒︵例︶カフェ エスティマ ブレンド 敢えてこのようなコーヒーを選ぶのも必要な行動なのでしょう。
﹃おいしいコーヒーの真実﹄の予告編はこちら。 冒頭の答えもでてきます。
 流通の仕組みは国内でも同様です。
いくつもの市場などの段階を経て消費者に届く複雑な構造です。
サンマのような生鮮品の場合は特に流通業者は鮮度のリスクを考え、買入れ価格を安く抑える傾向にあります。
一尾50円のうち、漁業生産者に届くのはどれくらいなのでしょうか。
従来の流通の段階は
︵1︶水揚げ産地
︵2︶産地市場︵卸売業者⇒買受人︶
︵3︶消費者市場︵卸売業者⇒仲卸業者︶
︵4︶小売店
︵5︶消費者
流通の仕組みは国内でも同様です。
いくつもの市場などの段階を経て消費者に届く複雑な構造です。
サンマのような生鮮品の場合は特に流通業者は鮮度のリスクを考え、買入れ価格を安く抑える傾向にあります。
一尾50円のうち、漁業生産者に届くのはどれくらいなのでしょうか。
従来の流通の段階は
︵1︶水揚げ産地
︵2︶産地市場︵卸売業者⇒買受人︶
︵3︶消費者市場︵卸売業者⇒仲卸業者︶
︵4︶小売店
︵5︶消費者
でしたが、高度経済成長期以降、道路網の整備や冷凍技術の進歩、冷蔵庫施設の整備、そして都市部における大規模小売店の展開などにより変革が起きました。 消費地市場を経由しない﹁市場外流通﹂の仕組みです。
︵1︶水揚げ産地 ︵2︶産地市場 ︵3︶大規模小売店 ︵4︶消費者 市場外流通は、段階が削除されるため﹁安い﹂という先入観がありますが、しかし現状では価格が適正に生産者に届く仕組にはなっていないようです。 大規模小売店が出漁の前に予め価格を決定してしまい、そこには生産者の意思が反映する余地が無いからです。 実際に、漁業者が受け取る金額は、小売価格の24%程度にとどまっています。 私たちにできることは、さまざまな商品の値段を目にしたときに、その価格の内訳がどのようになっているかを考え、調べるという習慣をつけること、そして、生産者が見える商品や、フェアトレード製品を意識的に購入するという行動です。 その一つひとつの積み重ねが歪んだ流通構造に改革をもたらすかもしれません。

貞昌院本堂において、 クラフト・エイド(SVA)などのフェアトレード製品を展示・頒布しています。是非お手にとってご覧ください。
■おすすめの本
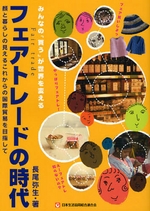
フェアトレードの時代 みんなの﹁買う﹂が世界を変える 顔と暮らしの見えるこれからの国際貿易を目指して
著者/長尾弥生/著 出版社名 日本生活協同組合連合会出版部 (ISBN‥978-4-87332-267-4) 発行年月 2008年04月 価格 1,365円︵税込︶
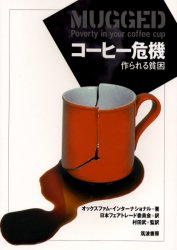 コーヒー危機 作られる貧困
著者/訳者名 オックスファム・インターナショナル/著 日本フェアトレード委員会/訳 村田武/監訳
出版社名 筑波書房 (ISBN‥4-8119-0238-6)
発行年月 2003年10月
価格 1,050円︵税込︶
コーヒー危機 作られる貧困
著者/訳者名 オックスファム・インターナショナル/著 日本フェアトレード委員会/訳 村田武/監訳
出版社名 筑波書房 (ISBN‥4-8119-0238-6)
発行年月 2003年10月
価格 1,050円︵税込︶
2008年10月 5日
原油高騰でもサンマは安値
以前、供物としてあげられる盛籠からマクロ経済の変化を考えた ことがありましたが、経済の変化を一番敏感に感じることができるのはスーパーの店内ではないでしょうか。
近年、特に今年に入ってからの原油の高騰は異常なほどでした。レギュラーガソリンの小売価格はリッターあたり200円間近にまで跳ね上がり、さまざまな影響をもたらしています。 第一次産業に与える影響も大きく、例えば水産業では、漁船に使う重油の価格高騰により、出漁できなかったり、その窮状を訴えるために組織的に出漁を取りやめたりといったことがニュースで流されました。
漁船の燃料を少しでも節約するため、集魚灯を点ける時間を制限したり、エンジンの回転数を下げ漁船の速度を落としエコ運転したりという努力も焼け石に水のようです。 政府は、燃料上昇分をいくらか補填する政策を打ち出しました。 しかし、そもそも大手小売スーパーにより価格が支配され、また、水揚げ直後にセリで価格付けされてしまうという、コスト上昇分を漁業従事者に反映できない流通のしくみを抜本的に改善しなければ、日本の水産業は壊滅的となってしまうでしょう。
昨日、地元のスーパーでのサンマの価格です。 消費者にとっては、新鮮な魚が安く購入できることは嬉しいのですが、漁業従事者の現状を考えると手放しに喜んでばかりはいられません。
この倍の価格でも十分安いでしょうし、その分を漁業従事者に還元できる仕組みができたらとつくづく思います。
かつては世界に誇る水産国であった日本でしたが、いまや魚介類の自給率は約60%。
日本は世界一の輸入国となってしまっています。
また、いつまでも輸入に頼るわけにも行かないでしょう。
農産物の例にもれず、水産物でも食の安全性に対する不安はありますし、それ以前に今後は﹁買い負け﹂により、輸入すらできないケースも増えていくことでしょう。
消費者にとっては、新鮮な魚が安く購入できることは嬉しいのですが、漁業従事者の現状を考えると手放しに喜んでばかりはいられません。
この倍の価格でも十分安いでしょうし、その分を漁業従事者に還元できる仕組みができたらとつくづく思います。
かつては世界に誇る水産国であった日本でしたが、いまや魚介類の自給率は約60%。
日本は世界一の輸入国となってしまっています。
また、いつまでも輸入に頼るわけにも行かないでしょう。
農産物の例にもれず、水産物でも食の安全性に対する不安はありますし、それ以前に今後は﹁買い負け﹂により、輸入すらできないケースも増えていくことでしょう。
水産業側は、漁船の低燃費化、漁業主体の大規模化が進み、消費者側は魚介類の消費量の低下、魚から肉主体の消費構造へと変化しています。 また、一時的には水産業全体の規模の縮小により、魚価が安定しているように見えています。 しかし、長期的にみると、この構図は持続しないはずです。 一消費者にできることは、まずは今安値のサンマをたくさんおいしく頂くことでしょうか。
■余談 ダイエット効果を期待してバナナは品薄。スーパーの棚にはまだ青いバナナも並ぶようになりました。 一本あたりの価格は、サンマ一尾の価格よりも高くなっています。 北海道産の餡子︵左2つ︶と中国産の餡子︵右2つ︶との価格差。
食の安全性と安値、どちらを選びますか?
北海道産の餡子︵左2つ︶と中国産の餡子︵右2つ︶との価格差。
食の安全性と安値、どちらを選びますか?

近年、特に今年に入ってからの原油の高騰は異常なほどでした。レギュラーガソリンの小売価格はリッターあたり200円間近にまで跳ね上がり、さまざまな影響をもたらしています。 第一次産業に与える影響も大きく、例えば水産業では、漁船に使う重油の価格高騰により、出漁できなかったり、その窮状を訴えるために組織的に出漁を取りやめたりといったことがニュースで流されました。
漁船の燃料を少しでも節約するため、集魚灯を点ける時間を制限したり、エンジンの回転数を下げ漁船の速度を落としエコ運転したりという努力も焼け石に水のようです。 政府は、燃料上昇分をいくらか補填する政策を打ち出しました。 しかし、そもそも大手小売スーパーにより価格が支配され、また、水揚げ直後にセリで価格付けされてしまうという、コスト上昇分を漁業従事者に反映できない流通のしくみを抜本的に改善しなければ、日本の水産業は壊滅的となってしまうでしょう。
昨日、地元のスーパーでのサンマの価格です。
 消費者にとっては、新鮮な魚が安く購入できることは嬉しいのですが、漁業従事者の現状を考えると手放しに喜んでばかりはいられません。
この倍の価格でも十分安いでしょうし、その分を漁業従事者に還元できる仕組みができたらとつくづく思います。
かつては世界に誇る水産国であった日本でしたが、いまや魚介類の自給率は約60%。
日本は世界一の輸入国となってしまっています。
また、いつまでも輸入に頼るわけにも行かないでしょう。
農産物の例にもれず、水産物でも食の安全性に対する不安はありますし、それ以前に今後は﹁買い負け﹂により、輸入すらできないケースも増えていくことでしょう。
消費者にとっては、新鮮な魚が安く購入できることは嬉しいのですが、漁業従事者の現状を考えると手放しに喜んでばかりはいられません。
この倍の価格でも十分安いでしょうし、その分を漁業従事者に還元できる仕組みができたらとつくづく思います。
かつては世界に誇る水産国であった日本でしたが、いまや魚介類の自給率は約60%。
日本は世界一の輸入国となってしまっています。
また、いつまでも輸入に頼るわけにも行かないでしょう。
農産物の例にもれず、水産物でも食の安全性に対する不安はありますし、それ以前に今後は﹁買い負け﹂により、輸入すらできないケースも増えていくことでしょう。
水産業側は、漁船の低燃費化、漁業主体の大規模化が進み、消費者側は魚介類の消費量の低下、魚から肉主体の消費構造へと変化しています。 また、一時的には水産業全体の規模の縮小により、魚価が安定しているように見えています。 しかし、長期的にみると、この構図は持続しないはずです。 一消費者にできることは、まずは今安値のサンマをたくさんおいしく頂くことでしょうか。
■余談 ダイエット効果を期待してバナナは品薄。スーパーの棚にはまだ青いバナナも並ぶようになりました。 一本あたりの価格は、サンマ一尾の価格よりも高くなっています。
 北海道産の餡子︵左2つ︶と中国産の餡子︵右2つ︶との価格差。
食の安全性と安値、どちらを選びますか?
北海道産の餡子︵左2つ︶と中国産の餡子︵右2つ︶との価格差。
食の安全性と安値、どちらを選びますか?

2008年8月 8日
元気をもたらす地域通貨(2)
日本の債務残高がリアルタイムに判る借金カウンター。
見ているだけで恐ろしくなります。
昨日︵8月7日︶、政府は月例経済報告における景気の基調判断を﹁弱含んでいる﹂へ下方修正しました。
景気は後退局面入りとなり、頼りになりそうな貿易黒字も、最近の急激な原油高により、さらに悪化することは間違いありません。
日本が保有する総資産である正味資産︵日本の土地、建物、金融資産、在庫、地下資源などの合計︶に対して、日本の借金は、その1/2に達するかどうかという所まで来ています。
抜本的な改革を早急に施さないと手遅れになります。
・・・暗い話題ばかりですが、話題を切り替えて、借金が﹁マイナス﹂の概念ととならない通貨のしくみをご紹介します。
それは﹁地域通貨﹂です。
地域通貨とは、一言で言えば﹁ある地域やコミュニティのみで流通する通貨﹂であります。 ﹁円﹂は、日本国内︵あるいは世界中)、﹁どこでも﹂﹁何とでも﹂交換可能ですが、そのような汎用性はありません。 けれども、それゆえに次のような特徴を持ちます。
■地域通貨の特長 ︵1︶地域やコミュニティーにより発行することができる。 ︵2︶ある地域やコミュニティのみでしか使えない。 ︵3︶利子はつかない。 ︵4︶貧富の格差が生じ難い ︵5︶地域の中で循環する仕組みのため、地域が活性化する。 現在は 300 を超える地域通貨が全国にあるといわれています。 一つの具体的な事例として、西千葉の地域通貨 ﹁ピーナッツ﹂を見てみましょう。 まずは、﹁ピーナッツクラブ﹂に入会します。 入会資格は、事業者であれば千葉県限定です。個人であればその括りはありません。 入会すると、通帳︵大福帳︶の発行を受けます。
通帳保有者の得意分野、提供できるサービスが登録され、カタログに掲載されます。 最初の通長記載残高は﹁0﹂。
サービスやモノの交換は、お互いの話し合いにより決定します。 AさんからBさんに○○を提供したから、BさんからAさんに○○ピー︵通貨単位︶を受渡すというような感じです。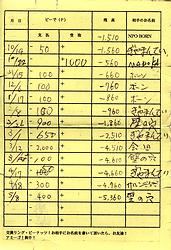

当初は、左のような手書きの﹁大福帳﹂に記載しておりましたが、現在では右のようなオンラインでの決裁が主流となっています。 サービス等を提供する側の人は﹁受取(+)﹂、受ける側は﹁支払(?)﹂。 お互いの大福帳を交換して﹁相手のお名前﹂欄にサイン、持ち主に戻したら・・・・・
最後に﹁アミーゴ!﹂と言いながら握手をして取引成立。

ここまで書いて、改めて地域通貨の仕組みは﹁お寺﹂に適切な通貨ではないかと感じます。 現在、お寺は﹁円﹂を中心として経済が成立っていますが、地域通貨では、お金をを払うようなことでないことに対してでも気軽に他人に頼めるし、例えば厚意でしていただいたことに対し、お金でお礼をすると失礼になるようなことでも、気兼ねなくお礼ができるということも特長です。 全国に曹洞宗の寺院は1万4千、宗派を超えると数万もの寺院があります。 寺院、檀家さん、地域住民の方々に通用する﹁地域通貨﹂を寺院で発行すれば、どれだけ影響力をもつか計り知れません。 寺院相互の遣り取りもそうですね。 お寺同士で随喜いただいたり、お手伝いいただいた際にも、地域通貨での遣り取りする仕組みをつくることは可能でしょう。
地域通貨とは、一言で言えば﹁ある地域やコミュニティのみで流通する通貨﹂であります。 ﹁円﹂は、日本国内︵あるいは世界中)、﹁どこでも﹂﹁何とでも﹂交換可能ですが、そのような汎用性はありません。 けれども、それゆえに次のような特徴を持ちます。
■地域通貨の特長 ︵1︶地域やコミュニティーにより発行することができる。 ︵2︶ある地域やコミュニティのみでしか使えない。 ︵3︶利子はつかない。 ︵4︶貧富の格差が生じ難い ︵5︶地域の中で循環する仕組みのため、地域が活性化する。 現在は 300 を超える地域通貨が全国にあるといわれています。 一つの具体的な事例として、西千葉の地域通貨 ﹁ピーナッツ﹂を見てみましょう。 まずは、﹁ピーナッツクラブ﹂に入会します。 入会資格は、事業者であれば千葉県限定です。個人であればその括りはありません。 入会すると、通帳︵大福帳︶の発行を受けます。
通帳保有者の得意分野、提供できるサービスが登録され、カタログに掲載されます。 最初の通長記載残高は﹁0﹂。
サービスやモノの交換は、お互いの話し合いにより決定します。 AさんからBさんに○○を提供したから、BさんからAさんに○○ピー︵通貨単位︶を受渡すというような感じです。
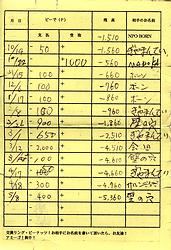

当初は、左のような手書きの﹁大福帳﹂に記載しておりましたが、現在では右のようなオンラインでの決裁が主流となっています。 サービス等を提供する側の人は﹁受取(+)﹂、受ける側は﹁支払(?)﹂。 お互いの大福帳を交換して﹁相手のお名前﹂欄にサイン、持ち主に戻したら・・・・・
最後に﹁アミーゴ!﹂と言いながら握手をして取引成立。

ここまで書いて、改めて地域通貨の仕組みは﹁お寺﹂に適切な通貨ではないかと感じます。 現在、お寺は﹁円﹂を中心として経済が成立っていますが、地域通貨では、お金をを払うようなことでないことに対してでも気軽に他人に頼めるし、例えば厚意でしていただいたことに対し、お金でお礼をすると失礼になるようなことでも、気兼ねなくお礼ができるということも特長です。 全国に曹洞宗の寺院は1万4千、宗派を超えると数万もの寺院があります。 寺院、檀家さん、地域住民の方々に通用する﹁地域通貨﹂を寺院で発行すれば、どれだけ影響力をもつか計り知れません。 寺院相互の遣り取りもそうですね。 お寺同士で随喜いただいたり、お手伝いいただいた際にも、地域通貨での遣り取りする仕組みをつくることは可能でしょう。
例えば↓このような感じ。
| 日 | 相手 | 内容 | + | - | 残高 | サイン |
| 8/1 | A寺 | 随喜謝誼 | +500 | - | +2500 | |
| 8/2 | Bさん | 境内清掃 | + | -300 | +2200 | |
| 8/2 | Cさん | 境内清掃 | + | -300 | +1900 | |
| 8/3 | Dさん | 原稿料 | +300 | - | +2200 | |
| 8/4 | Eさん | 犬の散歩 | + | -100 | +2100 | |
| 8/5 |
地域通貨のシステムでは、通帳に記載されている﹁黒字﹂や﹁赤字﹂は、特定の人に対する債務とはなりません。 地域通貨の流通するコミュニティー全体へのコミットメントでもあります。 ですから、地域通貨の﹁赤字が多い﹂ということは、それだけ、その人が地域の人から信頼を受けているということを示し、マイナスイメージということではありません。 そして、赤字が溜まったと思ったら、﹁自分にできること﹂で地域に還元すればいいのです。
私たちは、法定通貨が当たり前のように身の回りにあるため、その概念が当たり前であると思ってきました。 しかし、私たちは普段消費行動で使うお金と、世界中を駆け巡っている国際資本はあまりにもかけ離れすぎてしまっています。
﹁パン屋でパンを買うお金と、株式取引所で扱われる資本としてのお金とでは、まったくお金の種類が異なる・・・・﹂︵ミヒャエル・エンデ︶ 金融の自由化、市場経済のグローバリゼーションは、日本経済にバブル破綻と長引く不況を引き起こしました。 日本の借金は増え続け、失業率の増加、リストラ、地域の経済も危機に晒されています。 日本経済を崩壊から守る最後の手段、それは﹁地域通貨﹂なのかもしれません。
2008年6月 4日
共存する類似品
事務用品として重宝する輪ゴム。
文房具店で購入する際に気づくことは、どのパッケージもよく似ていること。
手元にある別メーカーのものを並べてみました。
 そっくりですね。
そっくりですね。
こういうのを類似品というのかどうかわかりませんが、どの市場においても、あるメーカーがヒット商品を開発すると、他の業者がわ?っと似たような製品を開発し、発売します。 はちみつレモンなんか酷かったですね。サントリーが発売し好調な販売を見せるや、似たようなパッケージが次々と発売され、自動販売機のほとんどのスペースがはちみつレモンになってしまっていた時期がありました。 そのうちに、オリジナル品と後続の類似品の競争が激化し、次第に飽きられて、いまでははちみつレモンを探すことすら難しい状況です。 詳しくはこちら おみやげ物の萩の月とか、テレビ番組などもそのような傾向は顕著です。 Googleで﹁類似品﹂を検索すると、そのような事例はいくらでも見つけられます。 さて、話を戻します。 輪ゴムのパッケージはこのように意匠がそっくりですね。 日本での輪ゴムは、協和というメーカーが﹁オーバンド﹂という製品で大きなシェアを占めています。 (c) Kyowa
(c) Kyowa
冒頭にご紹介した写真は、いわば亜流の製品です。 けれども、主流のオーバンドを含めてパッケージがそっくり。 これはこれで、類似品の共存関係がうまく成り立っている珍しい例ではないかと思われます。 輪ゴムは、消費量が増減する製品ではありません。 また、店頭に並べられたとしても、2社以上の製品が並べられることはないでしょう。 メーカーにとっては、消費者が﹁輪ゴム﹂であるということを認識しやすく見つけやすい方がプラスになるわけです。 輪ゴムのパッケージ=茶色と黄色というイメージが無意識に刷り込まれてしまっているわけですから。 ︵文末に追記あり︶
似たような類似品の共存事例として、﹁赤福﹂があります。 伊勢へ行くと御福餅、名福餅、名福餅、 伊賀福、 栗福餅、伊予福、伊勢遷宮福餅・・・・ 似たようなお菓子がずらりと並んでいます。 これも、地元に強大な影響力を持ち、幅広く支持されている︵偽装問題でイメージダウンしましたけれど︶﹁赤福﹂ならではの一強+恩恵にあずかるその他という関係なのでしょうか。 輪ゴムのパッケージから少し考えてみました。
追記 輪ゴムのパッケージが共存する・・・・と記事中で書きましたが、あまりに酷い事例は訴訟問題になっているようですね。 ◆No.358︵2000年7月11日判決︶ 大阪地裁は、﹁オーバンド﹂の商標で知られる輪ゴムの最大手メーカーの︵株︶共和の商標権を侵害するとして、﹁スーパーバンド﹂の文字を含むパッケージデザインの商品を販売したシモジマ商事に対して、損害賠償金2,800万円の支払いを命じた。︵H10︵ネ︶5161︶ http://www.ntspat.co.jp/pnr/so_2000_07.htm ということは、今回ご紹介した事例はグレーに近いシロという感じなのでしょうか。 それともシロに近いグレーなのか?
 そっくりですね。
そっくりですね。
こういうのを類似品というのかどうかわかりませんが、どの市場においても、あるメーカーがヒット商品を開発すると、他の業者がわ?っと似たような製品を開発し、発売します。 はちみつレモンなんか酷かったですね。サントリーが発売し好調な販売を見せるや、似たようなパッケージが次々と発売され、自動販売機のほとんどのスペースがはちみつレモンになってしまっていた時期がありました。 そのうちに、オリジナル品と後続の類似品の競争が激化し、次第に飽きられて、いまでははちみつレモンを探すことすら難しい状況です。 詳しくはこちら おみやげ物の萩の月とか、テレビ番組などもそのような傾向は顕著です。 Googleで﹁類似品﹂を検索すると、そのような事例はいくらでも見つけられます。 さて、話を戻します。 輪ゴムのパッケージはこのように意匠がそっくりですね。 日本での輪ゴムは、協和というメーカーが﹁オーバンド﹂という製品で大きなシェアを占めています。
 (c) Kyowa
(c) Kyowa
冒頭にご紹介した写真は、いわば亜流の製品です。 けれども、主流のオーバンドを含めてパッケージがそっくり。 これはこれで、類似品の共存関係がうまく成り立っている珍しい例ではないかと思われます。 輪ゴムは、消費量が増減する製品ではありません。 また、店頭に並べられたとしても、2社以上の製品が並べられることはないでしょう。 メーカーにとっては、消費者が﹁輪ゴム﹂であるということを認識しやすく見つけやすい方がプラスになるわけです。 輪ゴムのパッケージ=茶色と黄色というイメージが無意識に刷り込まれてしまっているわけですから。 ︵文末に追記あり︶
似たような類似品の共存事例として、﹁赤福﹂があります。 伊勢へ行くと御福餅、名福餅、名福餅、 伊賀福、 栗福餅、伊予福、伊勢遷宮福餅・・・・ 似たようなお菓子がずらりと並んでいます。 これも、地元に強大な影響力を持ち、幅広く支持されている︵偽装問題でイメージダウンしましたけれど︶﹁赤福﹂ならではの一強+恩恵にあずかるその他という関係なのでしょうか。 輪ゴムのパッケージから少し考えてみました。
追記 輪ゴムのパッケージが共存する・・・・と記事中で書きましたが、あまりに酷い事例は訴訟問題になっているようですね。 ◆No.358︵2000年7月11日判決︶ 大阪地裁は、﹁オーバンド﹂の商標で知られる輪ゴムの最大手メーカーの︵株︶共和の商標権を侵害するとして、﹁スーパーバンド﹂の文字を含むパッケージデザインの商品を販売したシモジマ商事に対して、損害賠償金2,800万円の支払いを命じた。︵H10︵ネ︶5161︶ http://www.ntspat.co.jp/pnr/so_2000_07.htm ということは、今回ご紹介した事例はグレーに近いシロという感じなのでしょうか。 それともシロに近いグレーなのか?
2008年5月 2日
元気をもたらす地域通貨
アウキ・ティトゥアニャ知事により、エクアドルを元気付けている地域通貨の事例が紹介されました。
エクアドルでは、2000年に国家通貨であった﹁スクレ(ECS)﹂を廃止して、米ドル化を行いました。
しかし、物を売りたい人、欲しい人がいても、遥か遠くの国で発行されたドルが無いというだけの理由で、売買が成立しないという混乱が生じ、その頃草の根で始まっていた地域通貨﹁シントラル(SINTRAL)﹂はドル化後の経済混乱※の中で着実に広まっていきました。
※2008/5/1現在、1.00 米ドル (USD) = 25000 エクアドル スクレ (ECS) ひぇ?!
エクアドルにおける地域通貨の仕組みは非常にシンプルです。 ・そこに住む地域の人が、地域通貨の仕組みを共有する ・地域住民が通貨を発行、供給する ・住民同士が直接売買を行い、その際小切手にサインする ・小切手は地域通貨の窓口で遣り取りが登録、全体情報を提供 というものです。
所詮、米国の発行するドルは﹁紙﹂だけにすぎません。 例えば、このお寺の本堂に集まっている人たちのグループが幾つかあるとして、それぞれにコメ、金、太陽・・・などの名前を付けます。 シンプルなチケットを作り、一つを一ドル相当と決め、あるグループがあるグループから魚を買い、また或いは他のグループがコメを買い・・・ ここで重要なことは、購入・売買は直接的であり、しかも税金がかからないという点にあります。 もちろん、金利もつきません。 コタカチ郡では、毎月、地域通貨により大体6万ドル相当規模の経済活動が地域通貨により行われています。 一年間では6万ドル×12ヶ月=72万ドル規模。
政府は税金が取れない地域通貨の仕組みを弾圧しないのか?という質問には、﹁禁止もしないし支援もしない﹂とのこと。 さらに、コタカチ郡では逆に地域通貨を支援、例えば物品がトラックでスムーズに運べるように便宜を図ってすらいます。
先進国では、いわば﹁足し算﹂の経済の考えが常識です。 つまり、月10万円で生活してきたものが15万円になれば豊かになり、それが﹁進歩﹂だと考えてきました。 しかし、地域通貨の考えは﹁引き算﹂の経済です。 地域通貨を用いることにより15万円の生活であったものを10万円に減らすことが出来ることが﹁進歩﹂だと考えるのです。
最後に、とっておきの新しい情報が披露されました。 それは、現在、エクアドルでは、地域通貨の単位として﹁シントラル(SINTRAL)﹂ではなく﹁エコシミア︵ECOSIMIA)﹂を用いているということです。
経済を意味するエコノミア(ECONOMIA)には、否定を意味する"No"が含まれています。 そこで、この"No"を、肯定の"Sí"に入替えて、エコシミア︵ECOSIMIA)としたのです。 粋な言葉遊びですね。 しかし、南米の凄いところは影響しあうということです。 この地域通貨の考え﹁エコシミア︵ECOSIMIA)﹂にはベネズエラの大統領も共感し、この地域通貨のアイデアを是非取り入れたいと表明しているとのことです。 人と人がお互い繋がりながらお互い活かし合い生活を営んでいくという、エコシミア︵ECOSIMIA)の考えこそが、本来の経済のありかたなのかもしれません。
﹁僕たちは、ファストな社会に生きています。いわゆる、“早い者勝ち”の社会。速さをめぐって競い合うと、人間と自然との間の、そして人間同士の繋がりが絶たれ、その結果、環境破壊や、地球温暖化、紛争や戦争が起こってきた。“スロー”というのは、もう一度その失われた繋がりを取り戻せるところまでスローダウンしよう、という意味です。ぼくたちは、自然界との繋がり、人々との繋がりやコミュニケーションなしに生きていけない存在です。またその繋がりこそが歓びであり、生き甲斐ですよね﹂ ︵辻信一先生のことばより︶
地元戸塚で﹁オーエン﹂という地域通貨を実験的に発行し、実績を重ねている善了寺︵今回会場となった寺院︶の住職さんと、全国に7万以上ある寺院が繋がって地域通貨を作ったら、きっと仏教界は檀信徒の皆さんを含めて、もっともっと元気になるでしょうね、という話で盛り上がりました。
通貨の単位は﹁縁﹂で。
■関連資料
全国地域通貨リスト
エクアドルにおける地域通貨の仕組みは非常にシンプルです。 ・そこに住む地域の人が、地域通貨の仕組みを共有する ・地域住民が通貨を発行、供給する ・住民同士が直接売買を行い、その際小切手にサインする ・小切手は地域通貨の窓口で遣り取りが登録、全体情報を提供 というものです。
所詮、米国の発行するドルは﹁紙﹂だけにすぎません。 例えば、このお寺の本堂に集まっている人たちのグループが幾つかあるとして、それぞれにコメ、金、太陽・・・などの名前を付けます。 シンプルなチケットを作り、一つを一ドル相当と決め、あるグループがあるグループから魚を買い、また或いは他のグループがコメを買い・・・ ここで重要なことは、購入・売買は直接的であり、しかも税金がかからないという点にあります。 もちろん、金利もつきません。 コタカチ郡では、毎月、地域通貨により大体6万ドル相当規模の経済活動が地域通貨により行われています。 一年間では6万ドル×12ヶ月=72万ドル規模。
政府は税金が取れない地域通貨の仕組みを弾圧しないのか?という質問には、﹁禁止もしないし支援もしない﹂とのこと。 さらに、コタカチ郡では逆に地域通貨を支援、例えば物品がトラックでスムーズに運べるように便宜を図ってすらいます。
先進国では、いわば﹁足し算﹂の経済の考えが常識です。 つまり、月10万円で生活してきたものが15万円になれば豊かになり、それが﹁進歩﹂だと考えてきました。 しかし、地域通貨の考えは﹁引き算﹂の経済です。 地域通貨を用いることにより15万円の生活であったものを10万円に減らすことが出来ることが﹁進歩﹂だと考えるのです。

最後に、とっておきの新しい情報が披露されました。 それは、現在、エクアドルでは、地域通貨の単位として﹁シントラル(SINTRAL)﹂ではなく﹁エコシミア︵ECOSIMIA)﹂を用いているということです。
経済を意味するエコノミア(ECONOMIA)には、否定を意味する"No"が含まれています。 そこで、この"No"を、肯定の"Sí"に入替えて、エコシミア︵ECOSIMIA)としたのです。 粋な言葉遊びですね。 しかし、南米の凄いところは影響しあうということです。 この地域通貨の考え﹁エコシミア︵ECOSIMIA)﹂にはベネズエラの大統領も共感し、この地域通貨のアイデアを是非取り入れたいと表明しているとのことです。 人と人がお互い繋がりながらお互い活かし合い生活を営んでいくという、エコシミア︵ECOSIMIA)の考えこそが、本来の経済のありかたなのかもしれません。
﹁僕たちは、ファストな社会に生きています。いわゆる、“早い者勝ち”の社会。速さをめぐって競い合うと、人間と自然との間の、そして人間同士の繋がりが絶たれ、その結果、環境破壊や、地球温暖化、紛争や戦争が起こってきた。“スロー”というのは、もう一度その失われた繋がりを取り戻せるところまでスローダウンしよう、という意味です。ぼくたちは、自然界との繋がり、人々との繋がりやコミュニケーションなしに生きていけない存在です。またその繋がりこそが歓びであり、生き甲斐ですよね﹂ ︵辻信一先生のことばより︶
2008年1月19日
再生紙問題ー製紙業界に走る激震
有力6社で再生紙偽装 印刷用紙など幅広く製紙メーカーが年賀はがきやコピー用紙の古紙配合率を偽装していた問題に関連し、三菱製紙、大王製紙、北越製紙の三社は十八日午後、社長らが相次いで記者会見し、はがきやコピー用紙など幅広い品目で実際の古紙配合率が公表値を下回っていたとする社内調査結果を発表し、謝罪した。また、中越パルプ工業も同日夜、印刷用紙や包装紙などで偽装を行っていたことを認めた。これにより既に偽装を公表していた日本製紙グループ本社、王子製紙を合わせ有力六社がそろって偽装を続けてきたことが明確になった。 日本製紙の社長は辞任の意向を示しているが、日本製紙以外で会見した四社の社長は辞任を否定した。 会見で各社は“業界ぐるみ”の様相を呈してきた再生紙の偽装について、激しい受注競争を背景に、営業を優先するあまり古紙利用と事実の公表をおろそかにした業界の体質などが影響したことを説明した。 偽装していた六社の紙全体の生産量のシェアは、合計で約80%︵二〇〇六年︶に達する。 しかし、偽装に手を染めた各社との取引を見合わせる動きも広がっており、今後、消費の現場に混乱を及ぼす恐れがある。 調査結果によると、三菱製紙は調査した二十品目中十一品目で偽装があった。環境に配慮した製品の購入を国などに義務づけたグリーン購入法に基づき、納入する全製品が公表値を下回っていた。公称100%の古紙配合率のコピー用紙︵月産六百九十二トン︶が実際は50%だった。 大王製紙も古紙配合率100%としていたコピー用紙の実際の配合率は41%だった。北越製紙はグリーン購入法対象の印刷用紙で公称配合率70%に対して実際は19%だった。 ︵東京新聞2008年1月19日 朝刊︶日本製紙、古紙の配合率を契約より低く・年賀再生紙はがき 日本製紙は9日、古紙を使った﹁年賀再生紙はがき﹂用紙の古紙配合率が契約で取り決めた水準を大きく下回っていたと公表した。契約では古紙を40%使うとしていたが、実際は﹁1―5%程度﹂︵同社︶にとどめていたという。日本製紙は40%の古紙配合率では十分な品質を確保できないと判断。配合率を引き下げていた。(日経新聞︶
昨年、再生紙・非木材紙は本当に環境にやさしいか という記事の中で、グリーン購入法と再生紙の問題について書きました。 去年一年は﹁偽﹂という一字に象徴された年だったようですが、年を越えてなおこのような問題が明るみになるということが残念です。 まだまだ発覚していない﹁偽﹂はたくさんあるのでしょう。
さて、昨年の記事での結論のうち、再生紙については、古紙100%使用の再生紙についての疑問を提示しました。 その際の結論の一つが
結論︵2︶ 紙の原料のうち、木材パルプについては、 環境的持続可能性︵生物多様性の維持、生態的プロセスや生態系の保全︶、 社会的持続可能性︵森林に依存している人間社会の維持︶、 経済的持続可能性︵継続的な木材生産と健全な森林経営︶ などを念頭において生産されることが必要であり、また、紙の使用目的に応じて、それぞれの古紙の配合率を考え、その中で全体として古紙配合率を高める︵決して100%ではない︶ことこそが、環境にやさしい紙であると言うことができるでしょう。
というものでした。 そもそも、古紙100%配合の再生紙そのものが環境に優しいわけではないし、しかも技術的にほぼ不可能であるというのに、グリーン購入法で古紙100%の再生紙購入を義務付けるという馬鹿げた構図が引き起こした偽装体質であると言わざるを得ません。 まずは日本製紙のプレスリリースを見てみましょう。 News Release 日本製紙 2008 年1月16日 弊社製品に関する社内調査結果について このたび、弊社が再生紙として製造している製品における古紙パルプ配合率について、全製品を対象にして調査した結果、決められた配合率を下回っている製品が葉書以外にも判明しました。その内容は別紙のとおりであり、それらの中には、グリーン購入法の基準を満たしていない製品もあります。弊社といたしましては、環境問題が国民の主要な関心事となっている今日、国民の皆様の信頼を裏切ってしまった事実を深刻に受け止め、ここに深くお詫び申し上げます。 このような事態を引き起こしました背景には、古紙パルプの配合率を上げることにより、再生紙の使途に求められる品質を実現することが、現状の弊社の技術レベルでは困難であるという問題があります。
当初から出来ないことがわかっていた訳です。
これまで弊社は、古紙は貴重な資源であるとの認識に立ち、古紙活用の最大化を技術的な課題として努力してまいりました。しかしながら、特定の古紙パルプ配合製品に求められる品質上の問題への対応に苦慮し、その結果、古紙パルプ配合率を下げることによって求められる品質の実現を優先させてしまいました。 環境意識の高まりにより社会からの要求が技術的に困難なレベルのものを要求されるようになり、品質を下げるよりは偽装を選んだということです。 しかしながら、このような論理がわかりません。 まったく釈明にもなりません。 古紙100%の再生紙を作ってみて、コストはこれだけ高くなります、品質はこれだけ落ちますということを素直に提示するべきでした。 それにより、グリーン購入法がいかに馬鹿げた現実離れした法律かがわかりますから。 こうした判断と行為は、これまで日本政府や組織団体、そして多くの国民の皆様が意識を持って取り組んでこられた環境保全に対する活動に水を差すものであり、たとえ﹁環境偽装﹂と言われたとしてもこれを否定できるものではありません。どんな理由があるにせよ決して許されない行為であります。 決して許されないでしょう。
結果として多くの皆様の善意を踏みにじることになってしまいましたことに対し深く反省するとともに、このような結果になってしまいましたことを重ねてお詫び申し上げます。経営責任につきましても、この事態を重く受け止め、原因の究明、責任の所在等、全容が明らかになった段階で、あらためて発表させていただきます。 今後の弊社の取り組みといたしましては、二度とこのようなことが起きないよう、再発防止体制とコンプライアンスの徹底を、外部の識者を交え実現させてまいります。また、古紙活用の最大化を目指し技術開発に取り組んでいくことはもちろんのこと、バランスを考えて古紙を上手に無理なくたくさん使う取り組みを進めてまいります。紙の用途に応じて、求められる白さや保存性を考慮した上で最適な古紙パルプの配合に努め、全体として古紙利用量を増やしていきたいと考えております。 このような弊社の取り組みを、お取引先及びお客様をはじめ、関係者の皆様にご理解いただけるよう、今後あらためて努力してまいります。
古紙100%の再生紙は、今後、ほぼ生産されなくなるでしょう。 そうなった場合、グリーン購入法はどうなるのでしょうか。 そもそも、再生紙の定義って何ですか? 日本製紙の実態調査の結果も余りにも酷いです。
年賀葉書は、殆んどが再生紙はがきです。 その古紙パルプ配合率の仕様基準は、化学パルプ60%、古紙パルプ40%とのことですが、実際の古紙パルプ配合率の実績は、今年平成成20年用の年賀葉書きで実に1% 。これでは古紙パルプの配合を行っていませんでしたと言っているのとほぼ同じです。 なお、年賀葉書は平成8年用から再生紙化されていますが、それぞれ5%以下︵1%?5%︶とのことです。 ■日本製紙の言い訳 葉書用紙が再生紙化された平成4年当時、工場内発生損紙も古紙として認識し、古紙パルプ6%と合わせた30%でテスト生産した結果、近い将来の技術革新で配合率40%の実現が可能と営業判断し受注を開始しました。その後、工場内発生損紙が古紙パルプとして認められないことがわかり、本来は古紙パルプを増配すべきところ、古紙由来のチリ、墨玉等の夾雑物が多くなるため品質を確保することができずに、古紙パルプ配合率が低いまま生産しておりました。それ以降、現在に至るまで配合率を上げるべく操業努力してまいりましたが、入荷する古紙の品質低下、異物混入に対する品質管理要望が高まり、配合率は上記の通り乖離しておりました。 それでは、コピー用紙などはどうでしょう
年賀葉書以外の製品について ︵1︶古紙パルプ配合率の基準と実績 現在生産を行なっている、古紙パルプ配合率の基準が設定されている製品のうち、コピー用紙などの製品に、残念ながら、基準と実績との間に乖離が確認されました。 再生紙として生産している銘柄 (生産量‥H19年10月?12月︶ (1)グリーン購入法対象品 情報用紙 コピー用紙 公称100% ⇒ 実際の配合率 59% 月生産量 6,540t (2)グリーン購入法適用以外の再生紙 ?情報用紙 コピー用紙 公称 100%・70% ⇒ 実際の配合率 11% 月生産量4,415t グリーン購入法を対象とする製品で基準に満たない製品があります。これらの製品につきましては、当社ブランド品については、直ちに生産を中止することとします。 また、お客様のOEMブランド品、および特定のビジネスユーザー向けの製品(特抄品)で、当初の交渉において取り決めた古紙パルプ配合率から乖離が出ているものがあります。それぞれのお客様に至急ご相談申し上げ、誠意ある対応をしてまいります。 また、付表にある、過去に生産した在庫品につきましても、お客様に至急ご相談申し上げ、誠意ある対応をしてまいります。
誠意ある対応として、古紙100%の再生紙と交換する・・という対応は考えられないですね。 生産できないわけですから。 とすると、品質の良いバージンパルプ100%の紙と交換するとか︵皮肉︶・・・・ ■日本製紙の言い訳 ?印刷用紙 製品の発売当初(平成11年ごろ)は、配合基準に合わせて古紙パルプを配合しておりましたが、古紙の品質低下により、製品品質として求められる夾雑物の基準を維持することができなくなる場合もありました。これまで古紙処理技術の改善等に努めてまいりましたが、古紙パルプの配合が基準未達となるケースが発生しました。 ?情報用紙、包装紙他 平成2年ごろより、リサイクル推進の観点から、コピー用紙の再生紙化を進めておりましたが、この時点では、古紙パルプ配合率の増加を努力目標としてとらえておりました。しかしながら、平成13年にグリーン購入法が施行された以降も依然として努力目標として考えており、同法の趣旨に関する理解が不足しておりました。 一方で、当初より求められる品質レベルが高かったため、古紙パルプ配合率を上げるのが容易ではないという事情がありました。その間にも、古紙パルプ配合率を増加させる努力は継続してまいりましたが、それでも、近年、消費者の皆様が保有している昨今の多種多様な出力端末機器や、その用途に対しさらに高い品質レベルが求められるようになり、加えて入荷する古紙の品質が低下するなどといった問題を抱えるようになったため、結果として古紙パルプ配合率を上げることができませんでした。その他の紙についても、同様な理由です。 3.再発防止策と今後の対応 年賀葉書だけでなく、それ以外の製品における古紙パルプ配合率が、決められた基準と乖離していた事実は、多くの国民の皆様の信頼を踏みにじる行為であったと深く反省しております。乖離を生じている再生紙製品の生産につきましては、弊社ブランドの古紙パルプ配合率の乖離品については、弊社として生産および販売の中止を指示いたしました。また、当該製品に関する一切の受注を中止いたしました。今後、乖離品の製造はいたしません。
古紙100%の再生紙はもう私たちの目にすることができない幻の紙になってしまったようです。
せっかくの機会ですから、新しい古紙100%マークを作ってみました。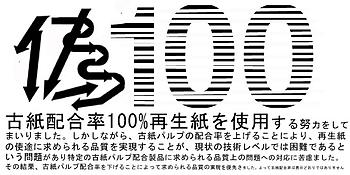
関連記事 再生紙・非木材紙は本当に環境にやさしいか
2008年1月 8日
寺と墓-誰も知らない巨大ビジネス
今日発売された ﹃週刊ダイヤモンド﹄ ︵ダイヤモンド社︶ が目に留まりました。
・特集 誰も知らない巨大ビジネス
寺と墓の秘密
多くの日本人の心に深く根づいている仏教。その根幹となる﹁寺﹂と﹁墓﹂の秘密を、この特集ではあえてビジネスの側面でとらえた。不謹慎とご批判を浴びるのは承知のうえで、現状の分析や問題点の指摘、将来の考察など、﹁寺﹂と﹁墓﹂の不思議な世界を多角的な観点から展開している。

なかなか読み応えのある特集です。 このような内幕は、これまでは﹃寺門興隆﹄などのような専門誌などで扱われてはきましたが、一般的にはなかなかその経済的な構造の全容は伝えられていないことが多かったはずです。 それゆえ、漠然と﹁坊主丸儲け﹂などと揶揄されたり、何だかわからないけれど触れてはならない聖域のように思われている部分もあったのだろうと思います。 表紙には ■お寺7万6000カ所、僧侶31万人が稼ぎ出す総額1.1兆円市場の全貌 ■檀家制度の形骸化で二極化が進むお寺経営の明と暗 ■10年間の盛衰がわかる全国153仏教宗派別﹁信者増減率ランキング﹂ ■なんと粗利4割!?霊園開発儲けのカラクリ教えます ■いざというときに迷わない正しいお墓の選び方 という文言が並びます。 さっそく読んでみました。 まずは、P28-29 見開きの﹁寺を取り巻く市場相関図﹂。 全国7万6000カ寺を中心に﹁仏壇・仏具店﹂﹁石材店﹂﹁墓地・霊園事業﹂﹁観光事業﹂﹁副業その他﹂﹁葬祭業﹂が密接に結びつき、そこに﹁檀家・信者・非信者﹂が経済的にどのようにかかわっているかという図式が描かれています。 この図式がすべての寺院に当てはまるわけではないことをご理解ください。
︻﹁寺﹂編︼ ■寺ビジネスの全貌?繁栄支えた檀家制度が形骸化 1.1兆円市場の厳しい現実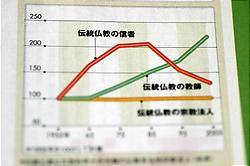 (P28)
伝統仏教の信者は1955年を100とすると、1975年頃には200を越えましたが、1985年から急減し続けています。対し、寺院数は横ばい。
この数字が正しいとすると、まともに影響を受けるのは、都会に比べて信仰心の篤い地方であり、かつ高齢化・過疎化の進む地域の寺院です。
したがって、現在は二極的構造が進んでいるのですが、やがてこの流れが全体を覆いかねないと警告します。
さらに興味深いのがP32にある宗教法人の売買価格算定方法、つまり宗教法人の経済的価値の算定です。
基本価格5000万円+所有不動産価値、これにプラス査定として﹁宗派に属さない単立法人﹂﹁都会にある﹂、マイナス査定として﹁離脱が困難な宗派に所属﹂﹁地方にしか拠点が無い﹂﹁信者がない﹂という基準です。
所属宗派がプラス査定マイナス査定にかなり影響があるようです。
(P28)
伝統仏教の信者は1955年を100とすると、1975年頃には200を越えましたが、1985年から急減し続けています。対し、寺院数は横ばい。
この数字が正しいとすると、まともに影響を受けるのは、都会に比べて信仰心の篤い地方であり、かつ高齢化・過疎化の進む地域の寺院です。
したがって、現在は二極的構造が進んでいるのですが、やがてこの流れが全体を覆いかねないと警告します。
さらに興味深いのがP32にある宗教法人の売買価格算定方法、つまり宗教法人の経済的価値の算定です。
基本価格5000万円+所有不動産価値、これにプラス査定として﹁宗派に属さない単立法人﹂﹁都会にある﹂、マイナス査定として﹁離脱が困難な宗派に所属﹂﹁地方にしか拠点が無い﹂﹁信者がない﹂という基準です。
所属宗派がプラス査定マイナス査定にかなり影響があるようです。
■Column 檀家300軒が採算ライン?税制面の優遇は盛りだくさん ﹁住職は寺の経営者であってオーナーではない。寺から給料をもらって生活しているのだ。だが、実際は寺の収入と住職一家のサイフがどんぶり勘定になっていることが少なくない。そして、現実には住職や家族が先生をやって、給料を生活費に充てていることも珍しくないのだ﹂︵p33より︶ この部分は、実際にそういうことがあるとすれば、一番の問題になるところです。やはり、会計上の流れは明確にしておかなければなりません。 P33には宗教法人税制の優遇制度に関する実例がわかりやすく描かれていますが、私たちは寺院会計において、宗教収入がなぜ非課税とされるのか。また、収益事業収入がなぜ公益法人として税制が優遇されているのか。そのあたりもよく胆に銘じておく必要があるでしょう。 公益性が明確にできないのであれば、税制の優遇制度も返上するくらいの心持ちでいたほうが良いのかもしれません。 この税制の恩恵を一番享受しているのは巨大新宗教団体です。
■お坊さんはつらいよ?生活支える読経アルバイト 住職になれない僧侶が増加中 ﹁僧侶の世界は嫉妬の世界。変化を嫌い、出る杭を打とうとする。寺の世界は一種独特の閉鎖的な世界だ﹂(P34) 実に辛辣なことばです。かつては、寺の僧侶は先進的に印刷技術や土木技術、建築技術、食文化などの最先端を導いてきたはずです。何時から変化を嫌うようになってしまったのでしょうか。確かに伝統的に護持し受嗣いでいかなければならない部分はあります。けれども、変わらなければならない、変えていかなければならない部分もあるでしょう。 むやみに社会に迎合することは必要ないと思います。むしろ社会を導く原動力になり文化の発信の源になるというくらいの心構えを持っていて良いかと思います。
■改革寺の挑戦?没落寺ばかりではない! 経営盤石な“元気印”を一挙紹介 まあ、この項は、こんな事例もあるのかな?という感じで読ませていただきました。
■緩む宗派のタガ?愛想尽かした末寺が“反乱” 疲弊するフランチャイズ制度 包括法人と非包括法人の関係、本山・末寺の関係です。 宗費賦課金を包括法人に拠出し、僧侶資格付与や布教支援を受けるという関係です。 宗派というブランド力の低下により、宗費についてどのように考えていくのかという項ですが、ここは、特に曹洞宗を中心に取材を行ってるようで、宗費賦課金の計算方法や記事の内容も曹洞宗の内容に沿った形で書かれています。 ﹁賦課金の決め方には自己申告項目があり、末寺は虚偽申告をすることで賦課金を安くする傾向が強く、ここにも不公平感が強まっていた。そこで曹洞宗は賦課金制度を07年度から変更し、地域補正、県民所得補正を取り入れた、より正確で実情に合った査定方により負担感の強かった地方に対する改善も実施した﹂︵P42) 宗費賦課金の算定方式は、曹洞宗が一番細かく複雑な方法をとっています。それゆえ、わかりづらいという声も多いことも確かです。 いかに公平に、いかにわかり易く・・・というのが永遠の課題であると思います。 ところで、P42の賦課金の計算方法の図ですが、間違いがあります・・・ダイヤモンドさん。
■Ranking 仏教宗派別の信者増減率ランキング これは実に興味ある表です。 是非一読ください。 曹洞宗がデータ不足で増減の計算ができていないのが残念ですが、その理由は明確です。 一つ前の項目で書きましたので敢えて書きませんが。
︻﹁墓﹂編︼ ■霊園開発のからくり?宗教法人も名義貸しで協力 石材店の粗利はなんと4割!? このあたりは、かつてはタブーとされていた領域ですね。 いかに利権が絡んだ世界であるかが明確にわかると思います。 もはや墓地は檀信者を引き止める手段とはなりえなくなっています。 改葬方法の具体的手続きチャート図(P56)が私たちにとっては一番の脅威であり、心しておく必要がある部分と言えるでしょう。 ■Column 消費者を手玉に取る石材店の墓石販売の手口 正しい墓の選び方?どこにどんな墓をつくるのか 今だからこそじっくり考えよう ■Chart お墓選びのフローチャート 公営霊園 安くても供給量や遺骨など条件厳しい 民営霊園 選択肢は幅広い ポイントは絞り込み ■Column バチ当たりか、人助けか 拡大する墓参り代行ビジネス 寺院墓地 交通至便がメリット 金銭面では高めに ■墓石の選び方 最大のカギは信頼できる石材店探し 永代供養墓 ﹁家﹂にこだわらず後に憂いを残さない 納骨堂 墓不足背景に増加 ネットで進化著しい 自然葬 樹木葬から散骨、宇宙葬まで種類豊富 ■改葬の方法 住職の理解が不可欠 費用も覚悟がいる
今号の﹃週刊ダイヤモンド﹄は、僧侶にとっても、関連業者の方にとっても、お寺の檀家さんにとっても、どのお寺にも属していない方にとっても一読の価値のある特集だと思います。 こういう内容を一部の業界の中の暗黙の了解にしておくことは、長い目で見れば決して良いことではないでしょう。 明確にするべきことは明確にし、少なくとも収益事業収入については完全に透明性のあるものとする必要があるはずです。 経済学は、最大多数の最大幸福の実現を目標とします。そのために限られた資源をどのように配分すれば人々の満足が高まるかを考察します。 対し、仏教は欲を制するという発想の転換を提示します。 経済活動に係わる世間と、菩薩行を実践する世界という異なる概念を強引に一致させる必要はないでしょう。両者をバランスをとらせつつ問題点があれば真摯に取り組み改善していかなければ寺院の将来は明るくないといえるでしょう。 逆に言えば、真摯に取り組み、改善していくことのできる寺院のみが生き残っていくのでしょう。 そして、もう一つ付け加えるとすれば、﹁改革寺の挑戦﹂の項にあるようなことまでは行う必要はなく、ただ行うべきことを行うことだけで充分であると感じます。
まあ、あまり内容をネタバレさせてもいけませんので、書店やコンビ二などで是非読んでみてください。 皆さまはどのようにお感じになったでしょうか。
■関連リンク
貞昌院檀信徒向け情報
寺院の果たすべき社会的責任
寺院の数はコンビニの数よりもずっと多い

なかなか読み応えのある特集です。 このような内幕は、これまでは﹃寺門興隆﹄などのような専門誌などで扱われてはきましたが、一般的にはなかなかその経済的な構造の全容は伝えられていないことが多かったはずです。 それゆえ、漠然と﹁坊主丸儲け﹂などと揶揄されたり、何だかわからないけれど触れてはならない聖域のように思われている部分もあったのだろうと思います。 表紙には ■お寺7万6000カ所、僧侶31万人が稼ぎ出す総額1.1兆円市場の全貌 ■檀家制度の形骸化で二極化が進むお寺経営の明と暗 ■10年間の盛衰がわかる全国153仏教宗派別﹁信者増減率ランキング﹂ ■なんと粗利4割!?霊園開発儲けのカラクリ教えます ■いざというときに迷わない正しいお墓の選び方 という文言が並びます。 さっそく読んでみました。 まずは、P28-29 見開きの﹁寺を取り巻く市場相関図﹂。 全国7万6000カ寺を中心に﹁仏壇・仏具店﹂﹁石材店﹂﹁墓地・霊園事業﹂﹁観光事業﹂﹁副業その他﹂﹁葬祭業﹂が密接に結びつき、そこに﹁檀家・信者・非信者﹂が経済的にどのようにかかわっているかという図式が描かれています。 この図式がすべての寺院に当てはまるわけではないことをご理解ください。
︻﹁寺﹂編︼ ■寺ビジネスの全貌?繁栄支えた檀家制度が形骸化 1.1兆円市場の厳しい現実
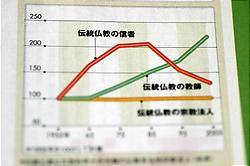 (P28)
伝統仏教の信者は1955年を100とすると、1975年頃には200を越えましたが、1985年から急減し続けています。対し、寺院数は横ばい。
この数字が正しいとすると、まともに影響を受けるのは、都会に比べて信仰心の篤い地方であり、かつ高齢化・過疎化の進む地域の寺院です。
したがって、現在は二極的構造が進んでいるのですが、やがてこの流れが全体を覆いかねないと警告します。
さらに興味深いのがP32にある宗教法人の売買価格算定方法、つまり宗教法人の経済的価値の算定です。
基本価格5000万円+所有不動産価値、これにプラス査定として﹁宗派に属さない単立法人﹂﹁都会にある﹂、マイナス査定として﹁離脱が困難な宗派に所属﹂﹁地方にしか拠点が無い﹂﹁信者がない﹂という基準です。
所属宗派がプラス査定マイナス査定にかなり影響があるようです。
(P28)
伝統仏教の信者は1955年を100とすると、1975年頃には200を越えましたが、1985年から急減し続けています。対し、寺院数は横ばい。
この数字が正しいとすると、まともに影響を受けるのは、都会に比べて信仰心の篤い地方であり、かつ高齢化・過疎化の進む地域の寺院です。
したがって、現在は二極的構造が進んでいるのですが、やがてこの流れが全体を覆いかねないと警告します。
さらに興味深いのがP32にある宗教法人の売買価格算定方法、つまり宗教法人の経済的価値の算定です。
基本価格5000万円+所有不動産価値、これにプラス査定として﹁宗派に属さない単立法人﹂﹁都会にある﹂、マイナス査定として﹁離脱が困難な宗派に所属﹂﹁地方にしか拠点が無い﹂﹁信者がない﹂という基準です。
所属宗派がプラス査定マイナス査定にかなり影響があるようです。
■Column 檀家300軒が採算ライン?税制面の優遇は盛りだくさん ﹁住職は寺の経営者であってオーナーではない。寺から給料をもらって生活しているのだ。だが、実際は寺の収入と住職一家のサイフがどんぶり勘定になっていることが少なくない。そして、現実には住職や家族が先生をやって、給料を生活費に充てていることも珍しくないのだ﹂︵p33より︶ この部分は、実際にそういうことがあるとすれば、一番の問題になるところです。やはり、会計上の流れは明確にしておかなければなりません。 P33には宗教法人税制の優遇制度に関する実例がわかりやすく描かれていますが、私たちは寺院会計において、宗教収入がなぜ非課税とされるのか。また、収益事業収入がなぜ公益法人として税制が優遇されているのか。そのあたりもよく胆に銘じておく必要があるでしょう。 公益性が明確にできないのであれば、税制の優遇制度も返上するくらいの心持ちでいたほうが良いのかもしれません。 この税制の恩恵を一番享受しているのは巨大新宗教団体です。
■お坊さんはつらいよ?生活支える読経アルバイト 住職になれない僧侶が増加中 ﹁僧侶の世界は嫉妬の世界。変化を嫌い、出る杭を打とうとする。寺の世界は一種独特の閉鎖的な世界だ﹂(P34) 実に辛辣なことばです。かつては、寺の僧侶は先進的に印刷技術や土木技術、建築技術、食文化などの最先端を導いてきたはずです。何時から変化を嫌うようになってしまったのでしょうか。確かに伝統的に護持し受嗣いでいかなければならない部分はあります。けれども、変わらなければならない、変えていかなければならない部分もあるでしょう。 むやみに社会に迎合することは必要ないと思います。むしろ社会を導く原動力になり文化の発信の源になるというくらいの心構えを持っていて良いかと思います。
■改革寺の挑戦?没落寺ばかりではない! 経営盤石な“元気印”を一挙紹介 まあ、この項は、こんな事例もあるのかな?という感じで読ませていただきました。
■緩む宗派のタガ?愛想尽かした末寺が“反乱” 疲弊するフランチャイズ制度 包括法人と非包括法人の関係、本山・末寺の関係です。 宗費賦課金を包括法人に拠出し、僧侶資格付与や布教支援を受けるという関係です。 宗派というブランド力の低下により、宗費についてどのように考えていくのかという項ですが、ここは、特に曹洞宗を中心に取材を行ってるようで、宗費賦課金の計算方法や記事の内容も曹洞宗の内容に沿った形で書かれています。 ﹁賦課金の決め方には自己申告項目があり、末寺は虚偽申告をすることで賦課金を安くする傾向が強く、ここにも不公平感が強まっていた。そこで曹洞宗は賦課金制度を07年度から変更し、地域補正、県民所得補正を取り入れた、より正確で実情に合った査定方により負担感の強かった地方に対する改善も実施した﹂︵P42) 宗費賦課金の算定方式は、曹洞宗が一番細かく複雑な方法をとっています。それゆえ、わかりづらいという声も多いことも確かです。 いかに公平に、いかにわかり易く・・・というのが永遠の課題であると思います。 ところで、P42の賦課金の計算方法の図ですが、間違いがあります・・・ダイヤモンドさん。
■Ranking 仏教宗派別の信者増減率ランキング これは実に興味ある表です。 是非一読ください。 曹洞宗がデータ不足で増減の計算ができていないのが残念ですが、その理由は明確です。 一つ前の項目で書きましたので敢えて書きませんが。
︻﹁墓﹂編︼ ■霊園開発のからくり?宗教法人も名義貸しで協力 石材店の粗利はなんと4割!? このあたりは、かつてはタブーとされていた領域ですね。 いかに利権が絡んだ世界であるかが明確にわかると思います。 もはや墓地は檀信者を引き止める手段とはなりえなくなっています。 改葬方法の具体的手続きチャート図(P56)が私たちにとっては一番の脅威であり、心しておく必要がある部分と言えるでしょう。 ■Column 消費者を手玉に取る石材店の墓石販売の手口 正しい墓の選び方?どこにどんな墓をつくるのか 今だからこそじっくり考えよう ■Chart お墓選びのフローチャート 公営霊園 安くても供給量や遺骨など条件厳しい 民営霊園 選択肢は幅広い ポイントは絞り込み ■Column バチ当たりか、人助けか 拡大する墓参り代行ビジネス 寺院墓地 交通至便がメリット 金銭面では高めに ■墓石の選び方 最大のカギは信頼できる石材店探し 永代供養墓 ﹁家﹂にこだわらず後に憂いを残さない 納骨堂 墓不足背景に増加 ネットで進化著しい 自然葬 樹木葬から散骨、宇宙葬まで種類豊富 ■改葬の方法 住職の理解が不可欠 費用も覚悟がいる
今号の﹃週刊ダイヤモンド﹄は、僧侶にとっても、関連業者の方にとっても、お寺の檀家さんにとっても、どのお寺にも属していない方にとっても一読の価値のある特集だと思います。 こういう内容を一部の業界の中の暗黙の了解にしておくことは、長い目で見れば決して良いことではないでしょう。 明確にするべきことは明確にし、少なくとも収益事業収入については完全に透明性のあるものとする必要があるはずです。 経済学は、最大多数の最大幸福の実現を目標とします。そのために限られた資源をどのように配分すれば人々の満足が高まるかを考察します。 対し、仏教は欲を制するという発想の転換を提示します。 経済活動に係わる世間と、菩薩行を実践する世界という異なる概念を強引に一致させる必要はないでしょう。両者をバランスをとらせつつ問題点があれば真摯に取り組み改善していかなければ寺院の将来は明るくないといえるでしょう。 逆に言えば、真摯に取り組み、改善していくことのできる寺院のみが生き残っていくのでしょう。 そして、もう一つ付け加えるとすれば、﹁改革寺の挑戦﹂の項にあるようなことまでは行う必要はなく、ただ行うべきことを行うことだけで充分であると感じます。
まあ、あまり内容をネタバレさせてもいけませんので、書店やコンビ二などで是非読んでみてください。 皆さまはどのようにお感じになったでしょうか。
2008年1月 6日
次世代DVD規格競争ついに決着か
米ワーナー、ブルーレイに一本化・DVD規格争い、早期決着もソニー、東芝両陣営による新世代DVDの規格争いで、米映画大手ワーナー・ブラザーズは4日、東芝陣営の﹁HD―DVD﹂規格のDVDソフト販売から撤退し、今年6月からはソニー陣営の﹁ブルーレイ・ディスク︵BD︶﹂規格のソフトだけを販売すると発表した。米DVD市場で20%前後のシェアを持つワーナーの戦略転換で勢力図は大きく変わり、規格争いが早期決着する可能性も出てきた。 BDを支持する映画会社のDVDソフトの販売シェアは、ワーナーのほかソニー・ピクチャーズエンタテインメント、ウォルト・ディズニー、20世紀フォックスなどをあわせて70%弱となる。HD―DVDを単独支持するパラマウント・ピクチャーズ、ユニバーサル・ピクチャーズの合計シェア20%強を大きく引き離す。 ︵IT+PLUS︶
直径12センチの円盤型の記録媒体は、CD(Compact Disk)、DVD(Digital Versatile Disk)というように大容量化が飛躍的に進んでいるところですが、記録データの大規模化、ハイビジョン放送の普及などにより、さらに大容量のメディアが求められ、いわゆる次世代DVDといわれる記録媒体が少しづつ市場に出回ってき始めました。 この次世代DVDについては、かつての家庭用VTRに見られたβ・VHSのような規格の分裂が再び見られ、日本のメーカーを中心にアメリカの映画会社やパソコン会社などが、東芝とNECが提唱するHD DVDと、ソニー・松下を中心にそれ以外の企業が参加するBlu-ray Disc両陣営に分かれて規格争いを繰り広げているところです。 その特長を端的に表現すると﹁作りやすさのHD DVD﹂と、﹁大容量のBlu-ray﹂ということができます。 またか・・・・という感じで、冷めた目で市場の動向を見ていましたが、いよいよ決着がつきそうな気配となりました。
そもそも、このような規格の分裂による争いは、消費者にとって不利益になることが多く、特に敗北した規格を購入してしまった場合には購入のし直しをしなければならないというように、大きな損失となってしまいます。 そのために、規格争いが決着するまで購入を見合わせている人も多かったはずです。 けれども、今後はある程度見通しが立ったことと、デジタルハイビジョン放送の普及に伴い、急速に次世代DVDの需要が増えることは想像に難くありません。 次世代DVDでは、HD DVD陣営が、2006年に東芝が世界初のHD DVDプレーヤー﹁HD-XA1﹂を発売するなど、一歩先にスタートしました。 Blu-ray Disc陣営は、半年以上遅れて松下が﹁DMR-BW200﹂﹁DMR-BR100﹂を発売。 価格を安く設定することで巻き返しを図ります。 次世代DVDの発売からまもなく2年。 日本における昨年10-11月の家電量販店2,300店舗のPOSデータベースで見る次世代DVDの売上シェアは、HD DVDは僅か2%、Blu-rayは98%となっており、既に圧倒的にBlu-ray優性の状況にあります。 ただ、欧米市場では、両者の差はそれほどついておらず、DVDソフトの販売枚数ベースでは、HD DVD 約30%、Blu-ray 約70%の割合となっています。 このままHD DVD が敗れると30%の消費者が︵Blu-rayが敗れると 約70%の消費者が︶かつてのβビデオの所有者のような不利益を被ります。 消費者に不利益な争いは、早く止めて欲しいものです。
β・VHS戦争を決定づけたのはソフトウエアコンテンツのパッケージ販売だったといえます。ですから、昨日の報道はHD DVDを推奨する東芝陣営にとってはかなりの痛手であることは間違いありません。 Blu-ray優性の流れを止めることはかなり困難ではないでしょうか。
2007年12月 1日
師走の値上げラッシュ
きょうから値上げラッシュ、パンも菓子もガソリンも!食パンやお菓子、ガソリンなど暮らしに身近な商品の値上げが1日から始まった。 今後もタクシー料金や即席めん、ビールなど値上げラッシュが続く。出費がかさむ年末年始の家計にとって痛手となりそうだ。 山崎製パンは1日、食パンや菓子パン、和洋菓子などを約8%値上げし、不二家もケーキやシュークリームなど定番の46商品の価格を段階的に引き上げ始めた。 石油元売り最大手の新日本石油は1日から灯油やガソリンの卸価格を前月より6・7円︵1リットルあたり︶引き上げた。ガソリンの平均店頭価格は150円から155円程度まで上昇するとみられる。 東京地区のタクシー運賃は3日から初乗りの上限が660円から710円に引き上げられる。ビールではキリンビールが来年2月1日から、アサヒビールが3月1日からそれぞれ値上げする予定だ。 (12月1日 読売新聞)12月に入り、今年も残り1ヶ月となりました。 今年は年末に向けて家計に厳しい冬となりそうです。 特にガソリンの値上げが顕著で、街中のガソリンスタンドではレギュラーガソリン150円台後半の店が目立ちます。 こうなっては、まだたまに見かける140円台のスタンドを見つけては給油をするということ、自動車の使用は最低限に留めるというのがせめてもの抵抗です。
そのような中、次のような報道もあります。
<生活保護>扶助基準の引き下げ容認 厚労省の検討会議 生活保護費の見直しを議論していた厚生労働省の検討会議︵座長・樋口美雄慶応大商学部教授︶は30日、生活保護費のうち食費など日常生活にかかわる﹁生活扶助基準﹂の引き下げを容認する内容の報告書をまとめた。生活扶助基準の引き下げは、同基準と連動している低所得者向け低利貸付などの福祉施策や最低賃金にも影響する。厚労省は来年4月実施を目指すが、具体的な引き下げ額については﹁慎重に検討する﹂としている。 07年7月現在の生活保護受給者は153万2385人。その7割以上が一人暮らしで、ほぼ半数が60歳以上。既に老齢加算が06年度に全廃され、母子加算も段階的削減され09年度に全廃されることが決まっている。しかし、生活扶助基準が、生活保護費を受けていない低所得世帯の消費実態に比べて高めだとの指摘もあり、見直しを検討してきた。 報告書は、04年全国消費実態調査の結果を基に、収入が全世帯のうち下から1割の低所得世帯と生活保護世帯を比較。夫婦と子供1人の低所得世帯の月収は14万8781円だが、生活保護世帯の生活扶助費は1627円高い15万408円だった。また、60歳以上の一人暮らしも低所得世帯は6万2831円だが、生活保護世帯は8371円高い7万1209円だった。このため、低所得世帯の水準に引き下げることを事実上容認する内容になっている。 生活保護制度は、地域の物価差などを基に、市町村ごとに受給基準額に差をつけている。最も高い東京都区部などと最も低い地方郡部などでは22.5%の格差があるが、報告書は﹁地域差は縮小傾向﹂と指摘した。 検討会議は、小泉内閣時代の骨太の方針06︵経済財政運営と構造改革に関する基本方針︶に、08年度に生活扶助基準を見直すことが明記されたのを受け、先月中旬から行われていた。厚労省は今後、報告書の内容に沿って具体的な引き下げ内容を決め、厚労相が告示する。地域差を縮める形で引き下げるとみられる (11月30日 毎日新聞)
生活保護は、生活困窮者の生活を支える最後のセーフティーネットであります。 この値上げラッシュの時期にあって扶助基準が引下げられると。受給者にとってはまさに死活問題です。 昨年は70歳以上を対象に一定額を上乗せする老齢加算が全廃されました。 さらに、来年には母子家庭への児童扶養手当加算も全廃される予定です。 経済的弱者に厳しい施策というのは如何なものでしょうか。
2007年11月 2日
自動車は脱石油の時代へ
NY原油、史上初96ドルを突破…金も28年ぶり高値ニューヨーク商業取引所の原油先物相場が10月31日︵日本時間11月1日︶、米追加利下げなどを受けて急騰し、史上初めて1バレル=96ドル台をつけた。 国際的な指標であるテキサス産軽質油︵WTI︶の12月渡し価格は、通常取引後の時間外取引で、一時1バレル=96・24ドルと、前日の通常取引の終値︵90・38ドル︶から6ドル近く上昇し、史上最高値を更新した。 これに先立つ通常取引でも前日比4・15ドル高の1バレル=94・53ドルで取引を終え、終値の史上最高値を2日ぶりに更新した。 米エネルギー情報局︵EIA︶が同31日発表した統計で、米国の原油在庫が前週より390万バレル減少し、需給が引き締まるとの観測が広がった。また、米追加利下げを受け、ドルの対ユーロの為替相場が最安値を更新し、ドル建て取引の原油市場への投機資金の流入が加速した。7?9月期の米実質国内総生産︵GDP︶成長率が3・9%と予想を上回ったことも買い材料となった。中東情勢の緊迫化も背景にある。 ︵読売新聞︶
原油価格が上昇しています。 原油価格の高騰は、物流コストや石油由来の製品の直接的な値上げをもたらし、物価上昇の引き金となります。 ガソリンスタンドでは、今日から一気に値上げをしたところも多く、この近辺ではレギュラーガソリンがリッター当たり150円を超えることも珍しくありません。 車はガソリンや軽油を燃料とするものが殆んどですが、今後は脱石油の動きが加速していくことでしょう。 本年のモーターショーで、これは乗ってみたいと思う車がありました。 それは三菱自動車の電気自動車﹃i MiEV﹄です。現在、電力会社との共同研究や実証走行試験を行っているところで、一回の充電での走行可能距離が160キロを超えることが出来た段階で発売されるという事です。 おそらくあと2年前後で発売になることでしょう。 その頃には、今乗っている車が6回目の車検を迎えます。
﹃i MiEV﹄は電気を家庭用コンセントからリチウムイオン電池に取り込むのですが、電気自動車ならではの特徴は ■CO2排出量の軽減 走行中にCO2を全く排出しません。 発電時のCO2排出量を含めても、同クラスのガソリン車のわずか3割です。 ■燃費の節約 ガソリン代に比べ、安価な電力を利用するため、同じ距離を走行するための電気代は、昼間電力でも1/3!、夜間電力では1/9!になります。 ■キビキビと 低速から高いトルクを発生する小型・高効率モーターによって、力強く加速します。 ■静かに エンジンのような上下振動を伴わない電気モーターによって、極めて静かに走行することができます。 ■どこでも充電できる 車載の充電器を使って、ご家庭の100Vあるいは200Vのどちらの電源でも充電できるほか、電力会社等で開発中の急速充電器を使えば短時間で充電できます。 このようなメリットも魅力的ですが、キュートなスタイルが素敵です。
﹃i MiEV﹄の発売が待てない方には、鉛バッテリーカーとしてタケオカ自動車工芸の ﹃REVA-CLASSIC﹄ とか ﹃ミリューR﹄ などが既に発売されています。 特に ﹃ミリューR﹄ は棚経とかに便利そうです。
これらの電気自動車は、今後急速に普及していくことでしょう。 一番のデメリットは充電に時間が掛かることですね。 急速充電という方法がありますが、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。
ところが、この問題を一気に解決する技術があるのです。 それがキャパシタです。 ﹁5分の充電で800km﹂新キャパシタ電気自動車 米EEStor社は、従来蓄電量の限られていたキャパシタを変革、容量の飛躍的な増大に成功したと主張している。まずはカナダ企業の電気自動車に搭載されるが、5分の充電で800キロメートルも走行できるという。 この記事の内容がどこまで信頼できるかは不明ですが、とにかくキャパシタは今までの充電池の感覚を覆すほどの画期的な技術です。 まさに、﹁電気自動車業界のアキレス腱は、エネルギーの貯蔵だった。間違いなく、これによって内燃機関は不要になる﹂という言葉が重みをもってきます。 私たちの身の回りには充電を要する家電製品が溢れています。 電気コードからの呪縛を解いてくれたのが充電池なのですが、なにせ充電に数時間を要します。 毎日使用するものであればなおさら充電に手間が掛かります。 しかし、キャパシタは化学的に電気を蓄えるのではないため、数秒?数分で充電が完了します。 電気自動車に限らず、あらゆる家電製品の利便性を飛躍的に高めてくれることでしょう。 期待大です。
もう一つ、着目すべき画期的な技術がありました。 それは三洋電機の 車載用全方位モニタシステム です。 これは、車体の四隅に取り付けられたカメラからの画像を処理し、ゆがみを補正し、あたかも上空から自分の車を見下ろしているような映像として合成し、車の死角を無くすというものです。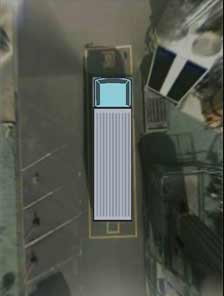
ミラーや車載カメラは凸レンズであったり広角レンズの画像そのままであったりしました。 それはできるだけ多くの画角を確保するために必要なことですが、その分画像はゆがみ、運転手がゆがんだ画像から状況を判断しなければなりませんでした。 コンピュータにより、このゆがんだ画像を処理し、つなぎ目の気にならない、あたかも自車を数十メートル上空から見下ろしたような直感的に見やすい映像を実現しています。 これは画期的な技術です。 車の運転でミラー越しのバックが苦手な方は多いのではないでしょうか。 駐車場の枠内にきちんと収めて駐車するためには空間認知力が必要とされます。 しかし、この方位モニタシステムを使えば、駐車も楽になるでしょう。 障害物や人がどこに位置しているのかも一目瞭然です。 このようにできるだけ運転者の負担を減らし安全性を高めることは必要です。 普及が進み、少しでも事故が減少することを願って止みません。
2007年7月25日
元気な印刷会社から学ぶこと
お寺関係の活動の中で、様々な印刷物を作るということがよくあります。
寺報、しおり、経本、ポスター・・・・・・
それこそ多種多様な印刷物があります。
自前のプリンターで作成できるものは良いのですが、部数が多かったり、カラー刷りをしたり、大判で仕上げたりという場合には、やはり印刷会社にお願いすることになります。
何社もの印刷会社とお付き合いがありますが、その中の三社についてご紹介します。
地元D社 主に、教区で発行している刊行物﹃生きる力﹄をお願いしています。 ﹃生きる力﹄は、毎年夏の施餓鬼会の時期に合わせて教区檀信徒の皆様向けに作成している教化資料です。 21か寺、10000部以上の発行部数を誇ります。 ■関連記事 ﹁生きる力﹂30号発行に向けて
この印刷会社は、いわゆる﹁職人気質﹂をもっています。鉛の活字を今も保存していて、昔ながらの厳格な印刷技術を受継ぐ会社です。 鉛の活字で印刷してくれるところって本当に少ないと思いますが、実は、私の名刺もこの印刷会社にお願いして活版で作っていただいています。 パソコン写植では、文字がきっちりと配置されますが、活字ならではの、文字配置や文字の太さなどの微妙な揺らぎがいい味を出しています。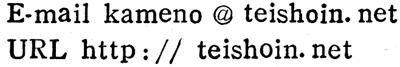
﹃生きる力﹄の編集作業は、パソコン上でワードを使って、教区出版部で校正作業を行うと同時に版組みを作成しています。その版を印刷会社に渡すだけで、そのまま製本をしていただいていますので、いわゆる印刷会社から来る校正版というものは無く、ただ色校正のみを行うだけで完成品が納入されます。 ここの専務さんには本当にお世話になっています。 10000部の冊子っていうのは半端な量ではありません。それを数箇所の拠点に納品していただいていますが、そういう大変な作業も快く引き受けてくださっています。
S社 ここには、主に、貞昌院に事務局があるSOTO禅インターナショナル︵SZI)関係の印刷物をお願いしています。 一番多いのは、年3回発行される会報なのですが、こちらはインターネットを活用して、主に校正作業はネット上に置かれたPDFを用いて行っています。 幸いにも、SZIスタッフにはインターネットに長けた方が多いので、原稿の集約や、編集会議などについて、インターネットを通じたやりとりで基本的な編集作業は完了します。そして、第一校正、第二校正、第三校正︵校了︶と、その段階ごとに印刷会社にネットを通じて校正内容をおしらせし、それを元に出来上がってきたPDFで確認をするわけです。 この会社の素晴らしいところは、テキストベースで原稿を送るだけで、きちんとデザインされた会報が仕上がってくるということです。そして、作業が早いということ。 それが何よりも嬉しいことです。
■関連記事 紙の文書を電子文書化することのメリット
P社
最近は、チラシやポスターなどを印刷することが多くなりました。 フルカラーの印刷物を作成する際に、一番の障壁になることは、料金の高さでしょう。 ところが、そんな固定概念を覆してくれるのが、このP社です。 ■関連記事 シルクロード・音楽の旅@檜ホール
ここの会社は、発注から受取まで、全てインターネットを通じて行います。 入稿する原稿は、完全なデータであることが条件です。つまり、文字校正とか、色校正などは基本的に行われません。データは直ぐに印刷工程に回されます。 ですから、最短翌日とかのオーダーにも問題なく応えてくれます。 ここの会社の特長の一つは、とにかく発注から印刷物完成まで、段階ごとに細かい連絡をしてくれるということにあります。 もしも、データに何らかの不備があった場合は、例え夜中であろうとも、即時メールにてお知らせしてくれます。 こちらからの問合せについても、基本的に365日深夜まで対応してくれます。 そして、もう一つ、この印刷会社は、単に安かろう早かろうという会社ではないということは、納品された印刷物に同封されている﹁私たちの志﹂﹁お客様のアンケート﹂に見ることができます。 なぜ、このような印刷会社を立ち上げたのか、会社設立から現在に至るまでの熱い思いが書かれており、そして、これからもユーザーの意見を積極的に取り入れて、向上心と意欲をもった態度がよくわかるのです。 ■欲しいと思われる方が、気軽に手軽に印刷物を手に入れられるようにしたい。 ■印刷の持つ良さをもっと広く普及させる存在になりたい。 ■心のこもった商品を作ろう。 このようなことを口先だけで言う事は簡単です。 それを真摯に実践できるかどうか、それが企業の真意を問われるところなのでしょう。 ご利用いただいたお客様からも、毎日お喜びの声を多数いただくようになりました。逆に、立上げ当初から現在にいたるまで﹁ここは使いにくい﹂﹁もっとこういうことはできないの?﹂といったご要望もいただけるようになり、一歩づつ改善を進めております。おかげさまで皆様に育てていただき、何とか軌道に乗ってきた今、私たちは今一度﹁初心﹂を確認したいと思っています。︵印刷会社より届いた手紙より︶
印刷業界は、厳しい時代を迎えています。
けれども、そのような逆境の中でも、このように元気な企業もあります。
それは何故なのか。
私たちも︵お寺の行事にも、なにかのイベントにも︶学ぶことは多いと、常々感じています。
元気な姿は、私たちにも元気な活力を与えてくれます。
地元D社 主に、教区で発行している刊行物﹃生きる力﹄をお願いしています。 ﹃生きる力﹄は、毎年夏の施餓鬼会の時期に合わせて教区檀信徒の皆様向けに作成している教化資料です。 21か寺、10000部以上の発行部数を誇ります。 ■関連記事 ﹁生きる力﹂30号発行に向けて
この印刷会社は、いわゆる﹁職人気質﹂をもっています。鉛の活字を今も保存していて、昔ながらの厳格な印刷技術を受継ぐ会社です。 鉛の活字で印刷してくれるところって本当に少ないと思いますが、実は、私の名刺もこの印刷会社にお願いして活版で作っていただいています。 パソコン写植では、文字がきっちりと配置されますが、活字ならではの、文字配置や文字の太さなどの微妙な揺らぎがいい味を出しています。
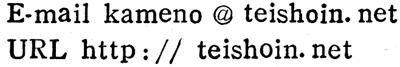
﹃生きる力﹄の編集作業は、パソコン上でワードを使って、教区出版部で校正作業を行うと同時に版組みを作成しています。その版を印刷会社に渡すだけで、そのまま製本をしていただいていますので、いわゆる印刷会社から来る校正版というものは無く、ただ色校正のみを行うだけで完成品が納入されます。 ここの専務さんには本当にお世話になっています。 10000部の冊子っていうのは半端な量ではありません。それを数箇所の拠点に納品していただいていますが、そういう大変な作業も快く引き受けてくださっています。
S社 ここには、主に、貞昌院に事務局があるSOTO禅インターナショナル︵SZI)関係の印刷物をお願いしています。 一番多いのは、年3回発行される会報なのですが、こちらはインターネットを活用して、主に校正作業はネット上に置かれたPDFを用いて行っています。 幸いにも、SZIスタッフにはインターネットに長けた方が多いので、原稿の集約や、編集会議などについて、インターネットを通じたやりとりで基本的な編集作業は完了します。そして、第一校正、第二校正、第三校正︵校了︶と、その段階ごとに印刷会社にネットを通じて校正内容をおしらせし、それを元に出来上がってきたPDFで確認をするわけです。 この会社の素晴らしいところは、テキストベースで原稿を送るだけで、きちんとデザインされた会報が仕上がってくるということです。そして、作業が早いということ。 それが何よりも嬉しいことです。
■関連記事 紙の文書を電子文書化することのメリット
最近は、チラシやポスターなどを印刷することが多くなりました。 フルカラーの印刷物を作成する際に、一番の障壁になることは、料金の高さでしょう。 ところが、そんな固定概念を覆してくれるのが、このP社です。 ■関連記事 シルクロード・音楽の旅@檜ホール
ここの会社は、発注から受取まで、全てインターネットを通じて行います。 入稿する原稿は、完全なデータであることが条件です。つまり、文字校正とか、色校正などは基本的に行われません。データは直ぐに印刷工程に回されます。 ですから、最短翌日とかのオーダーにも問題なく応えてくれます。 ここの会社の特長の一つは、とにかく発注から印刷物完成まで、段階ごとに細かい連絡をしてくれるということにあります。 もしも、データに何らかの不備があった場合は、例え夜中であろうとも、即時メールにてお知らせしてくれます。 こちらからの問合せについても、基本的に365日深夜まで対応してくれます。 そして、もう一つ、この印刷会社は、単に安かろう早かろうという会社ではないということは、納品された印刷物に同封されている﹁私たちの志﹂﹁お客様のアンケート﹂に見ることができます。 なぜ、このような印刷会社を立ち上げたのか、会社設立から現在に至るまでの熱い思いが書かれており、そして、これからもユーザーの意見を積極的に取り入れて、向上心と意欲をもった態度がよくわかるのです。 ■欲しいと思われる方が、気軽に手軽に印刷物を手に入れられるようにしたい。 ■印刷の持つ良さをもっと広く普及させる存在になりたい。 ■心のこもった商品を作ろう。 このようなことを口先だけで言う事は簡単です。 それを真摯に実践できるかどうか、それが企業の真意を問われるところなのでしょう。 ご利用いただいたお客様からも、毎日お喜びの声を多数いただくようになりました。逆に、立上げ当初から現在にいたるまで﹁ここは使いにくい﹂﹁もっとこういうことはできないの?﹂といったご要望もいただけるようになり、一歩づつ改善を進めております。おかげさまで皆様に育てていただき、何とか軌道に乗ってきた今、私たちは今一度﹁初心﹂を確認したいと思っています。︵印刷会社より届いた手紙より︶
2007年7月13日
お寺とマックとセブンイレブン
お盆の棚経廻りも今日からピークを迎えます。
訪問先の檀家さんの皆様、よろしくお願いいたします。
さて、お盆に先立ち、7月11日︵セブンイレブンの日だそう︶に、こんなニュースがありました。
セブン?イレブンがチェーン店数で世界一に
コンビニエンスストア、セブン?イレブンの店舗数が世界一になった。セブン?イレブン・ジャパンは11日、世界のセブン?イレブン店舗数が今年3月末で3万2208店となり、ハンバーガーチェーンのマクドナルドの世界店舗数3万1062店︵3月末現在︶を抜き世界最大のチェーンになったと発表した。
セブン?イレブンは、1927年に設立されたサウスランド・アイス︵現セブン?イレブン・インク︶が米テキサス州で創業した氷小売り販売店が1号店。コンビニエンスストアの元祖とされ、今年80周年を迎えた。
日本のセブン?イレブンは74年に1号店がオープン。2005年にはセブン?イレブン・ジャパンが、米セブン?イレブン・インクを完全子会社にしている。
小売業ではすでに世界最多の店舗数だったが、ファストフードを含めても最多店舗数になったことが分かり、7月11日の﹁セブン?イレブンの日﹂にこれを発表した。
セブン?イレブンは、米国、日本、台湾、タイ、韓国、中国、スウェーデンなど世界17カ国・地域に出店。6月末の店舗数は3万2711店で、この3カ月間でも503店舗増えている。
︵産経新聞︶
すごいですね。
生活には欠かせない存在となったコンビニエンスストア。
日本のどの街に行っても必ず目にしますが、セブンイレブンは日本だけでなく世界17の国と地域に店舗を巡らし、ついに世界最大のチェーンになったという報道です。
これまではマクドナルドがその記録を持っていたとのことですが、マクドナルドが、ほぼ全世界中にネットワークを張り巡らしているのに対して、17カ国・地域での記録はすごいです。
それだけ、まだ未進出地域に出店する可能性があるわけですから。
さて、ここで、前に書いた記事を併せてご参照下さい。
寺院の数はコンビニの数よりもずっと多い
文化庁発表のデータ︵平成18年︶を見てみると 全国社寺教会等宗教団体数
文化庁発表のデータ︵平成18年︶を見てみると 全国社寺教会等宗教団体数
|
項目
|
宗教団体(宗教法人を含む)
|
宗教法人
|
|||||||||||
|
神社
|
寺院
|
教会
|
布教所
|
その他
|
計
|
神社
|
寺院
|
教会
|
布教所
|
その他
|
計
|
||
| 総数 | 81,245 | 77,069 | 32,843 | 25,265 | 7,449 | 223,871 | 81,199 | 75,949 | 23,991 | 536 | 1,121 | 182,796 | |
| 系統 | |||||||||||||
| 神道系 | 81,166 | 11 | 5,543 | 1,059 | 806 | 88,585 | 81,135 | 8 | 3,888 | 183 | 214 | 85,428 | |
| 仏教系 | 21 | 77,020 | 2,432 | 2,443 | 4,452 | 86,368 | 19 | 75,905 | 1,223 | 158 | 449 | 77,754 | |
| キリスト教系 | ? | 2 | 7,021 | 1,194 | 1,159 | 9,376 | ? | ? | 4,030 | 33 | 212 | 4,275 | |
| 諸教系 | 58 | 36 | 17,847 | 20,569 | 1,032 | 39,542 | 45 | 36 | 14,850 | 162 | 246 | 15,339 | |
仏教系宗教団体数 77,069 仏教系宗教法人数 75,949 やはり多いですね。
セブンイレブンは17か国で 32,208 店 マクドナルドも世界中に 31,062 店 ということを考えると 日本一カ国で 75,949 というのが、いかにすごい数字かがわかると思います。 これだけある寺院がネットワークとして結びついて機能するようになると、それはそれは強大なネットワークになると思います。
そんなことを心の隅に感じながら棚経を回っていきます。 棚経というのは、檀家さんとお寺とを結ぶ、大切なネットワークのひとつですから。
2007年7月10日
禅プロジェクト
六本木・東京ミッドタウンの﹁ザ・リッツ・カールトン﹂、六本木ヒルズの﹁グランドハイアット﹂、丸の内には﹁フォーシーズンズホテル﹂、日本橋には﹁マンダリン・オリエンタル﹂、汐留には﹁コンラッド﹂というように、近年、高級ホテルが次々と開業し、過剰なまでの競争を繰り広げています。
対して、帝国ホテルやニューオータニなど、老舗のホテルも負けてはいられません。
新しいアイディアを出して対抗しています。
その中で、注目すべきプロジェクトがホテルニューオータニで現在進行中です。
その名も、 ﹁エグゼクティブハウス“ZEN(禅)”︵仮称︶﹂
まずは、ホテルニューオータニの﹁ハイブリッドホテルプロジェクト﹂について見てみましょう。
ホテルニューオータニ︵東京都千代田区紀尾井町、総支配人 清水 肇︶は、お客さまの安全や快適性と、地球環境への配慮の両立をめざし、2005年11月から2007年10月の2ヵ年、3期計画、総事業費約100億円で推進している﹁ザ・メイン﹂︵本館︶のリニューアル﹁ハイブリッドホテル プロジェクト﹂の第2期オープンを2007年4月11日︵水︶に迎え、プロジェクトでリニューアル予定の総室数のうち約70%、435室の営業を順次開始します。 ■ハイブリッドホテル プロジェクトとは? ﹁地球環境への配慮がお客さまの真の快適さにつながるホテルづくり﹂という、業界初のリニューアルコンセプトで取り組んでいる当プロジェクトでは、﹁安全﹂・﹁環境﹂・﹁快適性﹂をキーワードとして、以下のような具体的な施策を実現します。 ﹁安全﹂ ・・・ 最新技術の導入による耐震性強化構造体への制振ブレース取り付けや耐震処置により、阪神・淡路大震災を想定した震度6強以上の大地震に対しても建物の安全性を確保。 ﹁環境﹂ ・・・ 環境レベルの飛躍的向上オリジナル新空調システム﹁AEMS︵エイムス︶﹂により、総エネルギー使用量を22.7%、CO2排出量を28%削減しながら、お客さま一人ひとりの要望にきめ細かく対応した室内空調環境を実現します。 また、ザ・メイン2階及び16階屋上部分︵総面積約2,800?︶の﹁屋上緑化﹂により、ヒートアイランド現象を緩和します。 ﹁快適性﹂ ・・・ 抜群の眺望とITインフラの拡充リニューアル前に比べて約2倍の大きさとなった、壁全面ガラス張りの窓﹁フルハイトウインドウ﹂は、開放感溢れる空間演出をするとともに、Low?Eペアガラスという3層の複層構造により、断熱性にも優れ、紫外線を約50%カットします。 また、全客室にセキュリテイレベルの高い高速インターネット回線とビデオ・オン・デマンドによる80タイトルの映画や、11チャンネルの外国語放送を行うテレビシステムを導入します。
計 画‥ 2005年11月着工、2007年10月竣工予定 総事業費‥ 約100億円 設計監理‥ 株式会社日建設計、エヌアールイーハピネス株式会社 内装デザイン‥ 株式会社スタジオ・エム、株式会社日建スペースデザイン 施工‥ 大成建設株式会社 構造‥ SRC + S造︵地上17階、地下2階︶ 建築面積‥ 8,359.00?︵延床‥84,411.40?、施工床‥48,145.00?︶ ︵プレスリリースより引用︶
この壮大なプロジェクトの中の一つが﹁エグゼクティブハウス“ZEN(禅)”︵仮称︶﹂です。 ザ・メインのタワーのうち、11階と12階をこの﹁エグゼクティブハウス“ZEN(禅)”﹂専用のフロアとし、客室87室と、専用ラウンジを設置した最高級クオリティーのサービスを提供する計画で、専任のスタッフによるコンシェルジュサービスを超えたバトラーなみのカスタマイズサービス等を提供するそうです。 10月にこのフロアはオープンするそうですが、それに先立ち、案内をしていただきました。 なお、デザインを手がけるのは、京都のデザイン会社 スタジオ・エムの柴田嘉夫さんです。
まずはエレベーターホールから客室までのアプローチ。

 やはり、禅というと水墨画のイメージなのでしょうか。
そして、客室。
やはり、禅というと水墨画のイメージなのでしょうか。
そして、客室。
 改装の一番のポイントは窓の開口を広げた事。
腰の高さまであった壁を、全面窓とし、足元の庭園の光景も飛び込んでくるようになっています。
改装の一番のポイントは窓の開口を広げた事。
腰の高さまであった壁を、全面窓とし、足元の庭園の光景も飛び込んでくるようになっています。


 ニューオータニ全体1500室のうち、禅プロジェクトの対象となるのは87室。
写真でご紹介した部屋は、その中で最も広い115?の部屋です。
ちなみに、室料は16万円。
ニューオータニ全体1500室のうち、禅プロジェクトの対象となるのは87室。
写真でご紹介した部屋は、その中で最も広い115?の部屋です。
ちなみに、室料は16万円。
ドアの向こうは、廊下のモノトーンの世界から、モノトーンを主体にしつつも金や紫をアクセントとした上品な華やかさを持った世界になります。

 室内には、炭、盆栽などが置かれています。
室内には、炭、盆栽などが置かれています。


 どういった部分が﹁禅﹂として差別化されているのか。
その捉え方は、私たち僧侶にとってもとても参考になります。
例えば、欧米のインテリア装飾は、原色を基調とした色鮮やかな装飾が基本ですが、そのような中で、モノトーン、シンプル、侘び寂びという、﹁あっさり﹂を極めた日本の伝統文化は、新鮮に感じるのでしょう。
その根底には、複雑化する社会の中で、ミニマリズム・ナチュラリズム・ヒューマニズムという、いわゆる精神的な心地よさをそこに見出しているのだと思います。
ただ、日本文化をそのまま取り入れるのではなく、欧米それぞれのもつ文化と融合し、日本の禅とはちがう、﹁Zenスタイル﹂﹁Zenトリートメント﹂﹁Zenガーデン﹂・・・・といった、アメリカ流、ヨーロッパ流のZENという形になって表れています。
このように、海外では ZEN がブームになっておりますけれども、この﹁禅プロジェクト﹂は、その捉え方ともまた違ったアプローチです。むしろ、欧米化された日本の現代において、改めて日本文化、禅を見直す流れの中でのアプローチであり、日本人デザイナーがどのように﹁禅﹂というものを捕らえているのか、その自由な発想は、日本の禅宗の中で過ごしている私たちにとって、逆に新鮮です。
きっと、東京グランドホテルで﹁禅﹂をテーマに部屋をつくると、全く違うものになることでしょう。
どういった部分が﹁禅﹂として差別化されているのか。
その捉え方は、私たち僧侶にとってもとても参考になります。
例えば、欧米のインテリア装飾は、原色を基調とした色鮮やかな装飾が基本ですが、そのような中で、モノトーン、シンプル、侘び寂びという、﹁あっさり﹂を極めた日本の伝統文化は、新鮮に感じるのでしょう。
その根底には、複雑化する社会の中で、ミニマリズム・ナチュラリズム・ヒューマニズムという、いわゆる精神的な心地よさをそこに見出しているのだと思います。
ただ、日本文化をそのまま取り入れるのではなく、欧米それぞれのもつ文化と融合し、日本の禅とはちがう、﹁Zenスタイル﹂﹁Zenトリートメント﹂﹁Zenガーデン﹂・・・・といった、アメリカ流、ヨーロッパ流のZENという形になって表れています。
このように、海外では ZEN がブームになっておりますけれども、この﹁禅プロジェクト﹂は、その捉え方ともまた違ったアプローチです。むしろ、欧米化された日本の現代において、改めて日本文化、禅を見直す流れの中でのアプローチであり、日本人デザイナーがどのように﹁禅﹂というものを捕らえているのか、その自由な発想は、日本の禅宗の中で過ごしている私たちにとって、逆に新鮮です。
きっと、東京グランドホテルで﹁禅﹂をテーマに部屋をつくると、全く違うものになることでしょう。
さて、話を元にもどしますが、ここでの食事は、10月にできる専用ラウンジで取ることができ、朝食は 洋食 または お粥、スープとなるとのことです。 ちなみに、典座教訓ってご存知ですか?と準備室の方に尋ねたら、ごめんなさい、知りません、勉強中です・・・とのことでした。 ハードの面はだいぶ完成されているようですが、10月にどのようにソフト面の整備がなされていくのか、全面完成が楽しみです。 この禅 プロジェクトは、新聞雑誌などで紹介されることも多く、先日の朝日新聞でも次のような記事が掲載されておりました。
ホテルニューオータニ エグゼクティブハウス“禅”プロジェクト
コンシェルジュ・ ****さん︵**歳︶
一人一人に合ったもてなし
帰国前夜に﹁マグロの刺し身を持ち帰りたい﹂と言い出す国賓の宿泊客。名前と東京23区在住という記憶だけを頼りに、﹁20年前に日本で働いていたときの同僚に会いたい﹂という外国人客もいる。 そんな無理難題にもコンシェルジュとして奔走してきた。その姿勢が評価され、ニューオータニの2フロアを改装して今秋オープンするホテル・イン・ホテル﹁エグゼクティブハウス禅︵ZEN︶﹂の準備スタッフに抜擢︵ばってき︶された。 ホテル業界を志したのは学生時代の体験から。タイを旅行中、タクシーでホテルに帰ったとき小銭がなく、運転手に英語も通じず困っていたら、ドアマンが察して小銭をパッと差し出してくれた。上智大チアリーディング部の夏合宿では﹁買い食い禁止﹂がルールで、それを知る旅館のおかみさんが風呂上がりに﹁サプライズ﹂でアイスを用意してくれた。 ︵朝日新聞記事より、記事中名前部分は**としました︶
ホテルニューオータニ︵東京都千代田区紀尾井町、総支配人 清水 肇︶は、お客さまの安全や快適性と、地球環境への配慮の両立をめざし、2005年11月から2007年10月の2ヵ年、3期計画、総事業費約100億円で推進している﹁ザ・メイン﹂︵本館︶のリニューアル﹁ハイブリッドホテル プロジェクト﹂の第2期オープンを2007年4月11日︵水︶に迎え、プロジェクトでリニューアル予定の総室数のうち約70%、435室の営業を順次開始します。 ■ハイブリッドホテル プロジェクトとは? ﹁地球環境への配慮がお客さまの真の快適さにつながるホテルづくり﹂という、業界初のリニューアルコンセプトで取り組んでいる当プロジェクトでは、﹁安全﹂・﹁環境﹂・﹁快適性﹂をキーワードとして、以下のような具体的な施策を実現します。 ﹁安全﹂ ・・・ 最新技術の導入による耐震性強化構造体への制振ブレース取り付けや耐震処置により、阪神・淡路大震災を想定した震度6強以上の大地震に対しても建物の安全性を確保。 ﹁環境﹂ ・・・ 環境レベルの飛躍的向上オリジナル新空調システム﹁AEMS︵エイムス︶﹂により、総エネルギー使用量を22.7%、CO2排出量を28%削減しながら、お客さま一人ひとりの要望にきめ細かく対応した室内空調環境を実現します。 また、ザ・メイン2階及び16階屋上部分︵総面積約2,800?︶の﹁屋上緑化﹂により、ヒートアイランド現象を緩和します。 ﹁快適性﹂ ・・・ 抜群の眺望とITインフラの拡充リニューアル前に比べて約2倍の大きさとなった、壁全面ガラス張りの窓﹁フルハイトウインドウ﹂は、開放感溢れる空間演出をするとともに、Low?Eペアガラスという3層の複層構造により、断熱性にも優れ、紫外線を約50%カットします。 また、全客室にセキュリテイレベルの高い高速インターネット回線とビデオ・オン・デマンドによる80タイトルの映画や、11チャンネルの外国語放送を行うテレビシステムを導入します。
計 画‥ 2005年11月着工、2007年10月竣工予定 総事業費‥ 約100億円 設計監理‥ 株式会社日建設計、エヌアールイーハピネス株式会社 内装デザイン‥ 株式会社スタジオ・エム、株式会社日建スペースデザイン 施工‥ 大成建設株式会社 構造‥ SRC + S造︵地上17階、地下2階︶ 建築面積‥ 8,359.00?︵延床‥84,411.40?、施工床‥48,145.00?︶ ︵プレスリリースより引用︶
この壮大なプロジェクトの中の一つが﹁エグゼクティブハウス“ZEN(禅)”︵仮称︶﹂です。 ザ・メインのタワーのうち、11階と12階をこの﹁エグゼクティブハウス“ZEN(禅)”﹂専用のフロアとし、客室87室と、専用ラウンジを設置した最高級クオリティーのサービスを提供する計画で、専任のスタッフによるコンシェルジュサービスを超えたバトラーなみのカスタマイズサービス等を提供するそうです。 10月にこのフロアはオープンするそうですが、それに先立ち、案内をしていただきました。 なお、デザインを手がけるのは、京都のデザイン会社 スタジオ・エムの柴田嘉夫さんです。
まずはエレベーターホールから客室までのアプローチ。


 やはり、禅というと水墨画のイメージなのでしょうか。
そして、客室。
やはり、禅というと水墨画のイメージなのでしょうか。
そして、客室。
 改装の一番のポイントは窓の開口を広げた事。
腰の高さまであった壁を、全面窓とし、足元の庭園の光景も飛び込んでくるようになっています。
改装の一番のポイントは窓の開口を広げた事。
腰の高さまであった壁を、全面窓とし、足元の庭園の光景も飛び込んでくるようになっています。


 ニューオータニ全体1500室のうち、禅プロジェクトの対象となるのは87室。
写真でご紹介した部屋は、その中で最も広い115?の部屋です。
ちなみに、室料は16万円。
ニューオータニ全体1500室のうち、禅プロジェクトの対象となるのは87室。
写真でご紹介した部屋は、その中で最も広い115?の部屋です。
ちなみに、室料は16万円。
ドアの向こうは、廊下のモノトーンの世界から、モノトーンを主体にしつつも金や紫をアクセントとした上品な華やかさを持った世界になります。


 室内には、炭、盆栽などが置かれています。
室内には、炭、盆栽などが置かれています。


 どういった部分が﹁禅﹂として差別化されているのか。
その捉え方は、私たち僧侶にとってもとても参考になります。
例えば、欧米のインテリア装飾は、原色を基調とした色鮮やかな装飾が基本ですが、そのような中で、モノトーン、シンプル、侘び寂びという、﹁あっさり﹂を極めた日本の伝統文化は、新鮮に感じるのでしょう。
その根底には、複雑化する社会の中で、ミニマリズム・ナチュラリズム・ヒューマニズムという、いわゆる精神的な心地よさをそこに見出しているのだと思います。
ただ、日本文化をそのまま取り入れるのではなく、欧米それぞれのもつ文化と融合し、日本の禅とはちがう、﹁Zenスタイル﹂﹁Zenトリートメント﹂﹁Zenガーデン﹂・・・・といった、アメリカ流、ヨーロッパ流のZENという形になって表れています。
このように、海外では ZEN がブームになっておりますけれども、この﹁禅プロジェクト﹂は、その捉え方ともまた違ったアプローチです。むしろ、欧米化された日本の現代において、改めて日本文化、禅を見直す流れの中でのアプローチであり、日本人デザイナーがどのように﹁禅﹂というものを捕らえているのか、その自由な発想は、日本の禅宗の中で過ごしている私たちにとって、逆に新鮮です。
きっと、東京グランドホテルで﹁禅﹂をテーマに部屋をつくると、全く違うものになることでしょう。
どういった部分が﹁禅﹂として差別化されているのか。
その捉え方は、私たち僧侶にとってもとても参考になります。
例えば、欧米のインテリア装飾は、原色を基調とした色鮮やかな装飾が基本ですが、そのような中で、モノトーン、シンプル、侘び寂びという、﹁あっさり﹂を極めた日本の伝統文化は、新鮮に感じるのでしょう。
その根底には、複雑化する社会の中で、ミニマリズム・ナチュラリズム・ヒューマニズムという、いわゆる精神的な心地よさをそこに見出しているのだと思います。
ただ、日本文化をそのまま取り入れるのではなく、欧米それぞれのもつ文化と融合し、日本の禅とはちがう、﹁Zenスタイル﹂﹁Zenトリートメント﹂﹁Zenガーデン﹂・・・・といった、アメリカ流、ヨーロッパ流のZENという形になって表れています。
このように、海外では ZEN がブームになっておりますけれども、この﹁禅プロジェクト﹂は、その捉え方ともまた違ったアプローチです。むしろ、欧米化された日本の現代において、改めて日本文化、禅を見直す流れの中でのアプローチであり、日本人デザイナーがどのように﹁禅﹂というものを捕らえているのか、その自由な発想は、日本の禅宗の中で過ごしている私たちにとって、逆に新鮮です。
きっと、東京グランドホテルで﹁禅﹂をテーマに部屋をつくると、全く違うものになることでしょう。
さて、話を元にもどしますが、ここでの食事は、10月にできる専用ラウンジで取ることができ、朝食は 洋食 または お粥、スープとなるとのことです。 ちなみに、典座教訓ってご存知ですか?と準備室の方に尋ねたら、ごめんなさい、知りません、勉強中です・・・とのことでした。 ハードの面はだいぶ完成されているようですが、10月にどのようにソフト面の整備がなされていくのか、全面完成が楽しみです。 この禅 プロジェクトは、新聞雑誌などで紹介されることも多く、先日の朝日新聞でも次のような記事が掲載されておりました。
帰国前夜に﹁マグロの刺し身を持ち帰りたい﹂と言い出す国賓の宿泊客。名前と東京23区在住という記憶だけを頼りに、﹁20年前に日本で働いていたときの同僚に会いたい﹂という外国人客もいる。 そんな無理難題にもコンシェルジュとして奔走してきた。その姿勢が評価され、ニューオータニの2フロアを改装して今秋オープンするホテル・イン・ホテル﹁エグゼクティブハウス禅︵ZEN︶﹂の準備スタッフに抜擢︵ばってき︶された。 ホテル業界を志したのは学生時代の体験から。タイを旅行中、タクシーでホテルに帰ったとき小銭がなく、運転手に英語も通じず困っていたら、ドアマンが察して小銭をパッと差し出してくれた。上智大チアリーディング部の夏合宿では﹁買い食い禁止﹂がルールで、それを知る旅館のおかみさんが風呂上がりに﹁サプライズ﹂でアイスを用意してくれた。 ︵朝日新聞記事より、記事中名前部分は**としました︶
2006年3月10日
ペット供養は「収益事業」、課税は適法
ペット供養は「収益事業」、課税は適法…名古屋高裁ペットの供養は宗教行為に当たり、謝礼は非課税とするべきだとして、愛知県春日井市の宗教法人﹁慈妙院﹂︵渡辺円猛住職︶が、小牧税務署長を相手に課税処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が7日、名古屋高裁であった。 野田武明裁判長は﹁ペットの葬儀、遺骨の処理などの行為は収益事業に該当する﹂として、課税処分を適法とした1審・名古屋地裁判決を支持し、慈妙院側の訴えを棄却した。 判決によると、慈妙院は1983年ごろから、犬や猫などのペット供養として、読経や火葬などをした際、動物の重さや火葬方法などに応じ、飼い主から8000円?5万円の﹁供養料﹂を受け取った。また、墓地管理費を徴収し、墓石や位牌︵いはい︶を販売した。 慈妙院は、﹁人の供養と同じ宗教活動だ﹂として、所得を申告していなかったが、税務署側は、営利目的の収益事業に該当するとして、2001年3月期までの5年間で、無申告加算税を含めて約670万円を課税した。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060307i307.htm
1審・名古屋地裁判決が出たときにもブログで記事を書かせていただきましたが、高裁でも寺院側の訴えが却下されました。 過去の記事 ペット供養は宗教活動?収益事業? http://teishoin.net/blog/000067.htmlを併せてご参照ください。 寺院側が、ペット供養は﹁人の供養と同じ宗教行為で、非課税の非収益事業﹂ とするのに対し、読経は﹁請負業﹂、遺骨の管理は﹁倉庫業﹂に当たるとしています。 ※寺院など、公益法人の行う収益事業とは、次の33の事業︵付随して営まれるものを含む︶で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます︵法人税法第2条、施行令5条1項︶、 この判決に前後して、ユニークな寺院を見つけました。 宗教法人ではなく、あえて株式会社として設立した寺院です。 このような考え方もあるのかなとつくづく考えさせられる事例です。 ﹁株式会社﹂おぼうさんどっとこむ ︻以下、﹁株式会社﹂おぼうさんどっとこむより引用︼ なぜ宗教法人ではないのか? おぼうさんどっとこむは、宗教法人ではありません。 ﹁株式会社﹂としての運営です。 その理由には、二つあります。 1. オウム事件以来、新たな宗教法人の認可は、非常に難しい。 2. 国家益を考えた場合、旧態依然のシステムでは、ほんとうにお客さまのためになり難い。 以上の理由から、﹁株式会社﹂としての道を選択しました。 公明正大に活動を行った結果、報酬というご利益がまわってくるはずであり、 健全な会社運営を行い、しっかりと税金を支払い、 国家に貢献する法人でありたいと考えての会社設立なのです。
2006年1月13日
寺院の数はコンビニの数よりもずっと多い
<コンビニ>「飽和状態」について3社トップに戦略など聞く
30年にわたって成長を続けてきたコンビニエンスストアが、05年11月で既存店売上高のマイナスが16カ月連続を記録し、﹁コンビニ市場は飽和状態﹂との指摘も出てきた。コンビニの﹁老舗﹂で業界トップのセブン―イレブン・ジャパンと、新戦略でセブンを追うローソン、ファミリーマート。現状や戦略を3社のトップに聞いた。 ・コンビニ市場は飽和? ローソンの新浪剛史社長は﹁20代、30代の男性をコア︵主要な︶ターゲットにしてきたコンビニ市場は、飽和していると思う﹂と語る。これに対し、セブン&アイ・ホールディングスの鈴木敏文会長は﹁飽和しているのはコンビニではなく、消費そのものが変わっている。若い人口が減る中で、単純な成長はありえない﹂と強調する。 コンビニは75年に開店したセブン・イレブン豊洲店︵東京都江東区︶が第1号で、その後参入した店のモデルはセブン・イレブンだった。しかし、上田準二ファミリーマート社長は﹁以前は、セブンが成功モデルだった﹂と認めつつも﹁もはや、セブンのモデルを追いかける時代ではない﹂と語る。トップ3の05年12月末の店舗数は、セブン1万1069店、ローソン8273店、ファミリー6628店。上田社長は﹁規模の差は埋まらない。質を高めることに注力する﹂という。 ・新しいモデルは? ローソンは、﹁ナチュラルローソン﹂や﹁ストア100﹂といった従来のコンビニとは異なった店舗を展開し、託児所を併設したコンビニの開店準備も進めている。ファミリーも、オフィスビル内に高級感が高い﹁ファミマ!﹂を展開している。この動きを、鈴木会長は﹁マスコミ受けするだけで邪道だと思う。既存の店をどう強くするかを考えるのが、われわれの仕事だ﹂と強く批判する。 上田社長は﹁100円ショップや、生鮮コンビニの立ち上げも検討したが、既存店強化が先だと判断し、計画をボツにした﹂と語る。新業態の﹁ファミマ!﹂は、オフィスビル内への出店が中心で既存店とは競合しないとの考えだ。 ローソンは﹁ローソンが好き、というファンを作ることが重要。これまでと違う考え方で進める﹂という。﹁ストア100﹂などは、現在はすべて直営店舗だが﹁1、2年後、近隣でローソンを経営している加盟店に引き渡すことで、納得してもらっている﹂という。 ・それぞれの戦略 鈴木会長は﹁ひとつのパイを、同じレベル︵の企業︶で食い合えば、飽和状態になるが、︵経営の︶レベルが違う。セブンと他店との売り上げ︵1日あたり︶は十数万違う﹂と、強い自信をのぞかせる。ローソンは﹁コンビニはもはや、旧態依然になりつつある。一部から嫌われても、個性のある店をつくる必要がある﹂と、新しいモデルに積極的だ。 ファミリーは、全店舗にマルチメディア端末﹁ファミポート﹂を置いている。﹁これから伸びるのは、チケット販売などのサービス。保険とか、介護とかいろんなサービスに対応するためにも︵利用者が自分で操作するため、店員の負担を軽減できる︶マルチメディア端末が必要だ﹂と語る。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060113-00000166-mai-bus_all︻参考資料︼ 産業界の動き?多様化するコンビニエンスストア?住友信託銀行 調査月報 2005 年9月号 http://www.sumitomotrust.co.jp/RES/research/PDF2/653_3.pdf 拡大するFC︵フランチャイズチェーン︶の動向について?株式会社東京商工リサーチ http://www.tsr-net.co.jp/ICSFiles/afieldfile/2005/03/18/dbhl_fc.pdf︻参考‥フランチャイズの定義︼ ︵社︶日本フランチャイズチェーン協会の定義では、﹁フランチャイズとは、事業者︵﹁フランチャイザー﹂と呼ぶ︶が他の事業者︵﹁フランチャイジー﹂と呼ぶ︶との間に契約を結び、自己の商標、サービスマーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。﹂とされています。 従ってフランチャイザーが開発したフランチャイズシステムやノウハウと、それを象徴する商標などの事業を運営する方法を提供するのに対して、フランチャイジーは、自己資金を投入して、本部の開発した商売の方法、ノウハウを使用して営業を行い、お互いに利益を得ようとする﹁事業共同体﹂と言えます。日本に初めてのコンビニエンス・ストアが1960年代後半に誕生してから30年余りが経過し、コンビニエンス・ストアは若者から高齢者まで幅広い年齢層の生活に定着しています。 その総店舗数は︵社︶日本フランチャイズチェーン協会の資料によると、実に4万店舗を数えるに至っています。 街中いたるところにコンビにエンスストアの看板が目に付く訳ですね。 ところが、日本の寺院数は、これをはるかに上回っています。 文化庁・宗教年鑑によると実に7万7千を超える寺院があるのです。 http://teishoin.net/blog/000076.html ■全国の仏教寺院数 約7万7千か寺 ■僧侶の数 約30万人 ■信者数 約6000万人
けれども、寺院がコンビニエンスストアよりも存在感がないというのはどういう訳でしょうか。 日常の生活の中で、コンビニエンスストアに立ち寄る機会は数多くあります。最近は銀行や郵便、各種決裁の窓口から生鮮食料まで、ありとあらゆることがコンビニエンスストアに集約されていて、生活のなかで必須のものとなっています。 対して、寺院はというと日常の市民生活にどれだけ係わることができているでしょうか。 一昔前は、寺院が集落の核として、役所・学校・集会場の役割も果たしていました。 その役割も時代と共に変遷してきています。 寺院と檀家という、いわゆる檀家制度も急速に変化の兆しが見られます。 寺院をコンビニエンスストアと同列に扱って、信仰の問題も含めて、経済学で言うところの財・サービスとして論じることは不適切かもしれません。 例えば、誰かがある宗派を信仰していたとしても、それにより他の人がその宗派を信仰できなくなるわけではなく、むしろ、信仰する人が増えれば増えるほど、その宗派の価値は高まり、信者は増加していくでしょう。 信仰は習俗と結びついて習慣となります。 それは家庭や地域コミュニティーを通じて、周囲、子孫へと伝播していきます。︵⇒情報子としてのミームの伝播) ここまでが、今までの寺院を取り巻く環境でした。 しかし、仏教信仰が単なる受動的な︵能動的でない︶習慣になってしまうことにより、習慣は時代の急速な変化から取り残されていくことになります。 ・葬儀に僧侶を呼ぶことが当たり前だと思っていたけど、それは本当に必要なことなのだろうか? ・戒名をつけることは当然だと思っていたけど、それって必要ものなの? などなど。 コンビニエンスストアをはじめ、各企業は、常に世の中の動向をリサーチして、そのニーズの変化に対応していこうとしています。 それに対応できなければ、それは倒産の危機をもたらします。 さて、憲法で保障されている信教の自由は、寺院に与えられているものではなく、国民に与えられているものです。 家の宗教から個の宗教に変化しつつあるとすれば、寺院側が絶えず信者一人一人のニーズを汲み上げ、それに対応できるよう工夫する必要があり、葬儀・戒名の疑問にも真摯に情報を提供していく必要があると思うのです。 ﹁家﹂のミームの伝播機能が希薄化しているのであれば、それを寺院・僧侶が補っていかなければならないでしょう。 このような努力は、一般企業法人でも、利益を追求しないとされる公益法人でも、関係なく必要なことでもあります。 また、冒頭にある、フランチャイズの定義を、そのまま例えば﹁曹洞宗﹂と﹁寺院﹂の関係に当てはめるのは、やはり適切ではないと批判されるかもしれませんが、曹洞宗ブランドを掲げる曹洞宗寺院が、どのように今後展開していくのかということを考えるに、とても参考になります。 ︵公益法人の税制改革についても、このブログで論じて行きたいと思います︶ ブログのテーマに経済のカテゴリーを設置してあります。 寺院を経済の側面からみることにより、現在の寺院が抱える問題点が浮き彫りになってきます。 前向きな意味での問題解決が可能です。 寺院にとってマイナス面が取りざたされている昨今ですが、逆に、新たな可能性を秘めた時代であるともいえるのではないでしょうか。
2006年1月 7日
日本橋に空は戻るか?
日本橋の空を取り戻せ真上に首都高が通る日本橋首都高移設、来夏までに計画案 国土交通省は28日、東京・日本橋の上を走る首都高速道路の移設について、来年夏までに計画案をまとめる方針を決めた。 国交省や東京都、学識経験者などで構成する﹁日本橋 みちと景観を考える懇談会﹂︵座長=中村英夫・武蔵工大学長︶に、国交省の都市・地域整備局や住宅局、河川局関係者などを新たにメンバーとして加え、街づくりの観点を踏まえ、道路移設の工法や費用負担の割合などを協議する。 日本橋の上を走る首都高の移設については、小泉首相が有識者らに対し、来年9月までに移設の検討と報告書の提出を求め、﹁日本橋という昔からの名所の上に高速道路が走っており、景観が良くない。夢を持って日本橋の上を空に向かって広げ、川のたもとで散歩をできるように﹂と述べていた。 首都高速道路は、1964年の東京五輪に間に合わせるため突貫工事で作られた。土地買収の手間を省くため、公有地である川の上がルートに選ばれた。 http://www.yomiuri.co.jp/tabi/news/20051231tb04.htm
日本橋の上にかぶさる首都高速、高度経済成長時の象徴ともいえる高架橋によって橋の上から空を見上げることはできません。 これを何とか取り除くことはできないかという論議は、これまで何度かなされてきましたが、小泉首相の一言で、にわかに現実化してきました。 ︻関連リンク︼ 日本橋の上に空を 沸く地元﹁実現へ努力﹂ http://mytown.asahi.com/tokyo/news.php?k_id=13000000512280001 小泉首相 ﹁日本橋に青空を﹂一声発動 コイズミ記念碑? http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060106-00000023-maip-soci 日本橋地域のまちづくり http://www.ktr.mlit.go.jp/toukoku/michikeikan/ 美しい景観を創る会・悪い景観100景︵このNo.16とNo.23が日本橋︶ http://www.utsukushii-keikan.net/10_worst100/worst.html
日本橋は、東京都中央区の日本橋川にかかる橋です。 まずは、地図でその位置を確認してみてください。 http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=1&grp=MapionBB&nl=35/40/50.876&el=139/46/39.675&scl=10000&bid=Mlink 首都高速のこのあたりのルートは、見事に川の上︵あるいは川そのものの水を抜いて︶計画されたことがよく分かりますね。 さらに日本橋近辺の様子を立体的に表した図がありますのでご紹介します。 http://www.hido.or.jp/nihonbashi/jsp/chika/05.html 日本橋は、江戸時代から文化・商業の中心地であり、さらに五街道全ての起点でもありました。 現在でも、日本橋の中央には日本国道路元標が設置されており、︵1︶国道1号︵終点‥大阪府大阪市北区梅田新道︶ 、︵2︶国道4号︵終点‥青森県青森市︶、︵3︶国道6号︵終点‥宮城県仙台市宮城野区︶、︵4︶国道14号︵終点‥千葉県千葉市中央区︶ 、︵5︶国道15号︵終点‥神奈川県横浜市神奈川区︶、︵6︶国道17号︵終点‥新潟県新潟市︶ 、︵7︶国道20号︵終点‥長野県塩尻市︶ の7路線の起点となっています。 箱根駅伝においても、1999年から箱根駅伝の最後の見せ場として、10区のコースを日本橋経由へ変更しています。これは、昨年、駒澤が4連覇した時に撮影したものですが、正面に見えるのが日本橋川にかかる常盤橋。常盤橋の先を右に折れて直ぐのところが日本橋です。
そのような重要な場所ですから、小泉首相は特にこだわりがあったのでしょう。 歌舞伎など日本の伝統文化や歴史と共に、文化都市・東京のシンボルとして﹁日本橋に空を!﹂ということで昨年末、首相の私的な有識者懇談会が発足し、動き出したというのが冒頭の記事です。 しかしながら、一体どのようにして日本橋上空の首都高速を取り除くのでしょうか。 ただ取り除くだけでは、首都高速の機能が根本的に失われてしまいます。 従って、何らかの代替ルートを考えなければなりません。 第1次小泉内閣の時に、東京都心における首都高速道路のあり方委員会が4案を提示していますので、それを見てみましょう。 http://www.mlit.go.jp/road/yuryo/arikata/teigen/teigen.pdf︻第1案︼浅い地下案
まあ、これが一番現実的な方法でしょうか。 障害となる地下鉄は銀座線と半蔵門線。 特に、銀座線は日本で最も古い地下鉄の一つですから、浅いところを通っています。 ですから、日本橋川の銀座線の下を通すことは、比較的︵あくまでも比較的です︶簡単だと思われます。 新たに敷設する路線延長も短くて済みます。︻第2案︼別線地下案
これは、かなり大掛かりですね。 そもそも、日本橋川のルートを大きく変えて、靖国通りか外堀通りの地下を通す計画ですが、これは費用的にも、周囲への影響度からも、かなり困難な計画ではないかと思います。︻第3案︼一体整備地下案
これは面白い計画ですね。 日本橋川の北側に再開発ビルと一体化した路線計画とするものです。 ビルの基礎部分地下に路線を配置しますので、ビルの耐用年数が来て、建て替えるときも比較的簡単にできそう。︻第4案︼一体整備高架案
この案は夢があります。 首都高速は高い位置を通っていますから、既存路線との取り付け区間の工事もスムーズに行えます。 ただし、ネックは万が一事故が発生した時の、防災対策と、ビルが老朽化した際の建て替えをどうするかですね。それぞれ一長一短があり、また、これ以外の方法もあるかもしれません。 事業そのものをやらないというのも、もちろん選択肢の一つです。 総工費は案にもよりますが、3000億?6500億円とも見積もられています。 日本橋に空を取り戻すことの意義は大きいですが、それにかかる費用も膨大になりますから、よくよく検討して、国民の理解が得られから事業に取り掛かって欲しいものです。
2005年12月24日
20:80の法則
パレートの法則とは、イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレート︵Vilfredo Federico Damaso Pareto︶が発見した法則ですが、20‥80の法則といった方が親しみやすいかもしれません。
簡単にいうと、﹁全体の8割の事象は、全体を構成する2割の要素が生み出している﹂という法則です。
例を挙げると
 ■売り上げの8割は全顧客の2割によるものである。
■売上げの8割は、2割の商品の売上げである。
■仕事の8割は、全社員の内の2割がこなしている。
■不具合の8割は、2割の不具合項目に原因がある。
■蓄積された資料の約8割は不要である。
■所得税の8割は2割の人が払っている。
■宗費の8割は、2割の寺院が負担している。︵時事ネタ‥右グラフ参照︶
■売り上げの8割は全顧客の2割によるものである。
■売上げの8割は、2割の商品の売上げである。
■仕事の8割は、全社員の内の2割がこなしている。
■不具合の8割は、2割の不具合項目に原因がある。
■蓄積された資料の約8割は不要である。
■所得税の8割は2割の人が払っている。
■宗費の8割は、2割の寺院が負担している。︵時事ネタ‥右グラフ参照︶
といったものです。
この法則はいろいろなところで活用されています。 例えば、製品の品質管理における、改善項目を10項目あげた場合、そのうち上位2項目を改善することによって、全体の8割を改良したことと同様の効果が期待できるという、実に有用な法則なのです。 このことを逆に利用すると、実に興味深い事実が見えてきます。 例えば、顧客満足度調査をしたとします。 その中で、一番不平不満を訴えるのは、2割の主要顧客ではなく、それ以外の︵あまり重要ではない︶顧客である場合が多いということです。 つまり、2割の主要顧客は満足しているから、御得意さんであるわけで、この主要顧客の特性を理解し、そのような顧客層を広げていくことができれば、それだけ効率的に利益を拡大させることができる訳です。
今の世の中は、完璧を求める風潮にあります。 私は十数年前に、都庁の下水道局・計画部に所属していたことがありますが、いよいよ区部下水道普及率96%というところにあって、残りの4%がどれだけ困難であったか、身にしみて感じました。 現在は公称100%となっていますが、実際は1%未満のところでどうしても達成できていないところがあるはずです。 このように、8割程度までの効率までは簡単に達成できるでしょうが、そこから進んで、完璧まで残り数パーセントというところは、実に困難であることが分かります。 全てのことに対して、完璧をめざすのではなく、2割程度の余裕をもって、余裕があることを前提にゆったり過ごすことが、どれだけ生活に豊かさをもたらしてくれるのか計り知れません。 また、パレートの法則は、宗門の財政部門にあっては、宗費をどのようにしたら、より公平︵この定義も難しいですね︶に集めることができ、どのようにしたら、より公平に分配することができるのか、その答えを導き出す一つのヒントになることでしょう。
︻関連トピックス︼ http://teishoin.net/blog/000271.html ※グラフは﹃曹洞宗宗勢総合調査報告書﹄(1995年︶ 曹洞宗宗務庁発行 P176 より引用
 ■売り上げの8割は全顧客の2割によるものである。
■売上げの8割は、2割の商品の売上げである。
■仕事の8割は、全社員の内の2割がこなしている。
■不具合の8割は、2割の不具合項目に原因がある。
■蓄積された資料の約8割は不要である。
■所得税の8割は2割の人が払っている。
■宗費の8割は、2割の寺院が負担している。︵時事ネタ‥右グラフ参照︶
■売り上げの8割は全顧客の2割によるものである。
■売上げの8割は、2割の商品の売上げである。
■仕事の8割は、全社員の内の2割がこなしている。
■不具合の8割は、2割の不具合項目に原因がある。
■蓄積された資料の約8割は不要である。
■所得税の8割は2割の人が払っている。
■宗費の8割は、2割の寺院が負担している。︵時事ネタ‥右グラフ参照︶
といったものです。
この法則はいろいろなところで活用されています。 例えば、製品の品質管理における、改善項目を10項目あげた場合、そのうち上位2項目を改善することによって、全体の8割を改良したことと同様の効果が期待できるという、実に有用な法則なのです。 このことを逆に利用すると、実に興味深い事実が見えてきます。 例えば、顧客満足度調査をしたとします。 その中で、一番不平不満を訴えるのは、2割の主要顧客ではなく、それ以外の︵あまり重要ではない︶顧客である場合が多いということです。 つまり、2割の主要顧客は満足しているから、御得意さんであるわけで、この主要顧客の特性を理解し、そのような顧客層を広げていくことができれば、それだけ効率的に利益を拡大させることができる訳です。
今の世の中は、完璧を求める風潮にあります。 私は十数年前に、都庁の下水道局・計画部に所属していたことがありますが、いよいよ区部下水道普及率96%というところにあって、残りの4%がどれだけ困難であったか、身にしみて感じました。 現在は公称100%となっていますが、実際は1%未満のところでどうしても達成できていないところがあるはずです。 このように、8割程度までの効率までは簡単に達成できるでしょうが、そこから進んで、完璧まで残り数パーセントというところは、実に困難であることが分かります。 全てのことに対して、完璧をめざすのではなく、2割程度の余裕をもって、余裕があることを前提にゆったり過ごすことが、どれだけ生活に豊かさをもたらしてくれるのか計り知れません。 また、パレートの法則は、宗門の財政部門にあっては、宗費をどのようにしたら、より公平︵この定義も難しいですね︶に集めることができ、どのようにしたら、より公平に分配することができるのか、その答えを導き出す一つのヒントになることでしょう。
︻関連トピックス︼ http://teishoin.net/blog/000271.html ※グラフは﹃曹洞宗宗勢総合調査報告書﹄(1995年︶ 曹洞宗宗務庁発行 P176 より引用
2005年11月 1日
働き蟻と怠け蟻
黙々と働くと思われていた働きアリの約2割が、実はほとんど働いていないことを、北海道大大学院農学研究科の長谷川英祐助手(進化生物学)らが確認した。長谷川助手らは、林の土中などに生息するカドフシアリ約30匹ずつの3つのコロニー︵血縁集団︶を、石こうでつくった人工の巣に移し、1匹ずつマーカーで印を付けて観察。 1日3時間、昨年5月からの5カ月間で、行動類型を分類した。 すると﹁女王アリや卵などをなめてきれいにする﹂﹁巣の掃除をする﹂﹁エサ取りをする﹂などの労働行為をするアリは各コロニーの約8割で、﹁停止している﹂﹁自分の体をなめている﹂﹁何もせず移動している﹂だけで、ずっと働かないアリが約2割いた。 このうち1つのコロニーで、最もよく働く6匹を取り除いてみたところ、次によく働くアリの労働量が増えたが、働かないアリは何があっても働かなかった。 働かないアリは、年を取って働けないか、そもそも寄生するだけの存在とも考えられるが、長谷川助手は﹁働かないことでコロニーに何らかの貢献をしている可能性もある。 集団で行動する生物にとってどんな個性が必要なのか、興味がある﹂と話している。 ﹃東奥日報﹄2003年10月28日の記事 論文概要PDF
今、一つのプロジェクトに取り組んでいます。 約1万5000もある膨大な資料を精査して、データベース化すること。 これを一定の期間のうちに、約10人の仲間で成し遂げるというものです。 私は、その指揮のような役を担わせて頂いているのですが、このプロジェクト、コンピュータ入力を伴なったり様々な証書を解読したりといった複雑な作業でもあるため、なかなか大変なんですね。 それでも、皆さん、それぞれ真剣に取り組んでいただけることがとても有り難いです。 何人もいると、傍目には、進捗が遅かったり、無駄話ばかりしているように見える仲間もいるんですね。 しかし、それはそれで、貴重な人材であることにはかわりありません。 仮に、効率が悪いだろうということで、人を切って、進捗の優秀な人ばかり残したとします。 けれども、それでは、ギスギスした心地悪い、息苦しい雰囲気に包まれてしまい、全体の結果としては必ずしも最大の効率を生み出さないということなのかも知れません。 全員が一心不乱にバリバリ働いている、そんな職場、絶対に嫌です。 癒しをもたらす役割を果たす︵怠け者のように見える︶人がいてこそ、職場は効率良く回るのでしょうね。 また、いつもは我武者羅に頑張っている人も、たまには癒し系の役割を果たしてみることも必要なのではないでしょうか。 プロジェクトのゴールまであと数ヶ月。 一歩一歩、着実に進めていきましょう。追記‥このプロジェクトは無事終了しました。 御手伝いいただいた皆様、本当にお疲れ様でした! 宗務庁退任のご挨拶とお礼
2005年10月 4日
平成電電民事再生法適用&個人情報垂流し
民事再生法適用を申請=負債1200億円、値下げ競争激化で?平成電電格安通信サービスの平成電電︵東京︶は3日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、受理されたと発表した。固定電話市場での値下げ競争激化が響き、資金繰りが悪化、自主再建を断念した。顧客への通信サービスは継続する。負債総額は9月末で1200億円に上る。佐藤賢治社長が同日午後に記者会見し、正式発表する。 同社は、加入者と最寄りの電話局までの回線をNTTから借りて通信料金を大幅に引き下げる﹁直収電話﹂サービスに、業界で初めて参入した。しかしその後、日本テレコムやKDDIも追随し、顧客の獲得が伸び悩んでいた。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051003-00000037-jij-bus_allここ数年、通信料金競争が激しくなり、そのお陰で固定電話、携帯電話、インターネットなど、さまざまな料金の恩恵を受けさせていただきました。 しかし、そんな中、今回の平成電電のように、その過当競争のあおりで巨大な負債を抱えたまま民事再生法適用となる会社が出てしまいました。 TVのCMや新聞一面広告などを派手に連発したしていましたが、最近では予定現金分配率年10%相当という無茶苦茶な高配当の投資組合 ﹁平成電電システム21号匿名組合﹂を作ったり・・・ http://www.hdd-s.com/index.html
単なる一通信企業の行き詰まりということだけではなく、これからますます問題が波及していきそうです。 今日はその序章に過ぎないのかもしれません。 特に、平成電電システム21号匿名組合に対しては、投資者19,000人、総額490億円という資金が集まったとの速報もあります。 平成電電破たん 出資金総額は490億円、返還困難に やはり、この低金利時代が背景なのでしょうか、配率年10%相当に魅了されてしまった被害者がこんなにも多いことに驚かされます。 世の中、そんなに美味い話が転がっている訳が無いですよ、ということなんでしょうね。
さらに、別の大きな問題も発覚し始めています。 それは、九州にあるエステの顧客情報かアンケートで得られた個人情報が平成電電サイトのトップディレクトリーに置かれていたという問題です。 住所、電話番号や生年月日を含む約7,000件の個人情報がたやすく誰でも見える場所におかれており、それが流出して一部で騒がれはじめているのです。
平成電電のサイトをおいている同一サーバー内にエステサイトのデータ領域があり、サーバー管理者あるいはサイト作成担当者の不注意な管理によって、個人情報が垂流しの状態になったものと推測されます。 こちらのニュースも、そのうちに表沙汰になって大騒ぎになることでしょう。 本人の知らない間に、個人情報を晒されてしまうという、情報化社会の悪い面を見せ付けられた典型的な一例です。
2005年8月 8日
寺院運営と現代社会
﹁ワールドビジネスサテライト﹂
http://www.tv-tokyo.co.jp/wbs/
テレビ東京・9日深夜11時?
特集﹁寺院運営と現代社会﹂
カフェ、介護施設…お寺の経済学
葬式の簡略化や法事の減少、檀家制度の崩壊…。寺離れが進む中、お布施に頼らない収益基盤を作ろうと動き始めた寺がある。目指すは地域のニーズに応える事業。イギリス伝統の酒、スコッチウイスキーが巻き起こす新旋風も。
■浄土真宗本願寺派 光明寺︵東京都港区︶ オープンテラスで境内を開放している寺院 http://www.komyoji.org/welcome.html ■浄土真宗本願寺派 善了寺︵横浜市戸塚区︶ 庫裏を利用してデイサービスを始めた寺院 http://www.zenryouji.jp/ ■曹洞宗 長福寺︵藤沢市︶ 寺院が中心となって地域コミュニティを再生させていくため、 檀家組織という枠組みをこえた地域活動を進めている寺院
本日、上記の、個性的な活動をされている寺院の特集が放送されます。
︵8日放送予定でしたが、衆議院解散によって、9日の放送になりました︶
このうち、光明寺さんは、SOTO禅インターナショナルの会議場所としてよく利用させていただいております。
さらに、長福寺さんは、教区寺院であります。
よく知っている御寺院さんが紹介されますので是非ご覧ください。
 昨年秋の寺コンサート@長福寺
こども祭太鼓とアクワバ︵ガーナ出身のバンド︶とのセッションの写真です。
私も子どもたちと楽しませていただきました。
昨年秋の寺コンサート@長福寺
こども祭太鼓とアクワバ︵ガーナ出身のバンド︶とのセッションの写真です。
私も子どもたちと楽しませていただきました。
■浄土真宗本願寺派 光明寺︵東京都港区︶ オープンテラスで境内を開放している寺院 http://www.komyoji.org/welcome.html ■浄土真宗本願寺派 善了寺︵横浜市戸塚区︶ 庫裏を利用してデイサービスを始めた寺院 http://www.zenryouji.jp/ ■曹洞宗 長福寺︵藤沢市︶ 寺院が中心となって地域コミュニティを再生させていくため、 檀家組織という枠組みをこえた地域活動を進めている寺院
 昨年秋の寺コンサート@長福寺
こども祭太鼓とアクワバ︵ガーナ出身のバンド︶とのセッションの写真です。
私も子どもたちと楽しませていただきました。
昨年秋の寺コンサート@長福寺
こども祭太鼓とアクワバ︵ガーナ出身のバンド︶とのセッションの写真です。
私も子どもたちと楽しませていただきました。
2005年7月 9日
広告収入に頼らないメディアは存在しうるか
■はじめに
既存のメディアの収入を見てみると、例えば新聞社は、購読収入と広告収入の2つが重要な収入の柱である。このほかに、刊行物の発行などの付帯事業によって賄うというのがモデルである。
このうち、広告収入により印刷費と人件費、事務所経費をカバーできるのが理想的であると言われている。このようなモデルでは、広告収入を無視しては成り立たないことになる。
ところが、購読者が限られた小さなミニコミ紙や業界紙の場合は、購読料収入は読者層が少ないため、広告収入無くして経営していくのは至難の技である。実際にミニコミ紙のほとんどは、購読料収入よりも広告収入の割合が大幅に超過している。
購読料収入の割合がどれだけ少ないかということが、そのミニコミ紙がどれだけ評価の高い媒体といえるかという指標になりうる所以である。
■ウェブメディアでの可能性を探る さて、それではインターネットや電子メールなどによるニュース配信ではどうだったであろうか。1995年のウェブ系メディアでは、完全な広告収入モデルがほとんどであったと言える。しかし、1996年ごろから脱広告の動きがあり、WSJやESPNスポーツゾーンのように、広告収入+購読料型のメディアが出現した。しかし、あくまでも広告収入を重要な収入の柱と位置付けており、購読料だけで運営するということは目標には掲げていなかった。 その後の動向として、物品販売収入モデルというものも出現し、サンノゼマーキュリー+バーンズ・アンド・ノーブルのキックバックシステムや、また記事の内容を有料でビデオ配信したり、ESPNスポーツゾーンでも関連商品の販売を行っている。従って、広告収入・購読料収入・販売収入がどの程度の割合になるかという問題になる。
■広告の無いサイバーメディアとは それでは、完全に広告収入が無いメディアというのは成立するのであろうか。特定の組織が影響を与えるなら、広告収入無くしても成り立つかもしれない。しかし、そうではなく、一般的なサイバーメディアとしてそのようなメディアが成り立つかということを考えてみる。 まず、第一の可能性としては、サイバーメディアの発達によって、情報が氾濫し、情報自体の単価が下落していること、その他方で情報のライフサイクルが伸びていることによるものである。前者は、購読料収入にマイナス要因として働くが、後者は、データベースへの記事蓄積と全文記事検索により記事が将来的にも価値を持ちつづける可能性を示唆している。サイバーメディアではこのようなデータベース型のアーカイブの整備が容易なため、検索エンジンの構築如何によって記事を効率的に検索し、提供することが可能になろう。 そうなると時代を重ねるにつれて、情報のライフサイクルは伸び、データベースとしての価値が付加されていく。 このような蓄積された価値から、どのように利益回収を行うかということを確立するかということが、広告収入から脱却していく第一の可能性であると考えられる。 第二の可能性は、﹁良いコンテンツは儲かる﹂というモデルである。企業努力によるボランティア型の無料情報配信というモデルから、さらに一歩進めて、その企業だけが持ちうる独自の情報︵購読者が購読料を支払ってもその情報を得たいという質の高い情報︶を提供するということである。 第三は、供給するサービスを無料の部分と有料の部分とに階層化するということによる購読料収入の期待である。同じコンテンツを提供するとしても、単にテキストベースでアウトラインのみを提供するのと、詳細記事や映像の付加などの差別化を図ることにより付加価値を付ければ、料金を賦課することが可能であろう。 インターネットの情報=無料というモデルが暗黙の内に成立しているが、それは前段で述べたように情報の氾濫による情報単価の下落というよりは、どのような情報がそこで提供されているのかということが見えないからであり、質の高い情報が提供されているということが理解されれば、購読料を払っても良いと考える読者は多いのではないだろうか。 当然、購読料を払っても欲しいと思える情報を提供できるということが前提条件ではある。
■まとめ メディアが広告収入に頼ることは、少なからずメディアとしての自由さを失うということでもあり、裏返して言えば、広告の無いメディアというのが﹁ジャーナリズム﹂本来の、情報を売るという在り方であると思う。サイバーメディアは印刷メディアに比べて配信費用を格段に安く抑えることが出来る。また、フットワークの軽いメディアであるとも言える。そのような特徴を生かし、﹁本音﹂の情報を積極的に配信し、そこにエンパシィを感じる人たちを集めて行けば良いのではないだろうか。 サイバーメディアは既存のマスメディアとは異なった性質を持つメディアである。その点でマスメディアとは棲み分けが十分に可能であり、新しい領域のメディアとして存在していくことができると考えられる。 そしてサーバーメディアに求められる本来の姿というのが、インディペンデンスドであることであり、それを果たすためには、広告収入によらず、購読料収入のみで成立することがもっとも必要なことなのではないだろうか。 結論として、広告の無いサイバーメディアは可能であると考える。これは、広告収入があってはいけないということではなく、広告収入を前提とした在り方ではいけないということであり、それがサイバーメディアの理想的な姿であろう。
■ウェブメディアでの可能性を探る さて、それではインターネットや電子メールなどによるニュース配信ではどうだったであろうか。1995年のウェブ系メディアでは、完全な広告収入モデルがほとんどであったと言える。しかし、1996年ごろから脱広告の動きがあり、WSJやESPNスポーツゾーンのように、広告収入+購読料型のメディアが出現した。しかし、あくまでも広告収入を重要な収入の柱と位置付けており、購読料だけで運営するということは目標には掲げていなかった。 その後の動向として、物品販売収入モデルというものも出現し、サンノゼマーキュリー+バーンズ・アンド・ノーブルのキックバックシステムや、また記事の内容を有料でビデオ配信したり、ESPNスポーツゾーンでも関連商品の販売を行っている。従って、広告収入・購読料収入・販売収入がどの程度の割合になるかという問題になる。
■広告の無いサイバーメディアとは それでは、完全に広告収入が無いメディアというのは成立するのであろうか。特定の組織が影響を与えるなら、広告収入無くしても成り立つかもしれない。しかし、そうではなく、一般的なサイバーメディアとしてそのようなメディアが成り立つかということを考えてみる。 まず、第一の可能性としては、サイバーメディアの発達によって、情報が氾濫し、情報自体の単価が下落していること、その他方で情報のライフサイクルが伸びていることによるものである。前者は、購読料収入にマイナス要因として働くが、後者は、データベースへの記事蓄積と全文記事検索により記事が将来的にも価値を持ちつづける可能性を示唆している。サイバーメディアではこのようなデータベース型のアーカイブの整備が容易なため、検索エンジンの構築如何によって記事を効率的に検索し、提供することが可能になろう。 そうなると時代を重ねるにつれて、情報のライフサイクルは伸び、データベースとしての価値が付加されていく。 このような蓄積された価値から、どのように利益回収を行うかということを確立するかということが、広告収入から脱却していく第一の可能性であると考えられる。 第二の可能性は、﹁良いコンテンツは儲かる﹂というモデルである。企業努力によるボランティア型の無料情報配信というモデルから、さらに一歩進めて、その企業だけが持ちうる独自の情報︵購読者が購読料を支払ってもその情報を得たいという質の高い情報︶を提供するということである。 第三は、供給するサービスを無料の部分と有料の部分とに階層化するということによる購読料収入の期待である。同じコンテンツを提供するとしても、単にテキストベースでアウトラインのみを提供するのと、詳細記事や映像の付加などの差別化を図ることにより付加価値を付ければ、料金を賦課することが可能であろう。 インターネットの情報=無料というモデルが暗黙の内に成立しているが、それは前段で述べたように情報の氾濫による情報単価の下落というよりは、どのような情報がそこで提供されているのかということが見えないからであり、質の高い情報が提供されているということが理解されれば、購読料を払っても良いと考える読者は多いのではないだろうか。 当然、購読料を払っても欲しいと思える情報を提供できるということが前提条件ではある。
■まとめ メディアが広告収入に頼ることは、少なからずメディアとしての自由さを失うということでもあり、裏返して言えば、広告の無いメディアというのが﹁ジャーナリズム﹂本来の、情報を売るという在り方であると思う。サイバーメディアは印刷メディアに比べて配信費用を格段に安く抑えることが出来る。また、フットワークの軽いメディアであるとも言える。そのような特徴を生かし、﹁本音﹂の情報を積極的に配信し、そこにエンパシィを感じる人たちを集めて行けば良いのではないだろうか。 サイバーメディアは既存のマスメディアとは異なった性質を持つメディアである。その点でマスメディアとは棲み分けが十分に可能であり、新しい領域のメディアとして存在していくことができると考えられる。 そしてサーバーメディアに求められる本来の姿というのが、インディペンデンスドであることであり、それを果たすためには、広告収入によらず、購読料収入のみで成立することがもっとも必要なことなのではないだろうか。 結論として、広告の無いサイバーメディアは可能であると考える。これは、広告収入があってはいけないということではなく、広告収入を前提とした在り方ではいけないということであり、それがサイバーメディアの理想的な姿であろう。
2005年5月27日
賦課金 大幅見直しへ
浄土真宗本願寺派 算定基準「不公平」と声浄土真宗本願寺派︵本山・西本願寺、京都市下京区︶は、本山への﹁税金﹂にあたる賦課金の制度を1970年の導入以来初めて大幅に見直す。末寺への割当額を決める際の算定基準に対し﹁現状を反映してなく、不公平﹂との不満が相次いでいたためで、26日の臨時宗会で関連する宗則︵宗派の法律︶を可決した。 賦課金は同宗派の年間収入の約13%を占め、本年度の予算額は約10億8200万円。所属する僧侶の階級や人数、自主申告の門信徒戸数に基づく﹁護持口数﹂、寺院を8段階に格付けした﹁寺班﹂などを基準に、各教区や末寺への割当額を決めていた。ところが、江戸時代に寺院の由緒や規模を基に定められたといわれる﹁寺班﹂は、以前から宗派内で﹁実情からかけ離れている﹂﹁格付けは民主的でない﹂との批判が強く、今回の制度改革では算定の根拠から外し、実質的に廃止する方向となった。 また、護持口数も35年前の基準にのっとって定めていたため、新制度では寺院収入や所在する都道府県の県民所得など客観的な指標を用いるように改正した。ただ、奈良教区など負担額が従来より2倍以上に膨らむ地域もあり、﹁新たな不公平感を生む﹂との反発が出たため、護持口数の新制度導入は来年度以降に持ち越した。 http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005052700021&genre=J1&area=K1F
曹洞宗においては、平成11年2月15日に開催された級階査定委員会に於いて本級階査定委員会専門部会を組織することが承認され、同年6月8日に発足し、以来、抜本的な宗費負担の論議が約6年に亘り重ねられてきました。 若輩ながら、私もその専門部会委員に加えていただき、しかも自由な意見を発言させていただく機会を持ったことはとても貴重な体験でありました。 保守的と思われがちな伝統宗教行政の中でも、曹洞宗は先進的なシステムが構築され、若い世代の意見も通りやすい雰囲気にあるということはとても有難いことであります。 また、逆にそれだけ、重責を戴いたわけですので、自分なりにできる限りの調査研究をさせていただきました。 曹洞宗の宗費負担は、これまでも、他の宗派に比べて飛びぬけて綿密に出来ています︵と自負しています︶。 今回は、それをさらに改良し、各方面からの要望に応えるためにより公平感をもたせるべく、様々な係数を試行錯誤しながら作成したつもりです。 級階査定委員会、専門部会委員、宗務庁各役職員の皆さんで一丸になって練り上げてきた、その一応の成果が、先の第95回通常宗議会で審議可決された財務規程︵宗報5月号参照︶であり、各御寺院様へ届いているであろう寺院財産申告書となっているのです。︵というわけで、今は平日はほぼ毎日宗務庁へ出勤しています︶ もちろん、今回の財務規程が最終結論というわけではなく、時代に即した抜本的な宗費賦課基準というものを常に研究していく必要があると思います。 御寺院様におかれましては、10年に一度の寺院財産申告、どうぞご協力を伏してお願いいたします。 追伸‥業務についての詳細はブログに記載することはできませんので、寺院財産申告、級階査定についての質問事項は所定の方法によりお願いいたします。
2005年3月31日
ペイオフ覚え書き
あと数日、4月からペイオフの全面解禁となります。
寺院は非営利法人だから関係ないと思われがちですが、例えば諸堂の建設積立金とか、修繕積立金とか、護持会費とか・・・・・そのほか諸々の法人運営資金について、いざペイオフとなった場合に、対策を何も講じていなかったとすれば代表役員の責任が問われるかもしれません。
ペイオフ全面解禁後は、金利のつく預金はすべてペイオフ対象なるため、普通預金でさえも1000万円と利息分しか保護されないことになります。 ︻覚え書き︼ ■恒久措置として全額保護される預金等 決済用預金。 決済用預金は、﹁無利息、要求払い、決済サービスを提供できること﹂という3要件を満たすもの。 ・当座預金 ・利息のつかない普通預金など
■預金保護の対象となっている預金等 1金融機関1人当たり、合算して元本1,000万円までと、その利息等︵定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等を含みます。︶が保護される ・当座預金 ・定期預金 ・貯蓄預金 ・普通預金 ・通知預金 ・定期積金 ・別段預金 ・納税準備預金 ・掛金 ・元本補てん契約のある金銭信託︵ビッグ等の貸付信託を含む︶ ・金融債︵ワイド等の保護預り専用商品に限る︶ ・上記を用いた積立・財形貯蓄商品
■預金保護の対象となっていない預金等 保護されない預金等であっても破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われる可能性はある ・外貨預金 ・他人、架空名義預金 ・譲渡性預金 ・オフショア預金 ・日本銀行からの預金︵国庫金を除く︶ ・金融機関からの預金︵確定拠出年金の積立金の運用部分を除く︶ ・預金保険機構からの預金 ・無記名預金 ・導入預金 ・元本補てん契約のない金銭信託︵ヒット等︶ ・金融債︵保護預り専用商品以外のもの︶ 参考 預金保険制度・ペイオフ﹂・・・金融広報中央委員会
しかし、心に留めておかなければならないのは、実際に金融機関が破綻して、ペイオフとなった場合に、その保護された1000万円はすぐには下ろすことが出来ないだろうということです。 普通預金には、仮払金制度がありますが、破綻後一週間以内に60万円までとされており、さらに、定期預金には仮払金制度は適用されません。 したがって、法人の運営資金を工面するためには、相等の対策をとらないと、資金繰りに支障をきたすことになりそうです。 主なペイオフ対策は ■預金をいくつもの金融機関に分散する 手間はかかりますが、安全のためには致し方ないでしょう。 しかも、破綻の後に仮払がどの程度スムースに行われるかは疑問なので、ムーディーズなどの格付け機関による格付けの高い金融機関を調べておくことが必要でしょう。
■金利のつかない決済用預金に預ける 金利のつく預金はペイオフの対象になりますが、決済用預金のような金利無しの預金は全額保護の対象になります。 今のところは超低金利状態が続いていますので、決済用預金のメリットは大きいでしょう。
■郵便貯金を限度額まで利用する 郵便貯金は国が保証するため、安全性が特に高い。 しかし、一名義に対して元本1000万円の限度があるため、これを最大限に活動したほうがいいでしょう。 また、郵便振替口座は限度額は無いものの、決済用預金と同様、金利がつかない。
■国債や高格付けの公社債等に振り分ける 安全性はある程度高いことと果実を生み出す。 ■運転資金は、何らかの形で手元においておく 当面の運転資金は、いつでも引き出せる形の資金として持っておく とりあえず、こんなところでしょうか。 蛇足ですが、今日、宗務庁でペイオフに関してのテレビ局︵TBSニュース23︶からの取材撮影がありました。近日、宗務庁の様子が放映されるかもしれません。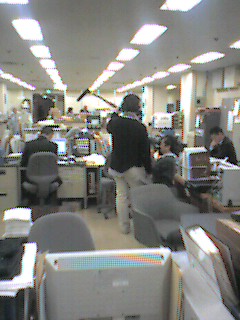
↑敢えてPHSのカメラでの写真です。雰囲気だけ・・・・
ペイオフ全面解禁後は、金利のつく預金はすべてペイオフ対象なるため、普通預金でさえも1000万円と利息分しか保護されないことになります。 ︻覚え書き︼ ■恒久措置として全額保護される預金等 決済用預金。 決済用預金は、﹁無利息、要求払い、決済サービスを提供できること﹂という3要件を満たすもの。 ・当座預金 ・利息のつかない普通預金など
■預金保護の対象となっている預金等 1金融機関1人当たり、合算して元本1,000万円までと、その利息等︵定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等を含みます。︶が保護される ・当座預金 ・定期預金 ・貯蓄預金 ・普通預金 ・通知預金 ・定期積金 ・別段預金 ・納税準備預金 ・掛金 ・元本補てん契約のある金銭信託︵ビッグ等の貸付信託を含む︶ ・金融債︵ワイド等の保護預り専用商品に限る︶ ・上記を用いた積立・財形貯蓄商品
■預金保護の対象となっていない預金等 保護されない預金等であっても破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われる可能性はある ・外貨預金 ・他人、架空名義預金 ・譲渡性預金 ・オフショア預金 ・日本銀行からの預金︵国庫金を除く︶ ・金融機関からの預金︵確定拠出年金の積立金の運用部分を除く︶ ・預金保険機構からの預金 ・無記名預金 ・導入預金 ・元本補てん契約のない金銭信託︵ヒット等︶ ・金融債︵保護預り専用商品以外のもの︶ 参考 預金保険制度・ペイオフ﹂・・・金融広報中央委員会
しかし、心に留めておかなければならないのは、実際に金融機関が破綻して、ペイオフとなった場合に、その保護された1000万円はすぐには下ろすことが出来ないだろうということです。 普通預金には、仮払金制度がありますが、破綻後一週間以内に60万円までとされており、さらに、定期預金には仮払金制度は適用されません。 したがって、法人の運営資金を工面するためには、相等の対策をとらないと、資金繰りに支障をきたすことになりそうです。 主なペイオフ対策は ■預金をいくつもの金融機関に分散する 手間はかかりますが、安全のためには致し方ないでしょう。 しかも、破綻の後に仮払がどの程度スムースに行われるかは疑問なので、ムーディーズなどの格付け機関による格付けの高い金融機関を調べておくことが必要でしょう。
■金利のつかない決済用預金に預ける 金利のつく預金はペイオフの対象になりますが、決済用預金のような金利無しの預金は全額保護の対象になります。 今のところは超低金利状態が続いていますので、決済用預金のメリットは大きいでしょう。
■郵便貯金を限度額まで利用する 郵便貯金は国が保証するため、安全性が特に高い。 しかし、一名義に対して元本1000万円の限度があるため、これを最大限に活動したほうがいいでしょう。 また、郵便振替口座は限度額は無いものの、決済用預金と同様、金利がつかない。
■国債や高格付けの公社債等に振り分ける 安全性はある程度高いことと果実を生み出す。 ■運転資金は、何らかの形で手元においておく 当面の運転資金は、いつでも引き出せる形の資金として持っておく とりあえず、こんなところでしょうか。 蛇足ですが、今日、宗務庁でペイオフに関してのテレビ局︵TBSニュース23︶からの取材撮影がありました。近日、宗務庁の様子が放映されるかもしれません。
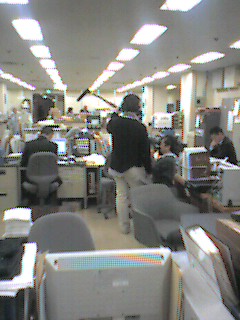
↑敢えてPHSのカメラでの写真です。雰囲気だけ・・・・
2005年3月25日
坊主は丸儲けかなぁ
新聞の投稿欄に、気になる投稿があったのでご紹介します。
先日のトピックスとも関連する部分があるかもしれません。
 お布施は﹁志﹂良心に従って
僧侶 ︵新潟県柏崎市︶
お彼岸参りに檀家さんを読経して回っている。2千円から5千円のお布施で寺のかき入れどきになっているのだが、3分ほどお経を読んでそれだけ頂くのだから、坊主は3日やったらやめられないと言われるのかもしれない。
千円しか包まれていないこともあるが、聖人でもない生臭坊主にはもった小ない金額である。
お布施は志だから本来、定価表はないが、私の山寺では戒名の末尾が﹁信士﹂﹁信女﹂の仏様の葬式では15万円頂く。信士料と本尊料、読経料が各5万円だ。
それより格が高い﹁居士﹂﹁大姉﹂ではその倍額。もう何十年来、ご理解を得ている。さらにその上の﹁院号﹂はめったにないが、その場合は50万円になる。
若いときはお布施をもらうのが恥ずかしくて目をそらして受け取ったものだ。
中年になってからは心の臓に毛が生え、しっかりと、またありがたく頂戴する。僧侶は正しい信仰をもって檀家さんに布教する義務があるからでもある。
以前、テレビで東京など大都市での葬式代に触れていたが、われわれの地方の倍以上の値段を伝えていた。
暴利とは言わないが、仏道にのっとって良心に恥じるところがないのか、と要らぬ気を回すこともある。
お布施は﹁志﹂良心に従って
僧侶 ︵新潟県柏崎市︶
お彼岸参りに檀家さんを読経して回っている。2千円から5千円のお布施で寺のかき入れどきになっているのだが、3分ほどお経を読んでそれだけ頂くのだから、坊主は3日やったらやめられないと言われるのかもしれない。
千円しか包まれていないこともあるが、聖人でもない生臭坊主にはもった小ない金額である。
お布施は志だから本来、定価表はないが、私の山寺では戒名の末尾が﹁信士﹂﹁信女﹂の仏様の葬式では15万円頂く。信士料と本尊料、読経料が各5万円だ。
それより格が高い﹁居士﹂﹁大姉﹂ではその倍額。もう何十年来、ご理解を得ている。さらにその上の﹁院号﹂はめったにないが、その場合は50万円になる。
若いときはお布施をもらうのが恥ずかしくて目をそらして受け取ったものだ。
中年になってからは心の臓に毛が生え、しっかりと、またありがたく頂戴する。僧侶は正しい信仰をもって檀家さんに布教する義務があるからでもある。
以前、テレビで東京など大都市での葬式代に触れていたが、われわれの地方の倍以上の値段を伝えていた。
暴利とは言わないが、仏道にのっとって良心に恥じるところがないのか、と要らぬ気を回すこともある。
う?ん、きっと本人は率直な意見を投稿しているのだろうし、悪気は無いんでしょうが、何だか悲しいですね。 先日は、宗教法人の課税問題について、﹁宗教活動の核心の部分だけは課税対象にしないべきだ﹂ということを書きましたが、こういう考えの僧侶が大多数であるならば、宗教法人の課税もやむなしという感じがします。 投稿内容の問題点を順次挙げて生きます。 ︵1︶お彼岸参りのお布施で寺のかき入れどきになっている 檀家さんから戴いた浄財を、単なる収入源としか見ていないのでしょうか。 ︵2︶3分ほどお経を読んでそれだけ頂くのだから、坊主は3日やったらやめられないと言われるのかもしれない。 その浄財をあたかも僧侶個人の収入にまるまる受け取る印象も与えます。まさに、読経の対価としての料金というイメージでしょう。 ︵3︶戒名の末尾が﹁信士﹂﹁信女﹂の仏様の葬式では15万円頂く。信士料と本尊料、読経料が各5万円だ。格が高い﹁居士﹂﹁大姉﹂ではその倍額。 まさに定価づけなのですが、このようなことを大っぴらにしていいのでしょうか。 ︵4︶中年になってからは心の臓に毛が生え、しっかりと、またありがたく頂戴する。僧侶は正しい信仰をもって檀家さんに布教する義務があるからでもある。 これも︵2︶と同様です。 ︵5︶テレビで東京など大都市での葬式代に触れていたが、われわれの地方の倍以上の値段を伝えていた。暴利とは言わないが、仏道にのっとって良心に恥じるところがないのか、と要らぬ気を回すこともある。 いやぁ、この最後の部分が一番ひどいですね。 まず、第一点に﹁暴利﹂という表現。 多くの都市部の寺院が、暴利を貪っているような表現、これはどうかと思います。 布施というのは、檀家さんが納得しただけのものを金銭という財施として、﹁お寺に﹂寄進するものです。 つまり、檀家さんからいただく布施の金額についてどうのこうの言うべきことではないということです。 そして、戴いたお布施は、僧侶の懐に入るのではなく、法人会計に入り、寺院のさまざまな経費に使われ、そのほとんどが檀家さんや公益のために使われるということ。残りの一部を給与として僧侶が戴いているわけです︵もちろん源泉徴収されます︶ 国語辞書を紐解くと、必ず次のように記載してあります。 ぼうず ばう― 1 ︻坊主︼ ――丸儲(まるもう)け 坊主は資本も経費もいらず、収入がそのまま全部儲けになる。 大辞林 第二版 ︵三省堂︶
﹁坊主丸儲け﹂のような誤解をなくすようにアピールしていかなければならないのに・・・・
ただし、確かに僧侶の中には、不心得なものもいることも確かです。 その代表が、一部の葬儀社が雇っていると契約しているアルバイト的な僧侶。 寺院を構えずにいる﹁マンション坊主﹂ともいうべきものです。 葬儀社から葬儀の依頼を受け、その布施のうち半分近くを葬儀社にキックバックし、残りを個人収入としてしまう。 このような現状を容認してしきてしまった社会風潮も残念なことです。 どちらにせよ、柏崎の僧侶の方の投稿は、投げかける対象を誤っていると思えてなりません。 公取委 葬儀トラブル防止へ 取引実態初の調査 指針策定を視野 公正取引委員会は、葬儀業の取引実態調査に乗り出した。 高齢化社会の到来で葬儀市場の規模が拡大するなか、業者間の競争も激しくなっている。 親族を亡くした直後の短時間で結ぶ高額契約だけに、 公取委は価格やサービスの表示方法に関する指針策定も視野にトラブル防止を図る。 日本消費者協会が平成15年に行ったアンケートによると、 葬儀一式費用の全国平均は150万円。 ただ、これ以外にも通夜からの飲食接待費用が38万円。 お経や戒名などの寺院費用が48万円かかっていた。 車に並ぶ大きな支出となるが、葬儀費用をどれくらいにするかは﹁親族の意見﹂(25.4%)、 ﹁社会的地位﹂(22.7%)、﹁葬儀社の助言﹂(22.7%)と、よく吟味して決めているとはいえないのが実情。 ﹃産経新聞﹄ 2005-2-8 ようやく、不透明といわれていた葬儀業界にもメスがはいってきました。 ﹁坊主丸儲け﹂に対する辞書の表現が自然に改まるように世間に認知してもらわなければならないし、寺院側も会計に関してもっともっと透明性を図っていかなければならない。 何故、宗教法人の宗教活動の部分が非課税とされるのかを寺院側はそれをしっかり受け止めていかなければならない。 そして、私たちも、今よりももっともっと僧侶としての資質を高めていかないと、世間から取り残される存在になってしまうでしょう。
-------------------------------- 同じ日の同じ欄に掲載されていた女子高生の投稿のほうが、よほどしっかりした考えを持った投稿だと思いますので併せて紹介します。
宗教の授業で自分見つめる 高校生 ︵愛知県日進市 17歳︶ 私が通っている女子高はカトリック系で、週に一度宗教の授業がある。その授業ではもちろん、神の存在について考えたりもするが、それ以上に自分自身のことを考える時間が多い。色々な角度から自分という人間を見て、色々な考えを持つ自分に気づく。 私はそんな宗教の時間があまり好きではない。自分って何だ、と考えるあまり、自分という人間が分からなくなったり、自分の冷たく小さな面に気づいてしまったりするからだ。プライドの高い私にとって、自分の冷たさや小ささと向き合い、これも自分なのだ、と認めることは、かなりの勇気がいることなのだ。 けれど最近、現実の自分を否定し続け、逃げてばかりでは、理想の自分に近づけないのではないか、と気づいた。私にとって宗教の授業は理想の自分と、現実の自分との闘いの場だ。やはり宗教の授業は好きではないけれど、自分という人間を好きになるために、もう少し、現実の自分の姿と闘ってみようと思う。
 お布施は﹁志﹂良心に従って
僧侶 ︵新潟県柏崎市︶
お彼岸参りに檀家さんを読経して回っている。2千円から5千円のお布施で寺のかき入れどきになっているのだが、3分ほどお経を読んでそれだけ頂くのだから、坊主は3日やったらやめられないと言われるのかもしれない。
千円しか包まれていないこともあるが、聖人でもない生臭坊主にはもった小ない金額である。
お布施は志だから本来、定価表はないが、私の山寺では戒名の末尾が﹁信士﹂﹁信女﹂の仏様の葬式では15万円頂く。信士料と本尊料、読経料が各5万円だ。
それより格が高い﹁居士﹂﹁大姉﹂ではその倍額。もう何十年来、ご理解を得ている。さらにその上の﹁院号﹂はめったにないが、その場合は50万円になる。
若いときはお布施をもらうのが恥ずかしくて目をそらして受け取ったものだ。
中年になってからは心の臓に毛が生え、しっかりと、またありがたく頂戴する。僧侶は正しい信仰をもって檀家さんに布教する義務があるからでもある。
以前、テレビで東京など大都市での葬式代に触れていたが、われわれの地方の倍以上の値段を伝えていた。
暴利とは言わないが、仏道にのっとって良心に恥じるところがないのか、と要らぬ気を回すこともある。
お布施は﹁志﹂良心に従って
僧侶 ︵新潟県柏崎市︶
お彼岸参りに檀家さんを読経して回っている。2千円から5千円のお布施で寺のかき入れどきになっているのだが、3分ほどお経を読んでそれだけ頂くのだから、坊主は3日やったらやめられないと言われるのかもしれない。
千円しか包まれていないこともあるが、聖人でもない生臭坊主にはもった小ない金額である。
お布施は志だから本来、定価表はないが、私の山寺では戒名の末尾が﹁信士﹂﹁信女﹂の仏様の葬式では15万円頂く。信士料と本尊料、読経料が各5万円だ。
それより格が高い﹁居士﹂﹁大姉﹂ではその倍額。もう何十年来、ご理解を得ている。さらにその上の﹁院号﹂はめったにないが、その場合は50万円になる。
若いときはお布施をもらうのが恥ずかしくて目をそらして受け取ったものだ。
中年になってからは心の臓に毛が生え、しっかりと、またありがたく頂戴する。僧侶は正しい信仰をもって檀家さんに布教する義務があるからでもある。
以前、テレビで東京など大都市での葬式代に触れていたが、われわれの地方の倍以上の値段を伝えていた。
暴利とは言わないが、仏道にのっとって良心に恥じるところがないのか、と要らぬ気を回すこともある。
う?ん、きっと本人は率直な意見を投稿しているのだろうし、悪気は無いんでしょうが、何だか悲しいですね。 先日は、宗教法人の課税問題について、﹁宗教活動の核心の部分だけは課税対象にしないべきだ﹂ということを書きましたが、こういう考えの僧侶が大多数であるならば、宗教法人の課税もやむなしという感じがします。 投稿内容の問題点を順次挙げて生きます。 ︵1︶お彼岸参りのお布施で寺のかき入れどきになっている 檀家さんから戴いた浄財を、単なる収入源としか見ていないのでしょうか。 ︵2︶3分ほどお経を読んでそれだけ頂くのだから、坊主は3日やったらやめられないと言われるのかもしれない。 その浄財をあたかも僧侶個人の収入にまるまる受け取る印象も与えます。まさに、読経の対価としての料金というイメージでしょう。 ︵3︶戒名の末尾が﹁信士﹂﹁信女﹂の仏様の葬式では15万円頂く。信士料と本尊料、読経料が各5万円だ。格が高い﹁居士﹂﹁大姉﹂ではその倍額。 まさに定価づけなのですが、このようなことを大っぴらにしていいのでしょうか。 ︵4︶中年になってからは心の臓に毛が生え、しっかりと、またありがたく頂戴する。僧侶は正しい信仰をもって檀家さんに布教する義務があるからでもある。 これも︵2︶と同様です。 ︵5︶テレビで東京など大都市での葬式代に触れていたが、われわれの地方の倍以上の値段を伝えていた。暴利とは言わないが、仏道にのっとって良心に恥じるところがないのか、と要らぬ気を回すこともある。 いやぁ、この最後の部分が一番ひどいですね。 まず、第一点に﹁暴利﹂という表現。 多くの都市部の寺院が、暴利を貪っているような表現、これはどうかと思います。 布施というのは、檀家さんが納得しただけのものを金銭という財施として、﹁お寺に﹂寄進するものです。 つまり、檀家さんからいただく布施の金額についてどうのこうの言うべきことではないということです。 そして、戴いたお布施は、僧侶の懐に入るのではなく、法人会計に入り、寺院のさまざまな経費に使われ、そのほとんどが檀家さんや公益のために使われるということ。残りの一部を給与として僧侶が戴いているわけです︵もちろん源泉徴収されます︶ 国語辞書を紐解くと、必ず次のように記載してあります。 ぼうず ばう― 1 ︻坊主︼ ――丸儲(まるもう)け 坊主は資本も経費もいらず、収入がそのまま全部儲けになる。 大辞林 第二版 ︵三省堂︶
﹁坊主丸儲け﹂のような誤解をなくすようにアピールしていかなければならないのに・・・・
ただし、確かに僧侶の中には、不心得なものもいることも確かです。 その代表が、一部の葬儀社が雇っていると契約しているアルバイト的な僧侶。 寺院を構えずにいる﹁マンション坊主﹂ともいうべきものです。 葬儀社から葬儀の依頼を受け、その布施のうち半分近くを葬儀社にキックバックし、残りを個人収入としてしまう。 このような現状を容認してしきてしまった社会風潮も残念なことです。 どちらにせよ、柏崎の僧侶の方の投稿は、投げかける対象を誤っていると思えてなりません。 公取委 葬儀トラブル防止へ 取引実態初の調査 指針策定を視野 公正取引委員会は、葬儀業の取引実態調査に乗り出した。 高齢化社会の到来で葬儀市場の規模が拡大するなか、業者間の競争も激しくなっている。 親族を亡くした直後の短時間で結ぶ高額契約だけに、 公取委は価格やサービスの表示方法に関する指針策定も視野にトラブル防止を図る。 日本消費者協会が平成15年に行ったアンケートによると、 葬儀一式費用の全国平均は150万円。 ただ、これ以外にも通夜からの飲食接待費用が38万円。 お経や戒名などの寺院費用が48万円かかっていた。 車に並ぶ大きな支出となるが、葬儀費用をどれくらいにするかは﹁親族の意見﹂(25.4%)、 ﹁社会的地位﹂(22.7%)、﹁葬儀社の助言﹂(22.7%)と、よく吟味して決めているとはいえないのが実情。 ﹃産経新聞﹄ 2005-2-8 ようやく、不透明といわれていた葬儀業界にもメスがはいってきました。 ﹁坊主丸儲け﹂に対する辞書の表現が自然に改まるように世間に認知してもらわなければならないし、寺院側も会計に関してもっともっと透明性を図っていかなければならない。 何故、宗教法人の宗教活動の部分が非課税とされるのかを寺院側はそれをしっかり受け止めていかなければならない。 そして、私たちも、今よりももっともっと僧侶としての資質を高めていかないと、世間から取り残される存在になってしまうでしょう。
-------------------------------- 同じ日の同じ欄に掲載されていた女子高生の投稿のほうが、よほどしっかりした考えを持った投稿だと思いますので併せて紹介します。
宗教の授業で自分見つめる 高校生 ︵愛知県日進市 17歳︶ 私が通っている女子高はカトリック系で、週に一度宗教の授業がある。その授業ではもちろん、神の存在について考えたりもするが、それ以上に自分自身のことを考える時間が多い。色々な角度から自分という人間を見て、色々な考えを持つ自分に気づく。 私はそんな宗教の時間があまり好きではない。自分って何だ、と考えるあまり、自分という人間が分からなくなったり、自分の冷たく小さな面に気づいてしまったりするからだ。プライドの高い私にとって、自分の冷たさや小ささと向き合い、これも自分なのだ、と認めることは、かなりの勇気がいることなのだ。 けれど最近、現実の自分を否定し続け、逃げてばかりでは、理想の自分に近づけないのではないか、と気づいた。私にとって宗教の授業は理想の自分と、現実の自分との闘いの場だ。やはり宗教の授業は好きではないけれど、自分という人間を好きになるために、もう少し、現実の自分の姿と闘ってみようと思う。
2005年3月24日
ペット供養は宗教活動?収益事業?
ペット供養は収益事業 寺院への課税認めるペット供養は﹁収益事業﹂に当たるとして課税されたのは不当として、愛知県春日井市の寺院﹁慈妙院﹂が、税務署に計約670万円の課税処分取り消しを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁の加藤幸雄裁判長は24日、原告の請求を棄却した。 原告側弁護士によると、ペット供養で課税をめぐる判決は初めて。 判決理由で加藤裁判長は、ペット供養の依頼者は宗教的意義を求め、供養は人の葬祭の形式を踏んでいると認定したが、﹁原告は料金表などを定めて支払いを受けており、民間業者と料金システムが類似。依頼者と原告は、料金の対価としてサービスを受ける関係にある﹂と述べた。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050324-00000068-kyodo-soci
さて、まず、基礎的な面からみていきましょう。 公益法人としての宗教法人が行う収益事業の考え方は、次のとおりとなっています。 ■公益法人等とは、財団法人、社団法人、宗教法人、学校法人など、特別法により設立された法人のことです。つまり、宗教法人は、宗教法人法により設立されている法人です。 ■公益法人等の収入は、 非課税とされる﹁非収益事業﹂﹁宗教活動﹂﹁公益事業﹂ 課税対象となる﹁収益事業﹂ とに分類され、収益事業に対して課税されます。 ■収益事業の範囲は、次に示された33の事業をいいます。 収益事業とは、次の33の事業︵付随して営まれるものを含む︶で、継続して事業場を設けて営まれるものをいう︵法人税法第2条、施行令5条1項︶、としています。 1.物品販売業 2.不動産販売業 3.金銭貸付業 4.物品貸付業 5.不動産貸付業 6.製造業 7.通信業 8.運送業 9.倉庫業 10.請負業 11.印刷業 12.出版業 13.写真業 14.席貸業 15.旅館業 16.料理店業その他の飲食業 17.周旋業 18.代理業 19.仲立業 20.問屋業 21.鉱業 22.土石採取業 23.浴場業 24.理容業 25.美容業 26.興行業 27.遊技所業 28.遊覧所業 29.医療保険業 30.洋裁 和裁 着物着付け 編物 手芸 料理 理容 美容 茶道 生花 演劇 園芸 舞踊 舞踏 音楽 絵画 書道 写真 工芸 デザイン 自動車操縦若しくは小型船舶の操縦︵以下 技芸という︶の教授 31. 駐車場業 32.信用保証業 33.その他工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権の譲渡又は提供を行う事業 ■公益法人の収益事業については 25%、平成14年4月1日以後開始した事業年度については22% の税率が適用されます。 ■公益法人等の寄附金の損金算入限度額は、収益事業から生ずる所得の 20%とされます。 収益事業部門から非収益部門への支出は、寄附金とみなす︵みなし寄附金︶ことになっています。 ■収益事業を営まなくても、住職や従業員等に支払われる給与には源泉徴収義務が生じます。
今回の司法判断は、ペット供養が宗教活動ではなく、収益事業と認められたということで、一見、きわめて意外な判断のように見えます。 古来から、日本人は動物や樹木などの生物に限らず、石や地面、水など無生物のものに対しても崇拝の対象としてきました。 ましてやペットについては家族同様に暮らしてきたわけですから、丁重に供養したいという要望はあるのでしょう。 ただし、今回の司法判断の重要なところは、 ☆料金表などを定めていた ☆したがって、依頼者と寺院は、料金の対価としてサービスを受ける関係にあった というところです。 葬儀や法要の費用は通常、布施ですから、お気持ちで…としか言いようがありません。 目安を…と聞かれても、それは、やはりお気持ちで…ということになるのでしょう。 逆に明確な定価を表示すると、それは宗教活動から離れてしまい、料金の対価と判断されてしまうわけです。 ですから、法要の際に御寺院さんへお布施を封筒に入れる際は、﹁読経料﹂ではなく、あくまでも﹁御布施﹂としていただいたほうがよろしいと思います。 さて、名古屋地方裁判所は、ペット霊園について収益事業と判断しました。 であるならば、寺院運営の面からみれば、ペット霊園にかかわる人件費、火葬炉の原価償却義、燃料費、その他諸々の経費を切り分けして、収益事業会計で独立させればそれで済む話です。 むしろ損金が多数発生して収益事業会計の利益はほとんど無くなるかもしれません。非課税事業として処理するよりは、収益事業として処理したほうが、寺院会計にとって健全な方向に向かうかもしれません。 ただ一点、家族同様にすごしてきたペットに対する供養が、宗教活動ではないと判断される点、この点だけは、宗教者としてとても残念な判断です。 これが拡大解釈されていき、あらゆる供養が費用の対価とみなされてしまうことです。 では地鎮祭は?ご神木の供養は?人形供養は? 宗教活動と収益事業の区分けは明確に出来ない部分が多いからです。
2005年3月13日
アスクルに学ぶ文具業界の流通革命
先日は、ハイパーマーケットの明暗について書いてみましたが、今日はここ数年で大きな変化をしている文具業界について考えてみます。
個人商店が、スーパーやコンビニ、さらにはハイパーマーケットのような大型店の進出、さらにはインターネットなどによる直販の普及により、競争で負けて撤退してしまう事例は多く見られます。中間業者排除による流通の変化です。
文房具屋さんも同様です。
思い返せば、学校の周りなどにいくつか文房具屋さんがあったのですが、今はほとんど店舗を見かけなくなりました。
どうなってしまったのでしょうか。
実は、文具業界は、他の業種と比べて独特の変化を遂げているのです。その流通の変化について、アスクルの例で考えてみます。
アスクルとは、文具・オフィス用品の通信販売で急成長を遂げている会社ですので利用されている方も多いでしょう。
https://www.askul.co.jp/
アスクルの﹁売り﹂は、社名の由来となった、注文した商品が翌日届く︵明日届く=明日くる︶ということなのですがであるが、東京・横浜・大阪などでは、なんと注文当日に届いたりします。
しかも2500円以上であれば無料配送されます。
アスクルの母体はPLUSであり、自社製品の通信販売がそのスタートとなっていますが、次第に取り扱い製品をライバル会社の製品にまで広げ、そればかりでなく食品や生活雑貨など、実に約19000アイテムに及ぶようになりました。
さて、冒頭で文具業界は、他の業種と比べて独特の変化を遂げていると述べましたが、中間業者排除の観点からアスクルを見てみると他の業種と少し特徴的なことがあるのです。 具体的には、営業・配送・受付業務を外部の企業と分担しているという点です。 従来の文房具の流通の仕組は、 メーカー⇒一次卸⇒二次卸⇒小売⇒消費者 というようなものでした。 もしも、アスクルがメーカーと顧客との直接カタログ販売をおこない、 メーカー⇒消費者 という構図になると、卸と小売の排除が起こり、既存の小売店の営業を阻害したことでしょう。 けれども、文具業界では単純な中間業者排除を行うのではなく、代理店としての役割分担を提起しているのが特徴です。 http://www.askul-net.com/askul-business.html ↑こちらに、その流通のしくみが分かりやすく図解されています。 つまり、全国1600の文具小売店と提携︵エージェントと呼ばれます︶し、料金回収と訪問営業を業務委託しているわけです。この点で既存の文具小売店を共存関係としてうまく利用していることがわかります。 代理店となった小売店は、従来の顧客をに対し、アスクルの営業活動を委託して行ないます。そして通信販売の売り上げを伸ばすということが、同時に小売店の利益に繋がるという新たな関係を築きあげていったのです。 そしてアスクルへ発注された商品の代金は、再び小売店が集め、その一部が小売店の利益となる構図なのです。 まとめると、 ︻顧客の新規入会からカタログ配送まで︼ 顧客からの発注⇒全国100万箇所の事業所へ⇒全国1600社のエージェントへ⇒アスクルへ登録依頼 ⇒ アスクルから顧客へカタログ発送 ︻発注から料金回収まで︼ 顧客からアスクルへFAX・インターネットで注文⇒アスクルから顧客へ商品配送⇒アスクルから顧客へ請求書発行︵送付代行‥アスクルからエージェントへ請求⇒エージェントから顧客へ請求︶⇒顧客からエージェントへ支払い→エージェントからアスクルへ支払い ということになります。 見かけ上は、エージェントの姿は表に現れないので、あたかもアスクルと顧客との二者間の単純な取引のように見えます。 アスクル エージェント でグーグル検索すると、大体その構図がつかめます。 http://www.google.com/search?hl=ja&rls=GGLD%2CGGLD%3A2003-50%2CGGLD%3Aja&q=%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%80%80%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr= なお、エージェント第一号は、東京の山崎文栄堂です。 平成5年当時、ごく普通の文具店であった山崎文栄堂は、数年間赤字経営が続いており、当時設立されたばかりのアスクルと事業提携をするようになりました。周囲からは、かなりの猛反対があったそうです。 それから9年が経過し、売上はエージェントになった当初から約25倍になり、全国のエージェントの中で、トップ5の常連となっています。 新しい流通構造の変化が、単純に中間業者排除にはならずに、新たな中間業者としての枠組みの構造を生じているのが面白い発想だと思います。 オフィス用品のように、購入したいものが予め明確になっているようなものは、カタログをみながらまとめて発注する方が顧客にとって便利です。 わざわざ文具店に出向いて必要なものを購入したりする必要もない。翌日に確実に届けられるという利便性も従来の流通では考えられなかったことです。また、2500円以上で商品配送料無料ということは中小事業所にとっても発注しやすい設定となっているといえます。 文具マーケットは1.4兆円とも言え、75%が法人向けと想定され、30人未満の事業所は実にそのうちの95%。 アスクルの分かりやすい発注の仕組みは、このような顧客層にまさにうってつけだったというわけです。 アスクル側は、インターネット上のカタログに掲載するための商品企画・開発、価格決定、カタログ製作、注文受付、在庫管理、商品発送、料金回収、クレーム処理が主な仕事となりますが、コア業務を行っている社員はわずか100名余であって、その数十倍もの周辺業務要員が存在するわけです。中段で述べた構図のように、これらが有機的に結びついて一体となった運営をおこなっている訳です。 アスクルが急成長を遂げ、かつ、高い顧客満足度を得る結果となっている理由には、カスタマーズリレーションシップマネジメントを1元管理して徹底的に行っているからといえます。また、物流システムの徹底的な整備によって、注文から発送までの時間を限りなく短くすることにより当日配送をも可能としているのです。 メーカが始めた通信販売はこれまでの文具︵現在では事務用品全般、電化製品、食品、飲料なども含まれる︶流通を大きく変えました。情報技術を使うことで、何種類もの商品の仕分けを早く正確に行い、運送会社による全国翌日配送、小売店に委託した顧客対応と営業力、新しい枠組みによる効率的な流通システムの再構築によって新しい構図を作り上げています。 アスクルは、有力文具小売店をはじめ様々な業態から参加したエージェント︵代理店︶とアスクルが一体となって、互いの長所と短所をカバーし、有効な機能だけを結び合わせる共存共栄の画期的な流通システムを展開することにより成功した企業の最たる事例といえます。 以降、文具業界だけでも次々と似たような仕組みが出来上がってきました。 ︻同様の主な文具企業︼ ぱーそなるたのめーる︵大塚商会︶ http://www.p-tano.com/ カウネット︵コクヨ︶ http://www.kaunet.info/ イーサプライ http://www.e-supply.co.jp/
企業間でそれぞれの力を組み合わせて、強靭な流通のしくみを作るという流れは、今後、様々な分野で進展していくことでしょう。 ----------------------------------- アスクルのカタログはこんなに厚い。 見ているだけでも楽しいです。 カタログが送られれくる度に、顧客の心をつかむサービスが付加されていることに驚かされています。
最近注文した発注リストが挟み込まれていたり・・・
︵注意‥決してアスクルの宣伝ではありません。貞昌院では同様のものも公平に利用しています。あくまでも先駆的な事例としての記載ですからご了承ください。︶
カタログが送られれくる度に、顧客の心をつかむサービスが付加されていることに驚かされています。
最近注文した発注リストが挟み込まれていたり・・・
︵注意‥決してアスクルの宣伝ではありません。貞昌院では同様のものも公平に利用しています。あくまでも先駆的な事例としての記載ですからご了承ください。︶
さて、冒頭で文具業界は、他の業種と比べて独特の変化を遂げていると述べましたが、中間業者排除の観点からアスクルを見てみると他の業種と少し特徴的なことがあるのです。 具体的には、営業・配送・受付業務を外部の企業と分担しているという点です。 従来の文房具の流通の仕組は、 メーカー⇒一次卸⇒二次卸⇒小売⇒消費者 というようなものでした。 もしも、アスクルがメーカーと顧客との直接カタログ販売をおこない、 メーカー⇒消費者 という構図になると、卸と小売の排除が起こり、既存の小売店の営業を阻害したことでしょう。 けれども、文具業界では単純な中間業者排除を行うのではなく、代理店としての役割分担を提起しているのが特徴です。 http://www.askul-net.com/askul-business.html ↑こちらに、その流通のしくみが分かりやすく図解されています。 つまり、全国1600の文具小売店と提携︵エージェントと呼ばれます︶し、料金回収と訪問営業を業務委託しているわけです。この点で既存の文具小売店を共存関係としてうまく利用していることがわかります。 代理店となった小売店は、従来の顧客をに対し、アスクルの営業活動を委託して行ないます。そして通信販売の売り上げを伸ばすということが、同時に小売店の利益に繋がるという新たな関係を築きあげていったのです。 そしてアスクルへ発注された商品の代金は、再び小売店が集め、その一部が小売店の利益となる構図なのです。 まとめると、 ︻顧客の新規入会からカタログ配送まで︼ 顧客からの発注⇒全国100万箇所の事業所へ⇒全国1600社のエージェントへ⇒アスクルへ登録依頼 ⇒ アスクルから顧客へカタログ発送 ︻発注から料金回収まで︼ 顧客からアスクルへFAX・インターネットで注文⇒アスクルから顧客へ商品配送⇒アスクルから顧客へ請求書発行︵送付代行‥アスクルからエージェントへ請求⇒エージェントから顧客へ請求︶⇒顧客からエージェントへ支払い→エージェントからアスクルへ支払い ということになります。 見かけ上は、エージェントの姿は表に現れないので、あたかもアスクルと顧客との二者間の単純な取引のように見えます。 アスクル エージェント でグーグル検索すると、大体その構図がつかめます。 http://www.google.com/search?hl=ja&rls=GGLD%2CGGLD%3A2003-50%2CGGLD%3Aja&q=%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%80%80%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr= なお、エージェント第一号は、東京の山崎文栄堂です。 平成5年当時、ごく普通の文具店であった山崎文栄堂は、数年間赤字経営が続いており、当時設立されたばかりのアスクルと事業提携をするようになりました。周囲からは、かなりの猛反対があったそうです。 それから9年が経過し、売上はエージェントになった当初から約25倍になり、全国のエージェントの中で、トップ5の常連となっています。 新しい流通構造の変化が、単純に中間業者排除にはならずに、新たな中間業者としての枠組みの構造を生じているのが面白い発想だと思います。 オフィス用品のように、購入したいものが予め明確になっているようなものは、カタログをみながらまとめて発注する方が顧客にとって便利です。 わざわざ文具店に出向いて必要なものを購入したりする必要もない。翌日に確実に届けられるという利便性も従来の流通では考えられなかったことです。また、2500円以上で商品配送料無料ということは中小事業所にとっても発注しやすい設定となっているといえます。 文具マーケットは1.4兆円とも言え、75%が法人向けと想定され、30人未満の事業所は実にそのうちの95%。 アスクルの分かりやすい発注の仕組みは、このような顧客層にまさにうってつけだったというわけです。 アスクル側は、インターネット上のカタログに掲載するための商品企画・開発、価格決定、カタログ製作、注文受付、在庫管理、商品発送、料金回収、クレーム処理が主な仕事となりますが、コア業務を行っている社員はわずか100名余であって、その数十倍もの周辺業務要員が存在するわけです。中段で述べた構図のように、これらが有機的に結びついて一体となった運営をおこなっている訳です。 アスクルが急成長を遂げ、かつ、高い顧客満足度を得る結果となっている理由には、カスタマーズリレーションシップマネジメントを1元管理して徹底的に行っているからといえます。また、物流システムの徹底的な整備によって、注文から発送までの時間を限りなく短くすることにより当日配送をも可能としているのです。 メーカが始めた通信販売はこれまでの文具︵現在では事務用品全般、電化製品、食品、飲料なども含まれる︶流通を大きく変えました。情報技術を使うことで、何種類もの商品の仕分けを早く正確に行い、運送会社による全国翌日配送、小売店に委託した顧客対応と営業力、新しい枠組みによる効率的な流通システムの再構築によって新しい構図を作り上げています。 アスクルは、有力文具小売店をはじめ様々な業態から参加したエージェント︵代理店︶とアスクルが一体となって、互いの長所と短所をカバーし、有効な機能だけを結び合わせる共存共栄の画期的な流通システムを展開することにより成功した企業の最たる事例といえます。 以降、文具業界だけでも次々と似たような仕組みが出来上がってきました。 ︻同様の主な文具企業︼ ぱーそなるたのめーる︵大塚商会︶ http://www.p-tano.com/ カウネット︵コクヨ︶ http://www.kaunet.info/ イーサプライ http://www.e-supply.co.jp/
企業間でそれぞれの力を組み合わせて、強靭な流通のしくみを作るという流れは、今後、様々な分野で進展していくことでしょう。 ----------------------------------- アスクルのカタログはこんなに厚い。 見ているだけでも楽しいです。
 カタログが送られれくる度に、顧客の心をつかむサービスが付加されていることに驚かされています。
最近注文した発注リストが挟み込まれていたり・・・
︵注意‥決してアスクルの宣伝ではありません。貞昌院では同様のものも公平に利用しています。あくまでも先駆的な事例としての記載ですからご了承ください。︶
カタログが送られれくる度に、顧客の心をつかむサービスが付加されていることに驚かされています。
最近注文した発注リストが挟み込まれていたり・・・
︵注意‥決してアスクルの宣伝ではありません。貞昌院では同様のものも公平に利用しています。あくまでも先駆的な事例としての記載ですからご了承ください。︶
2005年3月11日
ハイパーマーケットの明暗
カルフール、国内8店舗をイオンに売却へ 週内にも発表
カルフールは00年12月、千葉県の幕張に1号店を出店。南町田︵東京︶、狭山︵埼玉︶、東大阪︵大阪︶、尼崎︵兵庫︶など首都圏と近畿で8店舗を展開している。大量仕入れによる安売り販売の手法で外資系大手スーパーとして初めて日本市場に進出したが、業績が低迷し、昨年以降日本からの撤退を検討していた。
http://www.business-i.jp/news/ind-page/news/art-20050309220342-JCFCXKWQEF.nwc
昨日のニュースです。
カルフールは1959年にパリで創業した巨大なセルフサービス店であり、ハイパーマーケット︵売場面積2,500平方メートル超の食品主体のセルフサービス店舗︶の元祖とも言われます。
鳴り物入りで日本に進出しましたが、その幕切れはあっけないものでした。
そういった﹁暗﹂がある反面、元気なハイパーマーケットもあります。
その代表格が、コストコホールセールでしょう。
子供が通っている幼稚園のお母さん方には大変な人気で、グループ買いなどをしたりします。
割合近くに店舗があるので、早速行ってみました。
まず、コストコとは??という方は http://www.costco.co.jp/ をご参照ください。
主な特徴は
■コストコホールセールは、会員制の倉庫型店舗。
■入店時に写真つき会員証の提示が必要。
■会員はゴールドスターメンバーとビジネスメンバーの2種類。
■出店時にレシートと購入した商品の照合が行われる。
会員制ですから、会員証をまず作ります。
貞昌院でビジネスメンバーに入ってみました。
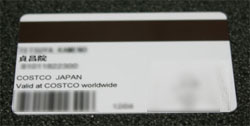 ハイパーマーケットは、車で行くことが前提になりますから、駐車場も整備されていて、大型のカートで直接店舗から駐車場まで運ぶことが出来ます。
最初に駐車場から店舗に入ると、まず店舗内部がやたら大きいことに驚かされます。
まあ、倉庫型の店舗ですから当然といえば当然ですね。
売っている商品の単位が一桁違いますので、買い込むには相当の覚悟が必要です。
日本製のポテトチップとかも、こんな大きな袋詰めは初めて見る・・・という驚きで、最初は十分楽しめると思います。
アメリカなどは、一週間分の食料品を買い溜めして冷蔵庫に突っ込んでおくといいますが、いかにも﹁アメリカの大量消費文化﹂を象徴するような店舗です。
日本の普通の家庭では、とても消費できる単位ではありません。
パンとかも36個入りとか、肉がキロ単位とか・・・・・・
逆に、レストランとかを経営している人にとってはとてもありがたい店ではないでしょうか。
それと、冒頭に述べたグループ買いですね。
かなり買いこんでしまったのですが、特にジュースとパン類はおすすめかもしれません。
見かけの大雑把さとは裏腹に、とても美味しいです。
ハイパーマーケットは、車で行くことが前提になりますから、駐車場も整備されていて、大型のカートで直接店舗から駐車場まで運ぶことが出来ます。
最初に駐車場から店舗に入ると、まず店舗内部がやたら大きいことに驚かされます。
まあ、倉庫型の店舗ですから当然といえば当然ですね。
売っている商品の単位が一桁違いますので、買い込むには相当の覚悟が必要です。
日本製のポテトチップとかも、こんな大きな袋詰めは初めて見る・・・という驚きで、最初は十分楽しめると思います。
アメリカなどは、一週間分の食料品を買い溜めして冷蔵庫に突っ込んでおくといいますが、いかにも﹁アメリカの大量消費文化﹂を象徴するような店舗です。
日本の普通の家庭では、とても消費できる単位ではありません。
パンとかも36個入りとか、肉がキロ単位とか・・・・・・
逆に、レストランとかを経営している人にとってはとてもありがたい店ではないでしょうか。
それと、冒頭に述べたグループ買いですね。
かなり買いこんでしまったのですが、特にジュースとパン類はおすすめかもしれません。
見かけの大雑把さとは裏腹に、とても美味しいです。

ジュースは1?×12個が一単位で売っています。南アフリカ産。単価はかなり安い。 アップルパイ。見かけはあまりよくないのですが、焼きリンゴがたくさん入っていて美味しい。
︵これを食べながら書込みをしています︶
------------------
コストコは、単なるハイパーマーケットではなく、Membership WholeSale Club=会員制の卸問屋であり、本来は飲食業や小売店、企業をターゲットにしていました。
それが一般消費者にターゲットを広げて現在の形になりました。
ゴールドスターメンバーよりビジネスメンバーの方が会費が安いという所に、その本来の特徴を垣間見ることが出来ます。
安さの秘密は、物流コストと人件費の大幅な削減が大きな要因になっているようです。
つまり、倉庫=売場であるため、出荷された商品が、工場出荷時状態でパレットごと積み上げられること、商品売場に人員をほとんど配置しないという大胆なコストカットを行っているわけです。
さらに、商品点数を絞り、ロットを大きくすることによって客一人当たりの購入単価を増やし、大量販売に徹することが出来ます。
また、年会費は高めに設定されているため、消費者は何度も通って元をとろうとする心理が働くでしょう。
︵これを会員制カードによる﹁メンバーシップ・ロックイン﹂効果といいます => ロックインについてはQWERTYのトピックスでも出てきましたね ︶
コストコとしても、年会費がかなりの収入源になるため、低い粗利益率を実現でき、限界に近い低価格が実現されています。
今までの日本型の小売店の常識を覆す特徴を兼ね備えているといえるでしょう。
このような倉庫型のハイパーマーケットが日本に根づくのか、それともカルフールのように一時的なブームに終わるのか。
推移を見守って行きたいと思います。
アップルパイ。見かけはあまりよくないのですが、焼きリンゴがたくさん入っていて美味しい。
︵これを食べながら書込みをしています︶
------------------
コストコは、単なるハイパーマーケットではなく、Membership WholeSale Club=会員制の卸問屋であり、本来は飲食業や小売店、企業をターゲットにしていました。
それが一般消費者にターゲットを広げて現在の形になりました。
ゴールドスターメンバーよりビジネスメンバーの方が会費が安いという所に、その本来の特徴を垣間見ることが出来ます。
安さの秘密は、物流コストと人件費の大幅な削減が大きな要因になっているようです。
つまり、倉庫=売場であるため、出荷された商品が、工場出荷時状態でパレットごと積み上げられること、商品売場に人員をほとんど配置しないという大胆なコストカットを行っているわけです。
さらに、商品点数を絞り、ロットを大きくすることによって客一人当たりの購入単価を増やし、大量販売に徹することが出来ます。
また、年会費は高めに設定されているため、消費者は何度も通って元をとろうとする心理が働くでしょう。
︵これを会員制カードによる﹁メンバーシップ・ロックイン﹂効果といいます => ロックインについてはQWERTYのトピックスでも出てきましたね ︶
コストコとしても、年会費がかなりの収入源になるため、低い粗利益率を実現でき、限界に近い低価格が実現されています。
今までの日本型の小売店の常識を覆す特徴を兼ね備えているといえるでしょう。
このような倉庫型のハイパーマーケットが日本に根づくのか、それともカルフールのように一時的なブームに終わるのか。
推移を見守って行きたいと思います。
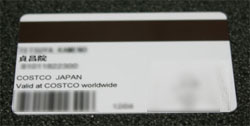 ハイパーマーケットは、車で行くことが前提になりますから、駐車場も整備されていて、大型のカートで直接店舗から駐車場まで運ぶことが出来ます。
最初に駐車場から店舗に入ると、まず店舗内部がやたら大きいことに驚かされます。
まあ、倉庫型の店舗ですから当然といえば当然ですね。
売っている商品の単位が一桁違いますので、買い込むには相当の覚悟が必要です。
日本製のポテトチップとかも、こんな大きな袋詰めは初めて見る・・・という驚きで、最初は十分楽しめると思います。
アメリカなどは、一週間分の食料品を買い溜めして冷蔵庫に突っ込んでおくといいますが、いかにも﹁アメリカの大量消費文化﹂を象徴するような店舗です。
日本の普通の家庭では、とても消費できる単位ではありません。
パンとかも36個入りとか、肉がキロ単位とか・・・・・・
逆に、レストランとかを経営している人にとってはとてもありがたい店ではないでしょうか。
それと、冒頭に述べたグループ買いですね。
かなり買いこんでしまったのですが、特にジュースとパン類はおすすめかもしれません。
見かけの大雑把さとは裏腹に、とても美味しいです。
ハイパーマーケットは、車で行くことが前提になりますから、駐車場も整備されていて、大型のカートで直接店舗から駐車場まで運ぶことが出来ます。
最初に駐車場から店舗に入ると、まず店舗内部がやたら大きいことに驚かされます。
まあ、倉庫型の店舗ですから当然といえば当然ですね。
売っている商品の単位が一桁違いますので、買い込むには相当の覚悟が必要です。
日本製のポテトチップとかも、こんな大きな袋詰めは初めて見る・・・という驚きで、最初は十分楽しめると思います。
アメリカなどは、一週間分の食料品を買い溜めして冷蔵庫に突っ込んでおくといいますが、いかにも﹁アメリカの大量消費文化﹂を象徴するような店舗です。
日本の普通の家庭では、とても消費できる単位ではありません。
パンとかも36個入りとか、肉がキロ単位とか・・・・・・
逆に、レストランとかを経営している人にとってはとてもありがたい店ではないでしょうか。
それと、冒頭に述べたグループ買いですね。
かなり買いこんでしまったのですが、特にジュースとパン類はおすすめかもしれません。
見かけの大雑把さとは裏腹に、とても美味しいです。

ジュースは1?×12個が一単位で売っています。南アフリカ産。単価はかなり安い。
 アップルパイ。見かけはあまりよくないのですが、焼きリンゴがたくさん入っていて美味しい。
︵これを食べながら書込みをしています︶
------------------
コストコは、単なるハイパーマーケットではなく、Membership WholeSale Club=会員制の卸問屋であり、本来は飲食業や小売店、企業をターゲットにしていました。
それが一般消費者にターゲットを広げて現在の形になりました。
ゴールドスターメンバーよりビジネスメンバーの方が会費が安いという所に、その本来の特徴を垣間見ることが出来ます。
安さの秘密は、物流コストと人件費の大幅な削減が大きな要因になっているようです。
つまり、倉庫=売場であるため、出荷された商品が、工場出荷時状態でパレットごと積み上げられること、商品売場に人員をほとんど配置しないという大胆なコストカットを行っているわけです。
さらに、商品点数を絞り、ロットを大きくすることによって客一人当たりの購入単価を増やし、大量販売に徹することが出来ます。
また、年会費は高めに設定されているため、消費者は何度も通って元をとろうとする心理が働くでしょう。
︵これを会員制カードによる﹁メンバーシップ・ロックイン﹂効果といいます => ロックインについてはQWERTYのトピックスでも出てきましたね ︶
コストコとしても、年会費がかなりの収入源になるため、低い粗利益率を実現でき、限界に近い低価格が実現されています。
今までの日本型の小売店の常識を覆す特徴を兼ね備えているといえるでしょう。
このような倉庫型のハイパーマーケットが日本に根づくのか、それともカルフールのように一時的なブームに終わるのか。
推移を見守って行きたいと思います。
アップルパイ。見かけはあまりよくないのですが、焼きリンゴがたくさん入っていて美味しい。
︵これを食べながら書込みをしています︶
------------------
コストコは、単なるハイパーマーケットではなく、Membership WholeSale Club=会員制の卸問屋であり、本来は飲食業や小売店、企業をターゲットにしていました。
それが一般消費者にターゲットを広げて現在の形になりました。
ゴールドスターメンバーよりビジネスメンバーの方が会費が安いという所に、その本来の特徴を垣間見ることが出来ます。
安さの秘密は、物流コストと人件費の大幅な削減が大きな要因になっているようです。
つまり、倉庫=売場であるため、出荷された商品が、工場出荷時状態でパレットごと積み上げられること、商品売場に人員をほとんど配置しないという大胆なコストカットを行っているわけです。
さらに、商品点数を絞り、ロットを大きくすることによって客一人当たりの購入単価を増やし、大量販売に徹することが出来ます。
また、年会費は高めに設定されているため、消費者は何度も通って元をとろうとする心理が働くでしょう。
︵これを会員制カードによる﹁メンバーシップ・ロックイン﹂効果といいます => ロックインについてはQWERTYのトピックスでも出てきましたね ︶
コストコとしても、年会費がかなりの収入源になるため、低い粗利益率を実現でき、限界に近い低価格が実現されています。
今までの日本型の小売店の常識を覆す特徴を兼ね備えているといえるでしょう。
このような倉庫型のハイパーマーケットが日本に根づくのか、それともカルフールのように一時的なブームに終わるのか。
推移を見守って行きたいと思います。
2005年3月 2日
使い辛いものをわざわざ使う理由
今、一所懸命このブログの文章を打ち込んでいる、御馴染みのキーボードですが、左上からQWERT・・・と並んでいるために、QWERTY配列と呼ばれます。
このキーボードの歴史は、タイプライターの歴史までにさかのぼり、レミントン社が生み出した配列です。
なぜこのような配列になっているのか・・・・
これは人間工学的に最も指が疲れないように工夫されたわけでも、英文の単語の出現頻度を調べて効率の良い配列にしたわけでもありません。
驚くことに、配列を工夫して打ちやすくしするとタイプラーターを速く打ってしまうため、印字アーム部分が絡み付いてしまうのを防ぐよう、わざわざ打ちにくいように配列してあるのです。 ︵注1︶
便利なタイプライターは生活・仕事上で重要な位置をしめ、一般社会に普及していきます。
時代はやがて、タイプライターからコンピューターへと移り変わり、機械的に印字アームが絡みつくという制約が無くなりました。
打ち辛いQWERTY配列は廃れてしまったでしょうか????
答えはもちろんノーですね。
実は、タイプライターからコンピューターへの転換期には、 Dvorak Simplified Keyboard のように、効率的で打ちやすい新しい配列のキーボードが幾つも生み出されていました。
しかしながら、結局デファクトスタンダードとして残ったのは、QWERTY配列キーボードだったのです。
ここで、QWERTY配列キーボードの歴史を改めて振り返ってみましょう。
1867年 Christopher Latham Sholes と Carlos Glidden, Samuel W.Soule らが ABC 順にキー配列したタイプ式ライティング機を特許申請。
1867年 James Densmore が加わり、キー配列を、印字棒の絡み合いがなるべく少なくなるよう研究し、現在の4段 QWERTY配列に近いものが出来上がった。
1873年 QWERTYキー配列を採用したE・レミントン社のレミントン機が発売された。
1873?1880年代初めには、QWERTY 配列のキーボードは、米国で 5000 台程度の普及であった。
1872年 テレタイプ機の基礎となった電機回転式印刷装置が登場し、印字棒がからむ問題は回避される機械が開発された。このころ、ハモンドやブリッケンズダーファーのタイプライターは、Idealキーボードのように、QWERTYよりも打鍵しやすいキー配列を採用していた。
1880年代 タイプライターブームにより、QWERTY に対抗するキー配列が数多く提案されていく。
1880年代後半 キー入力として、それまでは数本の指で打鍵していたが、10本の指を使う﹁タッチタイピング﹂が出現。タッチタイピングの習得手段として、QWERTYキーボードが広く使われだした。
1890年代 タイプライター産業は、国際標準として、 QWERTYキーをもったタイプライターを事実上標準化した。
1936年 ワシントン大学の August Dvorak 教授により、打鍵効率が格段に向上した DSK配列を開発・特許を取り普及に努めるが、すでにQWERTキーボードの勢いをとめることができなかった。
1970年代 コンピュータの出現により、業界紙の中で QWERTY を捨てる呼びかけがあったにもかかわらず、QWERTY は相変わらず使い続けられた。
では、なぜ、QWERTY配列キーボードが廃れなかったのでしょうか。 このような現象は、﹁ロックイン﹂﹁スイッチングコスト﹂﹁サンクコスト﹂というキーワードで答えを見出すことができます。 キーボード入力は、習熟を必要とする入力装置ですから、これを、サンクコストの観点から見てみると、 ﹁サンクコスト﹂とは、ある程度早く入力できるようになるために費やすトレーニングコスト といえます。 このコストは、一度投資してしまったら、回収不可能な費用でありますから、一度使い始めたキーボードに対して費やされたサンクコストの膨大さを考えると、それまで慣れしたしんで使っていたキーボードを放棄して、新しい配列のキーボードに乗り換えることに、大きな抵抗を感じます。 従って、タイプライターからコンピューターへの転換期にあたって、たとえ機械上の制約から解き放たれたとしても、依然として﹁わざと使いづらくした﹂キーボードを使い続けることになるわけです。 ﹁ロックイン﹂とは、その製品の他に、互換性がないような技術や製品のことを指します。 ある製品を導入して、その後ライバル製品が現れたとしても、いまさら新しいものに切り換えることが困難になってしまう現象であり、これによって消費者が不利益を被る場合も多々あることでしょう。 ﹁スイッチング・コスト﹂は、今使っているものから、新しい製品に切り換えるのために費やされる費用をいいます。スイッチング・コストが高くつくのであれば、消費者は他の製品にたやすく乗り換えることはできません。 これらの足かせは、製造業者・導入企業・タイピストそれぞれにどのような影響を与えているかを考えてみます。 ︵1︶製造業者 どのような配列のキーボードを製造するかを検討する段階で、需要の多い、一番普及している種類のものを選ぶことでしょう。一度 QWERTY配列に決定したら、別の型のタイプライターに転換するためには多少なりともコストがかかってしまうし、売れるかどうかも不明確でリスクが大きい。 ︵2︶導入企業 一番普及している配列のキーボードを導入すれば、タイピストが幅広く、安価に募集できる。逆に、マイナーなキーボードを採用すると、キー入力の習得のために、教育をしなければならないかもしれない。トータルとして、多少入力効率が悪くても、タイピストの確保や、教育の間作業が滞ることなどを考慮すると、一番普及しているものを採用するのが当然でしょう。 ︵3︶タイピスト 特定の配列に慣れてしまった場合、仮に他のキー入力へ変更するためには、トレーニングする時間と労力がサンクコストとして余計にかかってしまう。したがって、初めに習得する際には、より広く通用する、つまり一番普及している方法で習得しようと考えます。 結果として、三者とも最も普及しているキー配列を促進する方向に進んでしまうのです。 このように、キーボードのような、今まで使っていた製品から別の製品に替える際に必要となるコストは、新規投資費用、サンクコストの他に、リスクなどの心理的費用等がかかることになり、これらの費用︵すなわち、スイッチングコスト︶が大きければ大きいほど、今まで使っていた製品から他のものへ移ることが困難となります。 このように、一度選択されてしまうと、それ以降の変更が困難になり、将来の選択肢が規定されてしまうこと、これがロックイン効果であり、QWERTY配列が未だに幅広く使われていて、他の優れた配列のキーボードを排除してしまうメカニズムなのです。 世の中、全てが効率的な方向に進むものとは限らないのですね。 ------------------------------------ 注‥⇒この﹁打ちにくくすることを意図した・・という表現には異論もあります http://www.sixnine.net/keyboard/qwerty.html http://homepage1.nifty.com/cura/oya/kb_arguments.html などを併せてご参照ください。 けれども、少なくとも、最も効率的なキー配列でないはずです。 さらに言及すれば、日本語の﹁ローマ字入力﹂をする場合には、とてつもなく入力し辛いキー配列であることは間違いありません。 もしかしたら、打鍵速度を抑制したというより、単純に遊び心で適当にキー配列を決めたのかもしれません。 だって、タイプラーターって単語をキーボード上でたどってみてください・・・・TYPEWRITER・・・・・全部上の段ですよ。︵88へぇ︶
では、なぜ、QWERTY配列キーボードが廃れなかったのでしょうか。 このような現象は、﹁ロックイン﹂﹁スイッチングコスト﹂﹁サンクコスト﹂というキーワードで答えを見出すことができます。 キーボード入力は、習熟を必要とする入力装置ですから、これを、サンクコストの観点から見てみると、 ﹁サンクコスト﹂とは、ある程度早く入力できるようになるために費やすトレーニングコスト といえます。 このコストは、一度投資してしまったら、回収不可能な費用でありますから、一度使い始めたキーボードに対して費やされたサンクコストの膨大さを考えると、それまで慣れしたしんで使っていたキーボードを放棄して、新しい配列のキーボードに乗り換えることに、大きな抵抗を感じます。 従って、タイプライターからコンピューターへの転換期にあたって、たとえ機械上の制約から解き放たれたとしても、依然として﹁わざと使いづらくした﹂キーボードを使い続けることになるわけです。 ﹁ロックイン﹂とは、その製品の他に、互換性がないような技術や製品のことを指します。 ある製品を導入して、その後ライバル製品が現れたとしても、いまさら新しいものに切り換えることが困難になってしまう現象であり、これによって消費者が不利益を被る場合も多々あることでしょう。 ﹁スイッチング・コスト﹂は、今使っているものから、新しい製品に切り換えるのために費やされる費用をいいます。スイッチング・コストが高くつくのであれば、消費者は他の製品にたやすく乗り換えることはできません。 これらの足かせは、製造業者・導入企業・タイピストそれぞれにどのような影響を与えているかを考えてみます。 ︵1︶製造業者 どのような配列のキーボードを製造するかを検討する段階で、需要の多い、一番普及している種類のものを選ぶことでしょう。一度 QWERTY配列に決定したら、別の型のタイプライターに転換するためには多少なりともコストがかかってしまうし、売れるかどうかも不明確でリスクが大きい。 ︵2︶導入企業 一番普及している配列のキーボードを導入すれば、タイピストが幅広く、安価に募集できる。逆に、マイナーなキーボードを採用すると、キー入力の習得のために、教育をしなければならないかもしれない。トータルとして、多少入力効率が悪くても、タイピストの確保や、教育の間作業が滞ることなどを考慮すると、一番普及しているものを採用するのが当然でしょう。 ︵3︶タイピスト 特定の配列に慣れてしまった場合、仮に他のキー入力へ変更するためには、トレーニングする時間と労力がサンクコストとして余計にかかってしまう。したがって、初めに習得する際には、より広く通用する、つまり一番普及している方法で習得しようと考えます。 結果として、三者とも最も普及しているキー配列を促進する方向に進んでしまうのです。 このように、キーボードのような、今まで使っていた製品から別の製品に替える際に必要となるコストは、新規投資費用、サンクコストの他に、リスクなどの心理的費用等がかかることになり、これらの費用︵すなわち、スイッチングコスト︶が大きければ大きいほど、今まで使っていた製品から他のものへ移ることが困難となります。 このように、一度選択されてしまうと、それ以降の変更が困難になり、将来の選択肢が規定されてしまうこと、これがロックイン効果であり、QWERTY配列が未だに幅広く使われていて、他の優れた配列のキーボードを排除してしまうメカニズムなのです。 世の中、全てが効率的な方向に進むものとは限らないのですね。 ------------------------------------ 注‥⇒この﹁打ちにくくすることを意図した・・という表現には異論もあります http://www.sixnine.net/keyboard/qwerty.html http://homepage1.nifty.com/cura/oya/kb_arguments.html などを併せてご参照ください。 けれども、少なくとも、最も効率的なキー配列でないはずです。 さらに言及すれば、日本語の﹁ローマ字入力﹂をする場合には、とてつもなく入力し辛いキー配列であることは間違いありません。 もしかしたら、打鍵速度を抑制したというより、単純に遊び心で適当にキー配列を決めたのかもしれません。 だって、タイプラーターって単語をキーボード上でたどってみてください・・・・TYPEWRITER・・・・・全部上の段ですよ。︵88へぇ︶