« 言語表現はいかにして多値論理体系で説明できるか | 最新記事 | 言語表現はいかにして多値論理体系で説明できるか3 »
2006年10月26日
言語表現はいかにして多値論理体系で説明できるか2

光の3原色は赤・緑・青に限定されたものではないということは、昨日のトピックスで述べました。
人間の進化の過程で、たまたま赤・緑・青の錐体が発達した事により光の三原色が生じたわけですが、当然のごとく、他の3つでも色の識別は可能です。
まあ、私たちは結果として赤 ・緑・青 その3つの錐体からの信号を混成させて形成して、色として認識し、その感覚を﹁ことば﹂に変換する時点で、時代的・地域的な背景によって異なる色の系統を生み出してきました。
このあたりのところが、非常に興味深い点であります。
つまり、同じような感覚器官を持ちながら、それを表現する際に、異なった表現をするという現象です。
国・地域、文化の中で、基本的な一般色名のほかに様々な固有色名を生み出し、そこから慣用句が定着し、時代とともに変遷をしていきました。
米国の人類学者Brenf Berlin, Paul Key の研究によれば、色彩言語の発達過程は次のようになります。
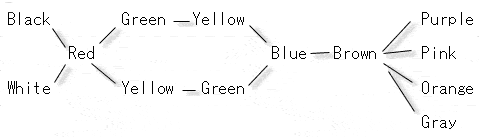 ここで、色相に関して、どれだけの語彙を持つかということを調べると大変興味深い結果が得られます。
例えば、ニューギニアやアフリカの一部人種では、言語にWhite, Black, Redに相当する語をもつのみです。
さらにジャワやスマトラではGreen, Yellow,Blue, Brownが加わり7種。
最も文化水準の高い人種ではさらにPurple, Pink, Orange, Grayが加わり11種となるとしています。
ここで、色相に関して、どれだけの語彙を持つかということを調べると大変興味深い結果が得られます。
例えば、ニューギニアやアフリカの一部人種では、言語にWhite, Black, Redに相当する語をもつのみです。
さらにジャワやスマトラではGreen, Yellow,Blue, Brownが加わり7種。
最も文化水準の高い人種ではさらにPurple, Pink, Orange, Grayが加わり11種となるとしています。
日本の古語においては明︵あか︶、顕︵しろ︶、暗︵くろ︶、漠︵あお︶という表現がありましたから、Berlinの研究をある程度裏付けているといえます。 しかし、色を表す語彙が少なくても、豊かな色を認識していることは、そのような時代・地域に於いても色彩感覚豊かな装飾や絵画があることから明白です。 それを表現する語彙が無いというだけです。 時代が進み、色に対する感性が高度になると、例えば室町時代のように﹁墨の五彩﹂や利休色といった微妙な色合いや、さらには﹁事物の数﹂だけ固有の色名があるような勢いとなります。 ︵この﹁事物の数﹂だけ固有の色名があるというのは、かえってズボラなだけのような気がしないでもないですが︶ 人間の能力として、実際にスペクトルの中に現れる色を人間がどの程度識別できるのか。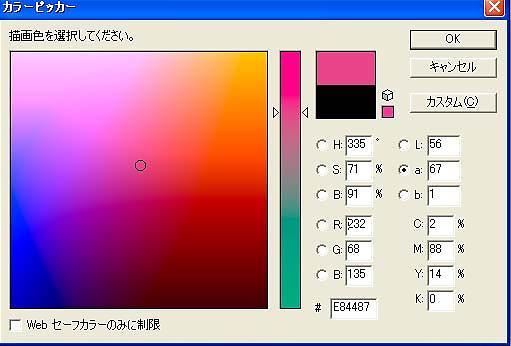 その答えは、120から200との見解が一般的です。
また、明度差による識別は500種くらい。
彩度による区別は70から170とされています。
この感覚的な識別能力に関しては、時代や人種によらず、ほぼ同じであると考えてよいでしょう。
後に,Paul Keyの弟子のマクダニエル︵C.K.McDaniel︶は,語彙化される色は,人間の生理学的な機構の反映であるとの説を提示しました。
すなわち,人間の眼というものは,白,黒を除くと赤,黄,青,緑の4色を基本的な色として知覚するようになっていて、他の色は,これら6色のいろいろの組合せからなるというものです。
その答えは、120から200との見解が一般的です。
また、明度差による識別は500種くらい。
彩度による区別は70から170とされています。
この感覚的な識別能力に関しては、時代や人種によらず、ほぼ同じであると考えてよいでしょう。
後に,Paul Keyの弟子のマクダニエル︵C.K.McDaniel︶は,語彙化される色は,人間の生理学的な機構の反映であるとの説を提示しました。
すなわち,人間の眼というものは,白,黒を除くと赤,黄,青,緑の4色を基本的な色として知覚するようになっていて、他の色は,これら6色のいろいろの組合せからなるというものです。
彼らの主張するところは、サピア=ウォーフの仮説︵言語が認識を規制する︶の裏返しであり、︿認識︵知覚︶が言語を規制する﹀ということにあります。 確かに、私たちの言語化の基礎にはこのような人類としての種に共通な生理学的なレベルでの認識があり、その認識は人類にとって普遍的であるという主張は十分に認められるものです。 生理学レベルでの認識を基層として、その上に、異なったレベルの意味論的な認識が層を成す構造になっているのです。 ﹁青は失恋﹂、﹁赤は怒り﹂などというような意味をもつレベルはさらに,国・地域、文化、ひいてはその人の生い立ちに密着したレベルの認識であります。
︵以下続く︶
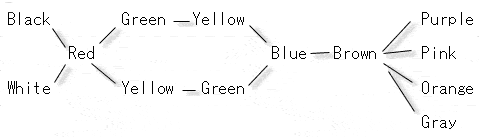 ここで、色相に関して、どれだけの語彙を持つかということを調べると大変興味深い結果が得られます。
例えば、ニューギニアやアフリカの一部人種では、言語にWhite, Black, Redに相当する語をもつのみです。
さらにジャワやスマトラではGreen, Yellow,Blue, Brownが加わり7種。
最も文化水準の高い人種ではさらにPurple, Pink, Orange, Grayが加わり11種となるとしています。
ここで、色相に関して、どれだけの語彙を持つかということを調べると大変興味深い結果が得られます。
例えば、ニューギニアやアフリカの一部人種では、言語にWhite, Black, Redに相当する語をもつのみです。
さらにジャワやスマトラではGreen, Yellow,Blue, Brownが加わり7種。
最も文化水準の高い人種ではさらにPurple, Pink, Orange, Grayが加わり11種となるとしています。
日本の古語においては明︵あか︶、顕︵しろ︶、暗︵くろ︶、漠︵あお︶という表現がありましたから、Berlinの研究をある程度裏付けているといえます。 しかし、色を表す語彙が少なくても、豊かな色を認識していることは、そのような時代・地域に於いても色彩感覚豊かな装飾や絵画があることから明白です。 それを表現する語彙が無いというだけです。 時代が進み、色に対する感性が高度になると、例えば室町時代のように﹁墨の五彩﹂や利休色といった微妙な色合いや、さらには﹁事物の数﹂だけ固有の色名があるような勢いとなります。 ︵この﹁事物の数﹂だけ固有の色名があるというのは、かえってズボラなだけのような気がしないでもないですが︶ 人間の能力として、実際にスペクトルの中に現れる色を人間がどの程度識別できるのか。
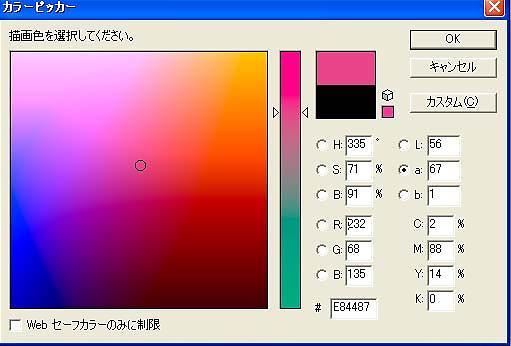 その答えは、120から200との見解が一般的です。
また、明度差による識別は500種くらい。
彩度による区別は70から170とされています。
この感覚的な識別能力に関しては、時代や人種によらず、ほぼ同じであると考えてよいでしょう。
後に,Paul Keyの弟子のマクダニエル︵C.K.McDaniel︶は,語彙化される色は,人間の生理学的な機構の反映であるとの説を提示しました。
すなわち,人間の眼というものは,白,黒を除くと赤,黄,青,緑の4色を基本的な色として知覚するようになっていて、他の色は,これら6色のいろいろの組合せからなるというものです。
その答えは、120から200との見解が一般的です。
また、明度差による識別は500種くらい。
彩度による区別は70から170とされています。
この感覚的な識別能力に関しては、時代や人種によらず、ほぼ同じであると考えてよいでしょう。
後に,Paul Keyの弟子のマクダニエル︵C.K.McDaniel︶は,語彙化される色は,人間の生理学的な機構の反映であるとの説を提示しました。
すなわち,人間の眼というものは,白,黒を除くと赤,黄,青,緑の4色を基本的な色として知覚するようになっていて、他の色は,これら6色のいろいろの組合せからなるというものです。
彼らの主張するところは、サピア=ウォーフの仮説︵言語が認識を規制する︶の裏返しであり、︿認識︵知覚︶が言語を規制する﹀ということにあります。 確かに、私たちの言語化の基礎にはこのような人類としての種に共通な生理学的なレベルでの認識があり、その認識は人類にとって普遍的であるという主張は十分に認められるものです。 生理学レベルでの認識を基層として、その上に、異なったレベルの意味論的な認識が層を成す構造になっているのです。 ﹁青は失恋﹂、﹁赤は怒り﹂などというような意味をもつレベルはさらに,国・地域、文化、ひいてはその人の生い立ちに密着したレベルの認識であります。
︵以下続く︶
投稿者: kameno 日時: 2006年10月26日 07:09


河本英夫先生の切り口のどんなものか興味がありますね。
私の詳論は、こつこつと書き足していくつもりです。
投稿者 kameno | 2006年10月26日 17:40